
そもそも品質工学 第120話 ペーパーホイール 物理法則の落とし穴
さーて、前回は生データを確認しました。
今回は計算した結果をどのように見るのか。
機能の定義は正しそうか?
利得の再現性はどうやって確認するのか?
そんなお話です。







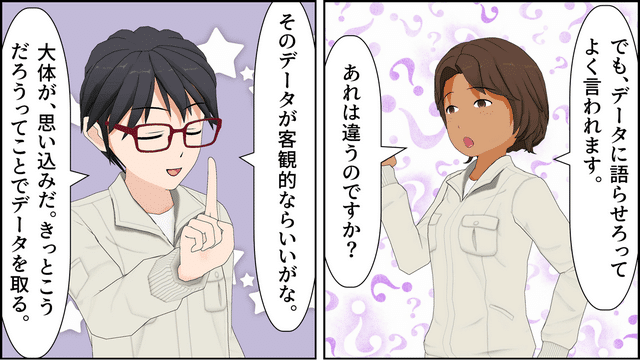






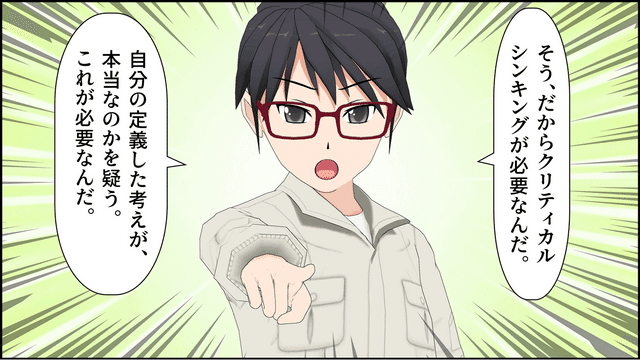



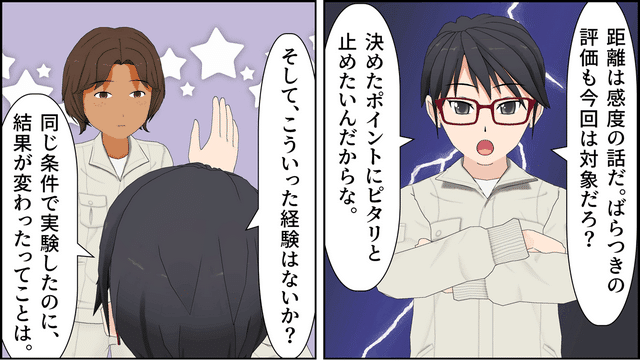



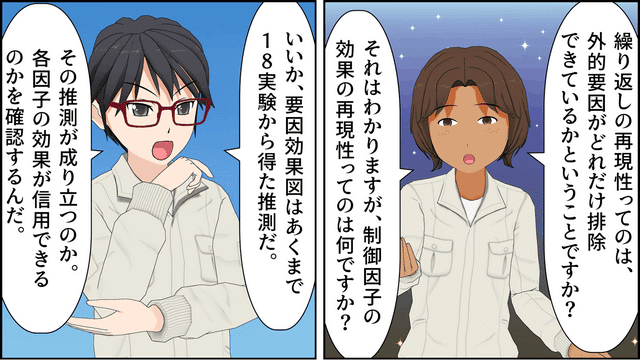




ここでご紹介したいのは2つ。
1つ目。
評価の観点では、物理法則はどうでもいいってこと。
技術者が、何を達成したいのか。
田口先生もよく言っていました。
「世の中にテレビの成る木はない」って。
自然界の法則をうまく組み合わせて、自然界にないものを作る。
機能も、自然界にはないものを、技術で生み出そうということ。
物理法則では、その関係は曲線でも、技術でそれを直線関係にする条件を探す。そういうことなのです。
それが、技術力ってことです。
2つ目。
確認実験をする意味。
傾向だけを知りたいというなら、確認実験は不要かもしれませんね。
でも、市場で再現する、ロバストな条件を見つけるという目的なら、確認実験は必須です。
確認実験の目的は2つあります。
同じことをしたら同じ結果になるのかという、実験そのものの再現性。
そして、因子の効果の足し算が成り立つのか、加法性のチェック。
通常の科学実験ですと、実験の再現性だけのチェックになります。
しかし、品質工学では、加法性のチェックも大事なのです。
経験上、この加法性は利得でいうと、50%程度あればいい感じでしょうか。
つまり、現状条件と推定した最適条件の真ん中ぐらいの性能です。
利得の再現性が100%なければならないってことはありません。
科学実験じゃないので。
現状より良くなればいいのです。
今回は、この2点についてのお話でした!
次回、ペーパーホイール編 最終話!
↓ ↓
いただいたサポートは、有益な情報を提供し続けるための活動にあてていきたいと思います!
