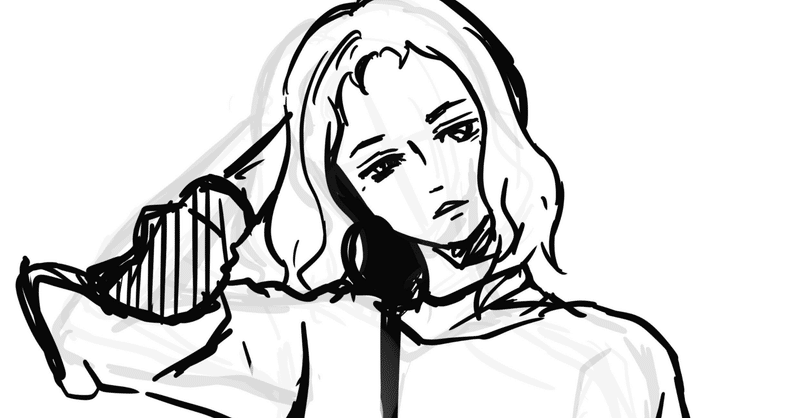
教師になる条件
字を丁寧に書く、速く書く、整えて書くなどのスキルの基本は毛筆です。 準備や片付け、住宅事情などを考えると手間は多いですが、要らんといって捨ててしまえるほど中身のないものではありません。
ぼくも最初は毛筆嫌やわぁって思ってたけど、書写の研修受けて教え方を教わるとなるほどなと思うことが多くて。 要る要らんで言ったら道徳や総合の方がもっと要らんで。
学校の授業の単元や領域で「こんなもん要らん」という人って、いい先生に恵まれなくて苦労した人かなんかだと思う。それはそれでご苦労さまと言いたい。でも、教師が、いい先生に恵まれなかった感をもってしまっているとしたらそれはちょっとよろしくない。
先生になるには、その人に先生がいることが不可欠だからだ。 初等教育ではもっと基礎基本を徹底して指導しないといけない。世の中のあれもこれもという声に折れていろんなことやってるけど、新しいことって、基礎基本の上に成り立っているわけで。
これだけ新しいことをたくさん盛り込まれても、基礎のない建物が地震に弱いのと同じで砂上の楼閣だ。新しいことを求められたら、その基礎はなんなのか、どのくらいの荷重がかかるのか、スキルの構造計算をするのが教育委員会の役目であって、民間企業の収益をあげるのが仕事ではない。
初等教育というのは中・高等教育の予備校ではないし、企業のための専門学校ではない。 書き初めなんて賞がつくのは書道教室通ってる子だけとか、書写作品ひとつ書き上げる間に演習問題がひとつ解けるとか、そういう点で批判してる人には恐らく話が通じない。
書写は作品を提出して賞をもらうためにやってるのではない。それは「書道」。 そもそも現場の先生が書道と書写の目的の違いがわかってないんだから話が噛み合わないのは当たり前だよね。 とめ、はね、はらいなどの書き方の基礎を毛筆で学んでるの。それが書写。
そんなの硬筆でもできる、ってのは確かにそうだが、土台にあるのは毛筆だってこと。えんぴつでいろはを縦に書いてみれば、平仮名が縦に書いた方が書きやすいとか、いろいろわかるはず。それに気が付かない人が先生やってるのなら、そういう研修ができてない先生方の労働環境が悪すぎるってこと。
長く伝統として残ってきたもの(製品や技術)が、技術の進歩で廃れてしまうのはよくあることだが、文化の基礎というのはその上に成り立って今があるのだから、一時の多忙を理由に簡単に捨てていいことではない。それは、建物の基礎に穴を開けるような行為だと、もっと慎重にやらなきゃいけない。
お願いだから、目先の利益にとらわれて、文化や教養の基礎を軽視しないで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
