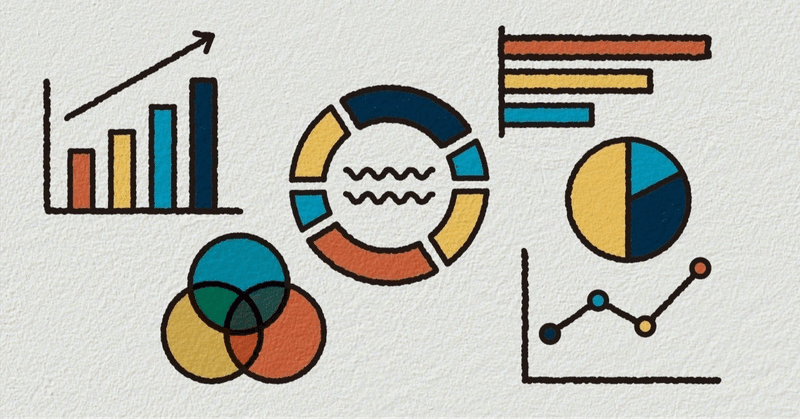
読書備忘録:LTVの罠
※ このブログのamazonリンクは、アフィリエイトリンクにより収入を得ています。
※ これは私個人の意見であり、会社の公式見解ではありません。
本の概要
本書はLTV向上施策において、顧客が逃げ出してしまう「4つのボトルネック=MAST」を浮き彫りにし、企業と顧客が向き合う接点ごとに有効な対処法を紹介。マーケティングや営業、顧客サービス部門の担当者がすぐに実践できるよう、多彩な事例を示しながら分かりやすく解説する。真に顧客から「愛される企業・ブランド・製品」を目指す企業担当者にとって必読の1冊。
読んだ理由
「『ゴールド会員』なんて顧客は嬉しくない」という見出しに共感したため
読んだ際の関連知識
マーケティング系のデータ分析を実施した経験あり
LTVについても何となく考えた経験あり(具体的には何も実施していない)
会員プログラムに関して、何となく疑問に思っている
また本業はデータアナリストなので、データの取得に関しては色々と思うところがありました。「本の備忘録」でコメントします。
全体の感想
一言で「顧客をちゃんと分析して戦略を立てましょう」という主張です。
著者がマーケティング会社で社長をしており、これまでの自社の知見を惜しみなく公開してくれているように感じます。
マーケティングに関わったことがある人なら、共感する箇所が多いはずです。
西口さんの「実践顧客起点マーケティング」でも定量調査と定性インタビューの重要性が語られていましたが、時代の流れなんですかね、、
本の備忘録
はじめに
「顧客囲い込み」「顧客データ活用」「ブランディング」と同じ文脈で「LTV」が語られやすいですが、著者は成功事例をあまり見たことがないようです。
カスタマージャーニーを設定し、ボトルネックを解消することが重要です。
「ゴールド会員」など名誉ある称号を与えれば顧客が喜ぶかといえば、全くそんなことはありません。自分が特に好きでもない企業から「あなたはゴールド会員です」と言われても、うれしいはずないでしょう。
デジタルの特性は「セルフサービス」と「ストック」です。一方で、マス広告はフロー。
デジタルマーケティングは本来は長期的な顧客とのコミュニケーションで利用されるべき。
私は、デジタルを”短期刈り取り”にばかり使う「CPAモンスター」と化してしまったマーケターに対して、デジタルを長期的な顧客とのコミュニケーションに使うべきだと説得する必要がありました。
第1章 LTVの「成功事例」が少ないのはなぜか?
著者は意図せずに溜まったデータを後から活用することには懐疑的です。
意図せずして社内にたまっているデータを後から活用しようとしても、うまくいくケースはほとんどありません。
その理由は、データの量と質が完全に不足しているからです。「大掃除の時に捨てられなかった大量のガラクタを、後からオークションに出したら1億円もうかった!」なんてことがないのと同じです。
Xでもいろんな人がつぶやいていますが、データ取得の設計からデータアナリストが関われると、データアナリストとしては非常にスムーズに効果検証が進められます。
まぁ統計学者の格言で「統計学者に相談にくるときには大抵遅すぎる」ってのがあるし、デザインの段階でかかわらなかった時点でほぼ負け戦なんだよ。
— Ken McAlinn (@kenmcalinn) March 6, 2024
しかし一方で、データアナリストとして働いていると、データの質と量が不足していたとしても、何かしらの知見を出さなければならない場面に遭遇したりします。
第2章 「MAST」に潜む罠
MASTとは次の4つの頭文字をとったフレームワークです。
M (Meet)
認識してもらうまでの障害が高すぎる
A (Attract)
顧客に魅力が伝わっていない
S (Sence)
接点がなくて、顧客の状況がわからない
T (Trade)
遠慮のしすぎでチャンスを逃している
第5章 「Sense(検知する)」のボトルネック
著者の会社によるメールマーケティングの実態調査です。
この調査によると、週2回から3回の配信が理想で、週4回は送りすぎです。
第7章 LTVボトルネックを取り除け!
LTVボトルネックは次の順序で取り除く
カスタマージャーニーの仮説を洗い出す
まずは社内のヒアリングを通じて仮説を洗い出す
事前仮説をもとに定量アンケート調査を実施する
社内ヒアリングで事前仮説が出ない場合、ユーザーに定性ヒアリングを実施しても良い
定量アンケートにより、定性インタビューの被験者を収集する
仮説で洗い出した「顧客接点」のうち、どれがメジャーなのか知る
LTVに影響する代替指標や顧客接点を知る(LTVに効くKPIを見つける)
定性インタビュー調査で、行動の順序と理由を深掘りする
定性インタビューで売りたい商品を営業してみる
定性調査で売れないような商品は、他に何をしても売れないといっても過言ではありません
第8章 LTVの成果を「見える化」する
LTVを計測するための完璧な指標は存在しないが、長期的な売り上げの増加につながるKPIを探索する必要がある。
LTV向上のKPI(重要業績評価指標)は、極論すればLTVにほんのわずかでも相関してさえいれば構いません。もっと言えば、短期売り上げに傾倒しそうなとき、長期利益視点を少しでも失わないようにできる指標ならそれでいいのです。
加えて、LTVには、「顧客視点」と「企業視点」の両方あることを忘れてはなりません。
私が支援するプロ野球球団では、webサイトを月に1回見る人よりも、毎日見る人のほうが、この球団のために使う金額がN円多いというデータを持っています。それならWebサイト運用のKPIに「Webサイトを毎日見る人数」を設定すればいいのです。
おわりに
最後は強めの言葉で締めています。
「LTV」という言葉に勝機を見い出したベンダーや、出世の道具にしたい浪費家の広告主が、全く必要のない「LTV」施策を打ち出し、成果が出ないまま言い訳して終えるのです。私は同じマーケティング業界に属する人間として、そんなコストパフォーマンスの悪い世界を許しません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
