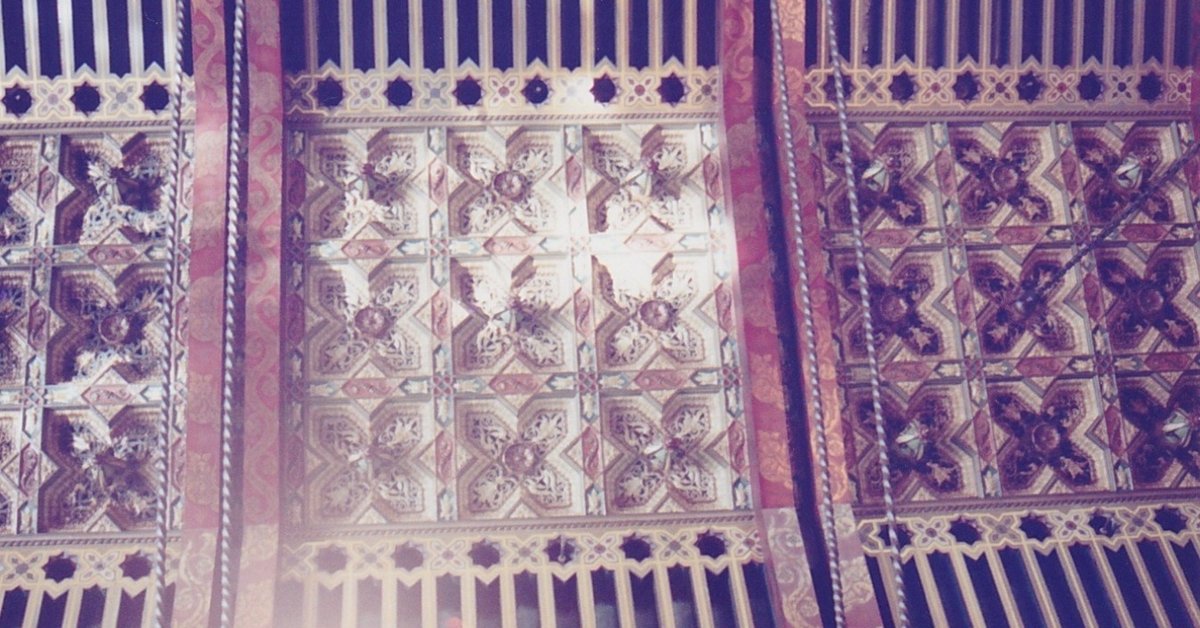
10『マクベス』
法政大学の授業「創作表現論」で学生が書いた作品の中から秀作を紹介します。第10回のお題は『マクベス』です。
「創作表現論」についてはこちらのページをご覧ください。
「カトマンズからポカラ」 魚取ゆき
「ネパール語なんかしゃべれて何になるんだ」とおやじは言った。高校3年生のとき、夏休みの模試の結果をみせたときに言われた言葉だ。
志望校判定欄はこんな感じだった。
西東京外国語大学言語コースネパール語学科 C
東東京外国語大学アジア語学部ネパール語専修 B
新大久保大学外国語学部ネパール語学科 B
山口下関大学国際コミュニケーション学部ネパール語専攻 A
高松国際言語大学グローバル学科ネパール連邦民主共和国学科 C
「祥太郎、おまえ進路の意味わかってるか? 大学の学問は習いごとじゃないんだ。ネパール語がやりたいなら、大学に進学してから自分でバイトでもしてネパール語の市民講座を受けたらいいじゃないか。それか、ネパールカレー屋でバイトでもして、ネパール語を教えてもらえばいい。大学の進路は一生にかかわることなんだから、もうちょっと真剣に考えてみろ。な?」
エプロン姿で肉じゃがに、おくらの煮びたしに、冷ややっこに、ねぎ塩トマトに、厚焼き玉子に、大盛りのごはんに、とつぎつぎテーブルに並べていきながら、おやじは困惑しきった顔でおれに言った。
「ネパール語は真剣じゃないの?」
「父さん、祥太郎の進路はできるだけ応援してやりたいとは思ってるんだ。でもなあ。ネパール語勉強して、将来何になるんだ? 外国語がだめだと言ってるんじゃない。英語とかフランス語とかロシア語とか、ネパール語以外にほかにあるだろ? ネパール語やってどうするんだ。カレー屋か? それともネパール大使館にでも就職するのか」
「じゃ、ネパール大使館でいい」
「ほかにないのか、もっとこう……」
「ラオス語でもいいけど」
「あのなあ」
「わかった」
わかったと言いながら結局冬の模試の志望校判定もネパール語ねらいで出した。返ってきた模試の志望動機欄をみて父はまた同じようなことを言った。
「ネパール語にするから」
言ったものの、けっきょく受験の願書を出したのはとある都内の外国語大学のロシア語学科だった。ロシア語にしたのは自分でルーズリーフにあみだくじをつくって、ロシア語が当たったからロシア語にしたのだ。ネパール語はだめだとおやじに強く言われたわけではなく(むしろ願書を出すころにはおやじは完全にあきらめているように見えた)、ネパール語がどうでもよくなったわけでもないのだが、「ネパール語なんかしゃべれて何になるんだ」ということばが心に残っていたことは事実だった。
そうしてあっさり、センター試験の国語と英語の点数だけで、ロシア語学科の学生になった。興味がないなりに1年たち、2年たち、ほとんどでたらめに見えるキリル文字の読み方も書き方も筆記体もおぼえ、数が多くて複雑な格変化や、まどろっこしい時制のパターンもおぼえ、曲がりなりにもロシア語が少しずつできるようになってきた。
大学3年生の夏休み、おやじは家を出ていった。急に出ていっていなくなったわけではなく、その半年前から出ていくと言われていたし、授業料や生活費にという名目で、お金が月々バイトしなくていいくらいにふりこまれていたので、困らなかった。どこで何をしているのかはわからなかったが、内科医のおやじは友人の医者がやっている医院でまとまった期間やとってもらったり、かと思うと仕事をしない時期があったり、大学病院に勤めたりしていたので、またどこかちがう街で、友人の医院で働かせてもらっているんだろうと思っていた。
おれが中学3年生のころから、おやじは勤務時間をへらしたり週4勤務にしたりしながら、家にいるときはいつもエプロン姿で朝夕の料理をつくったり掃除や洗濯をしたりしていたので、息子が大学生になり20歳にもなったのをきっかけに、気分を一心したくなったとか、そういうこともあるんだろうなと思っていた。
大学4年生になって、就活がはじまったころ、おやじから突然はがきがきた。手前に藤の花、奥に富士山というギャグみたいな構図のポストカードの余白に、〈元気ですか?〉と油性の細いマジックの字で書いてあった。住所は横浜の関内になっていた。
就活がおわって、内定をもらったのは大手のファミリーレストランを経営する会社だった。そのほかに、全国展開のコンビニ店を経営する会社からも内定をもらっていたが、コンビニのほうは最初の2年間は直営店での店舗実習だときいて、ファミリーレストランのほうをえらんだ。ロシア語はいかせなさそうだったが、引きつづき大学院で勉強するとか、ロシア語に関係がある職場で働きたいというモチベーションはなかったし、翻訳や通訳をしようと思えるほどロシア語がじょうずになってもいなかった。卒業後もロシアに関わる進路を選ぶ同級生はみな、大学4年間をロシア語の勉強にささげ、一年以上の長期留学に行っていた。
大学4年生がおわる春休みに、クラスの仲のいいメンバー4人でモスクワを6日間旅行した。現地でロシア人の友だちをつくり、それなりに旅行会話もなんとかなり、ロシア語はやりきったという感じもあった。
働きはじめて7、8か月たったころ、おやじからまたはがきが来た。あのはがき以来、とくに連絡もなかったし、電話もおやじが家を出ていってから1、2度むこうからかかってきたっきりだったのだけれど、社会人になってからもあいかわらず、生活費という名目で額こそ減ったが毎月まとまった額のお金がふりこまれていた。はがきは、青と赤のハンコがおされた国際郵便はがきで、見返り美人図みたいな構図の、サリーを着たインド風の女の子の写真のポストカードだった。裏面には、英語でJAPAN、そしてそのあと日本語で家の住所と名前が書いてあった。送り主のところには虫がのたくったような、ヒンディー語やサンスクリット語のような上に線のある文字が書いてあった。
ヒンディー語かな? そう思いテーブルにはがきを置きっぱなしにしてそれから2、3日後、会社から帰ってきて、寝る前にきゅうに思いあたった。これはネパール語なんじゃないだろうか?
高校生のころ、ネパール語にばくぜんとあこがれていたけれど、実際にネパール語を勉強することはなかったし、あきらめたことでかえってネパール語から遠ざかっていた。ネットで検索すること30分、それがヒンディー語ではなくほんとうにネパール語で、はがきの住所にはネパール、そしてポカラという街の名前がたしかに書いてあることがわかると、手のひらに汗をかき胸がどくどく鳴った。何か理由があるわけではないのにどうしようもなくネパール語にひかれる、あのときの気持ちがよみがえってくるようだった。
変な話だがそれからもういちどはがきを裏返してから気がついた。見返り美人図みたいな構図の、サリーを着たインド風の女の子の写真の下の余白に、おやじのボールペンの字で書いてあった。〈結婚します。たまに日本に帰るようにします〉
会社はいわゆる体育会系の会社だった。ネットではブラック企業と書かれることもあるのだが、同期のほとんどが現場や営業にまわされる中で、なぜか配属されたのは本社の経理部だった。他の部署にくらべてずいぶんゆったりした雰囲気の部署で、研修中になにか粗相でもあっただろうかと考えたのだが、思い当たるふしもなく、ほかの部署ではやめていく新人もいるなかで、そのゆるさを享受していた。新入社員が有給取得はおろか、正月休みさえもらえそうにない会社の中で、やけに新入社員に理解がある部長と次長がそろったおかげで、おやじの事情について申し出ると、意外なほどあっさり年末年始に7日間の休みをとれた。さすがに教育係は7日間は非常識だとしぶっていたが、「まあ、楽しんでこいよ」と送り出してくれた。
羽田空港発、インドのデリー乗り換えでカトマンズ空港に到着すると、そこはもうあっけないほどにネパールだった。
タクシーカウンターにむかっていくと、ほりの深い、がインド人ほどはほりが深くない、小顔で目と目のあいだがせまい感じの顔をしたネパール人の男たちがわらわらと寄ってきて、英語で何か話しかけてきた。何を言っているのかまったく聞き取れないので、ロシア語のつもりで「タクシ」言うとタクシーカウンターはここだとまわりのネパール人たちがいっせいにカウンターのほうを手のひらで示した。正規のタクシーカウンターのようだった。
「カトマンズの中心街にいきたい。タメル地区あたりで降りたい。どのくらいお金がかかるか」
日本語以外にまともにしゃべれることばが日常会話程度のロシア語しかないので、すくなくとも日本語よりは通じそうなロシア語をしゃべってみるのだがやはり通じず、が、「カトマンズ」「タメル」で通じたらしく、タクシーに案内されて、20分もしないうちにタメル地区についた。
「スパシーバ」
言うと、「シエシエ」タクシーの運転手に中国語で返された。
「ニエット。ヤポンスキ」
「シエシエ」
タクシーの運転手は言った。
タメル地区で一泊して、翌日、宿で手配してもらったポカラ行きのバスに乗りこんだ。バスの中で、おれは父が結婚したというネパール人の新しい奥さんのことを考えていた。おやじからうけた電話によると、2年前、横浜の関内にある友人の医院で働いているとき、同僚とランチを食べにネパールカレー屋にいったら、そこにカレーを食べにきていたネパール大使館で働くネパール人とアメリカ人のハーフのネパール人女性と知り合い、結婚して、今はネパールにいるということだった。
おやじから渡された住所をネットで検索したら、ポカラの、外国人向けの一等住宅地の一画が出てきた。
窓の外を見ながら、スマホでレゲエをきいていた。母さんが死んだのは中学2年生のときだった。中学1年生のときに母さんが家を出ていき、出ていった先でクレーンを扱う仕事をしていて、工事中の事故であっけなく死んだ。母さんをいちどもうらみに思わなかったのは、おやじが母さんをずっと好きでいたからだ。
エプロンをかけ、朝夕の料理を出し、洗濯をし、床をぞうきんがけするおやじは、母さんが死ぬ前も、死んだあとも、母さんを好きだといつも言った。周りの人がどう言おうと、父さんは母さんが好きなのだと。
道は舗装されているようで舗装されていなかった。アスファルトの上を走っているようで、ところどころ穴が開いているのか、ぽこぽこ音を立てながらバスは走行し、バスの窓に身をもたせかけていると座席がういたりしずんだりしてガラスが頭にぶつかった。窓ガラスの向こう側では茶色い砂ぼこりが霧のようにたっていた。カトマンズからポカラまで3時間はかかるということだった。のりこむとき、バスの運転手にロシア語でそうきいたら、ネパール語と英語で何か言われ、わからなかったので時計の針を3時間ぶんうごかして見せると、むこうも自分の時計を指さしてうなずいたので、3時間かかるとわかったのだ。
目をつむって、おやじが「ナマステー」と言っているところを思いうかべてみた。それからあのガムか何かをかんでいるような、内にこもった発音のネパール語をおやじがしゃべっているところを思いうかべてみた。
車内のスピーカーからネパール語のポップスらしい音楽が大音量でながれはじめ、おれはイヤホンを外してレゲエをきくのをやめた。それから見返り美人風のサリーをきた女性と、あと4ヶ月で産まれてくるらしい23歳年下の弟について考えた。
なぜだかわからないが、ネパール語でなくてロシア語でよかったのだ、という気がした。そのときになってようやく、学校で選んだロシア語や、全国チェーンのレストランの会社でよかったのだと思った。
「ロミオとジュリエット」 山田菜々瑚
仕事の有休をもらって、二日の休みを貰った。グリーンイグアナのロミオが死んだ。10歳だった。電話口で何を話したかわからない。ただいつも厳しい上司が「大丈夫、こっちはいいから。ゆっくり休んで」と言ったのはなんとなく覚えていた。家のベランダで、ロミオを膝に乗せて、煙草をふかす。大学の頃、しょうもない友達とつるんでいる時だけキャンパスで煙草を吸っていたが、それ以来だった。よくまだ携帯式灰皿など捨てずに持っていたなと呟きながら、固くなったその尻尾に触れる。……やっぱり、生きていなかった。気がつけば煙草の空き箱が風に飛ばされて下に落ちていった。ロミオをソファーに眠らせて、ブランケットをかけて拾いに行く。
「どうして死んじゃったの、ロミオ」
自分の部屋の扉がギィ、と鳴った。
煙草の空き箱をアパートの前のゴミ箱に捨て、ふと上を見上げる。武蔵小金井の14畳ワンルーム、トイレ・バス別、三階でオートロック。一人暮らしにしては広いが、それはロミオ以外、趣味も何もなかったから。……次に引っ越すなら、1LDKでもいいかもしれない。くだらないことを思いながら、自分の部屋へと引き返す。
「カラン」
ふと、自分の後ろでアスファルトに何かがぶつかった音がした。どっかの部屋から何かが落ちてきたのかと振り返ると、自分の携帯灰皿が転がっている。反射的に三階を見上げる。自分の部屋のはずのベランダに、小学生くらいの男の子がいるのを確認すると、何か言葉を投げかけるでもなく、オートロックの扉をさっさと通り抜けて走った。
自分の悪い癖なのだが、焦ると思考が全部止まる。よって、今回もエレベーターが一階で止まったままだったのにも関わらず、三階まで何故か階段を使った。扉の前でいったん深呼吸をして、いざ、とドアノブに手をかけたところで、ドアがガチャンと乱暴な音で開いた。
「あ、お姉さん。待ってたよ」
子どもは我が物顔で玄関に居た。思わずその肩を掴んで揺らす。
「ボクさぁ、ここ人のお家だよ?どうやって入ったの?」
「お姉さん、ドア」
振り向くと、自分のスニーカーが挟まって、ドアが閉まりきっていなかった。
「僕いつも見てるけど、お姉さん、ドアちゃんと閉まるまで見てないよね。それ危ない人が知ったら、オートロックでも後ろ付けて部屋まで入ってくるから気をつけなきゃ」
自分の4分の1ほどの年齢の子どもに注意されて、赤面しながらスニーカーを靴箱にしまう。子どもはうんうん、と満足げに頷いたら、すぐに部屋の中へと走って行った。
「それで君、どこの部屋? 早く戻らないとお母さん探し回っちゃうでしょ」
「僕、ここの人じゃないよ、あそこから来たんだ」
窓を開け、身を乗り出して空を指さす。その指は、確実に嘘をついていないように見えた。
「……空?」
子どもが大きくうなずく。唖然とする私をよそに、ロミオを撫でた子どもは、そのまっすぐな目で変色の始まる亡骸を見つめた。
「この子、お姉さんのお友達?」
「そうだよ」
「へぇ。お名前は?」
「……」
「ないの?」
「……ロミオ」
ふぅん、と自分で聞いておいたくせに興味の無さそうな顔をして、子どもは私に近づいた。
「じゃあお姉さん、『マクベス』、知ってるよね?」
「……そりゃあ、まぁ」
子どもは答えを待って、ポケットを漁る。取り出したのが1枚の金貨――コインか?おもちゃかと思ったが、よく見るとそれはしっかり重さがありそうだった。
「これ、本物の金貨。おじいちゃんから貰ったんだ。……これを、首に乗せたらどうなるか―――シェイクスピアが好きなお姉さんならわかってるでしょ?」
一瞬にして遅くなっていた血の巡りが速くなった。この子、何歳だ?明らかに小学生だ。なのに、シェイクスピアを読んで、しかもイングランド王の「王の病」まで理解して、挙げ句の果てに本物の金貨。……私もちゃんと覚えていないが、確かマクベスの対比として書かれたイングランド王は、医者もさじを投げるほどの重病患者の首に一枚金貨を乗せ、念を込めるとたちまちそれを治してしまうと言われていたのだ。
「君、もしかして――」
子どもはコインを投げる。それをしっかりその小さな右手で受け止め、笑う。脳のどこかがはっきり活発化しているのがわかる。
「ロミオくん、僕なら“治せる”よ」
不適にその子は笑う。キラリと光る金貨が、説得力を生む。
「でも、死んだ命を吹き返すなんて、そんなの――」
「“禁忌”だって言いたいの?」
ソファーの上からロミオのしっぽが覗く。少し変色が始まって、しっぽの先だけ茶色くなっていた。
「女の子がイグアナなんて、ってたくさん笑われたよね。それで近所にはペットがイグアナなんて言わなくなったし、好きだった彼氏もイグアナ見て怖がって逃げ帰ったよね」
真実しか語らないその口を、思わず塞ぎそうになる。すんでの所で押さえ、今度はその目を見る。全てを見抜いているよ、と言われている心地がして、足が震える。その子はロミオを抱き上げて私に差し出す。ロミオの変色が、どんどん鮮やかだった緑を消していく。
「どうする?……樹里さん」
鼓動の音が、自分の耳にまで訴えかける。名乗っていないのに、どうして?そもそもイグアナを飼っているなんて、どこで知った?どうやって知った?――緊張?焦り?恐怖?この感情が何であるかもわからないが、きっと神様を直視した人間は、こうなってしまうのだろう。うるさい心臓の音に耳を塞ぎ、必死に答える。
「私は、ロミオと――」
言いかけた言葉は、ガチャンとドアが開く音と、誰かが名前を呼ぶ声で消えた。
その後、その子どもは突如現れた母親に腕をひっぱられて連れて行かれた。数分後、その母親はちゃんとピンポンを押して丁寧に謝罪しに来た。あの子はまだ小学三年生で、虚言癖が酷く、同じアパートの住民を観察したり、うろうろ廊下を回って話し声を聞いたりして、気になることがあったら勝手に入り込んであれこれ言ってしまうらしい。その際は金貨を持って行って、自分は命を吹き返せるのだと決まって言うという。私はどこの子かも確認せず申し訳なかった、こちらは迷惑していないし、むしろペットの死でとても沈んでいたけどちょっと心が軽くなったから助かったとお伝えして、扉をギィと閉めた。……しっかり鍵も閉めて。
部屋の扉を開け、ソファーで安らかに眠るロミオに寄り添う。その亡骸を撫でながら、うとうとと眠りにつく。色々と疲れていたのかもしれない。――私がソファーの隙間に落ちた金貨と、ロミオの変色が少し戻っているのに気がつくのは、目が覚めて、また少し経ってからの話である。
「マクベスと魔女」 もこ
マクベスに登場する3人の魔女たちは不思議な言葉をたくさん発している。
「きれいは汚い、汚いはきれい」
「戦いに負けて勝ったとき」
といったように矛盾を孕んだ発言が多くみられる。一見すると意味がわからないけれど、マクベスを読んでいるとなんとなくわかってくるような気がする。マクベスのターニングポイントに居合わせる異形の魔女たちはマクベスの心に巣食う葛藤なのではないかと私は考える。そして、魔女から発せられる予言はマクベスの野心そのものであり、誰かに背中を押してもらいたかったのではないだろうか。
マクベスは予言に呑み込まれて多くのものを失うが、頑なに予言を信じている。野心に囚われ大切な友人や慕っていた王、そして妻を失っても。結果マクベスは予言通り森が動き、女の股から生まれていない者に命を奪われることになるが心のどこかで呪縛から解き放たれることを望んでいたのではないだろうか。王を殺めたとき、血に汚れた己の手を見て心のきれいなマクベスはこんなことを続けていられないと思ったから新たな予言を求めたのではないだろうか。王になれたとしても自分の決断が国民の命を握るという重圧は耐えがたいものだろう。だから他者の予言によって自分の正当性を保っていたかったのではないだろうかと思う。そして自らの手を汚すことなくきれいなままでいた妻は、王を殺す際にも躊躇いはなく、夫のためならどんな手も尽くす芯のある女性だった。結果として自分の手が汚れて見える幻覚にとらわれ亡くなってしまう。非情な妻だがマクベスとの関係は良好で、美しくもあり恐ろしい存在であったことだろう。きれいは汚い、汚いはきれいという言葉はマクベスの中では納得のいくものだったと感じる。
罪の意識や野心に苛まれ、予言と運命に翻弄されたマクベス。彼の中に巣食う葛藤に打ち勝ち、予言という形で背中を押され続けてきた彼であったが、森が動くはずがない、女の股から生まれぬ人間などいないと驕りを見せた彼の油断により命を落とす。自信は必要なものであるけれど、過度な自信は驕りを呼ぶ。3人の魔女の中にいる、驕りの魔女に負けてしまったのだろう。彼が魔女と決別するには命を落とすほかなかった。魔女が死ねば彼が死ぬし、彼が死ねば魔女も死ぬ。予言を聞いて自分に勝てるものはいないのだと葛藤することなく思考停止することで魔女の役目はなくなったのだ。だから彼は死んでしまったのだと私は感じた。睡眠は葛藤と引き換えに手に入る成功の代償だったのだ。しかし彼は葛藤することをやめてしまった。だから永遠の眠りを手に入れた。矛盾のように思える言葉たちは全てメビウスの輪のようにつながっていて、回り回っている。だから私たちは思考することを止めてはならない。優しくすることだけを考えていては優しくはなれない。優しくないことが裏側にあるから人は優しさに気づくことができるし、優しく振る舞うことができる。常に一方からではなく他方から物事と対峙しなければ森は動くし、魔女は消える。魔女はマクベス自身が産んだものなのだ。女の股から生まれていない異形の魔女にこそマクベスは敗れたのだと思う。もちろん、心の中に魔女を飼うことは悪いことではないと思うけれど、きれいに育てて一生を共にする覚悟でいなければならないだろう。異形であることからわかるように、マクベスは魔女を上手に育てることができなかったのだ。私たちは日々自分に降りかかる様々なこととまっすぐ向き合い、魔女に打ち勝ち続けていかなければならない。
「都合の良いマクベス」 N
「やったね。よし寝るか」
私がマクベスの世界観で、王になるなどの予言をもらったらこう言うでしょう。物語を読むときに、自分だったらこうするなあ、と自分を主人公に当てはめることをよくします。今回の作品では、自分だったらまず、予言をもらった時点で何もしなくなると思います。ここで疑問に思ったのはどうしてマクベスがあんなにも必死に予言を叶えようとしたのか、です。現代日本における予言者の権力は、マクベスの世界とは比べものにならないくらいに弱いものです。むしろ怪しまれる存在でもあるくらい。マクベスの世界では、宗教の背景もあり、予言者の言うことは必ず起こると信じるはずです。そう思うので予言をもらったら、絶対に真実になるから怠惰になるに違いない。(死ぬという予言なら抗うかもしれません。)しかし、予言を絶対だと信じているはずのマクベスや夫人は自分から行動を起こします。いくら予言通りになるか危ういと思っても、この世界観の中では予言の絶対性を信じると思っていました。マクベスは次にもらった予言は固く信じていました。ああこういう事ってあるなと。都合のいいように捉えて信じる様は現代の私たちと同じです。
都合よく捉えるというのは言い換えるとポジティブに考える、ということです。自らの悲劇をポジティブに考えて、結果裏切られたマクベスですが、私はこのマクベスが自分と似ているように感じてしまいます。自覚していたわけではありませんが、私はここ最近、周りの人たちをみて、自分はポジティブな方なのではと思うようになりました。私が臨床心理学科を専攻した理由は、心の病にかかる人の考えや気持ちを理解したかったからです。臨床心理学を志した後の話ですが、友人によく学校を休んだりする人がいて、カウンセリングなどは受けていないようでしたが、よく病むと口にしていました。どうしてか尋ねても漠然としてよくわからない、と言います。ある日その友人に、「Nは絶対病まないよね、羨ましい」と言われ、私は彼女の気持ちを理解できないのだと思いました。そこから私と彼女との違いを考え、おそらく物事の捉え方が違うのだという結論が出たのです。例えば、よくある話ですが、高校三年生のとき、彼女がE判定で落ち込んでいたので「私もEだった。Eでも受かった人はいるよ」と言うと「Aで落ちる人もいるよ」と返されてしまいました。私と彼女の考え方の違いがよくわかる場面です。単純にいえば彼女はネガティブで、私はポジティブ、今でも仲が良いですが、よく友達になったなあと思います。ポジティブに考える私はポジティブな自分が好きです。大学だって彼女には妥協だと言われそうですが、自分は臨床心理学が学びたかったので、むしろ第一志望の心理学科でなくて良かったと思っています。第一志望だったら今頃一般教養しか学ばせてくれなかったでしょう。ずっと大学に納得していなかったら学ぶ気力まで失われてしまいそうです。ポジティブなのが一筋に良い、とは言いきれませんが、こうやって生きていくのが私には合っています。だからこそあの都合の良いマクベスに親しみをもったのだと思います。私にとってこの物語はマクベスや夫人の貪欲さより、最期のポジティブマクベスが印象強いのです。
「アンチの君へ的な」 とろろ
宮崎あおいが出演していたCMで流れていた「ドブネズミみたいに美しくなりたい、写真には写らない美しさがあるから」という歌詞がいつまでも私の心をつかんで離さない。私は美しくなれるのだろうか。美しくなりたい、という気持ちはずっとずっとあるはずなのだ。中高一貫の女子校に通い、音大に推薦で合格した。何が嫌なのか分からないけど全部がくだらなくてよく家出をした。下着の色まで指定されてそれを呑む人生何なのだろう。Twitterでよく見るアイドルはブスって批判されていた。好きなアーティストはメンヘラの神って言われていた。痴漢はされる方も悪いんだって知った。あなたの娘が、大切な女性が、痴漢されても同じこと言えるの? って言うやつウザイ。娘とか大切な女性がいなかったら痴漢しても許されるのかよ。今の若者は本物の音楽を知らないんだってAKB48を批判してる人がいた。山口百恵は神だと言っていた。ネットに一喜一憂するなって言われてもしょうがないじゃん。ネットが居場所なんだ。アイドルになりたかったからTwitterに自撮り載せたらアンチができた。ブスなんだってさ。金持ちアピうざいんだってさ。確かに経済的に不自由したことないし、音大にも通わせてもらえているけど私の環境に生まれたのは私なんだからしょうがないよね。発達には遺伝も関係しているらしいよ。その時点で君とは結果が違うの。もちろん環境が大きいけど、私の才能は私のものだし。ってか私も自分のことブスだと思うよ。鏡かち割りたいって思うこともあれば、世界で一番かわいい天才って思うこともあるし。めんどくさいよね。ドブネズミが美しいって思えるように私もなりたい。そんな素敵な人になりたい。桜は満開のときより散るときのほうが美しいよね、情緒を感じるよねって言いたい。でもどう考えてもドブネズミは汚いし無理だし、桜は満開のほうがきれい。何が嫌なのか、というか全部が嫌なのかもしれないけど、無意味に人生に絶望してしまう。音大へ行ったとしてもその道に進むわけでもなく、音楽教室の先生をやるか会社員になって生きていくのだ。その中でやりがいが見つかるのだろうか、好きな人と結婚してかわいい子どもでも育てるのだろうか。世の中の人はいつ向こう側に行くのだろうか。私もできることならここに留まりたいけど、いつか行くことになるのだろうな。シェイクスピアが書いたマクベスに出てくる魔女は、私そのものだし君そのものだ。気づいているだけ私のほうがマシかも。それでも結果が変わらないのだから、どのような思いで殺そうが、後悔しようが、殺人という罪は変わらないのと同じで。君の美しいの定義は何かな。君はしょせん誰かの美しいを借りて私を批判しているに違いない。自分の言葉も話せないなんて、ママのお腹からやり直したらどうかな。女の股から生まれた君には負けないし、お腹を破って生まれてから話そうね。もしお腹を破って生まれているなら良かった。早く済むよ。私と君は一騎打ちして両方すぐに死ぬことになる。なんだがアンチの君にあてた手紙みたいになっちゃったな。これってきっと明日の昼に読んだら死にたくなるやつだわ。まあ誰に見せるわけじゃないから良いよね。
「高慢と偏見」 Y
『「いっけな〜い! 遅刻遅刻!」 私、別井真希、高校2年生! 朝から知らない男の子にぶつかっちゃった! と思ったらすっごいイケメン! 彼は手を差し伸べてくれるけど……「私、帝王切開の人としか結ばれない運命なんです……」凍りつく空気、校内に知れ渡る私の“帝王切開フェチ”! 私の学園生活、どうなっちゃうの〜!?!?』
シナリオのメモを見ている教授の顔が、強張るのがわかる。さすがに攻めすぎたかと反省したが、顔色伺って引っ込めるような漫画は描くなという教授のセリフを思い出した。
「なぜ帝王切開で生まれた人としか結ばれないの?」
当然の疑問である。
「ええっと、最初に魔女が出てきて真希にお告げを言うんです……あったあった」
中高年である教授のためにわざわざ印刷した、紙媒体の原稿を慌てて探し出して、教授に手渡す。
『お前は女の股から生まれた者と結ばれることはない』
教授は顔の皺を更に深くして、うーんと唸った。通知音が鳴って、自分のガラケーを一瞥したあと、静かに乾いた口を開いた。
「でもこういうのって、最近うるさいからねえ。聞く所によると、自然分娩で出産した女性は帝王切開で出産した女性に対して、“陣痛を経験してない母親は親の自覚がない”っていう偏見があったり、“帝王切開はお産じゃない”って差別したりすることもあるらしい……そういった差別や偏見に加担しているとか、帝王切開を笑い者にしていると受け取られるかもしれない」
自分の顔が強張るのがわかった。
「差別や偏見に加担しているわけではないです。こっちを読んでください」
食い気味に反応して、別のシナリオメモを渡す。これは偏見を助長する話ではない。魔女からお告げで、「女の股から生まれた者とは結ばれない」と聞いた真希は、一生誰とも結ばれないのだと早とちりする。あとになって、お腹から生まれる、帝王切開で生まれた人となら恋することができると気づく。けど男の子に自然分娩で生まれたか帝王切開で生まれたか聞くことの難しさ、デリケートな話題に触れられない距離感に苦悩する……ふざけた設定に反して示唆に富む話なんだよな。
「君の熱量は伝わってくるけどねぇ」
2人しかいない夕方の教室の、打ちっぱなしの壁に沈黙が染み込んでいく。
「あんまりこういう繊細な話題は触れないのが良いと思うなあ。サークルで出版するものならなおさら」
歳を取ると保守的になるものなのか。私の内にはそういう汚い猜疑心が湧き上がってしまった。
「私がイケメンとかお金持ちと結婚したいって言ったら差別だと思いますか?」
「そういう考えを持っているのはおかしいことじゃない、と思うかな」
「じゃあ私が自然分娩で生まれた人と結婚したいって言ったらどう思いますか?」
「やっぱり美大に入る人は変わってる人多いなあって思う」
そっちの方が偏見じゃないのか。
「私がイケメンと結婚したいって言うのと、自然分娩で生まれた人と結婚したいって言うのと何が違うんですか?」
勢いに任せてまくし立てたせいで、唇を潤していたリップの味がほのかに口内に広がっていく。面倒くさいことになったなと言わんばかりに教授は、左手で後頭部を掻きながらうーんと唸った。
「それが差別かどうかなんて、どうでもいいんだよ」
「どういうことですか?」
教授はさっきよりも困ったような顔をした。
「あのねえ……社会が差別だと判定すれば差別だし、過半数が偏見だと思えば偏見だし、みんなが間違ってる言ったら間違ってるんだよ。本当は差別じゃないとか偏見じゃないとかは、関係ない」
「そんなの、不健全なことだと思います」
教授は諦めたような顔をしだした。
「僕もそう思うけど、これはどうしようもならないんだ」
表現がそんな社会に屈していいのか? 本当に正しいことを貫いてこそ表現じゃないのか? やっぱり教授という地位に一度座ると冒険したくなくなるのだなと思い、私も諦めたような顔をしていた。
「わかりました。ご指導いただきありがとうございます」
原稿をバッグに押し込んで、失礼しますと言って教室を出た。スマートフォンを操作しながら速歩きで外へ向かう。誰もいない、暗い廊下の壁に足音が反響する。アプリのグループに、pdfファイルを投下して、メッセージを打つ。
『問題ないとのことでした。このまま進めてください。』
勝負にでなければ結果は得られないのだと、教授にわからせてやろうと決意して、私は紙の原稿を廊下のゴミ箱に突っ込んだ。
< 9「絵本」か「コミック」 | 11「コロナの時代のわたしたち」 >
