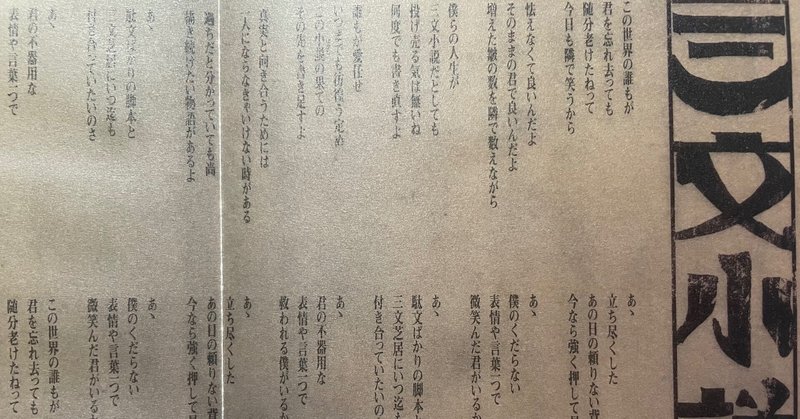
『三文小説』 vol.2【小説】
これは、三文小説。
枕詞は「あなたは知らないだろうけど、」 で始まる物語。
―――高橋映子、の場合―――
「あなたは知らないだろうけど、ね」
さっきまで、トリアノンの喫茶室で、鶴崎に叱られていたことなど、すっかり忘れた顔で、映子は、美夏の右腕につかまりながら、歩いている。
11月とは思えない、汗ばむような陽気だ。
今日の、支援内容は、買い物同行と、リハビリを兼ねた、散歩の付き添いのはずだった。朝九時に、高橋コーポの正面玄関の、ベルを押した。
返事はなし。なんどか押してみて、
「高橋さーん、映子さーん、スマイルサポート
でーす。お約束の時間ですぅ」
と声を上げたが、中に人がいる気配はない。
と、上の階の窓が開いて、頭にカーラーを巻いた女性が、洗濯物を干しながら、
「大家さんなら、さっき出かけましたよ、お姉
さんと。二人とも、杖ついて」
へっ? 今日はリハビリの約束じゃん、とスマホを確認し、すぐに鶴崎に連絡する。
「またか~、いつもすっぽかしてぇ、ったく、
あの二人は!」
電話口で、憤った鶴崎が、
「高木さん、ちょっと悪いけど、駅前のトリア
ノン、見てくれる? あそこのモーニング行
ってる可能性、高いわ。
わたしも今、事務所出るところだから、寄り
ます」
案の定、トリアノンのオレンジ色のイスに、嬉しそうに並んで座る、高橋姉妹を発見した。美夏が店に入ると、
「あら~、ヘルパーさんじゃないのぉ、奇遇ね
え」
と映子が、手招きするようにして、笑った。
「奇遇って…、高橋さん、今日はお買い物と、
リハビリの日ですよ」
あら~すっかり忘れてた、天気も良いしねえ、モーニング食べに来ちゃった、ねえ~と肩をすくめ、姉の芳子と、顔を見合わせて、また笑う。
てか、この感じ、女子高生かよ、生徒指導の教師になったような気持ちで、美夏も呆れていると、後ろから、
「こら~高橋さん! ケアの日には、家にいろ
って、言ったでしょ」
と、鶴崎が、ずんずん店内を進みながら、言った。
「だってぇ、天気も良いしさぁ。ま、いいじゃ
ない、ここで会えたんだし」
しれ~っと答える映子に、鶴崎もぶつくさ言いながら、
「とにかく、今から時間内に、買い物と、歩い
てうちまで帰ってもらいます、いいですね。
高木さん、あと、頼んだわよ」
「はあ~い、すいましぇ〜ん」
姉妹は、大げさに反省して見せると、女子トークに戻っていった。
「昔はね、純情商店街、なんて名前じゃなかっ
たのよ。高円寺銀座どおり。純情なんて、小
っ恥ずかしくて、言いにくいじゃない?
でも、今も、たいてい何でも売ってるのは、
ありがたいね。
あたしたちは、ヘビ屋って呼んでたけど、昔
は、なんの肉売ってるか、分からない肉屋が
あったりしてさ、店の前に、ヘビがいっぱい
入ってる籠があって・・・」
美夏の右腕に、つかまりながら、一歩一歩、確かめるように、歩く。
買い物だろうが、銭湯だろうが、一緒に歩くたび、いつも同じ、高円寺の昔ばなしをしてくれる。
それを美夏も、毎回、初めて聞くように、楽しんで聞く。
それは、本当だった。
高橋姉妹を訪れるようになって、一年近く経つが、その間、美夏にも、いろいろあった。
この仕事をするようになって、毎回、同じ昔ばなしに、その変わらない何かに、人は安心するのではないか、と思うようになった。
美夏にはもう、両親も、田舎もないが、もし帰るべき故郷があったら、帰省すると、こんな気持ちになるのかもしれない。
姉の芳子は、映子に輪をかけて、陽気な毒舌家で、美夏的には、かなりパンクな存在だった。高血圧で、血糖値も悪いのに、食欲旺盛で、なかでも、
「魚政の銀ダラの西京漬けが、食べられないな
ら、あたしゃ死ぬよ」
と、本当に食べ続け、近所の総合病院に、緊急搬送されるたび、叱られている。
芳子は、姉妹が「ヤブ北」と呼ぶ、その病院に、明日から、また入院することになっていた。お天気が良いからモーニング、などと言っている場合じゃないのだ。
ヤブ…じゃない、山北病院には、もう何度も入っているが、今度ばかりは、帰れないかも知れない、そんな予感を、美夏も拭えないほど、芳子の顔色は、悪く、むくみもひどい。今朝も、駅前まで、よく歩く気になったものだ。
だが、美夏には、二人の気持ちも、よく分かった。
高野青果で、姉の好きな、安納芋の焼き芋を買い、中通りに入って歩きながら、映子は、いつもの昔語りを、今日はあまり話さない。
もう帰れない…、その不安は、きっと、二人の中で、日に日に、大きくなっている。
翌日、予定どおり入院。
その後、容態は急激に悪化し、それでも最後まで、タラの西京漬けを出せと、悪態をつきながら、芳子は旅立った。
姉の四十九日が過ぎるころ、映子のリハビリが、再開した。
久しぶりに会う映子は、ひと回り小さくなったようだった。
美夏は、芳子の仏壇に、香典代わりの、好物だった紅玉を供え、手を合わせた。
あんた、気が利くねぇ、満足げに笑う、懐かしい芳子の声が、聞こえるような気がした。
「昔はねぇ、ここいらの銭湯ったって、ドブ川
みたいに、汚かったのよ。そんな湯に、赤ん
坊もパンパンも、みんな浸かって、生きてき
たんだから。
姉さんとあたしで、焼け残った親の家に、赤
線の女たちと身寄せ合って…。
みんな、きれいな湯屋になってねぇ。
こないだなんか、湯船でとなりに腰かけて
た、若い娘さんがさ、写真撮らせてくださ
い、って。
いやだ、裸じゃないわよぉ。
もう小杉湯に、七十年以上、通ってるって言
ったら、その娘、びっくりしちゃって。いん
すた?に載せても良いですかって、なにが珍
しいんだかね」
買い物同行の仕事を済ませ、これから銭湯に行くという映子と、庚申通りを歩きながら、小杉湯の前で別れた。
「芳子姉さんの、背中、もう一度、流してあげ
たかったわ・・・昔から、ほんとに真っ白
で、きれいな肌してた。あたしが男だった
ら、放っておかないくらい」
映子とは、それが最後になった。
翌日、家賃を収めに来た、二階の女性が発見したときには、息が無かったそうだ。
こたつの上には、きれいに剥かれた紅玉が、二つのお皿に、載っていた。
せっかちな芳子に、いいから、あんたも早く、りんご持って、あの世に来いと、急かされたのかも知れない。
https://open.spotify.com/track/7BMKWT0Vw0EKDELXLvuWCp?si=q3ZVWvt6TIGpVuEfYBZxpg
(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
