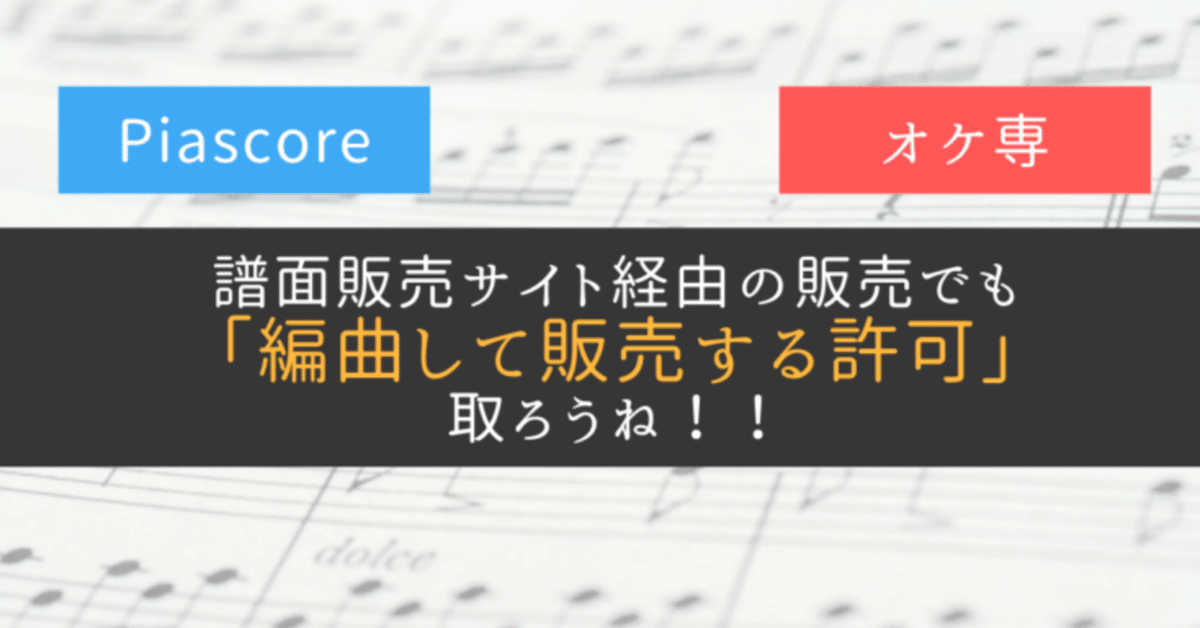
【譜面を販売したい人向け】譜面販売サイト経由の販売でも「編曲して販売する許可」は取ろうね!!
こんにちは。
ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
粍井です。
私は、音楽の趣味が高じて、譜面作成・販売活動をしています。
作った譜面を掲載して、購入いただけたら、販売料金の何割かが入ってくるというシステムです。
実際私も、たまにではありますが購入いただけているため、「耳コピ能力を使って趣味と実益を兼ねたい」という方には、おすすめの活動です。
で、現在私は、「Piascore(ピアスコア)」と「オケ専」の2つのサイト上で譜面を販売しています。
「あの曲をあの編成で演奏したらいい感じかも」とか妄想しながら編曲するのが楽しくて。
譜面を書ける方の中には、「譜面販売してお小遣い稼ぎしようかな。」という方もいらっしゃるんではないでしょうか。
完全に個人で販売するとなると、著作権管理団体(JASRACやNexTone)や各音楽出版社と、著作権(楽曲利用許諾)関連の色々なやり取りをしないといけません。
※著作権が切れている楽曲を編曲する場合は、著作権(楽曲利用許諾)関連のやり取りは発生しません。
しかし、先程紹介したような譜面販売サイトを経由した販売だと、その辺の面倒なやり取りを代行してくれるというのが大きな利点。
とはいえ、販売者自身で著作権について確認しなければならない事項もあるのです。
それが、「楽曲権利者から編曲・販売許諾を得なければならない」というケースです。
実際私は…
譜面販売サイト経由なら、楽曲権利者とのやり取りなんて要らないんじゃないの!?
え、要るの?何でよー!
なんて思ってたことがあったので、同じような疑問を持つ方の助けになるよう、今回の記事を書きました。
※今回の記事は、「著作権管理団体の管理下にある楽曲の編曲・譜面販売」についてのお話です。
(自作曲や著作権切れの曲は関係ありません。)
著作権管理団体とは?
本題に入る前に、この手の話で必ず登場する、著作権管理団体(JASRACやNexTone)について確認してみましょう。
まずはJASRAC。
著作権使用料の記述を引用しました。
JASRACは、膨大な数の管理楽曲をデータベース化し、演奏、放送、録音、ネット配信などさまざまな形で利用される音楽について、利用者の方が簡単な手続きと適正な料金で著作権の手続きができる窓口となっています。
お支払いいただいた使用料は、作詞者・作曲者・音楽出版者など権利を委託された方に定期的に分配しています。
続いてNexTone。
こちらも、著作権使用料の記述を引用しました。
著作権者からの委託を受け、音楽著作物の利用の許諾と使用料の徴収・分配を行っています。
一応、Wikipediaからも引用。
「著作物を使用する様々な個人や集団」には、もちろん譜面販売者も含まれます。
また、「著作権者」は、JASRACの記述には明記されている通りですが、その原曲の著作権を持っている作曲者・作詞者・音楽出版社などです。「楽曲権利者」と言われることもあります。
そのため、
「著作権管理団体は、譜面販売者から各楽曲権利者に支払うべき著作権使用料を、代わりに一括で徴収してくれる。」
と、噛み砕くことができます。
なお、既存曲の譜面を作って販売する時点で、著作権使用料は発生しているので、たとえ1つも売れてないとしても、お支払いはしないといけません。
これは辛い!!
著作権料支払いの救世主:譜面販売サイト
「1つも売れないとしても著作権料はお支払いしないといけない」
こんな辛い状況を助けてくれるのが、譜面販売サイト。
こういうサイトのこと。
(冒頭でご紹介したのも含みます)
サイト側が一括で、著作権管理団体に著作権料を払ってくれるんです!
(その他色んな手続きを代行してくれます。)
その代わり、譜面が売れたらその都度手数料が引かれるという仕組みです。
つまり、譜面販売サイトで販売すれば、
著作権料の支払い手続きは不要。
譜面が売れたら手数料をひかれた分が収益になる。
ということです。
なので、譜面販売サイトで販売すれば、権利関係の面倒な手続きは不要…。
と思ったら、そんなことはありませんでした。
「著作権料の支払い」とは別で、もう一段階、「楽曲利用許諾」を取らなければいけないのです!
「著作権」の問題はクリアしてるのに!!
楽曲権利者に別途利用許諾を取らないといけない理由
それはなぜかと言いますと。
譜面販売サイトは、著作権管理団体と契約して、著作権についての問題をクリアしていってくれています。
なので、譜面販売サイトで販売すれば、著作権に関しては気にしなくていいわけです。
しかし!
「編曲した譜面を販売する」には、著作権問題のクリアだけでは足りないのです。
JASRACのサイトに、こんな記述があります。
なお、JASRACでは編曲権・翻案権の譲渡を受けていないため、編曲することなどについて許諾することはできません。
そんな訳で、「編曲して販売」の許可については、楽曲権利者に直接お伺いしないといけないわけですねー。
実際、譜面販売サイトにもその旨が書かれています。
クリエイターズ・スコアは…、少なくともホームページではそういう記載を見つけられなかったんですが、念の為問い合わせしてみたら、やっぱり「編曲の許諾は自分で取ってね」ということでした。

なお、Piascoreについては、「一部の音楽出版社が管理する楽曲の利用許諾を、販売者の代わりにPiascoreが取ってあげるよ。」という「代理申請」を設けてくれています。
ジブリやディズニーも対象なのがありがたい限り。
全楽曲の代理申請をしてくれるともっと嬉しいですが、それはそれでかなり手間がかかります。
なので、基本的には販売者自身で楽曲利用許諾を取るものと思った方が無難です。
楽曲権利者から編曲・販売の許諾を得てみよう
ここからは、実際に編曲・販売の許諾を得る流れについて、ざっくり説明していきます。
実際の細かな流れについては、各譜面販売サイトに書かれているので、ここでは大まかな手順のみ。
「配信」可能かどうか確認する
譜面を販売したり、参考音源をYouTubeに上げる(後述)には、JASRACやNexToneの作品データベース上で「配信」が許可されていないといけません。
楽曲を検索して、配信可能かどうか確認します。
参考音源を用意する
譜面販売時にどうせ必要になりますが、譜面の参考音源を用意しておきます。
譜面販売サイトにもよりますが、YouTubeが望ましいです。
私は、こんな感じで作ってます。
YouTubeであっても、楽曲そのものを載せるのはアウトです。
しかし、自身で演奏・作成した音源を載せるだけならOKだそうです。
(だから「歌ってみた」「演奏してみた」は、基本的にOK。)
楽曲権利者を特定する
先程利用した、JASRACやNexToneのデータベースで、楽曲権利者を確認します。
JASRACでは「出版者」が、NexToneでは「権利者」が該当します。
楽曲権利者に問い合わせる
楽曲権利者がわかったら、問い合わせをします。
ホームページの問い合わせフォームから問い合わせたり、メールアドレスを見つけ出して直接メールするなど、方法は様々です。
もしも電話で問い合わせることがあっても、最終的にはメールなどで、やり取りを形に残しておきましょう。
「言った言わない論争」の防止ももちろんですが、譜面販売サイトによっては、「楽曲利用許諾取得の証拠書類」を提出する必要があるからです。
私の場合は、こんな感じで問い合わせをしています。
突然のご連絡、失礼致します。
私、管弦楽・鍵盤系楽譜を作成・販売しております、〇〇と申します。
この度、【△△(作曲者)】さん作曲の【□□□□(楽曲名)】を、吹奏楽用の楽譜に編曲させていただきました。
参考音源:https://www.youtube.com/watch?v=××××××××××
編成:youtubeサムネイル記載の通り
こちらの参考音源の譜面を、掲載・販売しても問題ないか、ご確認いただけますでしょうか。
掲載及び販売先:https://×××××××
また、問題ない場合は、コピーライトの表記内容もお教えいただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
返事が来る
問い合わせの返事が来たら、それに応じて対応します。
単に「販売していいですよ」と返事をくれる所もあれば、専用書類の提出を求めるところもあります。
「販売しないで」と言われたり、そのまま返事が来ない場合は、大人しく引き下がりましょう。
私の場合、「販売しないで」と言われたことは無いのですが、そのまま返事が来ないところは結構あります。
なので、そういう曲に関しては、YouTubeの参考音源公開に留めています。
たまに督促するのはありかもしれませんが、そこは良識の範囲内で。
譜面販売手続きを済ませる
無事に楽曲利用許諾を得られたら、各サイトの手順に従って、譜面販売手続きを済ませましょう!
まとめ
著作権関連は、取り決めがあるとはいえグレーな部分や知られていないことも多くて、ややこしいですよね。
ただし結局のところ、「楽曲権利者が楽曲を勝手に使われる損害や不快感をなくすための取り決め」だと、個人的には思ってます。
その考えに従えば、然るべき手順を踏むのは当然ですよね。
多少面倒な手続きではありますが、楽曲に関わる全ての人(譜面販売者も含め)を守るため、定められた手続きを行うようにしましょう!
私もまだまだ勉強中の身なので、誤り等にお気づきの際は、ご指摘いただけると嬉しいです。
私自身も、誤りを見つけた場合は、順次修正していきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
