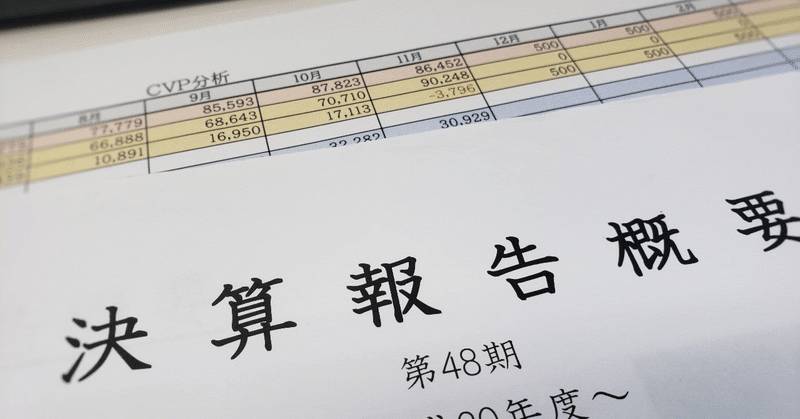
少しだけ税効果会計がわかったような気がします
【 自己紹介 】
プロフィールページはこちら
このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、600日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。
毎日ご覧くださってありがとうございます。本当に励みになっています。
法律に関する記事は既にたくさん書いていますので、興味のある方は、こちらにテーマ別で整理していますので、興味のあるテーマを選んでご覧ください。
【 今日のトピック:税効果会計 】
僕は今、来年(2022年)の8月に実施される公認会計士試験の論文式試験に合格することを目指しています。
まだまだ全く勉強が追いついていないので、本当は急ピッチで進めたいのですが、なかなか一朝一夕に必要な勉強すべてを終えられるものでもなく、毎日少しずつ、できる範囲で進めています。
司法試験合格者が公認会計士試験を受験する場合は、なんと、短答式試験を受けなくてパスすることができるので、僕は論文式試験のみに集中することができます。
だからといって、司法試験合格者が、受験で圧倒的に有利かというとそうではないと思っています。
というのも、司法試験に合格しているということは、その合格までに費やしたお金や時間を取り戻すべく、みんな一生懸命働いているわけで、わざわざ公認会計士試験に割くことができる時間なんて基本的に皆無です。
いくら司法試験に合格していても、公認会計士試験に求められる知識は全く別なので、きちんとゼロから勉強する必要があります。
普段の仕事で公認会計士試験合格に必要な知識が得られるわけもなく、なんというか、受験勉強の時間を捻出するのがとにかく大変です。
せっかく時間を捻出しても、その時間に自分が必ずしも勉強するわけでもなく、疲れ切った身体の思うままにダラダラしてしまうことがほとんどです・・・。
とまあ、こういった公認会計士試験受験生のリアルをお伝えするのも有意義だと(勝手に)思っているのですが、今回は、今日の受験勉強で学んだことを、少しだけ自分の復習のために書いてみようと思います。
タイトルのとおり、今日は、「税効果会計」について学びました。
この「税効果会計」は、簿記2級の勉強でも出てきました。
ただ、どうも、意味がわかりませんでした。何やっているか、ちんぷんかんぷんでした。
「どうもよくわからんなー」という思いを抱えたまま簿記2級の試験日を迎えました。今となっては、税効果会計が出題されたかされなかったすらよく覚えていませんが、少なくとも、税効果会計の知識・理解が合否を左右しなかったおかげで、僕は無事に簿記2級に合格しました。
今日勉強して、やっと、少しは何をやっているかわかりました。
なんというか、税効果会計って、その名のとおり、あくまで「会計」の処理なんです。
会計と税務って、かなり似通っているのですが、でも、根本の思想は異なっています。
「会計」は、株主に見せるもので、「株主自身が投入した(ベットした)お金がどう利益を生んでいるのか・どんな資産に変わっているか」を表すためのスキル・技法です。
だから、株主や、株主から経営を任された社長などの役員の視点に基づいて、作成方法も考えられています。
これに対し、税務の目的は、「課税」です。課税所得を割り出して、その課税所得に税率をかけて算出した税金を納付してもらうことが、税務の目標です。
課税所得を算出する際には、複式簿記という会計スキルを使うので、非常に似通っているのですが、ただ、会社でなく個人であれば、複式簿記ではなく単式簿記を使うこともOKなので、やっぱり、会計と税務ってイコールではないのです。
で、税務では、「租税法律主義」のもと、法律に基づいた公平・平等な課税が求められます。
こういった、会計と税務の性質の違いに起因して、会計上の「利益」と、税務上の「課税所得」にはズレが発生します。
僕も、ここまではわかっていました。
そして、この会計と税務のズレを修正するのが、どうやら「税効果会計」なるものらしいところまでは理解していたのですが、そのやり方がどうも意味不明だったのです。
でも、今日やっと、少しわかりました。
なんというか、会計って、見た目を気にするらしいんです。
例えば、会計上の利益として100万円が計上されていて、税率が40%だとすると、会計の視点からすれば、税額が40万円で、税引後利益が60万円となっていなきゃいけません。
こういう数字が並んでいたほうが、「キレイ」であり、数字がズレていると「汚い」と見えてしまうのが、どうやら「会計」です。
ところが、会計と税務は、先ほど書いたとおり、根本的な思想から違っています。その結果、会計上の利益が100万円の場合に、課税所得が110万円となってしまうこともあって、そうすると、税額は44万円となってしまいます。
そうなると、会計上の利益が100万円であるにもかかわらず、税額が44万円と損益計算書に書かれてしまい、会計的には、どうやらこれが非常に「気持ちが悪い」ようです。
この気持ち悪さを取り除くために、44万円が課税されているにもかかわらず、「課税されたのは40万円ですよ」と、会計上の利益に迎合させる形で記載を変えちゃうんです。
なんともまあ、利己的にも見えるんですが、こういった、「会計上の利益」に合わせた税額に実際の税額を修正する作業を「税効果会計」と呼んでいて、で、修正した金額を「法人税等調整額」という名目で計上し、その相手勘定が、税金の前払いと捉えられる場合は「繰延税金資産(DTA)」となり、税金の未払いと捉えられる場合は「繰延税金負債(DTL)」となります。
「なるほどなるほど」という感じで、今日はウェブ講義を聞いていました。
ただ、この理解は、まだまだ途中な気もしています。
とはいえ、一足飛びにすべてを理解するのはムリなので、今日ここまで理解できたことを、とりあえずよしとします。
それではまた明日!・・・↓
*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*
TwitterとFacebookでも情報発信しています。フォローしてくださると嬉しいです。
昨日のブログはこちら↓
僕に興味を持っていただいた方はこちらからいろいろとご覧ください。
━━━━━━━━━━━━
※内容に共感いただけたら、記事のシェアをお願いします。
毎日記事を更新しています。フォローの上、毎日ご覧くださると嬉しいです。
サポートしてくださると,めちゃくちゃ嬉しいです!いただいたサポートは,書籍購入費などの活動資金に使わせていただきます!
