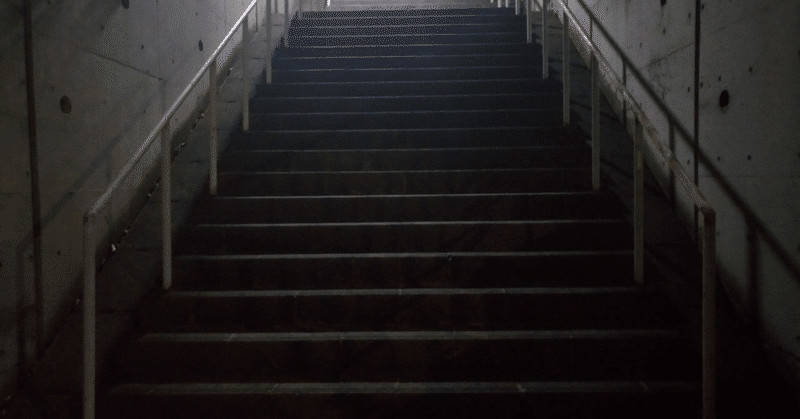
関ヶ原の戦いについて
(2023年5月15日初稿)
豊臣秀吉から徳川家康へ、関ヶ原の戦いで時代が動くんだけど、仮に朝鮮出兵がなければ、豊臣家の内部分裂もなかった訳だし、徳川家康が天下を取る事もなかったやろうな。関ヶ原で、東軍についた武将の大半は、朝鮮出兵してるし、西軍についても、朝鮮出兵していた武将は生き残りにほぼ成功してる。
関ヶ原の戦いの原因が、朝鮮出兵による日本国内の不満と考えると、家康に敵対しても所領安堵された西軍の武将が多いのは、東軍の主力武将に取っては、朝鮮での友軍の恩義があったから、家康も取り潰せなかったのかもしれない。
秀吉の朝鮮出兵の原因は、よく分かってないらしい。でも、明治維新後大日本帝国が侵略戦争を第二次大戦で敗北するまで続けた歴史を知ると、似た原因に思える。つまり、戦争で経済が回りだすと、簡単には戦争をやめられない。戦争で勝ち続けると負けるまでやめられない。
秀吉には、背後に堺の武器商人がいたんだろう。堺の武器商人にしたら、戦争がなくなると困る。秀吉にしても日本統一をして、朝鮮侵略に自信があったんだろう。結局、明と朝鮮の連合軍に敗退する訳だけど、秀吉が死ぬまで戦いが続いた。
秀吉の命令で朝鮮出兵した武将達は命懸けの戦いで、消耗した上にろくに恩賞もなく、不満が関ヶ原で爆発したんだろう。もしかしたら、秀吉の死も毒殺の可能性もあるのだろうか?それくらい恨まれても仕方なさそう。
(2023年5月18日追記)
関ヶ原前後の武将の石高の増減とか見てると、色々な要素があるんだろうけど、上手く説明がつかない増減が多いと思う。慶長の役が勃発して、まもなく秀吉が死んで、帰国。参加武将の内、いわゆる七将が不満を募らせて石田三成を襲撃してる。この七将が、関ヶ原の戦い後、悉く大幅加増を勝ち得ている。
武士の行動原理として、鎌倉時代以来御恩と奉公があると思う。つまり、見返りがあるから、忠誠を尽くす。文禄・慶長の役では、秀吉の命令で諸大名が朝鮮侵略を行った。しかし、朝鮮、明との戦いで最終的には領地を獲得できず、敗退した。命懸けで、戦ったのに何の加増もなければ、不満が生じる。秀吉の命令で朝鮮出兵した各武将は配下に与える褒賞がなく、統治上死活問題となっただろう。直接の上司(豊臣秀吉、秀頼)には逆らえない為、中間管理職たる石田三成を襲撃したように思える。しかし、配下に恩賞を与えるためには、三成襲撃では足らず、新たな戦争が必要になる。それが関ヶ原の戦いではなかったのか?
関ヶ原の戦いの前段として、文禄・慶長の役を捉えると、関ヶ原の戦いで躍動する東西軍の武将が多く参加している。西軍主力は石田三成、小西行長、宇喜多秀家で、関ヶ原後斬殺や所領没収される。東軍主力の七将は、大幅加増された。寝返り組で加増された小早川、所領安堵された脇坂、西軍なのに何故か所領安堵された島津、一旦所領没収されるが復活する立花宗茂。関ヶ原で観望して所領没収された長宗我部。様々な結果だが、文禄・慶長の役で、生じた豊臣家の内部分裂を天下取りに繋げた家康と所領加増された七将が関ヶ原のメインキャストなのは間違えないだろう。七将に分配する所領を捻り出すには、石田三成、小西行長、宇喜多秀家の所領だけでは足りないので、色々な武将が所領を減らされたのだと思う。そこに文禄・慶長の役での貢献も加味された可能性はあると思う。
文禄・慶長の役の敗北と関ヶ原の戦いの関連をドラマなどでもしっかり描くべきではないか?これまでは、あまりに触れられていないと思う。
(2023年5月19日追記)
文禄・慶長の役が元で豊臣政権は崩壊したんやろうし、明も崩壊したらしい。対外戦争で、勝敗がつかなかったら、犠牲のみとなって双方痛手が大きいよな。
安土桃山時代というが、秀吉が天下をとって没するまでの大半が文禄・慶長の役だった訳で、秀吉の巨万の富は、文禄・慶長の役の軍事経済に支えられていたのだろう。文禄・慶長の役は、武器商人には莫大な利益をもたらす。武器商人といえば堺の商人。当時流行の茶の湯で、密談をしていたのだろう。堺について調べると興味深い事実が。堺の代官は秀吉時代には、二人体制なんだが、何と小西家と石田家が担っていたそうな。小西行長の父と兄、石田三成の父と兄。つまり、文禄・慶長の役で少なくとも小西家と石田家は、莫大な利益を上げていた可能性がある。しかも石田三成の直轄地は近江佐和山城で、領内に国内有数の鉄砲産地の国友村を抱えていた。堺の商人と結びつきの強い豊臣家も含めて、小西家、石田家が文禄・慶長の役で莫大な利益を上げていたら、七将から恨まれるのは分かる。当時のもう一つの鉄砲産地の紀州根来は、浅野家の領地だった。鉄砲産地の堺、国友を抑える石田家、小西家を主力とする西軍は関ヶ原で十分勝ち目があったのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
