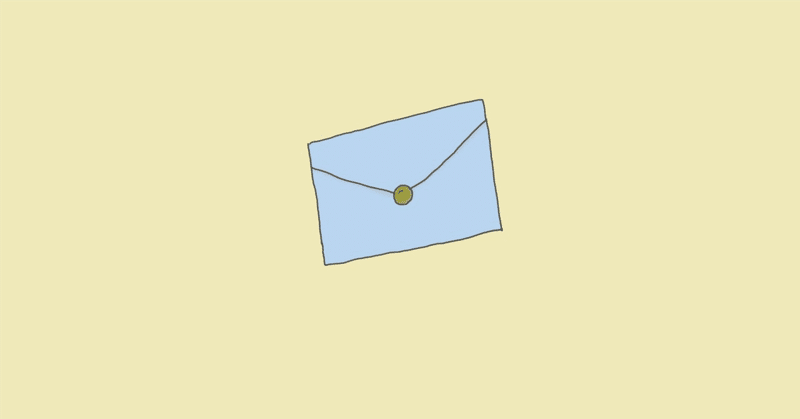
ライトノベル的な何か:エピソード2
「なんで犬なん?」
友達1が聞いてきた。もちろん、目線はアイスに釘付けのままだ。
「だってなんかさぁ、犬って見るからに忠実じゃん。自分の飼い主を絶対裏切りません感すごくない?」
ここは紛れもない私の本音である。
そうだ。私は、確実に信じて信じられているあの関係に憧れていたのだ。動物種族の垣根を超えた、あの関係に。
自称頭がいい人は、ここで気づくかもしれない。だったら、犬になるのではなくて犬を飼う人になったほうがいいのではないか、と。
だがそれは違う。全くの見当違いだ。いくら大学受験を頑張ってレベルの高い大学に入ったからといって、調子に乗らないでいただきたい。
私は、「信じたい」のだ。
何も気にせず、ただひたすらに何かや誰かを全力で信じてみたいのだ。
昔々あるところに、私という純粋無垢な中学生がこの小さなしょうもない世界で息をしていた。当時の私はなぜだかわからないが、一部活の一部長を任されてしまい、日々魂を削られる想いで、いや、実際に削られながら奔走していた。
やりたくなくてなったとしたって、立場は人を変える。無駄に責任感なんていうものを持つようになった私は、立場ならではの悩みなんかも抱えるようになった。もともと誰かに話したり頼ったりするのが苦手だった私は、その当時も例外ではなく、誰に心のうちを明かすことがなかった。そのうち、血も涙もない冷徹な部長になってしまったため、そのことを自覚してからは、その上からチャック付きの着ぐるみを暑い夏も寒い冬も着ることにした。
そんなある日の18時頃、流石に中学生ぽい人間の形を保つことに限界を感じた私は、副部長をしてくれていた友人兼ライバルに悩みを打ち明けた。というか、打ち明けてしまっていた。仕事ができそうで一生懸命そうだったため私が指名した副部長だったが、いつの間にか立場にかまけて何もしなくなってしまっていたので、自分の本当の部分などさらさら言う気はなかったのに。
翌日から卒部、卒業の日まで悲劇は続いた。もはや喜劇に方向転換しなければネタ切れなのではと思うくらいまで、それは続いた。
普段分厚い着ぐるみを被っている私の核の部分は、すれ違う人みんなが知っている『部長の闇』になり、「そんなこと思ってたんだありえない」的な、よくある反旗の翻し方をされ『ハブ』が始まった。忘れていないだろうか、私は部長だったのだ。部長がハブられる世界線とは、この青く広い世界中どこを探してもこのど田舎中学校吹奏楽部だけだったと言えるだろう。
そりゃあたまにはいた。私1人だけ譜面台を隠されていても何も言わず一緒に帰ろうと声をかけてくれる心の優しい同級生や、みんなに無視され続ける私を何も言わずに輪に入れてくれるのちの友達。上履きを隠されなかっただけ、ノートにバカだのブスだのと書かれなかっただけマシだったのだろうか。
もともと信じる能力が欠けていた私は、その一度の裏切りで真っ暗闇に特大特注サイズの南京錠をぶちかけ、いろいろなものを閉じた。
ど田舎中学校卒業の日、何通も手紙をもらうくらいには関係性は良くなっていた、いや、卒業モード全開のみんなからは忘れ去られていたのだろう。「卒業卒部おめでとう!ハルがいたからやってこれたよ!ありがとう!」
ありがとうこちらこそだよ、とうまく笑って返したあのときの私だけは、何百年経っても国民栄誉賞を与えるに相応しいと思う。
それから12年の月日が経とうとしている今、30×10×10立方センチメートルほどのささやかなダンボールパンパンに入れ込まれている手紙を開けたことは一度もないし、その文字に込められた想いとやらが私の目を通して届いたことも一度もない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
