
「アイデアを自分の外に出し、客体化する」ピタゴラスイッチの企画などで知られる佐藤雅彦教授に、これからのコンテンツ作りについて聞いてきました(後編)
こちらの記事は過去に掲載したものの再掲です。
東京芸術大学の佐藤雅彦研究室がLINE NEWSで配信中の新番組『ご協力願えますか』は、見ている人にちょっと変わった「協力」をしてもらう映像実験番組。
視聴者は、映像に従って「ご協力」を重ねるうちに、胸の中に「得も言われぬ気持ち」が沸き起こる、不思議な映像体験を味わうことになります。
▼『ご協力願えますか』本編はこちらからどうぞ。
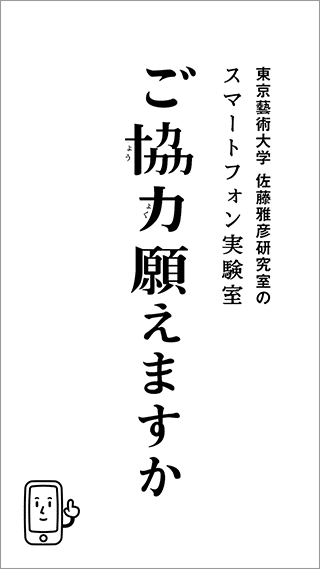
この番組について、佐藤雅彦教授と今回制作の中心となったCANOPUSの平瀬謙太朗氏、豊田真之氏(共に東京藝術大学 佐藤研究室の修了生)、番組を担当したプロデューサーの谷口マサトが対談しました。
番組のテーマである「映像の身体性」についてじっくりお聞きした前編に続き、後編の今回は、チームでのものづくりやアイデア出しなど、制作プロセスについてのお話をお送りします。
▼対談前編▼
「スマホによって映像は身体の一部になった」ピタゴラスイッチなどで知られる佐藤雅彦教授に、これからのコンテンツ作りについて聞いてきました(前編)

谷口:佐藤先生と撮影にご一緒して驚いたのが、ご休憩コーナーに出演してもらっている加藤小夏さんのエプロンでした。当初は小夏さんにエプロンをつけてもらうという想定で、スタイリストが複数のエプロンを用意していました。
事前の打ち合わせでも佐藤先生はエプロンについて熱く語り、「私は、ロケ先などで世界中のエプロンを集めるのが趣味で、たくさん持っているから私のベストエプロンも持ってきますよ」と言って実際にエプロンを持ち込んでいました。

そこまでこだわったエプロンなのに、衣装合わせで「あ、エプロンつけると固い印象ですね、やっぱりやめときましょう」って(笑)
衣装合わせでの変更は多いので当たり前に思うかもしれないですが、その判断に「ためらい」が無さすぎたし、ブレストでもご自分の出したアイデアに対しても一切固執されない。極端にさっぱりした姿勢に驚きました。
佐藤:言葉にすると「客体化」――要は、身体の外に出るとアイデアを客観視できますよね。そうすると、そのアイデアが「自分のものだから」といったことの利己的な要素を失い、「良いか悪いか」だけになる。
だから、簡単に捨てられるんだと思います。研究室では、日常的に行わせていることです。
谷口:一番衝撃的だったのが、ブレスト中に佐藤先生が「このアイデアはすごいね、誰が考えたの? え、僕なの」って。自分のアイデアかどうかも忘れている。
佐藤:(平瀬氏と豊田氏に向かって)僕は、ほとんど忘れるよね?アイデアを外に出すと忘れちゃうんです。研究会では毎回のように笑われます。研究生を信用していて、外部記憶装置のような存在として感じているんですね。

谷口:アイデアに対してフラットに意見を言えるので客体化は「チームでのモノづくり」において重要だと思いますが、実際、研究生にはどのような指導をされているのでしょう?
佐藤:「忘れる」っていう指導はしてないですよ。
平瀬:忘れるっていう指導(笑)。
佐藤:みんな、いろんなアイデアを漠然と言うことが多いんですけど。まず「具体的に絵や見取り図で出しなさい」とは言いますね。その後に、的を得た「言語化」も要請します。
谷口:(前編で触れた)「work in progress」のお話もそうですが、「ご協力願えますか」の制作を進めてきたなかで、「まずは撮ってみる」――プロトタイピングを大事にされているなと感じました。あれも、やはり客体化ですか?
佐藤:まず作ってみて、とりあえず自分のアイデア(構想)を自分の外に出すことはすごく大事ですね。言葉にするのは最後。「このアイデアは、こういうことだからおもしろい」って最初に見抜ける時もありますけど、見抜けないことがほとんどです。
谷口:言葉だけで表現することは不十分だと警戒されているんですか?
佐藤:いや、警戒はしてないですよ。本当に自分たちがやりたかったこと、おもしろいと思っていることを言葉にする作業はすごく大切なことです。
カンヌ国際映画祭にノミネートされた『八芳園』も典型的で、とにかく作るんですね。2年ぐらいかけて撮影して、編集しながら「これはなんで良いのか」をみんなで話していきます。
ただ、そこで通り一遍の言葉をペタペタペタとつけてしまうと、一見説明したかのように見えてしまう。それには用心しなくてはなりません。本当に既存にない的を得た言葉を見つけると「それだ!」ってなるんですね。その言葉は、すごくあたらしい佇まいをしているんです。
谷口:その「得も言われぬ感覚」を掴み取るために、プロトタイピングが大事であると。
佐藤:そうですね。その時、身体はすごく頼りになります。手で作るものってすごくありがたい。ただ頭で考えただけのものとは全然違うものを作っています。
谷口:どのように違うのでしょうか?
佐藤:例えば、セオリーどおりに構図を考えるのも大事ですが、それだけだと従来の理屈の内側で作ることになってしまいます。でも撮影という行為は、視覚が「これはおもしろいから」と撮る。その時、それまでの理屈を超えた理屈を身体が生み出すんです。

「最前線」とは「失敗」という崖のギリギリに立つこと
谷口:それで思い出したのが、以前の先生の公開講座で「イマジナリーラインは本当に絶対か?」という話をされていた時のことです。
イマジナリーラインは「対面している2人を撮影する際に、2人を結ぶ仮想の直線を引き、その線の片側エリアのみにカメラを配置して撮影する」という映像撮影の基本的な技法ですが、先生は「そもそもそれって本当なの?」という指摘をされた。
イマジナリーラインはあくまで理屈なんですよね。実際にイマジナリーラインを超えている作品をたくさん紹介されて、超えたほうがインパクトが強く成立している事も多い。理屈よりも、身体がより良い構図と感じたものの方が良い。
身体性という意味では、事前の打ち合わせよりも撮影現場で判断されることが多いかったのも「あえて」かなと思いました。

佐藤:撮影現場というのは、最前線なんです。最前線というのは「失敗」という崖のギリギリのところに立つこと。なので、一歩踏み外すと転落してしまう状況です。普段なら「これはこうなるから、ここにいると安心」みたいな場所に身を置きがちで、最前線にいることって中々ないですよね。
谷口:なるほど。自らを崖っぷちに追い込んでいく状況設定なんですね。
佐藤:そう。橋なんてかかってない崖っぷちで、向こう側には到底行けないから「ジャンプ」するしかないんです。最前線は、必然的にジャンプが必要な状況になるんです。
谷口:余談ですけど、武道の先生から「試合じゃないと技は出てこない」と聞いたことがあります。
佐藤:ぼくも、かつてアイスホッケーをやっていましたが、実際の試合が一番新しいフォーメンションを思いつきました。撮影現場も試合みたいなものですよね。
谷口:佐藤先生は、かなりの現場を踏まれてきていますからね。
佐藤:ええ、もう現場はいろんなことが起こりますから。天候や人のコンディションの問題以外にも、とんでもない思いも寄らないことがいっぱい起こります。
その時にどう判断するかなんです。とんでもない問題は、とんでもない解答を引き出してくれるんです。つまりジャンプですね。

谷口:試合並みの緊張感と同時に、一方ではチームメンバーへの「心理的安全性」を配慮されているなとも思いました。LINEグループ内でのブレストでも、先生自らまだ未完成のアイデアをどんどん出されていて、みんなが発言しやすくされている。
チームの関係性がすごく良いと感じたんです。
平瀬:普通、大学の研究室と言うと「教授」と「教え子」という上下関係があって、ヒエラルキーも強いものだと思うんです。ただ「ものを作る」ことの前ではチームの全員がフラットであるべきというのが、常に先生の姿勢としてあるように思えます。
その分、自分たちの責任が増えることもありますけど、その責任がやりがいにもなるし、一番アイデアを出しやすい環境だとは思います。
佐藤:アイデアを出さないと始まらないんですよね。自分としてはすごく良い案だと思っているんですけど、言った瞬間に「あ、とんでもない」とか「くだらないな」と思うものもいっぱいあります。
くだらないものは、その場で消費されていくけど、良いものは空間的、時間的な普遍性を持ちますよね。だから、量を出す。「量は、ある時から、質に変換する」ので、結果的に良いものが作れるんです。
谷口:状況によるとは思うんですけど、営業会社だったら組織作りは軍隊式のような縦社会のほうが良い場合もあると思うんです。フラットさを追求されているのは面白いですね。もの作りについてはフラットな方が良いのでしょうか。
佐藤:フラットさが必要なのは「アイデア出し」の時ですね。僕はかつて電通という広告代理店にいた頃には、同じチームの営業の方達にもコピーを書くことを決まりとしてました。クリエイティブの部署って営業の方達を上から見がちなんですよ、あいつセンスないよねと言って。僕はそれに腹が立って。
谷口:全員参加なんですね。
豊田:さっきの「アイデアを出すと忘れちゃう」みたいな話でいえば、今回の「ご協力願えますか」は“佐藤研”で作っているので、出したアイデアは研究室に所属するみんなのもの。全員フラットに参加で、そこは良いチーム体制ができているのかなと思います。
谷口:ブレストに参加させていただいて、アイデアがダメだった場合に、その発案者自体に佐藤先生がダメだしすることはないと感じました。アイデアには厳しいが、人には優しい。
教えるということは「自分の拡張」をするということ
佐藤:ダメな時は、「なぜダメか」をなるべく説明したいですが、人は否定しないですね。みんなアイデンティティがあって、その人ならではのものを持っているので。
藝大の佐藤研では学生に「自分が何をやりたいか」というテーマを書かせて壁に貼ってるんですけど、作品を作るたびにテーマの文章がどんどん更新されて明確になっていくんです。その度に、私は、段々とその学生のことがわかっていくんですよ。
佐藤:「ご協力願えますか」の「囚人」を作った学生も、いろんなことを書くんです。最初は「時間割を作るのが好きだ」とか「見取り図を描くのが好きだ」。あるいは「予定表を組むのが好きだ」とか。そのつど、研究会で一見バラバラなことを出す。
試しに作品を作ってみると、どうも「ままごと的なことが好きだな」と感じました。それで、「新しいままごと」って言うテーマが見えてきます。学生が自分を見つけるまで数年かけて二人三脚で探しますね。
豊田:僕は面談を受けたタイミングで研究テーマが決まっていなかったんです。でも、先生は「次に会う時までに何か作ってきなさい」って言ってくださって。
まだ研究室に入る前の段階で課題をもらって、最初の研究会で2本の映像を観ていただきました。その時に「こうやって点をたくさん打っていると、点がつながって線になっていくから、点をたくさん打ちなさい」と言われたんです。
佐藤:豊田の場合は、「映像をやりたい」けど「音楽もやりたい」と言っていて。どっちをやりたいんだ? って聞いても「どっちもやりたい」と。それが、すごく難しかったですね。
谷口:平瀬さんの場合はどうでしたか?
平瀬:僕は笑っちゃうぐらい、在学中は何も定まらなくて。藝大は作家志望の人が多いので、自分の内なるものを表現としてどう外に出すかっていうのが大きな姿勢としてあるんです。
でも僕はそういうものから切り離された、理屈や仕組みが好きで。在学中は独特な理屈や仕組みを持った映像装置をひたすら作っていました。その装置で流すコンテンツは全然作らないで。
それは未だに変わらないというか、メディアそのものだったり、メディアの特性だったりということにとても興味がありますね。
谷口:映像自体ではなく、メディアへの興味?
平瀬:今回のプロジェクトも、スマートフォンの持つセンサを使えばインタラクティブなことは色々出来るんですけど、あえてそうではなくて、シングルチャンネルの映像によるインタラクティブな体験に挑戦しています。
すると、メディアの機能を制限してみる事で、視覚による身体の表象(知覚・気持ち)が際立ってくるところが面白くて、メディアの特性と表象の関係性に興味がわきました。
谷口:毎回違う答えを出す学生それぞれに向き合い続けるのは、すごいことですよね。先生にとって「教える」とは何なのでしょか。
佐藤:教えるというのは「自分の拡張」です。僕もそこで学んでいるんですよね。

谷口:先ほど話された学生それぞれのテーマは、その学生がどのように世界を見ているかという視点のユニークさに関係すると思います。視点が違うから違ったアイデアがでてくる。
先生は営業でもクリエイティブでも関係なくアイデア出しを推奨されて様々な視点を集めつつ、自分の視点のバラエティも同時に拡張されている。拡張以外に教えることで意識されていることはありますか。
佐藤:慶応義塾大学で初めて教鞭をとるまでに、膨大なもの――コマーシャルを何百本も作っていたし、プレイステーションのゲームや歌もつくっていた。それらを体系化すると、興味があるのにいままで手つかずだった部分がはっきりするんです。
離散数学的な、連続でないとびとびなものが好きなのに、もの作りに活かせていなかった。それまでいた広告代理店では出来なかったことも、大学ではやっていいんだって気がつくわけです。
慶応義塾大学の佐藤研では、体系化を大きなテーマにしようと。だから、教えることは自分を知ることにもなるんです。
谷口:自分の「好き」を体系化して、学生に教えることで「客体化」も同時に行っている。
佐藤:そうですね。自分がおもしろいなと思っていてもそれが普遍的かどうかはわかりにくい。学生と一緒に実験を重ねることで、どのアイデアが普遍性をもつのか、授業を通して幾つかわかりましたからね。

谷口:これまで聞いた話を振り返りつつ、佐藤雅彦研究室と1年間ご一緒して感じたのは、まず「客体化によってアイデアと発案者との切り離し」を徹底していること。
それによってアイデアに対してシビアな意見をぶつけると同時に、制作メンバーの心理的安全性、どんなアイデアを出しても大丈夫という雰囲気を作られている。
下手に心理的安全性を重視すると、厳しい意見を言わない「ぬるま湯」になりがちですが、客体化によって心理的安全性とアウトプットに対する厳しさを両立されているように感じました。
現場での緊張感などでアイデアのジャンプを促すなど、安全性と緊張のバランスをすごく配慮されている。

谷口:もう一つは、個々人のテーマ、世界をその人はどう見ているかという各人の視点をとても重要視されている点ですね。全員参加でアイデアをできるだけフラットに広く集めようとされている。
最後に、先生自ら試行錯誤されている様子を見せ続けていること。前述の公開講座でも、先生自ら撮影の実演をして、けっこう失敗された。それで観客はハラハラしていたわけですが、最後に先生が「実演したのは、目の前でやってみせることで、それを見ている人の頭の中に映像が流れるようにするためでした」と言われた。
ハラハラする状況によって観客は先生に自分を投影し、撮影に参加させられていたのですね。
LINEを介した「新しい気持ち」を起こさせるコミュニケーション
谷口:最後に、今回の作品を配信するLINEについても伺えればと。あらためて制作の際に、LINEをどのようなものとして意識されていたのでしょうか。

平瀬:LINEって自分たちのことを「メッセージアプリ」とか「チャットアプリ」と言わずに、「コミュニケーションアプリ」って表現していますよね。だから今回制作する動画コンテンツも、やはり本質的にはコミュニケーションにまつわることがテーマだと良いなと思っていました。
その上で、先生にまずはLINEをもっと知ってもらいたいと思い、今回は積極的にLINEで連絡を取り合うようにしていました。この件が始まってから、もうわざとLINEで送る。「気付くかわかんないけどLINEのほうで送ろう」みたいな。スタンプも送ってみたり。
佐藤:ちょっと前まで、スマートフォンじゃないフィーチャーフォン(通称ガラケー)を使っていたんですが、これが始まるちょっと前ぐらいにちょうど、スマートフォンにしたんです。
僕は研究テーマが「コミュニケーション」で、結局は「どうやったらそれが伝わるか」ということに尽きるんですね。なので、やはりそういう観点でLINEを見ていましたね。
「新しい表象」っていうとすごく難しいんですが、「新しい気持ち」を起こさせるコミュニケーションが出来たらなっていうのが、今回の「ご協力願えますか」です。
だからまだ実験段階ではありますが、一般の人にも、そういう気持ちを取り込んでもらえれば、本当に嬉しいなと思っています。
谷口:先生には作品だけでなく、どうやってコンテンツを作るのかということについても多く学ばせて頂きました。本当にありがとうございました。
*****
現在、2019年に配信された映像実験番組『ご協力願えますか』の新シーズンが再び公開されています。詳しくはこちらから。
東京藝術大学 佐藤雅彦研究室
NHK Eテレ『ピタゴラスイッチ』『0655・2355』の監修などで知られる佐藤雅彦(東京藝術大学大学院映像研究科教授)による研究室。
「メディアデザイン」をテーマとして、研究生たちが日々作品制作に励む。本番組『ご協力願えますか』は、佐藤教授と研究室の修了生たちによって、「メディアデザイン」の教育番組としてLINE NEWSの中で制作された。
CANOPUS(カノープス)
「メディアデザイン」をテーマに活動するクリエイティブグループ。
東京藝術大学映像研究科メディア映像専攻の修了生が多く在籍し、デザイナー・エンジニア・映像ディレクター・コンポーザーなど、多様なスペシャルティを持ったメンバーが集まる。
谷口マサト
記事・マンガ・動画など様々なWebコンテンツの企画・制作を担当している。
TEXT:金井悟PHOTO:木原基行『ご協力願えますか』メイキング写真提供:東京藝術大学 佐藤雅彦研究室
