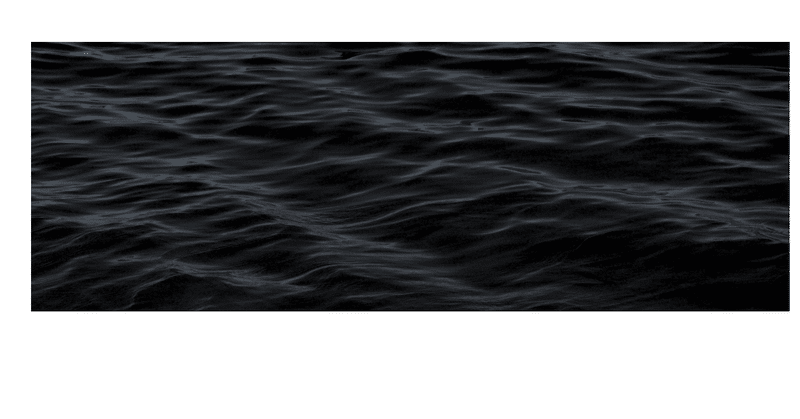
痣 第1話
あらすじ
顔を含む右半身に痣をもつ一香は、ある田舎町で疎まれながら暮らしていた。
この地方の地主・五百扇と、彼と愛人関係にあった一香の母の争いに巻き込まれ、火傷を負ったためにできた痣だった。
そんなある日、五百扇の屋敷から火の手が上がる。
金庫に入っていた1億円が何者かに強奪され、五百扇は殺害されてしまう。
五百扇の双子の息子のうち弟の影彦も行方不明に。
5年後の東京。
ある女性が出会ったのは、双子の兄・雪彦だった。
雪彦を追う女性記者や背後に潜む謎の存在を巻き込みながら、事件が再び動き出す。
契約
【本当に、よろしいのですか?】
闇の中に、パソコンの画面がぼぅっと浮かび上がる。
「良いんですよ。この厄介な物を消すだけでね」
パソコンに向かう人物は含み笑いを漏らしつつ、左の頬から首にかけて指を滑らせた。
冷えた空間に、キーボードを叩く音だけが響く。
【後になって変更では困りますよ】
相手との交渉は続いている。
「もちろんです。きっちりお支払いしますよ。3千万」
そう答えた直後、階下から物音がした。
応接室に仕込んだカメラの映像に切り替えると、ずぶずぶに肥えた老人が真紅のガウンを纏い、暖炉を背にして立っている。
──いつ見ても胸糞悪い爺だ。
パソコンに向かう人物は、吐き気を催して口元に手を当てた。
老人の足元に平伏しているのは、いつも金を借りに来る茶髪の男だ。
やがて茶髪の男は悪態を吐き、悔し紛れか傍らのソファを蹴りつけて部屋を後にした。
交渉は決裂したようだ。
以前からの借金の返済を迫られたものと思われる。
パソコンに向かっていたその人物は、すぐさま玄関へと移動した。
音もなく、影のように。
「お困りですか?」
驚愕する茶髪の男に向かって口を開く。
「金が欲しいなら、良い方法がありますよ」
──時は満ちた。
その人物は、小型ナイフでバサリと髪を切り落とした。
伸び放題だった髪が闇に溶け、パソコンの画面から発せられる光に、その顔が露わになる。
まだ少年といっても差し支えなさそうな容貌である。
──愚かな男だ。疑いもせず、尻尾を振って擦り寄ってくるとは。
その人物は見開いた目を煌々と光らせ、悍ましげな笑みを浮かべた。
その様相は、およそ少年とは思えない。
闇に棲む亡霊のようであった。
【変わった人だ。
顔を変えてしまえば、絶対的に安心な未来が手に入るというのに】
チャット画面に、新しいメッセージが表示される。
その人物は、くぐもった笑いを零すとパソコンに向かった。
「これは決定事項です。代わりと言っては何ですが」
勿体ぶるように手を止める。
「あと1人、確実にそちらへ向かう筈だ。この命を賭けてもいい。
その時には──」
伝えるべきことを伝えると、その人物は恍惚として闇を仰いだ。
笑いが止まらない。ついに、この時が来たのだ。
【……面白い。契約成立としましょう】
時は満ちた。
【過去を隠し通せるかどうかは、あなた次第。
楽しみにお待ちしております。
──東京湾の魔女】
◇
この冬、初の吹雪の夜のことだった。
水浜一香は目を瞠った。
何故、こんな場所に札束があるのか。
一香
裏寂れたスナックの勝手口を出ると、ゴミ置き場がある。
一香は客の前には出ない。
地元の中学を卒業して3年、ずっと掃除婦のようなことをしている。
このスナックで客の相手をする母にここへ連れて来られ、いつの間にかそういうことになっていた。
物心がついた頃には、既に母・直子からの壮絶な虐待が始まっていた。
父親はいなかった。
自分が、男狂いの直子と誰の間に生まれたか。
そんな疑問が沸き出す以前に、一香は生きることだけに精一杯だった。
夜毎、卑俗な喧騒に咽せるような酒の匂いが混じる。
狂酔した、顔ぶれの変わらない客。
そこで呼吸する自分。
ここは、世界の掃き溜めだ。
まだ店の者さえ来ない。
本当はこんなに早く出てくる必要はなかったのだ。
それでも一香は、外を彷徨い歩いていることが多かった。
直子が男を連れ込んでいるからだ。
外に出ても、都会のように気軽に立ち寄れる場所はない。
自分の顔を晒したくもない。
ゴミ袋を持って勝手口を出ると、饐えた臭気が鼻をつく。
午後6時過ぎ。吹雪いてきた。
勝手口から漏れ出る電灯の光で、一香の周りだけがぼんやりと明るい。
だから、目についた。
冬枯れの草の間から覗く、グレーのナイロン生地。
堂々と打ち捨てられたスポーツバッグの中身を見て、思わず周囲に目を走らせる。
帯封が付いたままの、一万円札の束。
一束が百万として、その束の数は10やそこらではなかった。
スポーツバッグの中身に雪が降りかかる。
手が伸びた。
枯れ草が思いのほか大きな音をたてる。
辺りを憚るが人気ひとけはない。
札束は、全部で50束であった。
つまり、5千万──。
岐阜の山に囲まれたこの田舎町で、これほどの現金を一度に扱える人物は限られている。
五百扇泰造。
この地域の地主である。
その金が、何故ここに──。
瞬刻の後、一香は僅かに呻いた。
時を遡れば、思い当たる節はあった。
◇
「おい、幽霊」
山の端に隠れようとする夕陽を前に、畦道を急ぎ始めた時だった。
蛇のような声に、一香は鬱々とした気分になる。
こんなところで行き合うとは。
地主の息子。
五百扇雪彦だ。
五百扇家には、一香と同い年の双子の兄弟がいる。
兄・雪彦は形としては高校生だが、実際にはただ遊び歩いているだけ。
制服すら着ていない。
弟の影彦は、長らく引きこもっているとの噂だった。
「なぁに、この子?」
雪彦の隣にいる女が言った。
紅い唇の、都会的な女だった。
「幽霊」
雪彦は、踵を履き潰したスニーカーで地面を蹴りながら近づいてくる。
一香は動かない。
雪彦に髪を引っ張られ、一香の顔が露わになる。
女が叫んだ。
「やっば! なにその顔!? 私だったら生きて行けないわ!」
右の頬から首にかけて。
また身体の一部にも走る、赤黒い痣。
女が叫んだのは、これを見たからだ。
一香の痣は爬虫類の皮膚のようで、人を不快にさせるには充分だった。
だから、この手の反応には慣れている。
一香が抵抗しないのは恐怖からではない。
無でいれば嵐はいずれ去る。最短で。
幼い頃に一香が獲得した術であった。
痣を覆うように髪を伸ばす一香を、誰もが「幽霊」と呼んだ。
小・中学校でのいじめは惨烈を極めた。
不快ならば見なければ良いものを、わざわざ人前に晒して蔑む。殴る、蹴る。
特に女子たちは、父親に似ず甘い顔立ちの雪彦のやり方に喜んで従った。
田舎の人間関係は狭い。
一度でき上がった階層構造が揺らぐことなど、あり得ないのだ。
一香を嬲って気が済んだのか、雪彦は女と共に去って行く。
山に囲まれたこの地域は温泉宿が多い。連れの女も旅行者だろう。
雪彦は、週末になると市街地の方でそんな女を引っかけてくる。
そして、遊ぶ金を泰造にせびるのだ。
一香は立ち上がって土を払うと、買い物袋の中身の無事を確認する。
雪が降り始めた。
ボロ屋に辿り着くなり耳に入ったのは、母親の嬌声だった。
それから、顔を背けたくなるような澱んだ臭気。
男がいる。
「出てけよ、気持ち悪りぃ顔しやがって」
物音に気づいた母、直子が下着姿のまま一香を睨む。
仕事前に軽く食べたいと言われたから、一香は片道30分もかかるコンビニへ行ってきた。
だからと言って特に感情が動くこともない。よくあることだった。
ここ半年ほど、直子は自分より一回りは年下であろう男の虜である。
テツという、茶髪で濁った目の男だ。
一香が背を向ける前から、直子は耳を捥ぎたくなるような善がり声を上げ始めていた。
男と行為に及ぶ時、直子はいつも飢えた獣のようになる。
建て付けの悪い戸を閉める直前、染みで汚れた掛布団が上下に蠢くのが一香の視界に入った。
夕刻に降り始めた雪は、まだ積もるほどではない。
陽は落ちている。
灰雪を肩に受けながら歩き出した時、誰かが足を引きずりながら一香の前を走り過ぎた。
薄闇の中、雪彦でなく影彦だと認識できたのは、彼の頬に一香と同じ赤黒い何かが見えたからだった。
◇
札束は、圧倒的な存在感をもって変わらず一香の目の前にあった。
時間の経過と記憶から推し量るに、この金は雪彦が持ち出したものだろうか。しかし、いくら何でも多過ぎる。スナックのゴミ捨て場なんかに置いておく理由も分からない。
屋敷に引きこもっていた影彦が、逃げるように走り去った理由も。
──だから何だ。
躊躇は、一瞬にも満たなかった。
今、金を掴んでいるのは自分だ。
──何が悪い。
この顔に痣をつけたのは直子だ。
そして、その要因を作ったのは五百扇泰造なのだ。
一香が幼い頃、泰造と直子は愛人関係にあった。
ほんの一時期、一香は雪彦・影彦兄弟と遊んだことがある。
ある時。泰造の妻が、若い男と出奔した。
後釜に座れると思い込んでいた直子と、その気がなかった泰造。
子どもの前で、醜く罵り合う2人。
激昂した直子が、暖炉に焚べてあった薪を振り回す。
近くで隣り合って座っていた一香と影彦は火を浴びた。
一香は右半身に、影彦は左半身に。
火傷の痕は赤黒く、爬虫類の皮膚のようにザラリとした痣に変化した。
直子は、呪うように一香を殴った。
一方、元から要領の悪かった影彦は、泰造からますます疎まれることになる。やがて姿を見せなくなった。
今しかない。始めるなら。
働いても金は直子に吸い上げられ、それは男へと流れていく。
あの濁った目の男に。
まだ店は開いていない。
ここにいるのは一香だけだ。
ここは、世界の掃き溜めだ。
息苦しく、理不尽な。
いつも、空を見ていた。
一香を閉じ込めるように迫り来る山々を、軽く越えて行く鳥たちが羨ましかった。
鳥になる。
ここに居なくて良いのなら、どんなに強い向かい風にも喜んで立ち向かおう。
力を込めて札束を胸に抱いた一香は、笑ってさえいた。
▼次話以降▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
