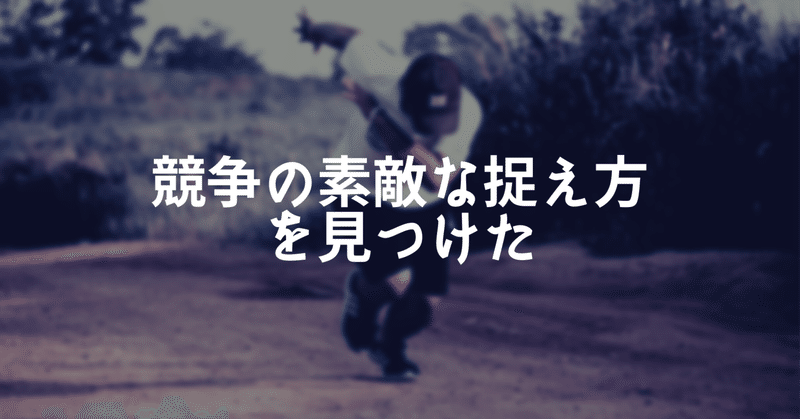
私にとって魅力的な「競争」の捉え方を見つけました
2021年に開催された東京オリンピックの時に偶然見つけた記事に感銘を受けました。その記事は男子走り高跳び決勝で起こった出来事について書かれていたものでした。
(私が読んだ記事は削除されていたため雰囲気が伝わるように別の記事を貼ります)
この決勝は2時間にも及び、カタールのムタズエサ・バルシム選手とイタリアのジャンマルコ・タンベリ選手は五輪記録である2メートル39センチをともに3回失敗しました。それまでお互いに1度も失敗がなく全く同じ成績だったので決着はつきません。
大会側は、決着が着くまで1回ずつ跳躍する「ジャンプオフ」を提案したそうですが、バルシム選手は「金メダルを2つもらえないか」と提案し、大会側が受け入れる形で決勝が終わりを迎えたのです。
バルシム選手がそのような提案をした背景についても書かれていた当時の記事はすでに削除されていたのですが残っているメモから引用したものがこちらです。
金メダルを分かち合うことが決まった瞬間、2人は抱き合って喜びを共有した。試合後、ジャンプオフを行わなかった理由について、バルシムは「それは歴史だ」と語った。ここ数年、2人はけがで苦しい時期を過ごした。それでも懸命に調整して東京五輪に体調を合わせてきた。「バルシムでなかったら、金メダルを共有することはなかっただろう」とタンベリ。国際大会でしのぎを削り、同じような苦境を味わった「友」だからこそ誕生した2人の金メダリストだった。バルシムは「スポーツマンシップであり、これが私たちが若い世代に届けるメッセージだ」とコメントした。
私はこの記事を読んだ当時、この2人の金メダリストが魅せてくれたのは、70年代に端を発すると言われるコーチング創成期のキーパーソンの1人である、テニスコーチのティモシー・ガルウェイがその著書「インナーゲーム」に書かれていた"真の競争"だと思いました。
「筆者は、ベストの能力を互いに体験し合うためにこそ、協力して互いの障害になることが真の競争だと結論づけた」
私は初めてこの書籍を読んだ時に一番この箇所が印象に残っていました。
また、別で見つけた岡本太郎さんのこちらの言葉にも似たものを感じます。
「ほんとうの対決というのは
自分を相手にぶつけ
相手も自分にぶつかってきて
お互いがそれによって
活きることが対決なんだよ。」
※こちらの動画では2人の声・言葉も聴くことができるのでよければぜひご覧ください。
ここまで私にとっては新しく魅力的な競争の定義を紹介させていただきましたが、アスリートの方や学生時代にトップクラスの成績を出されていた方にとっては「当たり前でしょ!」と言われるかもしれません。
これは余談ですが、なぜ私この定義に惹かれたのか?心動かされたのか?について少し考えてみると、ここには自分の原体験が関係していそうです。
このあたりをここ数年、実践探究している成人発達理論を参照して掘り下げられそうだと思ったので別途記事にしてみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
