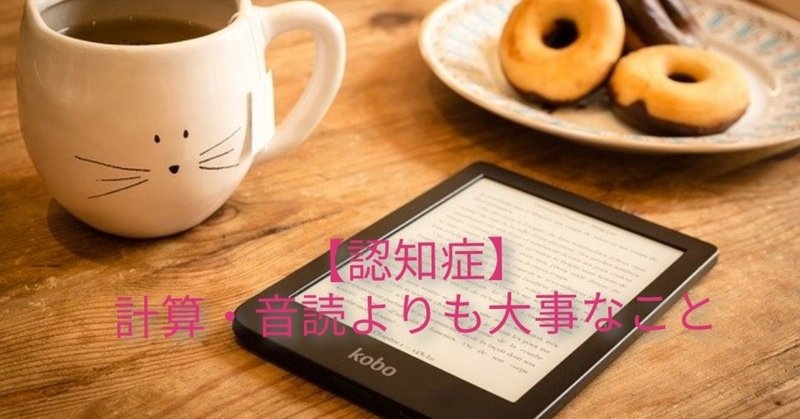
【認知症】計算・音読よりも大事なこと
今回のお話は認知症になったは優先すべきことは?
その時、周囲のフォローはどうすべきか?👈
【認知症は生活障害】
認知症になるとどうなるか…、大まかには「生活のつまずき」が多くなります。
ここでいう「つまずき」は
「家事がうまくできなくなる」
「新しいことが習得できなくなる」
「電化製品がうまく使えなくなる」
「感情的になり家族とうまくコミュニケーションがとれなくなる」
などを指します。
つまり「自分の生活をコントロールできない状態=生活障害」になります。
なぜ起こるかは「脳の機能低下」によるものと考えられてます。
例えば、
記憶障害
見当識障害(時間、場所、人などが認識できなくなる)
遂行機能障害(物事をうまく進められない)
などです。
【認知機能訓練】
ここで注目されやすいのが「認知機能回復」です。
昨今では認知機能に効果があるといわれる計算ドリルや読み書き、塗り絵、パズルなどがあります。
これらを「認知機能訓練」とします。
私も作業療法士として、機能回復を目標に「認知機能訓練」をたくさんしてきました。
結果は…、「?」でした。
そもそも「認知機能訓練」によって良くなっているのか?という疑問が湧きました。
良くなるとはどういうことか?
確かに認知機能検査の点数は良くなる人もいますが、それにより「生活障害改善」につながっているのか?といった疑問が出ました。
「認知機能訓練」はそもそも、主に認知機能回復に焦点を当てたもの(そうでないものもあります)アンチエイジングや予防介護に向いていると考えられます。
【生活に焦点を当てる】
では認知症になったら何を優先すべきか、それは「生活」だと考えます。
まず生活を考える上の前提として認知症の方の特徴、一般的な周囲の対応から述べます。
特徴は
「手続き記憶」(服を着る、食事をする動作など身体が記憶していること)
「長期記憶」(昔の思い出)
「感情表現」
が重度になっても残る場合が多いといわれてます。
そしてその特徴から工夫すれば生活を豊かに、生活障害を改善することはできそうな感じがします。
ただし、本人は
「できること・できないことの区別がつかない」
「生活を規則正しく送れない」
「うまく意思表示ができず感情的になる」
など生活のコントロールがうまくできない状態です。
一般的な周囲の対応は「できないことが増えてくる」と当人へ手を差し伸べたくなります。加えて、そのお手伝いの多くは過度になりがちです。そして次第に、できるはずのことも、できなくなってきます。
今までのお話を生活面からまとめますと
①認知機能低下②生活のつまずき(生活障害)③過度に生活を手伝う④さらにできなくなること増える⑤認知症進行の悪循環に陥りやすくなるといえます。
【生活フォローの方法】
ではどのように生活をフォローしていくのがよいか?
私達も仕事と余暇と休息のバランスが崩れると心身も崩れるのと同じで認知症の方も生活のバランスが崩れると心身も崩れます。
生活障害に対するフォローの目安は
「本人がストレスに感じていないかどうか」
「楽しくしているかどうか」
「疲労が残らないか」
と考えます。
では、どなたがそれをするのか?余裕のあるご家族へは、認知症や対応に関して理解を深める取り組みも有効ですが、高齢であったり、キャパシティオーバーの方もたくさんおられ、そのため適切な生活のフォローをご家族へしていただくことは困難な場合が多いといえます。
【専門職の役割】
ここで、介護職の役割が大きいと感じます。
介護職は生活に密着したサービスですので、
生活活動を一緒にすること、あるいは促すことで、自然と認知機能は維持されると考えられます。ストレスが少なければBPSDも軽減する可能性があります。生活習慣は知らない間に身体も気持ちも認知機能も使います。
作業療法士も「できる・できないの判断」や、「生活の組み立て」など、介護職と連携をとっていきます。
【認知機能訓練の是非】
経験上「認知機能訓練」で劇的に生活や認知機能、感情面が良くなるものではありません。あくまで「生活習慣」の一部として楽しみとして行うと堅苦しくないかもしれません。本人の意思が伴わず、ストレスになるのであれば行わないほうが良いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
