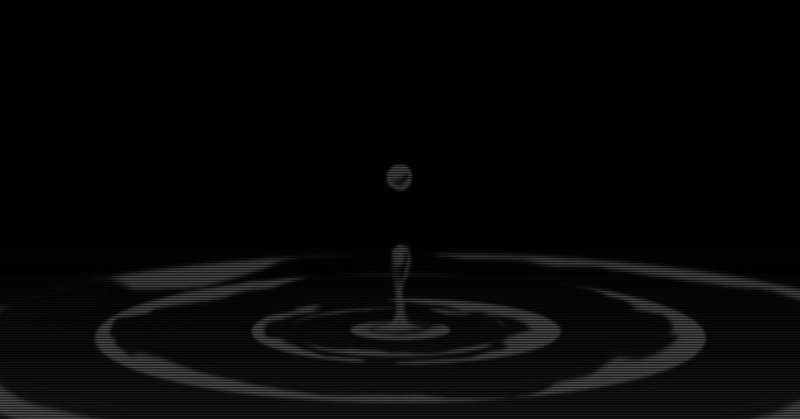

俺は源沖継。東京近郊の芳沢市在住、高校三年生。歳は十七だけど、明日、五月二十一日が誕生日でさ。もうすぐ十八歳って言った方が早いかも。
世間的には、十八歳ってひとつの節目らしいよな。
たとえばうちの両親は「十八になったらさすがにもう子供扱いできないな」だの「法的にも結婚できる歳ですしね」だの言いながら昔日を偲ぶ遠い目をしてたし、たまたま俺と生年月日が同じ親友の拓海も「競馬やパチンコ、車の免許、そして何よりエロ方面もついに全面解禁だな!!」なんて嬉しそうにはしゃいでたっけ。
でも、少なくとも俺には、この日を境にとうとう大人の仲間入りだぜ的な感慨は微塵もない。進路相談や大学受験が控えてる身の上で入籍なんぞ問題外だし、バクチも普通免許もポルノもぜーんぶ来年春の卒業式までお預けだって生徒手帳の校則欄に書いてある。もし破れば良くて停学、悪けりゃ退学だ。拓海のヤツも知らんハズはないから冗談飛ばしただけだろうが、万一本気で言ってんならアホにも程がある。
もう十八歳、ってよりも、まだ高校生。
それが現実。
明日になれば戸籍上の数字がひとつ増えて、連綿と続いてきた日常の一部が繰り返される。それ以上でもそれ以下でもなし。実際、十七歳と三百六十四日目だった今日を振り返ってみても、何かしら劇的な変化が起きる予兆なんて全くなかったもんな。
○
まず朝、俺はいつも通りにスマホのアラームで目を覚ました。
「……っハわっ!!」
上体を撥ね起こすのと同時に枕元のスマホを手に取り、アラームを止める。夢の世界から現実に戻ったんだと納得し気持ちを落ち着かせたところで、布団に包まれたままの腰から下へ手を入れ、注意深くまさぐって状態を確認して――よし、大丈夫。特に問題なし。
俺はベッドを降りて、パジャマ代わりの半パン姿のまま部屋を出た。我が家はどこにでもあるような二階建ての小さな建て売り住宅なので、階段を下りればすぐにリビングだ。
「あら、お早う沖継。今日も時間ぴったりね」
朝食を作っていた母さんが俺の気配に気付いて、キッチンの方から顔を出す。何となしに口元を押さえた左手の薬指には趣味の悪いスカルモチーフの指輪が光ってるが、顔に浮かべたニヤニヤ笑いはそれ以上に趣味が悪かった。
「今日は、ベッドのシーツ、替えなくていいの?」
俺の足元から頭のてっぺんまでじろじろと見回しながら訊いてくる。
これだよ、ほんとにこの母親と来た日には。
「今朝はノープロブレムだよ! つーかうっかり暴発しても全部自分で処理するからって何度も何度も言ってんだろ! 朝っぱらから息子を変な目で見んなっ!」
「そんなに照れないの。沖継が正常な男の子だっていう証拠なんだから。恥ずかしがることなんてなーんにもないのよ?」
「正常な男の子はそういう部分に親が干渉するのを死ぬほど嫌がるものなんだよ!」
「わあ、正論。ごめんね、ついつい息子の成長が気になっちゃって」
ぺろっと小さく舌を出し、母さんがキッチンへと戻っていく。
俺が言うのも何だけど、うちの母さんは綺麗な人だ。愛嬌も人一倍ある。だからこんなキワドい会話をギリギリ許容できてるんだけど、普通なら嫌気が差して仁義なき親子喧嘩に発展、そのまま積み木崩し的な家庭崩壊に至ってもおかしくないと思うんだが。
まあでも、気にし過ぎても仕方がない。こんなのはいつものことだ。とっとと洗面台に行って寝癖を取って顔でも洗ってこよう。目も覚めるし気分も変わるだろ。
俺が通ってる都立芳沢高等学校の男子制服は黒詰襟に金ボタンの典型的な学ランなので、それを着て家を出る。季節柄ちょっと蒸し暑いけどアンダーはTシャツだけだし、前のボタンを開けときゃそれで充分。車庫から愛用の安物自転車・MTBモドキ号を引っ張り出して走り出す。
するとすぐ、歩道やら交差点やらを数人で固まって歩くセーラー服姿の女の子を見かけるようになる。俺と同じ学校の女子たちだ。
最近はもう学ランとセーラー服それ自体が絶滅危惧種なんで、見た目だけなら伝統のあるお上品な名門校みたいなんだけど、うちの高校は全国平均よりちょっと上に位置する程度の超フツーな公立校なので誤解なきように。ほらほら、どこにでもありそうな何の変哲もない鉄筋コンクリ建ての校舎外観が全てを物語ってやがりますよ。
「よう、源」
「あ、源くん、おはよう」
俺の姿を見かけて挨拶してくる知り合い連中に「おーっす、おはよー」なんて返しつつ校門を潜り、MTBモドキ号を駐輪場へ放り込んで昇降口へ向かう――と。
ばさばさばさっ。
上履きを取り出そうとして下駄箱の扉を開けた途端、封筒、便箋、付箋、カードその他、紙切れの類が滝のように流れ落ちてきた。女の子らしい丸っこい文字で「源くんへ」と宛名書きされたものがほとんどだけど、中にはキスマークつきのEメールアドレスもある。
これも、いつものこと。慌てず騒がず一通ずつ大切に拾い集めて、バッグの中へ。
続いて朝のホームルーム。以前行われた大学入試模擬試験の結果が出たらしい。担任の教師が結果通知表をクラスの一人一人に手渡していく。
やがて俺の順番。大学受験を控えた身の上だから人並みに結果は気になるんだけど、ざっと見る限り問題はなさそうだ。偏差値もいつもの水準で安定。
「源、何か悩み事でもあるのか。先生でよければ相談に乗るぞ」
いきなり担任が話しかけてきた。しかもやたらとシリアスな顔で。
「すんません、意味わかんないんですけど。何のことですか?」
担任は無言で、俺の手元にある通知表の片隅、地域別順位を指差した。
いつもよりか十か二十くらい、順位が落ちている。
「ひっかけ問題をミスったんじゃないですかね。設問の意図が掴めなかったヤツが一つだけあったんで。解けなかった訳じゃないですよ」
「本当にそれだけか?」
「上位は一点差で何人もひしめき合ってるんだし、ポカミスでもこのくらい変動しますよ。そんなの先生が一番よく知ってるでしょ?」
「先生はなあ、お前の将来が楽しみなんだ。この天才は将来どんな大物になるのかと」
「…………」
「期待してるぞ、沖継。先生のためにも頑張ってくれ」
何であんたのために頑張らにゃいかんのだ。
まあ、教師に過度な期待をされるのもいつものことだし、気にしない。
四時限目は体育。野球。もうじきクラスマッチが開かれるのでみんな練習に熱が入る。特に三年生は有終の美を飾って終わりたいって気持ちが少なからずあるものだから、みんな結構真剣に取り組んでいた。もちろん俺も例外じゃない。
「ま、エースで四番の沖継がいる限り、俺たち三年五組の優勝はぜってー不動だけどな」
クラスメイトの一人が気楽に言う。いやいや、勝負はやってみるまでわからんぞ?
「おい、沖継。ちょっと来い」
授業が終わって解散した直後、体育教師に呼び止められた。ああもう後にして下さいよ、早く着替えして購買に行かないとからあげ弁当争奪戦に敗北しちゃうじゃないですか!
「心配するな、源。お前の昼食は校長室に用意してある」
「……あの、まさか、また、ですか?」
連れて行かれると、案の定。校長の他、背広姿の数人の大人たちが俺を出迎える。
「すみません、俺、プロスポーツ選手とかぜんっぜん興味ないんで」
用件なんてわかりきっているので、先手を打って話を潰しにかかったんだけども。
「まあ、源くん。そう言わずに。箸をつけながら、話だけでも聞いてくれないか」
なぜか校長が申し訳なさそうに額を掻きつつ言い、テーブルの上に置いてあった鰻重を勧めてくる。何でアナタがスカウトのフォローをしてるんですか。まさか買収でもされたんじゃあるまいな。
「君は間違いなく、十年、いや、百年に一度の逸材なんだ!」
スカウトの人が熱っぽく語り始めたんだけど、俺にとってはメシがまずくなる類の雑音でしかない。球界一の名門だか何だか知らんけど、おたくの会社の耄碌おじいさまの下で働くなんて御免被ります。
「私は絶対に諦めないよ、源くん。明日はカツ丼がいいかな?」
アンタまさか、これを俺の日常にする気か。諦めろよいい加減に。
俺は特に部活動も課外授業も受けていないので、放課後はたいてい、朝受け取った大量のラブレターを読んで返信を書く作業に追われることになる。
こればっかりは「いつものこと」なんて気分で適当に済ませる訳にはいかない。俺にとっては毎日似たようなことの繰り返しでも、差出人の中には一世一代の決心をして筆をとったコもいるんだから。
夕陽のオレンジ色に染まった教室で、俺はひたすら真剣に便箋と向き合い続ける。
ごめんね、すまない、申し訳ない、許してくれ、気を悪くしないで――。
ああもう、どうやったって似たような文面になっちまう。文才ないなあ、俺。
「……あの、沖継先輩」
突然、俺の背後から女の子の声がする。
いや、突然と言っても、気配はずっと前からはっきり感じてたんだけども。
ちらっと振り返ると、案の定、一年生の見知った後輩だ。
彼女とは以前、文化祭の出し物の手伝いをした時に一緒に作業することがあって、それ以来たまに話をしたりする仲なんだけど、数ヶ月前からちょっと妙な雰囲気が漂い始めて、それとなーく距離を取ってたんだ。直に会うのは久しぶり。
「ごめん、今ちょっと忙しいんだ。もうすぐ終わるんで、用事はその後に……」
言いかけたところで、いきなり後輩が俺の背中に抱きついてきた。
「好きです、先輩」
来ました恋のマジックワード。しかしそれだけはどうか避けて欲しかった。
でも残念ながら、俺の中にOKという選択肢は存在しない。やんわり断らなきゃいけない。なるべく傷つけたくないので、精一杯の優しさを込めて。
「ごめん、気持ちは嬉しいんだけど」
しがみついてきた彼女の腕を解きながら言う。こんな時ですら手紙と同じ、似たような台詞しか出て来ない。向こうは全身全霊で訴えてきてるのに、その気持ちの十分の一すら応えてあげられない。それが口惜しくてたまらない。
「で、でも、沖継先輩、誰とも付き合ってないんですよね?」
「残念ながら、彼女いない歴イコール年齢の記録を更新中だよ」
「じゃあ、誰か他に、好きな人が……。やっぱり、滝乃先輩とか……」
「いや、コノはどーでもいいんで。ほんと関係ないよ、あいつは」
「他に好きな人が居てもいいんです、遊びでも、身体だけの関係でもっ」
おいおいおいおいおいおいおいおい。この歳でどこまで思い詰めてるんだよっ。
「私、本気ですよ?!」
こりゃまずい。目がマジだ。
できれば誰も傷つけたくない、なんて中途半端な構えで相対してたら、惚れた方も惚れられた方も揃って不幸になりかねん。仕方がない。覚悟完了。
「実は俺、男にしか興味ないんだ」
「…………」
「ダチの拓海と心の底から愛し合ってる。だから、君とは交際できません」
もちろんウソだぞ。俺は骨の髄まで異性愛者だし、拓海なんぞに愛を語るなんて冗談でも願い下げだ。
ただ、俺がこういう状況になった時はこのウソをつくぞ、ってこと自体は、拓海の承認をちゃんと取ってあるんだ。もしフッた女の子が「証拠を見せて下さい」と食い下がってきた場合、一回一万円で俺の熱烈なベーゼを受けてくれる手筈もつけて。
とはいえ幸いなことに、これまで告白してきた女の子たちはウソをついた時点で引き下がってくれたんで、拓海とのトラウマ級ファーストキスを経験せずに済んでるんだけどね。はてさて、かなり思い詰めちゃった彼女はどう出るのか――。
って、何で泣き出しちゃうの?!
いやちょっと待ってどうしてお願い泣かないで!!
「ウワサ、で……聞いてた、通りで……何もかも……。やだ、もう……」
ぽろぽろと、大粒の涙がこぼしながら。
それでも彼女は、俺の目を見て、無理にでも笑おうと頑張って。
「やさ……し、すぎます、よ。先輩……。私が、勝手に……好きに、なって……。なのに、私を庇って、そんな嘘……。そんなことされたら、ますます……。もう、絶対OKもらえないって、わかったのに……わかっちゃったのに……」
それだけでも、情が深くて優しいコなんだなって、伝わってくる。
でも、そうわかっていても、俺は。
「……ごめん」
手垢がついたありきたりの言葉しか、かけてあげられなくて。
あとはもう、夜六時前の強制下校まで彼女の側にいて、ひたすら慰め続けた。彼女に魅力がない訳じゃない、俺が変わり者なだけだと納得してもらうまで、誠心誠意。
あ、こんな事件はさすがに、滅多にあることじゃないぞ。こんなのが日常だったら俺の心が保たない。告白するのも勇気が要るだろうけど、断るのだって辛いんだ。
すっかり暗くなってしまったので、告白してきた後輩の女の子をちゃんと家まで送り届けて、やっと帰路に就く。
時刻は夜の八時をとうに過ぎていた。すっかり暗くなった河川敷の土手の上、アスファルトが敷いてあるサイクリングロードをMTBモドキ号で走り抜けていく。
「……あれ」
異様な気配をふと感じてフルブレーキ。サドルに跨がったまま足をつき、土手の下、傾斜を下って空き地を抜けた先にある闇の中をじっと見つめる。
俺、視力にはかなり自信があるんだ。夜闇も苦に思ったことがない。目玉に暗視装置でも入ってるのかって呆れられるほどなんで、すぐに気配の源泉に気がついた。
そこは結構大きな廃工場。開きっぱなしの窓や崩れた壁の向こうに、一昔前で言うところのチーマーやカラーギャングの類が集まってる。二手に分かれて睨み合いながら、そろそろ抗争を始めますよーという殺伐とした雰囲気をプンプンさせてんの。
あ。うわあ。
たった今、本当に殴り合いが開始されました。
平和を愛する善良な一市民であるところの俺としては看過できないので、とりあえず自分のスマホを使って警察へ通報しといたんだけど、さて、それだけで事足りるかどうか。最寄りの警察署から今すぐパトカーが出たとして到着までざっと十五分。道路の混み具合によってはもっとかかるかも。廃工場の正門が封鎖ないし施錠されてて手間取れば、警官が現場に到着した頃には何もかも終わってたりして。
怪我人だけで済めばいいけど、下手すりゃ死人が出かねんぞ。
だって、衝突してる二つの勢力。片方は四、五十人いるのに、もう片方はその半分以下なんだよ。少数勢力の方が士気は高いらしくて今のところ互角にやりあってるけど、根性だけでひっくり返せるような戦力差じゃない。善戦すればするほど多数派の傷を増やして怒りを買うだけ。遅かれ早かれ明暗はクッキリ分かれるだろう。興奮状態で余力を残した勝者と、逃げる気力も失った満身創痍の敗者。自制心ゼロの一方的なリンチの幕開けだ。それは悲観論でも未来予想でもない。自明の理、当然の帰結。
止めるべきだ。一刻も早く。
そう決断した次の瞬間、俺はMTBモドキ号に乗ったまま土手の斜面を猛スピードで駆け下りて廃工場へ一直線に突進。二つの勢力がぶつかり合うど真ん中に猛然と殴り込みをかけた。ていうか、何人か轢いたり撥ねたり踏んだりした。ギャッ、グエッ、ゲボッ、とかいう声にならない声を上げたきり起き上がってこないのもいるけど、大丈夫。大怪我しないようにちゃんと加減したから。問題ない。
「はいはいはい、みなさん落ち着いて。日本人なら和の心で共存を」
MTBモドキ号を降りて両手を挙げ、注目を引くよう声を張り上げる。どちらの陣営も第三者の乱入を想定してなかったらしく、俺の方へ一気に視線が集中、抗争は一時中断。
よし、これでいい。このまま少しでも長くお喋りを続けて時間を稼ごう。
「あっ、あンた、沖継さンじゃなっスか!」
弱小勢力のリーダーらしきヤツが、こういう人種に特有な滑舌の悪さで俺の名前を呼んできた。こんな面白ユカイな髪の色と髪型してるヤツに知り合いなんて――あ、いや待て、かすかに歪んだその鼻は見覚えあるぞ。だって俺が殴った跡だし。
「お前、まだこんなことやってたのかよ?! もう喧嘩すんなっつったろうがっ!」
本当はこのリーダー、俺よりだいぶ年上らしいんだけどさ。今までさんざんブン殴って言うこと聞かせてきたもんだから、俺の方が兄貴分になっちゃったんだよな。
なもんで、いつもなら俺が一喝すれば「すンません」となって終了なんだけど。
「いくら沖継サンのメーレーでも、こンどばッきゃア聞けねェワ」
睨みを利かすな、別に迫力ねえから。ていうかお前は何でそんなに滑舌悪いんだ。
「コイツら、こン街でアイスやハーブを捌いてやがンだ。裏でヤクザと繋がってンのさ。オレのツレも十人近くヤられてる。こンままじゃこいつらもっと図にのって……」
そのリーダーの話が終わる前に。
俺は手近に居た敵対勢力のチンピラにハイキックを叩き込んだ。そいつは「うびゃら」とか変な声を上げて数メートル横へ飛んでいく。前歯が吹っ飛んで鼻も曲がって血ィダラダラ出てるけど、大丈夫、気絶しただけ。なーんにも問題ない。
「リーダー、敵のボスはどいつだ? 縛り上げて警察に突き出そうぜ」
突然のことに大口開けてポカーンとしていたリーダーに話しかけつつ、俺は制服のポケットから紳士のハンカチを二枚取り出し両手の拳に素早く巻き付けた。素手で人を殴ると皮が剥けるし、折れた歯が刺さったりすることもあるから。
このリーダーは嘘がつけるほど器用じゃない。憶測や思い込みで極論を言うほど頭がおかしい訳でもない。先の話は充分信じるに値する。
「ま、マジすか……!! 助かった、アンタがいりゃゼッテ負けねェよ!!」
弱小勢力、もとい、俺たち正義の軍団が気炎を上げて敵に襲いかかる。乱闘再開。
「沖継サンの居るこン街で! 勝手できッと! 思ンじゃねェぞッラぁ!!」
いや、お前ら、あんまり俺の名前を連呼すんなよ。一歩間違えば退学なんだぞ。こんなの日常にしたくないから。今夜だけだぞ、今夜だけ。ほんとに今夜だけな。
夜の十時過ぎになって、やっとこさ家に戻ってくる。
「……疲れた……」
喧嘩自体は俺たちの圧勝、しかも十分ちょっとで終わったんだけど、薬物売買の主犯格をとっ捕まえた以上は最低限の事情聴取は受けなきゃいけなくて。いや、地元の刑事さんや署長さんとはすっかり顔なじみだし、これでも早めに帰してくれた方なんだけどさ。
「おお、沖継。遅かったな。どうした、ずいぶんしんどそうな顔をして」
二階にある自室へと階段を上がる途中、たまたま廊下を歩いていた父さんが声をかけてきた。ここ数年で一気に禿げ上がった頭が薄桃色に染まってるところを見るに、奥の書斎に一人で籠もって晩酌でもやってたのか。部屋着の和服姿も相まって、見た目は磯野家の大黒柱にそっくりだった。
「実際しんどいんだよ。ごめん、もう寝る。風呂も飯も明日の朝に……」
「まあ待て。一分だけでいい、話があるんだ」
「? 何だよ、またテレビ局が何か言ってきたとか?」
「さすが勘が鋭いな、その通り。噂のスーパー高校生を取材したいんだと」
「あいにく、ミナモトさんちのご長男はマスコミ嫌いなので。どうか平穏無事な毎日を平和に過ごさせて下さい……ってことで、適当に断っといて。あと、スーパー高校生、って言い方はセンスないですよってツッコミもよろしく」
「そう言うと思ったが、一応本人に知らせないといかんだろ」
苦笑しながらバツが悪そうに左手で頭を掻く。薬指には母さんとお揃いの悪趣味な指輪が鈍く光っていた。あれでも一応結婚指輪らしいからつけっぱなしで当然なんだけど、和服姿の時くらいスカルモチーフは避けた方がいいんじゃないですかね父さん。
「それとな、沖継。明日は早く帰って来い。夕方四時半を厳守だ」
「放課後、直帰してこいってこと? 何で?」
「十八歳の誕生日祝いだ。親戚連中も来ることになってるから」
「何だよ、誕生日くらいで大袈裟な」
「まあそう言うな。待ってるからな、学校が終わったら真っ直ぐに帰って来いよ」
「はいはい……」
部屋に入る。荷物を投げ捨て、制服を脱いで、シャツとパンツだけでベッドに倒れ込む。
(どうか、今夜も……。逢えます……ように……)
夢でしか逢えない愛しいひとのことを、密かに想いつつ。
俺は自分の意識を手放して、一日を終える。

○
以上が、俺の十七年と三百六十四日目の全て。滅多に起きないことも若干含まれてたけど、何とかギリギリ「俺の日常」と呼べる範囲の出来事だ。
そんな高校生が居る訳ないとか、中二病的な妄想だとか、共感できるのは朝の暴発と彼女いない歴イコール年齢と脳内彼女の話だけだとか、いろいろと言いたいことはあると思うけど。俺は誇張も歪曲も一切していない。どうかそれだけは信じて欲しい。
明日、十八歳の誕生日も、どうせこんな調子なんだろう。ただ違うのは、年齢を示す数字が戸籍上で一つ増えるだけ。つーかこれ以上めんどくさい事件が起きてたまるか。
――と、思ってたんだけど。
現実に訪れた十八歳の誕生日は、俺の予想のはるか上、成層圏どころか地球圏も太陽系も銀河の果ても飛び越えて、時空すら突き抜けていきやがった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
