
「キャリアデザイン」と「キャリアデザインを学ぶ」ということについて
当記事をご覧頂き有難うございます。
・コロナウイルス感染症による自宅待機で、まとまった時間ができたこと
・友人からキャリアコンサルタントについて多く質問をいただくこと
・アパレルブランドからの応援
上記3点を受けて、
つらつらと書くことを決めました。
読んでもらう上で少しでも気づきがあったら嬉しいですし、
多くの人の目に触れるようであればブラッシュアップもしていこうと思います。
=応援してくださったブランドの紹介=
After Workを気張らず過ごす。“LauleaBeach”の応援で成り立っています。
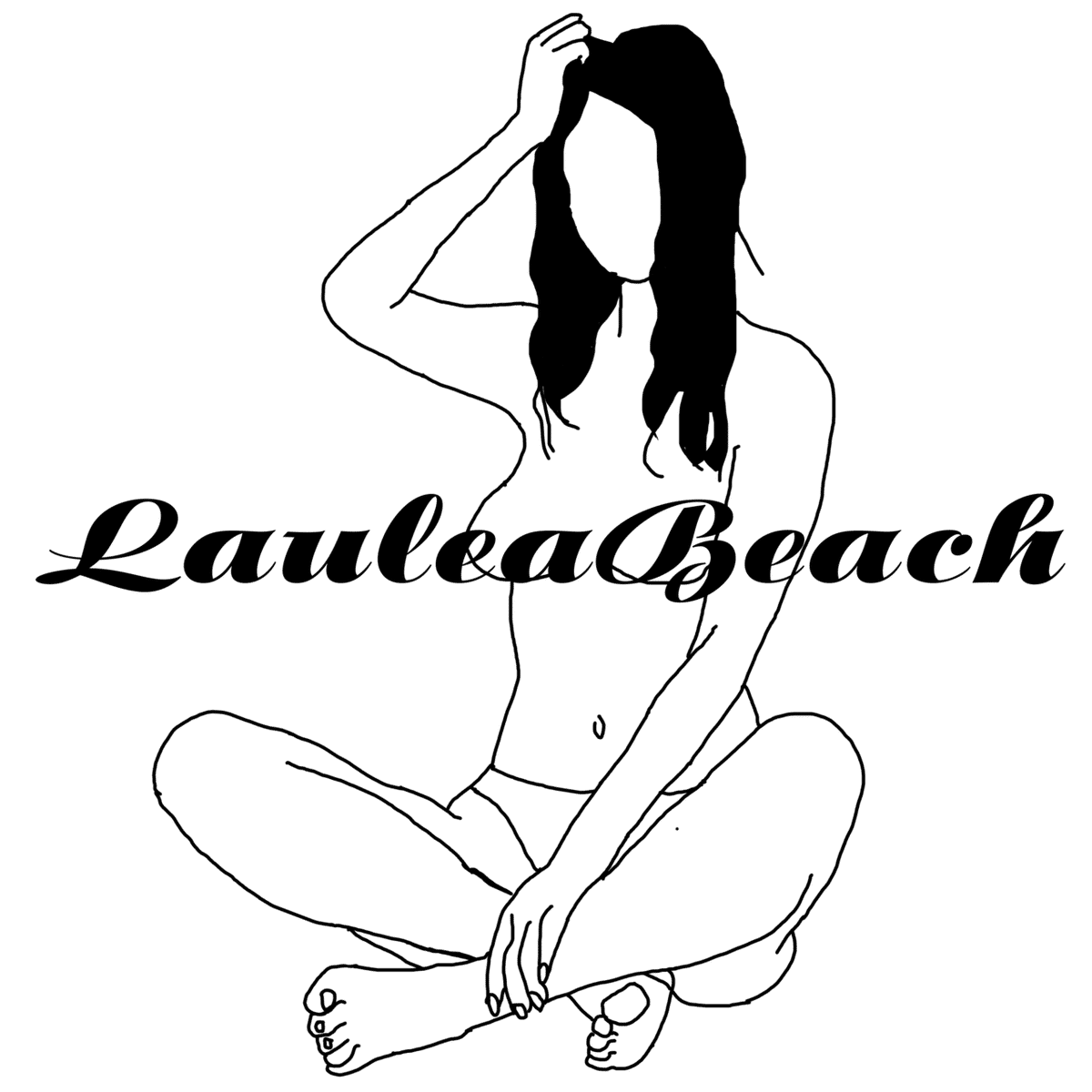
■当記事でお伝えしたいこと
<キャリアに迷いがある人へ>
・今後のキャリアを考えるうえでの大大前提をお伝えします。
・それぞれの相談先のメリットデメリットを考えるヒントをお伝えします。
<キャリアコンサルタントに興味がある人へ>
・キャリアコンサルタント資格を取るうえでできるようになることをお伝えします。
・どんなことをしたい人が挑戦するとよいと思うか個人的見解をお伝えします。
■お伝えすること
(1)自己紹介

#国会資格キャリアコンサルタント #講演家 #体育会 #オリンピックマルチサポート事業 #新卒就活支援
【本業】
年間100本程度の講演会等登壇講師(中高生向けキャリア教育等)をしたり、割と何でもやさんをやっています。キャリアデザインや学習など、資質能力(コンピテンシー・アダプタビリティ)の育成が専門です。
【本業外】
2017年~現在 新卒就活相談。100人以上の大卒後の進路相談相手に。
2019年 キャリアコンサルタント講座受講。
2020年 国家資格キャリアコンサルタント合格
学生時代は早稲田大学体育会活動の毎日。
新卒就活まで「仕事」なんてことには興味もなく、
ただ時間を過ごしていました。
そんな学生時代の最後に
ひと世代上のある人が立ち止まる機会を作ってくれた。
「輝ける時間を見つけられるあの人のおかげだ」
そう思い、
私自身もキャリアデザインというものについて見識を深めていくことに決めました。
自分もあの人のような他人を輝かせられる人になりたいというところです。
元からそういう世話役が好きだったのは間違いありません。
そのほかは、
・文科省の委託事業でアドバイザー(運動力学)
・臨床心理(資格こそとってませんが)
・アパレルブランド立ち上げ(EC)→デザイン/販促などすべて。
などいろいろやっていました。
興味がある人は声をかけてください。
こんなところで、
どういう人間が書いているのか、
興味を持っていただけたようであれば嬉しいです。
今回は私が合格したという国家資格キャリアコンサルタントの学習過程で「学んだこと」をまとめたいと思います
その前に、、、、、
そもそも「キャリアコンサルタントって何なの」という疑問に答えましょう。
(2)日本におけるキャリアコンサルタント資格
<国家資格キャリアコンサルタントの基本情報>
国家資格キャリアコンサルタントは、
2016年4月に職業能力開発促進法を受けて国家資格化したものです。
裏を返せば、日本における歴史は決して深くはありません。
ただし、
国家資格化した後は急増しており、
50,376名(2020年03月末時点)まで増えています。
※厚生労働省キャリアコンサルタントwebサイトより
(https://careerconsultant.mhlw.go.jp/p/about.html)
国としても平成36年度末(2024年度末)までに登録者を10万人まで増加させることを目標としており、
今後の活躍が求められている分野ととらえています。
日本のような終身雇用がうたわれてきた中では浸透度が低いかと思いますが、
元から人材の流動性が高いアメリカでは非常に多いお仕事にもなっており、「キャリアカウンセラー」といわれていたりします。日本以上に名乗るためのハードルが高かったりするため、実状は異なることもあります。ただし、日本のキャリアコンサルタントもアメリカでのキャリアコンサルティングの理念を取り込もうという意思が強く感じられますため、目指している機能は同じといえるのではないでしょうか。
<国家資格キャリアコンサルタントを取得すること自体のメリット>
・キャリアコンサルタントと名乗ることができる
・厚生労働省のキャリアコンサルタントに登録され仕事の依頼が来るようになる
以上・・・。
そもそも資格と免許の違いですが、
独占業務を持たない資格ですので資格を持っていることだけへのメリットはそれほど多くないことが事実です。
自己研鑽資格と表現するのが個人的にはしっくり来ています。
臨床経験を通して学び始めるうえでの、
最低限の知識・技能・志向性をもった人が取得できる資格だと認識するとよいかもしれません。
ひとまずはどんな人間が書いているかということと、
その人間が学習したことについて簡単にご説明をいたしました。
ここからは、
キャリア理論上どんなことが言われているのか、
可能な限りテキスト上での表現ではなく、
私自身の言葉で表現したいと思います。
(3)今後のキャリアを考えるうえでの参考にしたい理論について<本題>
■21世紀型キャリアデザイン~理論を統合的にとらえた4つの教訓~
身近に感じるシーンも日々増えてきましたが、
科学技術の発展や少子高齢化、グローバル化など社会変化を受けて私たちの働き方は大きく変わるとされています。合わせて、今回のコロナ感染症により私たちの働き方の変化スピードは間違いなく上がっていくことでしょう。
結果として、
副業、複業、独立するひとなども増えていくとされています。
あわせて、
企業側でも正社員として終身雇用を約束する人数を減らす
ということが起きてきます。
日本では非常にリストラはしにくいですが、
海外でいうリストラ層の待遇を下げ、
副業・独立を促すということは大いにありうるとされています。
そうした社会変化の中で、
「プロティアンキャリア(ホールの理論)」「キャリア構築理論(サビカス)」という考え方が話題になっています。
少し実際の理論と乖離があるかもしれませんが、
数多くの理論と日本人の思考を統合的にとらえ、
4つの教訓として表現したいと思います。
①他人のものさしからの脱却せよ
②所属よりも「スキルの向上」と「ありたい姿」の探索に努めよ
③仕事に限らず、これまでの経験を言語化せよ
④サラリーマンとして稼ぎたいなら業界をとらえよ
①他人のものさしからの脱却せよ
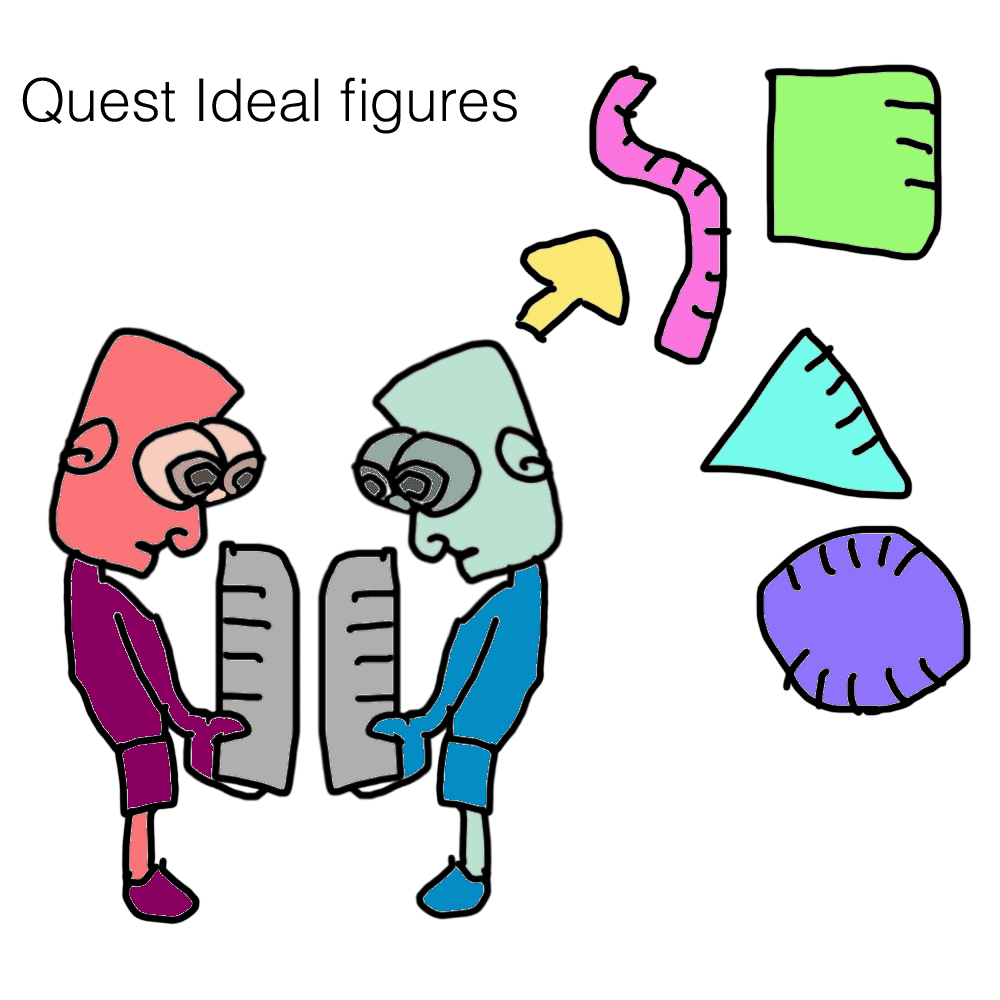
キャリアのPDCAのC部分が、給与や地位のような客観的な評価軸でなく、主観的(総合的満足度)であることが持つべき思考とされています。これまでの伝統的思考では、地位や賃金がキャリアの良しあしを判断する物差しとされていましたが、現在はそういった一律の指標での判断軸をよしとはしなくなっています。何よりも客観指標として置かれていた「金」「地位」は外部変化による影響度が大きい。そして外部変化はコントロールしにくいということから生み出された思考と捉えています。何よりもこの考えの中で大事なのは「偶発的出来事」に対して、どれだけポジティブに迎えられるかということです。そのうえでは他人の物差しではなく、自分の中に物差しがあることがあなたの「幸せ」や「最大のパフォーマンス」のためには重要ではないでしょうか。ひとつひとつ自分で意思決定をするときに、「何故自分はその選択肢を選んだんだろうか」問いかけてみてください。あの人がこう言っていたから、あの人がこうしていたから・・・。そこにあなたの「ありたい姿」は存在するでしょうか。
②所属よりも「スキルの向上」と「ありたい姿の探索」に努めよ

責任の所在が企業ではなく、個人に変わるといわれています。
先ほど社会変化について記載した通り、
東証一部上場企業に入社できれば人生勝ち組だとか、
そういうことはないということです。
企業側からの減給等も容易に想像ができ、
いざその時になってから、「こんなはずじゃなかった」
なんていうのはもう甘えという時代に突入しているということになります。
仮にリストラ等の偶発的な状況を迎えても、
別の場所で働くことができる
能力と志向性(ありたい姿)を持っていくことが重要です。
※理論ではもっと細かく言われていますが・・・。
ここでいう能力と志向性とは、
何か偶発的な出来事があった際に、
「対応ができる、順応できる能力」と、
「次の選択肢の優先度をつけることができるための在りたい姿の解像度の高さ」
といえると思います。
特にありたい姿の解像度が低い人にありがちなのが、
「私はどうしたらいいのでしょう」と外に答えを求めようとする姿です。
これほどまでに能力でなく、
解像度の低さから変化に順応できなくなっています。
③仕事に限らず、これまでの経験を言語化せよ

キャリアコンサルティングを学ぶ上でキャリアの定義は非常に幅広く定義をされます。
ハローワークへはこんな相談があるそうです。
「ずっと専業主婦をしていて、子供を産んでからずっと仕事をしていないんです。こんな私にできる仕事なんてあるのでしょうか」
何が問題かというと、
キャリアを非常に狭くとらえてしまっていることです。
“キャリア”について我々キャリアコンサルタントはこう定義します。
“その人がこれまで経験(事実と感情)してきたことすべて。”
こういったこともあり、
ボランティアや趣味で行っていたことも棚卸をして、
実際の仕事に還元しているなんて人も多くいます。
少しユニークなものであれば、
NTT社員がとんでもなく強いゲーマーだったということで、
E-sportsの子会社立ち上げたみたいな話もありました。
https://www.asahi.com/articles/ASN1Z56VPN1WULFA041.html
あなたの過ごしてきた時間すべてがあなたの特徴になります。
誰しも時間は有限ですから、
必ずしも自己投資らしい投資をしていない人にも特徴(強み)は備えています。
※市場価値(希少性)はまた別軸だとは思いますが・・。
あなたの強みと価値観をしっかりと整理していきましょう。
具体的な手法については、
後程続編で書きたいと思います。需要があれば・・。
④サラリーマンとして稼ぎたいなら業界をとらえよ
市場価値のお話ももちろんそうですが、
市場価値以上に給与への影響度が高いのは業界といえます。
分かりやすいたとえとして、
野球選手とバスケ選手のプロでの給与などが比較されたりします。
優秀さだけでなく、業界による待遇の違いが多いと言えるでしょう。
このことについては受け売りです。
どんな本でもよいですが、
転職の思考法などは非常に学びの多い本だと思ったので読んでみてもよいのではと思います。
いかがでしたでしょうか。
随時追記・修正行いながら整理をしていきたいと思っています。
誹謗中傷は疲れますが、建設的なご意見いただけますと嬉しいです。
ここまでこれからのキャリアデザインを考えるうえでの教訓を紹介してきました。
是非とも自分の在りたい姿と向き合っていってくださいね。
最後に
キャリアについて相談したい・・・。
と思ったときにどこに相談すればよいのかということ紹介して終わりたいと思います。
(4)キャリアコンサルタント(CC)とキャリアアドバイザー(CA)の違い
よく混同されがちなのが、
キャリアコンサルタントとエージェントのキャリアアドバイザーです。
両方を備えた人も多くいるために記載をすることがよろしくないことは事実です。が、しかし、CCへの苦言を呈す声もあるため、何ならできるのかを明記をしておきます。
■CC特徴
・資格取得の過程では人材市場はかじる程度。市場感覚は身につかない。
・専門は相談者の意思決定支援
自己概念の開発・成長と表現をします。
その人自身の在りたい姿を言語化するお手伝いを身に着けています。
■CA特徴
・数多くの求人を扱い、企業人事とのやり取りをしていることで企業側が必要とする人材に詳しかったり、実際の業務についても情報を持っています。
・一方で、「面接を設定すること」「内定が決まること」などが CAの利益になる構造であることも事実のため、実際にCAとして働く人からは一人一人の相談にしっかり乗っていると売り上げにはならないなんていうことも良く伺います。(当然、理念ベースで運営を行い、丁寧に支援をしていたりもします。)
お互いの特徴を踏まえたうえで、
こんな流れでキャリアを考えていくといいのではないかというのが、
下の図の通りです。
(作成中)
CCにできないこと、
CAにできないこと(したら売り上げにならないこと)などがあると思います。
飽くまで参考程度にですが踏まえてもらえるとよいと思います。
(5)最後に考えていること
この記事については、
書き始めたもののタイムオーバーで詰め切れない部分が非常に多く、
多方への配慮が至らぬ個所も多く存在する可能性も多く含んでいると予想しております。
一方で、
日本人のキャリアの考え方の課題は非常に根深く、
1人でも多くの人が立ち止まるきっかけになればと思い、
3割レベルの完成度ながら投稿することを決めました。
たくさんの補足いただくことになるかと思いますが、
その内容随時修正点として組み込んでいき、
完成版のリリースに向けて動いていきたいと思います。
たくさんの意見、議論の題材お待ちしております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
