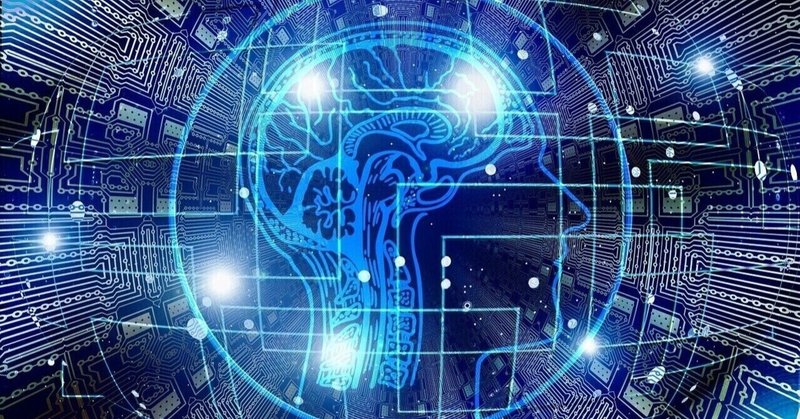
BlockChainについて薄く技術・ビジネス・社会の側面から触れる本
参考はこちらの本。ブロックチェーンの知識が名前だけの状態から読破。
結論
管理者不在・情報がオープン・即時性もある「インフラ」らしい。
要点1「管理者不在」
まず「管理者不在のインフラ」だという。あらゆるWebシステムではサーバーとクライアントが存在していて、中枢処理を施すサーバーを誰かが管理している。これは管理者が中心の中央集権的なシステムとなっているわけ。しかしこれには弱点がある。例えば、みずほ銀行のシステム障害においても、中枢の故障により多くのクライアントがトラブルに巻き込まれたことを思い出せ。まさにこれが中央集権の弱点。
そこでブロックチェーンでは「管理者不在で公平かつ障害に強い社会」を構築した。例えば「契約事項を処理する人間」が中枢の管理者以外に委ねられる、など。
なぜそんなことが可能なのか?誰も管理しなくても大丈夫なのか?
管理者は一人ではなく「不特定多数のユーザーが互いにチェックし合っている状態」を生み出している。不特定多数のユーザーが契約事項のチェックを行なっているイメージらしい。これにより不特定多数の一人に障害が発生しても、別の誰かが補完してくれるわけ。
どんなメリットがあるか?
・多極分散型構造なので障害発生に強い
・管理者がいない分、不特定多数にとっては情報の透明性が高くなる
・客観的指標に基づき、物事が動きやすい実力定量社会
具体的には?
・投稿記事の視聴数に応じて報酬が支払われる契約を作り出す。
→ ライターの質と信頼性できちんと評価されるシステム
→ 管理者による恣意的な制御が許されない
要点2「情報の公共化」
不特定多数の人間が契約をチェックするには情報がオープンにされる必要がある。そしてブロックチェーンでは過去に発生した出来事を網羅的に記録している。どこでいつ何が起こったのかが事細かに記録され、しかもそれが改竄できない・コピーできないのだ。
セキュリティに問題ないのか?
勿論、契約内容をそのまま白文でネットに公開されるわけではない。契約内容は自分が所有する秘密鍵で暗号化される。暗号化された状態でネットワークに公開される。当事者が所有する鍵でしか情報を確認できず、当事者たちが契約した「事実」をネットワークに公開するわけだ。
これらのチェックを行う不特定多数の人は、暗号計算を行い、ネットワークに改竄が無いか、正常かを決定する。この不特定多数の人はこれらの作業により得られる報酬目当てだが、この作業をマイニングと呼ぶ。
どんなメリットがあるか?
・情報が公共化されているので、相互に合意形成を獲得しやすい
・情報がオープンなので「誰が何を所有しているか」の追跡が可能
具体的には?
・製品規格やメーカーが異なるデバイス間の連携も、情報が公共化されているので、互いにコンセンサスを獲得し、連携していく社会となる。
・NFTに代表されるように誰の所有物なのか明確化、所有物の固有化。
→ 情報の不正コピーがなされることなく、製作物の価値の維持に繋がる。
要点3「即時性」
アナログの強みは資料は固有で複製するのに時間がかかるので不正に強い。
アナログの弱みは手続きが煩雑。
デジタルの強みは手続きが楽。
デジタルの弱みは資料は固有で複製するのが容易で不正に弱い。
先ほどまで述べた通り、ブロックチェーンはデジタルの弱みを崩したのだ。
ではデジタルの強みをどう活かすか?
ブロックチェーンではデジタルの強みをさらに進化させた。
仮想通貨で「Bitcoin」の次くらいに有名な「イーサリアム」では「スマートコントラクト」の機能を兼ね備えていることから、爆発的に人気が急増した。
今までは「取引合意+記録」だったのが、「スマートコントラクト」により「取引合意+記録+自動履行」まで兼ね備えるようになった。これが取引にかかる時間の省力や取引の流動性の底上げに役立つ。
どんなメリットがあるか?
・直接、当事者間で取引可能となり仲介手数料が不要になる。
・スピード感のある取引と取引の流動性を加速
具体的には?
・プロシューマーが消費者に電力売る時に、需給の兼ね合いからスマートコントラクトにより価格が決定し、仲介手数料が不要に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
