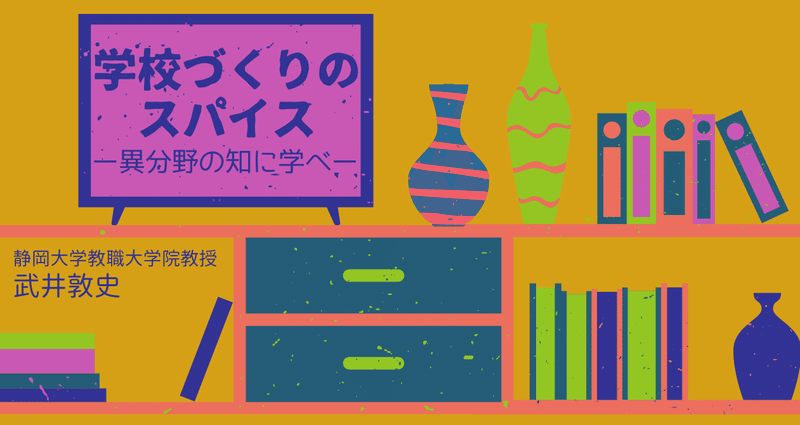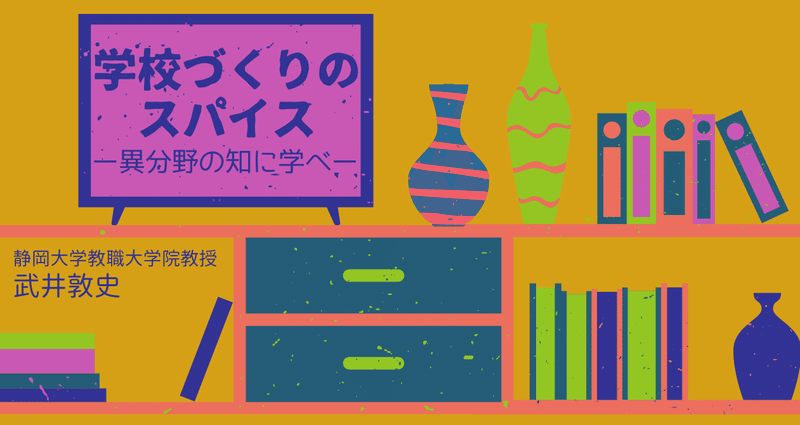#60 同調圧力克服法~大塚ひかり『くそじじいとくそばばあの日本史』より~|学校づくりのスパイス
教員にしても児童・生徒にしても、とかく「足並みをそろえる」ことが重視されてきたのが日本の学校現場です。この原因の一端は従来の日本社会のあり方自体に由来するものであろうし、よい面も確かにあるのですが、一方で学校という社会集団に必要以上の同調圧力を産む可能性もあります。
2021年の中央教育審議会でまとめられた、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)」においても「従来の社会構造の中で行われ