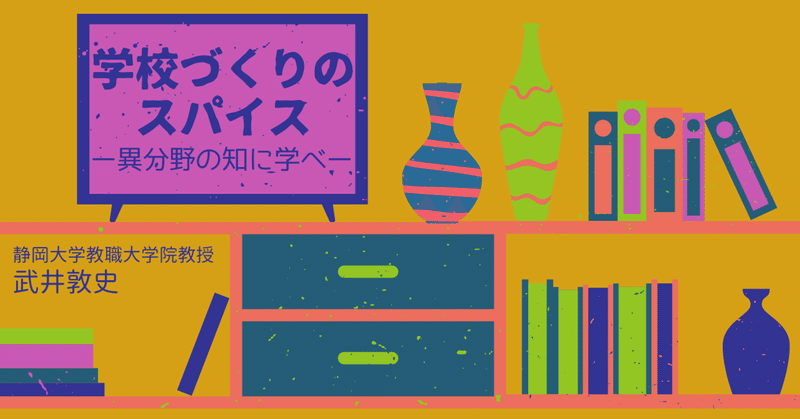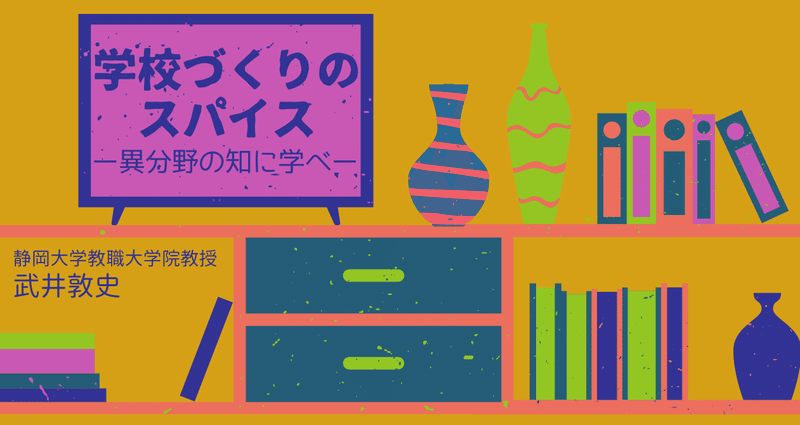
学校のリーダーシップ開発に20年以上携わってきた武井敦史氏が、学校の「当たり前」を疑ってみる手立てとなる本を毎回一冊取り上げ、そこに含まれる考え方から現代の学校づくりへのヒントを…
- 運営しているクリエイター
2023年1月の記事一覧
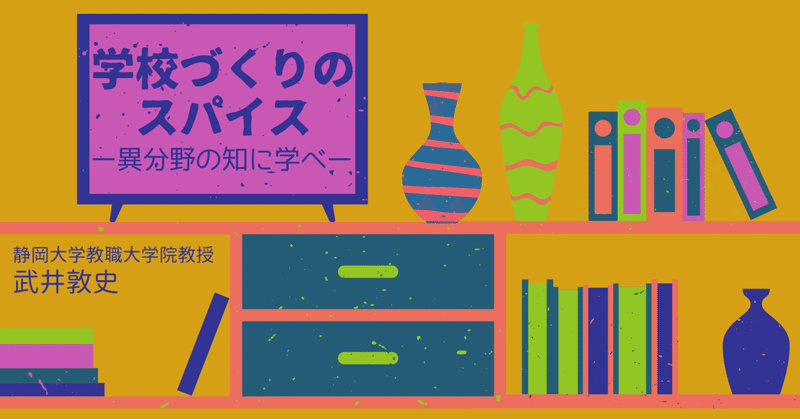
#43「複式簿記」思考を身につけよう~ 近藤哲朗ほか『「お金の流れ」がたった1つの図法でぜんぶわかる 会計の地図』より~|学校づくりのスパイス
ドイツの詩人ゲーテの文学作品に次のような一節が出てきます。 「複式簿記が商人にあたえてくれる利益は計り知れないほどだ。人間の精神が産んだ最高の発明の一つだね。立派な経営者は誰でも、経営に複式簿記を取り入れるべきなんだ」(ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代〈上〉』岩波書店、54 頁)。 複式簿記を学ぶ意義のある点については、学校経営者もその例外ではない、というのが今回の連載の結論です。今回は近藤哲朗、沖山誠、岩谷誠治『「お金の流れ」がたった1つの図法でぜんぶわ