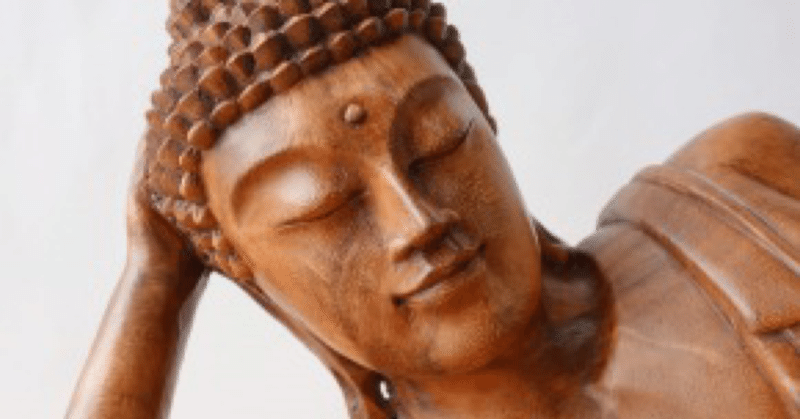
ブッダのおしえとは③四苦八苦、三毒
四苦八苦 の意味・使い方
非常に苦労すること。 ... 「八苦」は「四苦」に『愛別離苦(あいべつりく)』(親愛な者との別れの苦しみ)、『怨憎会苦(おんぞうえく)』(恨み憎む者に会う苦しみ)、『求不得苦(ぐふとくく)』(求めているものが得られない苦しみ)、『五蘊盛苦(ごうんじょうく)』(心身を形成する五つの要素から生じる苦しみ)を加えたもの。
『苦』は伝統的に『四苦八苦』という言葉で説明される。
その中、『四苦』とは生、老、病、死の四苦に「怨憎会苦」「愛別離苦」「求不得苦」「五蘊盛苦」を加えて八苦と呼ぶ。まず四苦の生は「生きる」の生しでなく「生まれる」の生である。輪廻の中の一個体として生まれて来ることを「生」と言いそれをさ「苦」ととらえて生苦と呼んでいる。「老」「病」に関しては体自体に身体的苦痛の自覚がある。ただし肉体的苦痛が全てではなく老齢という現実に対して青年時の記憶があることが労苦のほとんどを生んでいる。病苦に対しても同じで健康時の自分を知っていることが病苦の大半を作っている。さらに「老」「病」「死」に関しては予測的不安感が苦痛を増幅している。死はすべての個体が未経験であるにもかかわらずその状態を予想するだけで苦悩が広がる。労苦も病苦も未経験の「死」と繋がってることによって苦悩の度合いを増していくのである。
『怨憎会苦』と『愛別離苦』は本質的に同じことである。つまり避けたいと思う事柄に遭遇すること、そしてできればそうあって欲しいと思うことから離れて行くことは同じであってそれは次の『求不得苦』をまとめることもできる。求める状態と現実とのギャップが苦痛を感じさせるのである。いわば自己中心的な欲求を持つのかと言えば、それは我々が個体存在であり、五蘊(ごうん)が仮に作り上げた『自己=我』を実体あるもののように思い込み、仮想された自我に執着することで苦悩を生産する。これが『五蘊盛苦』である。
『我々の欲望つまり煩悩こそが我々の苦悩の原因といっていい』そしてその煩悩はどのような形で我々の心に起こってくるのだろうか。
『煩悩として現れる我々の欲望』
煩悩というのは心を錯乱しさとりを妨げるありとあらゆる心の動きをいう。煩悩の種類は六代煩悩や十代煩悩という分け方が一般的である。
六代煩悩
貪、瞋、癡、慢、疑、見
の六種であって最後の『見』が邪見、見取、戒禁取
、辺執見、有身見を入れて十代煩悩と呼ぶ。
六代煩悩の最初の3つは煩悩の中でも特に我々の判断を誤らせる煩悩なので『三毒』という
三毒(さんどく)とは、仏教において克服すべきものとされる最も根本的な三つの煩悩、すなわち貪・瞋・癡(とん・じん・ち)を指し、煩悩を毒に例えたものである。
六大煩悩はこれらに慢(まん)・疑(ぎ)・悪見(あっけん)が加わる。
「慢」は「自慢・慢心」の「慢」。「自」と「他」を分けた上で、自分を他より優れていると思うことである。
「疑」は真理や道理に対して疑いの気持ちを持つという心の働きである。例えば、「本当は原因・結果の法則なんてないんじゃないか」というような疑いだ。誠意が感じられない人に「あいつを信頼して大丈夫か?」という「疑」ではない。
最後に「悪見」。これは次の5つの煩悩の総称である。
1 「私という存在がある」と思ったり、「これは私のものだ」と思い込む発想
2 極端な見解に立つこと。死んだら無になるとか、死んでも自分の個性と記憶を引き継いだ魂は永遠のものだなどと考えることなど。
3 原因があって、結果があるという法則を信じないこと。
4 上記3点を真理として受け容れてこそ、悟れるのだと思いこむこと。
5 苦行をすれば悟れるなど、誤った真理への到達方法を信じこむこと
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
