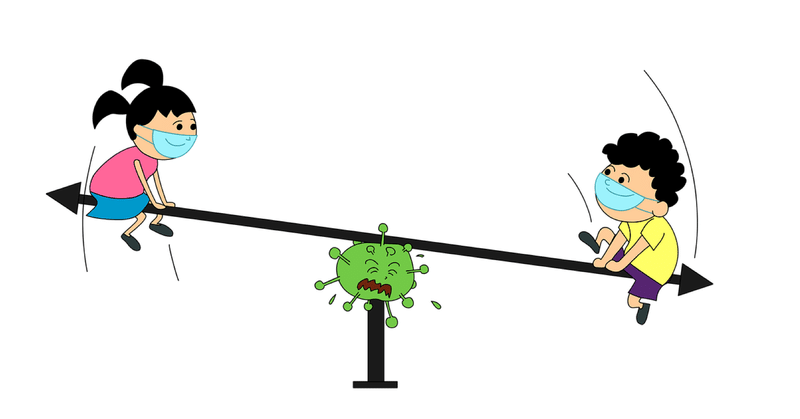
1月13日(巣ごもり六日目) 居場所を整えるために
再び緊急事態が宣言され、研究室内の昔のチャットを眺めながら、昨年四月の様子を思い起こしていた。3月にはいって、他大学は遠隔授業に切り替えていた。一方、ぼくが勤めている東京工業大学の意思決定はかなり遅かったように記憶している。3月末近くになって開講延期、遠隔授業、Zoom の使用が内々に知らされたように思う。
以下のメッセージは、好天に恵まれた三連休で人々が一斉に花見に出かけ、後に感染を加速させたと反省させられた時期に送ったものだ。この時点で、すでにロックダウンを覚悟したような書きぶりで、学生にもその準備を促している。

年度末の3月は研究室の構成員が大きく動く時期である。卒論を提出して卒業する学部生、卒業せずに修士課程に進学する人々、修論を提出して修了する人々、外部から入学する人々、そして4月から卒研配属される新四年生がいる。
例年、新四年生向けのセミナーは正式な所属を待たずにこの春休みに始め、基礎的な教科書の輪講やプログラミングの基礎訓練を施す。ところが、昨年は帰省、合宿免許の取得、アルバイトなどで新四年生の予定が合わなかった。この時点で彼ら3人には、配属決定直後のささやかなお茶会の場面だけだった。彼らのほとんどとはそれ以来 Zoom でだけ出会うようになっている。
新四年生のうち2人は地方出身だ。事態が厳しさを増し、少なくとも半年は四年生が大学に来る必要がなくなることを説明すると一人は地元に戻り。もうひとりは東京に残ることを決めた。地方出身の学生にとって、非常事態を孤独に過すことの精神的な負担はいかばかりかと想像しつつ、軽く「勉強や研究のサポートはするから、しばらく、実家に戻っていたら」と勧めてはみたものの、あまり強要はできない。志村けんさん、岡江久美子さんの訃報が伝わったのはもうすこしあとのことだが、すでにいわゆる「東京の人、怖い」は始まっていたからだ。また家庭の事情というものは伺い知ることができない。
心配なのは彼ら新四年生ばかりではない。修士の学位を得た二人と卒業する一人は、希望する企業への就職が決まっていた。いつもの年ならば、卒業や修了が決まれば指導教員の心配はなくなり、肩の荷がおりた気持ちになる。しかし、彼らの会社もいきなりのリモートワークと聞いた。企業の方も大学人と同様、リモートワークやリモート研修の経験は少ないだろう。本来ならば希望に満ち溢れて社会に巣立っていったはずの彼らだ。丸の内の大手IT企業に内定した学生はしばらくまえ に「ドラマに描かれるような理想的な社会人生活で輝くんです」と冗談めかして語っていた。その目はキラキラと光っていた。それが、入社してからの数ヶ月を自宅のパソコンに向い、会社の見知らぬ同僚とネットワーク越しにやりとりをするのだ。さぞかし残念だろうし、ぼくからすれば奥手の彼がきちんと人間関係を構築できるのか大いに心配だった。
すでに研究室に所属していて、進級・進学する学生はある程度、気心が知れているが個性的な学生ごとに心配なことはある。Zoom ミーティングを始めてすぐは千葉や八王子から一時間近くをかけて通ってくる学生からの評判はよかった。
「満員電車に乗らないで住むのは快適ですね。これからずっと遠隔ミーティングにしたいです」
「ミーティング開始は9時でもいいですよ」
などと勝手なことを言ってくる。そんな彼の様子がロックダウンが続くにつれて、不安定になってしまった。必要がないと家を出ない生活をしているうちに、鬱っぽくなってしまうようだ。散歩やジョギングを勧めるものの、必要のない移動は好まないようだ。今でこそ、好んで散歩をするぼくだが、(若き日の自分を含めて)若者というのはなぜぶらぶら歩くことを厭うのだろう。
緊急事態にはいってしばらくしたころ、ある学生が漏らした。
大学に行っちゃだめですか。ぼく家で勉強できない性格なんです。
これまでにも何人もの学生が「ぼくは〜な性格なんです」と訴えてきた。「ぼくの一日は48時間で、まとめて16時間寝ないと生きていけないんです」と主張した学生は今は毎日、早起きしている。「レモンでできている」はずの学生は、クエン酸の作用で虫歯になり、さらに亜鉛欠乏症で味覚障害を起して始めて普通食に切り替えた。いったい「家で勉強できない性格」というものがあるだろうか?
不要不急の外出が制限されているときに、そんなあやふやな理由から入構を認めるわけにいかないことを説明すると
ですよね〜
ときた。でも、彼は漫画喫茶からミーティングに参加するようになった。お金を払ってでも家庭外で勉強しなければならないのはどうしたことだろう。ミーティング後に時間を作って、話してみたところ、彼の両親は二人とも働きに出ており、はっきりとは言わないものの日中は一人で寂しいようだ。一日のほとんどを孤独に過すことに耐えられない人がいるのは不思議ではない。
ぼくらが大学に集まらなくなってしばらくして、研究室のチャットで学生同士で相談して、毎日、夕方に筋トレをすることになったようだ。筋肉ムキムキのあるメンバーがほかの人々を巻き込んだようだ。高強度インターバルトレーニング (HIIT) というのだそうだが、休憩を挟みながら短時間集中的に負荷を与える運動を繰り返すようだ。5時頃になるとZoomを繋げ、思い思いのトレーニングを一緒にやっていたようだ。かなり真面目にやっていたようで、Zoom越しにも参加者の面々の身体が大きくなるのが確認できた。
みんなが HIIT に参加するわけではなく、なかには何ヶ月も文字通り家から一歩も出なかった学生もいた。ある日、彼が家族のお祝いで一緒に食事に出かけたのだそうだが、久しぶりに出てみた町がひどく恐しかったのだそうだ。個人的には何がそんなに恐しかったのか、地方から出てきた人が東京の雑踏を眺めたような恐しさなのか、感染リスクの恐しさなのか、あるいはなにか別の恐しさなのか訊ねたかったが我慢した。何にせよ、好奇心旺盛な若者が恐しいと感じるのだから、行動変容は大変なものだ。
9月頃だったろうか。目立って気持ちが揺らいだような学生が出てきた。研究はもちろん、ゲームにも読書にも身がはいらないという。軽い鬱だろうか。こんな生活が続くのだから、こういうことにも備えておこうと思って、妻が勧めてくれた鹿目将至先生の1日誰とも話さなくても大丈夫 精神科医がやっている 猫みたいに楽に生きる5つのステップを思い出した。新型コロナ禍で精神科医ですら、おかしくなりかけたそうだ。この本は、その危うさをプロの知識で調整した方法論をわかりやすく教示してくれる。そのなかで印象的だったことに「日の光にあたる効用」がある。詳しいことは記憶にないが、屋外で一日10分程度でもいいから過すとよいそうだ。すると、光の刺激がきっかけて脳内物質が生まれ、気分が効用するとともに、睡眠が深くなるために気持ちが安定するのだろうだ。今、不安に苛まれている人は、屋外で日の光にあたってみるとよいかもしれない。(ちなみに日のあたる屋内は思いのほか光が弱いので効果が薄いそうだ)
そうそう、最初の非常事態宣言は今よりもずっと厳しかったが、個人的には今回よりも明るい気持ちで過ごせたように思う。ひとつには首相が陰気な人物に変った面はあるだろう。だが、社会全体として暗いように思う。これは単に冬で日が短くなっただけのことではないと思う。非常事態宣言だから当然のことながら「〜をしないで下さい」と毎日のように禁句を聞かされるのは同じだ。禁句を何度も聞いていると落ち込む。だが、初回では同時に「〜は大丈夫です」というメッセージも確かに受け取った。たとえば京大の山中先生が出てきて「ジョギングは三密を避ける最高の運動です」と勧めてくれた。医者は「家にばかりいては足が萎えます。散歩しましょう。」と、呆け防止効果も伝えてくれた。
社会の雰囲気も密を避けながら、どうにか楽しみを見つけようという機運があった。俄に家でパンを焼く家庭が増えたり、独立な楽器演奏を合成したシンフォニーの作品を作成したり、いろんな工夫があった。ぼくは特になにをしたというわけでもないけれど、そこにニュー・ノーマルを感じて面白がっていた。
ところが、今はどうだろう。今日のニュースで都知事は「夜に限らず昼も不要不急の外出はお止め下さい」と言っている。そもそも、彼女の口から「運動しましょう」の言葉が出たのを聞いた記憶はないが。フレイルや認知症の心配が消え失せるはずもないけれど、それだけ病魔の対応に終われ、人々の精神的な健康に目を向ける人がいなくなってしまったということだろうか。
緊急事態宣言下でも東京での感染は勢いが衰えているように見えない。今日のNHKの報道によれば、「緊急事態は一ヶ月で収束すると思いますか」という問いに対して8割以上の回答がNoだそうだ。ぼくも政治的な思惑を排除すれば3月一杯はかかるように思っている。その間、ぼくらは精神的な支えをどこに求めればいいのだろうか。役人として公助を整える役割を放棄していると見える首相に期待しても仕方あるまい。しかし、自分の命がかかっていることだから、目をつむるわけにもいかない。新型コロナ禍において、身近な人々が精神の健全を保てるように配慮していかないといけないと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
