
原発回帰は不可能:専門家
原発は出来るだけ作らないという3.11後の方針を180度転換して原発重視を打ち出している岸田政権だが、「原発回帰は不可能だ」と日本原子力発電元理事・日本原子力産業協会元参事の北村俊郎さんは断言する。
北村さんは2024年6月11日(火)に郡山駅前MARUCO貸事務所にて「福島原発行動隊」主催の講演「原子力基本法改正をどう評価するか」で語った。その講演をオンラインで受講した。
北村さんは1967年に原子力専業の日本原子力発電に入社した。定年まで勤めあげ、原子力産業協会に移った。そこは原子力関連企業がほぼすべて参加している「原子力村の中心」だった。

20年ほど前、リタイアのことを考えて温暖な地がいいと思って福島県浜通り、福島第一原発から南に7キロほどのところに家を建てた。
住み始めて約11年後、東日本大震災・福島第一原発事故が起こった。住民は全員避難となる。郡山市に避難して小さな家を購入した。
「「なぜそんな原発の近くに家を建てたんだ」といわれたが、原子力をやっている人が近くは嫌だなんていうのはおかしいと考えていた。しかし、事故が起こって避難せざる得なくなったのは非常に皮肉なことでした」。
「浜通りは帰還困難区域に入っているが、2020年代終わりには解除され帰れると言われたが、家は住んでいないと古くなるし、地震もあって傷んでおり、昨年解体したが、数百坪の庭があり雑草取りが大変だ」という。
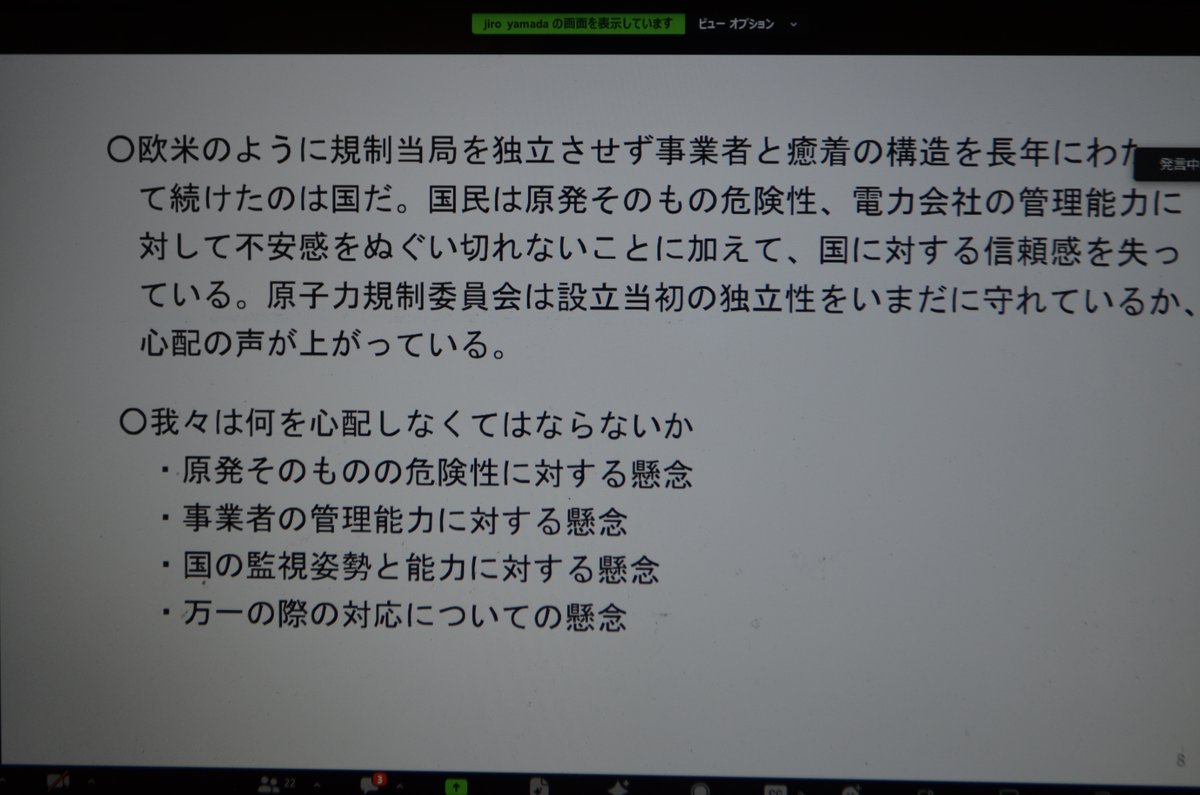
西洋文明にのっとった原発重視からの転換を
「国も産業界も原発に入れ込まずに、主力になると目されている再生可能エネルギー、蓄電池、(電力)需要削減にもっと力を入れるべきです。原発はリードタイムが長すぎる」と話す。
原発は動くまでに約20年かかる。それに対して、太陽光はおよそ8年、風力は約10年、水力は13年だ。

「思うのは、西洋文明(西洋文化)から脱して、日本文明(日本文化)に切り替えていけばいいのです」。エネルギー政策は、日本の得意としている自然を敬う気持ち、節約、リサイクルなどと親和性が高いという。
一方、アメリカは西部開拓の中で必要ならばどんどんと掘り返してきた文化で、そこから私たちは足を洗うべきで、その先頭に日本が立つべきだと考えていると北村さんは持論を展開した。
「せっかくだから言っておきたいのは”ならぬものはならぬ”ということ。これは会津藩の教育の基本です。政府・与党、経産省は議会民主主義を破壊している。やめさせなければいけない。意図的に議論をかみあわないようにした。なぜメディアはここを強く非難しないのか。歯がゆく思っている」。
不合理、非科学的なことを強行すれば必ずあとで痛い目に遭うという。東日本大震災・東電福島第一原発事故から学ばなければいけなかった。
「その被害者は国民、消費者なんです」。

電力需要増=原発増設は短絡的
今話題になっている政治とカネの問題だが、企業・団体の政治献金はなぜよくないかを明らかにすべきだと話す。
「電事連(電気事業連合会)もたくさん献金している。なぜパーティー券を買うのか。政治献金だって見返りを求めているわけです。自分たちの有利なように政策、法律を決めてもらう」。
「いんちき、いかさまです。結論を間違えてしまう」。
エネルギー基本法が目標と定めている2050年に火力発電をゼロにするには毎年4カ所、400万キロワットの火力発電所を廃止してゆく必要があるという。「原発を代わりにするには100万キロワット級の原発を毎年4基完成させないといけない。そんなことは出来ません」。
原発は日本に適していないと北村さんはいう。
「原発は発電コストが高い。地震が多い。人口密度が高い。国土、平地の狭さ。今注目しているのは台湾の動きです。今の台湾の政権は、止めている原発を動かすつもりはない。洋上風力を第二の半導体産業のように育てようとしている。非常に参考になる」。
電事連会長が「原発の再稼働・新増設には国の財政的支援が必要だ」と話したが「これは原発がコスト高だといっているようなものです。なぜコストが高くても原発回帰なのかをきちんと説明しなければいけない」。

また、AIやデジタルで電力需要が増えるから原発を増設せよというのは短絡的だというのが北村さんの考え方だ。
「これまでの10年、1%ずつ電力需要が毎年減ってきた一方、将来の人口減が予測され、経済活動縮小の予想もある。供給、需要両面で今すぐできることをまだやっていないのです」。
「再エネのポテンシャルもまだまだ引き出せる。デマンドコントロールも、電力足りない時には使わないようにする。蓄電池で貯めておく。農業でのソーラーシェアリング。また、新しい半導体によって電力消費が従来の100分の1になるという話もあるのです」。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
