
#7 全統小(3年生6月)の結果からいろいろなことを考える
2023年6月の全国統一小学生テスト(通称:全統小)の結果が返ってきました。その結果をもっていろいろなことを考えたので備忘録程度に残しておきたいと思います。
1.小3の全統小の傾向について
小3の長女は今回からマークシート方式。マークシートの方法が不安だなと思って、無料の「対策講座」も受けてみた。受験票と一緒にマークシート(受験番号とかを塗る練習?)が同封されていたので家でも練習してみてくださいということなのかな。
テストを終えて「マークシートでよかった!」と言っていたのは、算数でケアレスミスをしたのに気づけたから。出した答えが選択肢の中になくて、見落としに気付けたらしい。まぁ、そういう利点もあるよね。
マークシートになって大きく変わったのは国語の方だと思う。記述の「文中から抜き出しなさい」がなくなって、この時の主人公の心情を選択肢の中から選びなさいというものが増えた。まぁ、この選択肢が難しいわ難しいわ…。大人でも悩む。しかも文章が長いし。。(全統小の文章が長いのはいつものこと。でも前回、前々回は本で読んだことがある物語が出題されるというラッキー問題だったので、今回の初見の物語の流れを理解するのに苦労したんだろうな) 漢字も記述からマークシートになったことで、問題の量が増えてた。これはそろそろ本格的に漢字と語彙をやらなきゃなと痛感。。
受験者数は前回(2022年11月の2年生秋)の約2万人から、5千人増えて約2万5千人。推移としては1年春(1万3千人)→1年秋(1万7千人)→2年春(1万9千人)→2年秋(2万人)→3年春(2万5千人)。やっぱり学年が上がるにつれて増えていくんだなぁ。
2.小3長女の成績を見て撃沈…(完全に愚痴です)
長女個人の偏差値としては、前回より少し落ちました。。。過去5回受けて、最高の偏差値の時から10くらい落ちてる。完全にボリュームゾーンの一員。中学受験しようとしている子の中ではいたって「普通」の子というレベル。いや、全統小って受験考えてない子も受けるから、やっぱり中学受験考えてる子の中では普通以下じゃない?
こんなに(というほどではないけど、毎日コツコツやってるのに)勉強してるのに落ちるのかーーーーーーと思ってめっちゃヘコむ。3年生から通塾した子が、どんどん力をつけてるのかなと考えたり。新4年生からでいいやと思っていたけど、うちも早めに塾に通わせたりした方がいいのかなと考えたり。家でやってる教材があってないのかなと考えたり。足りないものが何なのかわからないし、成績を上げてきている子は何をどうやっているんだろうか。全然わからん。当初あこがえれていた中学の偏差値からはどんどんどんどん遠ざかり、もう地元中学でもいいやーとか思ったり。期待するから落ち込むと思って期待してなかったけど、期待してないと思っていて本当は期待してたんじゃん。ミラクルあるかと思ってた自分にも自己嫌悪。あーーー、悶々とする。本当に凹む。。。。(私、こんなんで6年生までやっていける?涙)
子どもにその気持ちをぶつけないためにも、ここで書いているので許してください(全統小の良いところは、校舎に成績表を取りに行かなければならないので、校舎からの帰路で自分の中で落ち込んだ気持ちを少し整理することができるところ)私も毎回の全統小で女優になる訓練を積んでいると思おう。。
3.テスト結果から見る課題①
今回のテストでわかった課題は、長女の算数の処理の処理の遅さ。前半の問題を丁寧にやりすぎて後半の大問に手が出ないまま時間が終了した。この時点で150点満点が120点満点になっちゃうんだよね。。
半年前の全統小・日能研の全国テストで計算にケアレスミス続出して、この半年は計算の精度を上げることに力を入れて、今回の全統小を受ける前にも「今回の一番の目標は計算ミスをなくすこと」と約束していたので、前半の問題を少しばかり丁寧にやりすぎんだろうな。。
計算、長女はもともと私に似ておっちょこちょいな性格ではあって、難しめの算数ドリルでも学校のカラーテストでも宿題のプリントでも難易度にかかわらず、必ずってくらい1問計算ミスしてきてたんだけど。佐藤ママが何かで言ってた「ケアレスミスはケアレスなんかじゃない。ただの実力不足です!!!」っていう言葉に確かになーと思って半年かけて計算強化してきた。
その結果、今回は計算ミスゼロになったから、それだけでも万々歳だと思うことにしよう!!!!(山本塾の計算ドリルは、短時間で集中して取り組めて確実に計算力上がってきたと思うのでリンク貼っておきます)
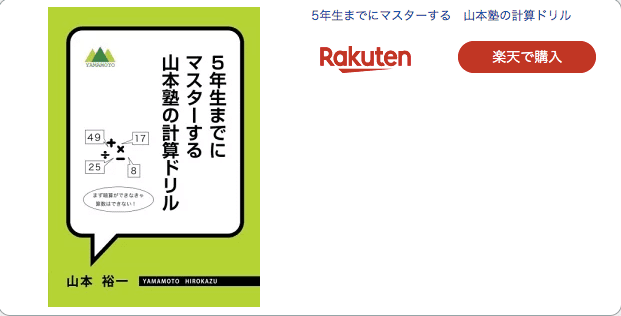
計算の精度は少し上がってきたので、次は処理速度を上げることを目標に。
とりあえず、学習タイマーを導入して時間を気にしながら解いていくということをしよう。

4.テスト結果からみる課題②
あと、致命的な長女の欠点に気づきました。日々の勉強の中で、間違った問題を「わかった」→「できる」にしていないということ。
今回、植木算がでるんじゃないかなと私がやまをはって、1〜2週間前くらいからやってたの。はじめは「???」だったんだけど、何日かしたらまぁ理解できるみたいになって。ちょっと日にちあけて、また植木算の問題出したら間違うんだけど、私が解説したり図解したらすぐ「あーーー!そっか!そっか!」ってわかったようなリアクションだったから大丈夫かなぁと思ってた。
実際、今回のテストにオーソドックスな植木算が出て、問題用紙にはきちんと図解して解いた形跡があったからできたなと思ったんだけど、結果を見たら間違っていましたよ!!!!普通に問題文に書いてある数字そのまま使って掛け算しただけになってる!え、あの図の意味は?どーゆうこと??
そういえば、過去のテストでも水のかさ(dL,L,ml)が出るだろうと思って、直前に類似問題を何度もやってたのに、テストで間違うという今回と同じパターンがあった。
と、長女、この「わかった」だけで「できる」になっていない状態が多々あるのではと思った。
その日やった問題集のできなかったところを一応「解き直し」はするんだけど、それがまぁいい加減というか「とりあえず感」「はやく終わらせたい感」「はいはい、ただのケアレスです、次やったらできます感」がすごくて、きちんと理解して自分のものにしていないままその日の勉強を終える。
そして数日後に同じ問題解かせると、やっぱり同じところで間違う。私はそれを「このパターンは苦手なパターン」と勝手に思ってしまっていたんだけれど、多分違う。1回目に間違った時点で、きちんと「できる」の状態にしていないんだ。。
しばらくは、この「やっつけ」で勉強している姿勢とか意識を改革しないといけないと思って取り組んでいこうと思います!早めに気付けて良かったと思おう。うん。
今までないがしろにしていた「勉強の仕方」とか「問題集の取り組み方」をもう一度ゼロから考え直そうと思うきっかけになった、今回の3年生6月の全統小でした。

フォローしてくれたら喜びます❤︎サポートしてくれたらもっと喜びます❤︎❤︎
