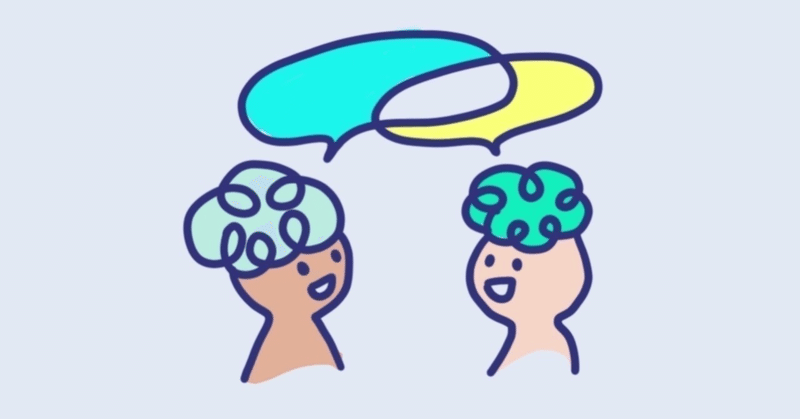
Photo by
ayaadukuf
対話について
小学校では、今年度から新学習指導要領が全面実施となった。これまでも「系統主義」「ゆとり」や「生きる力」「言語活動の充実」といったそれぞれの改訂ごとに目玉とされる内容があり、今回は「主体的・対話的で深い学び」が掲げられた。
そんなわけで、世の中には対話をテーマにした研究会や本がたくさんある。今回、その中の一つを手にとって、考えてみた。
対話はめんどくさい。時間もかかる。だからなくしてしまえ…と、流されてしまいそうなときに、いやいやちょっとまてや、と対話の価値を思い出させてくれるような1冊だった。
対話の難しいところは、ただのおしゃべりとはちがって、問題を解決するための協働作業であるということだと思う。そのため、相手の言おうとするところを理解して、自分の思うところはちゃんと伝えようとしなければならない。
ただ、これは大人にとっても難しい。ちょっと周りを見回すだけでも、会議で何も発言しない人、SNSでやたら人を叩く人など、そもそも対話しようという気をなくす例が山のようにやる。
最近、大人も子どもも、自分自身を語る言葉を失っているなぁという漠然とした危機感があるということ。このままいくと、どうなっちゃうのかな。という、悪い予感。
言葉を失っているのか、それとも場を失っているのか、相手を失っているのか、それはわからないけれど、とにかく自分とは異質な他者と語り合う力が、急速に失われているのを感じる。俺は、もっと話し合いたいのに、話し合えないもどかしさ。他の人もそれを感じているのだろうか。
いちばん怖いのは、わかりあおうとする人が減ってしまうことだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
