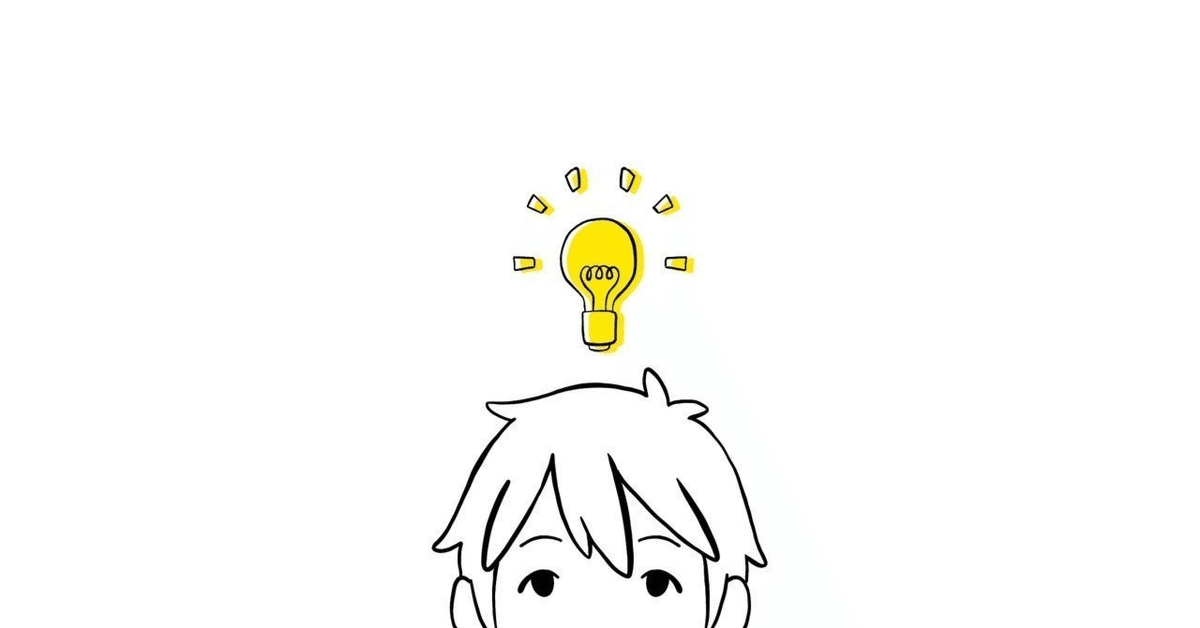
「チームビルディング」と「ロジカル」
東京コミュ塾生のKuroです。
東京コミュ塾のプライベートレッスンで次のことを相談しました。
「チームのまとめ方」と「ロジカルとはどういうことか」
新年明けましておめでとうございます。ということで、2023年の私の目標は、次の2つです。
①チームをまとめられる(人を動かせる)こと
②「ロジカルとは」を説明できること
2022年12月末時点の私
①チームをまとめられる(人を動かせる)こと
・アポイントが取れない
・私のお願いを実行に移してくれない
②「ロジカルとは」を説明できること
・説明できると思い込み
⇒何となく分かるは理解していないということ(JIN先生からのツッコミ)
■チームをまとめるには
JIN先生より3つのアドバイスを頂きました。
①マンツーマンでフォローする
②双方向&多方向を生み出す
③経験成長モデル
①マンツーマンでフォローする
私はチームメンバー5人に対して、ミーティングの場で次のお願いをしましたが、お願いを聞いてくれたメンバーは0人でした。何でやらないんだろうと悶々としました。
「1週間後までに、担当業務で抱えている課題を一覧に入力してください。」
お願いを聞いてくれない要因の一つに、私がお願いをミーティングの場でしたことにより、各メンバーの入力する意識が5分の1に薄まってしまったことが挙げられます。
確かに私もメンバーの中の一人だったらどこか自分事に感じないと思います。なぜならば、直接話しかけられていないからです。
どうすれば、お願いを聞いてもらえるのか。それは、ミーティング後に一人ひとりにフォローすることです。何故か?5分の1に薄まったお願いを1分の1の濃いお願いにすることができるからです。そうすることで、各メンバーにやらなければいけないという意識が芽生えます。
例)入力していないメンバーがいた場合
私 :「入力していないけど、私が手伝えることありますか?」
Aさん:「他の業務で忙しくて…」
私 :「10分間だけ時間をください。一緒に入力しましょう。」
Aさん:「10分だけならいいいですよ。」
②双方向&多方向を生み出す
相手に動いてもらおうと思ったとき一番最初に思いつくのは、相手にお願いや指示をすることだと思います。
例えば、次のような場面はよくあります。
上司から部下に「最近残業が多いから仕事を効率化するために、月末までにマニュアルを作成しておいて」と指示を出す。月末に部下に確認すると「すみません。仕事が忙しくてまだ完成していません。」
お願いを聞いてくれない要因の一つに、コミュニケーションが一方通行だからということが挙げられます。一方通行ではこちらが思った通りに動かないことが多いです。
どうすれば、お願いを聞いてもらえるのか。それは、コミュニケーションを一方通行から双方向にするということです。つまり、相手に言わせるということです。何故か?相手に言わせることによって、じゃあそれをやってきてくださいねと相手にコミットをとることができるからです。
相手にコミットをとったとしても、相手が自分より格上だったり、日頃の関係性が密でない場合、相手は思った通りに動いてくれないことがあります。
例えば、自分からAさんとは日頃から関係性が密ではないとします。Aさんから「月末までにマニュアル作成を完成させます。」とコミットをとったとしても関係性が密でないので「まぁいいか。後回しで。Bさんに頼まれたことを優先させよう。」みたなことはあります。
どうすれば、お願いを聞いてもらえるのか。それは、コミュニケーションを一方通行から双方向。そして双方向だけでなく多方向にするということです。つまり、自分と相手(Aさん)の1対1の関係だけでなく、相手(Aさん)と相手(Bさん)の間でも連携してもらいましょうということです。
例えば、「Bさん。Aさんがマニュアル作成に困っていたら助けてあげてくださいね。」というようにAさんとBさんを連携させることです。Aさんは自分との約束は破ってもいいかと思っていても、Bさんから「マニュアル作成で困っていない。」と聞かれれば動くからです。何故か?AさんはBさんを困らせてはいけないとやる気がでるからです。
このように、お互いを助け合わせることでチームメンバー間でコミュニケーションが生まれ、チームをまとめる(人を動かす)ことができます。
③経験成長モデル
人は経験でしか成長しないというデータがあります。多くの本を読んで勉強して、いろいろな知識をインプットしたとしても成長できないということです。
ということで、自分も含めてチームメンバーに経験(動いてもらう)をしてもらいましょうということです。何故か?経験を積み重ねることでチーム全体が成長するからです。また、メンバーが経験することで成長することを実感してもらえれば、主体的に動いてくれるようになると思います。
注意点としては、経験するだけではダメなんです。経験⇒内省⇒概念化⇒実践⇒経験・・・・・。とPDCAを回す必要があります。
・経験
考えや理論を実行に移すことで結果(成功 or 失敗)がでます。
・内省
それは何故成功したのか。または、それは何故失敗したのか。ということを自問自答して振り返ることで自分自身を見つめ直します。
※自問自答の仕方
失敗したことや成功したことに対して「帰納法的アプローチ」をすることです。だから何?で?と自分自身に問いかけます。
・概念化
内省した結果、物事の本質に気が付き、今後同じようなことが起きたときにどう対処すればよいか学び、他の業務にも展開できる程度まで抽象化します。
・実践
概念化(抽象化)した考え方を実行に移します。
■ロジカルとは
チームビルディングは必要です。ただ、自分が説明したことが相手に理解してもらえないようでは、チームビルディングどころではありません。人に動いてもらうには、自分のお願いや指示を相手に理解してもらうことが大前提としてあります。そこで必要なのがロジカルです。
ロジカルを一言で説明すると「筋道を立てて理由が説明できること」です。
「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざでロジカルを説明します。
ことわざ自体の意味は諸説ありますが、ここでは次のように定義します。
「自分に関係ないところで起こったことが、巡り巡って自分に関係しますよ。」つまり、いろんなことにアンテナを張って意識していろんな情報を集めてくださいよ。準備してくださいよ。という戒めのことわざです。
このことわざは、原因と結果の筋道(因果関係)が見えないです。つまり、ことわざ自体はロジカルではありません。
原因:「風が吹く」
結果:「桶屋が儲かる」
ことわざをロジカルに説明すると次のようになります。
①風が吹いたら砂埃が舞います。
②砂埃が舞ったら砂が通行人の目に入ります。
③砂が通行人の目に入ったら通行人は失明してしまいます。
④失明したひとは三味線弾きの職業に就くことが多いです。
⑤三味線弾きが増えると三味線の需要が増えます。
⑥三味線の需要が増えると、材料に使われる猫の皮の需要も増えます。
⑦猫の皮の需要が増えれば、市中にいる猫の数が減ります。
⑧市中にいる猫の数が減ると、市中にいるネズミの数が増えます。
⑨市中にいるネズミの数が増えると、市中にある桶をかじって壊します。
⑩市中にある桶が壊れると、桶を買う人が増えます。
⑫桶を買う人が増えれば、桶屋が儲かります。
このことわざは①ならば⑫の状態なんです。①ならば②、②ならば③、とつなげて、①ならば⑫ですときちんと説明しなくてはいけません。
※注意しなければいけないこと
どこまで深く説明しなければいけないのかということです。細かすぎると聞く方が面倒臭く感じてしまいます。目安としては大人の7割が理解できる論理展開を意識します。
※論理展開がうまくいっているかどうかを確認する術。
「それは何故?」と「だから何?」を自問自答するということです。自問自答出来たらロジカルということです。
「それは何故?」と主張から原因へ向かって自問自答してみます。
主張は桶屋が儲かるです。
それは何故?桶を買う人が増えるからです。
それは何故?ネズミが桶をかじって壊すからです。
それは何故?ネズミの数が増えるからです。
それは何故?猫の数が減るからです。
それは何故?・・・・。
「だから何?」と原因から主張へ向かって自問自答してみます。
・・・。だから何?
猫の数が減ります。だから何?
ネズミの数が増えます。だから何?
ネズミが桶をかじって壊します。だから何?
桶を買う人が増えます。だから何?
桶屋が儲かります。(主張)
■プライベートレッスンで得たこと
・人を動かすという前に、まず自分が動かなければいけないこと。
・何となく理解していると思っている事は、理解していないということ。
・プライベートレッスンで習ったことは、繋がっているということ。
(今回はアサーティブコミュニケーションや帰納法的アプローチ)
■プレゼンテーション
「チームをまとめるために何をすべきか」「ロジカルとはどういうことか」
についてお伝えします。
まず、「チームをまとめるために何をすべきか」について説明します。
チームをまとめるために意識することが3点あります。
1つ目は「マンツーマンでフォローする」ということです。
例えば自分がリーダで5人の部下がいるとします。5人の部下に対してこういうことをやってください。といってもなかなか全員はやってきてくれません。
何故なら自分の指示が5分の1に薄まっているからなんです。キックオフミーティングでこういうことをやってきてくださいというのはいいんですが、
その後にきちんとAさんに対して、マンツーマンでフォローしていく。
Bさんに対してもマンツーマンでフォローしていく。そうすることによって5分の1だった自分の指示が1分の1になりますよね。1分の1の指示になればAさんもBさんもやらなければいけないなという意識が芽生えます。
だからマンツーマンでフォローしていく。ということがチームをまとめるために重要な考え方です。めちゃめちゃ面倒ですがやってください。
次2つ目、「双方向と多方向を意識して生み出していきましょう」ということです。
相手を動かそうと思った時、一番最初に考えるのは指示をするということだと思います。指示をするというのは一方通行なんです。例えばリーダーから部下や先生から生徒に指示をする。ということです。
一方通行ではなかなか相手は動かないです。じゃあどうするかというと、相手に発言してもらうことです。つまり、双方向を意識するというコミュニケーションが大事なんです。
例えば、どうすれば、仕事が効率よく進められるか?という課題に対して
自分から「マニュアルを作ってください。」と指示を出すのではなく、「どうしたらいいと思いますか?」と相手に聞きます。そうすることで、相手に
「マニュアルを作った方が良いんじゃないですかね」と言わせることができます。
相手に言わせることによって、じゃあそれをやってきてくださいねと相手にコミットをとることができます。つまり、相手に言わせるということを意識する。ということです。
もう一つは多方向を意識するということです。AさんBさんCさんDさんといたら、AさんとBさんをチームにしたり、CさんとDさんを互いにサポートさせます。
これで、一方通行が双方向になって、双方向から多方向の連携をとることができます。Aさんもリーダーとの約束だったら守らなくてもいいかなと思うかもしれませんが、AさんとBさんというチームを作れば、Bさんとの約束も生まれます。多方向という連携をつくることでチームとしてまとまっていく。ということです。
一方通行でなくて双方向、双方向でなくて多方向の連携をとっていきましょう。ということがチームをまとめるためのコツです
3つ目は経験成長モデルを意識しましょうということです。
人は経験でしか成長できないというデータがあります。いろんな本を読んで勉強をして知識を詰め込んだしたとしても経験しないと成長できないということです。
つまりチームのメンバーにいろんな経験をしてもらいましょう、ということです。ただ、注意点がありまして経験するだけではダメなんです。
経験すれば失敗をします。成功もします。それは何故失敗したのか。それは何故成功したのか。ということできちんと内省します。そして、「だから何?」と自問自答して概念化します。
そうすると、結局こういうことが良かったんじゃないのか。こういうことが悪かったんじゃないのかのかと辿りつきます。そして、概念化した考えを他の業務に展開していくということが大事なんです。こうすることでどんどん成長していくといわれています。
ですので、チームメンバーには知識だけを詰め込むのではなく、実践、経験、内省、概念化しもらい、そして概念化した考えを実践させてみる。つまりPDCAをきちんと回していくというのが大事です。
この3つを意識することでチームをまとめていくことができます。
チームビルディングという考えもありますが、まずは、自分がロジカルに説明して、みんなに理解してもらうことが必要です。
ロジカルとはどういうことなんですかということを説明します。
一言で言うと、「筋道を立てて理由が説明できる」ことです。
「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざで説明します。
ことわざ自体の意味することは「自分の関係ないところが、巡り巡って自分に関係しますよ。」つまり、いろんなことにアンテナを張って意識していろんな情報を集めてくださいよ。準備してくださいよ。という戒めのことわざです。
ただこのことわざ自体は、原因と結果のつながりが見えないんです。
桶屋が儲かるという結果の原因は風が吹いたからとうことなんですが全然わからないですよね。なぜならば、因果関係が全く説明できていないからなんです。だから、このことわざはロジカルではありません。
どうやってロジカルにしていくかというと
「風が吹いたら砂埃が舞います。」
「砂埃が舞ったら砂が通行人の目に入ります。」
「砂が通行人の目に入ったら通行人は失明してしまいます。」
「失明したひとは三味線弾きの職業に就くことが多いです。」
「三味線弾きが増えると三味線の需要が増えます。」
「三味線の需要が増えると、材料に使われる猫の皮の需要も増えます。」
「猫の皮の需要が増えれば、市中にいる猫の数が減ります。」
「市中にいる猫の数が減ると、市中にいるネズミの数が増えます。」
「市中にいるネズミの数が増えると、市中にある桶をかじって壊します。」
「市中にある桶が壊れると、桶を買う人が増えます。」
「桶を買う人が増えれば、桶屋が儲かります。」
というようにきちんと筋道立てて説明をします。
このことわざはAならばZの状態なんです。AならばB、BならばC、とつなげて、最後にAならばZですときちんと説明しなくてはいけません。
注意しなければいけないのが、どこまで深く説明しなければいけないのかということです。細かすぎると聞き手はうざく感じてしまいます。目安としては大人の7割が理解できる論理展開を意識しましょう
また、論理展開がうまくいっているかどうかを確認する術があります。
「それは何故?」と「だから何?」ということを自問自答するということです。
主張は桶屋が儲かるです。それは何故ですか。桶を買う人が増えるからです。それは何故ですか。ネズミが桶をかじって壊すらです。とこのように
自分の説明に「それは何故?」と主張から原因へ向かって自問自答することです。
次に原因から主張へ向かって自問自答していきます。
ネズミが桶をかじって壊します。だから何ですか。桶を買う人が増えます。だから何ですか。桶屋が儲かります。
というわけでロジカルということを自分の言葉で説明できるようになれば、
自ずと自分の説明もロジカルになり相手に伝わります。是非トライしてください。
以上最後までご清聴頂きましてありがとうございました。
