
新カード解説③(デュエプレ12弾)
こんばんははじめまして。海月です。
書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。
自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。
とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。
12弾の新カードの考察第3弾です。
第2弾はこちらをどうぞ。
指標はこんな感じ。
9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。
7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。
5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。
3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。
0~2点 → 見なかったことにしていい。
基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。
それでは以下、本題です。
封滅の大地オーラヴァイン

事前評価:5
紙からの変更点は、3コスト以下2体をマナに送る効果が、計6コストに変更された点です。
このカードがそれなりに知名度がある理由は”七英雄”という括りに含まれているからです。
ただ弱いだけの上のカードと違い、弱いながらもみんなから絶大な支持を得ているカードたち…それこそがデュエル・マスターズ七英雄である。
とまあ、あまり名誉な称号ではなく、該当カードが好きな方にとっては不愉快に感じる場合もあることなので、リンクを貼る程度の紹介に留めておきましょう。
ただ、今回デュエプレでの実装にあたって、このページ内で提案された効果になってしまっているのは皮肉なものです。
さて、改変後の効果は、紙で言うところの「めった切り・スクラッパー」のようになりました。

こちらは何かと活躍の機会が多いカードでしたが、それはトリガーを持っていることにも依っているので、「オーラヴァイン」と比較すると大きな差です。
ただ、それでも6コストでコスト相当のパワーに、今のデュエプレには少ない複数体除去の効果を持っている性能は悪くありません。
相手のマナを増やしてしまう点で利敵行為となってしまいやすいですが、ハンドリソースの乏しい横展開のデッキに対して出せば有効に機能する場面もあるでしょう。
問題点はこのカードをサポートできるカードが非常に少ないところ。
初の自然のコマンド・ガイアコマンドを持って登場しましたが、現状のデュエプレでコマンド種族が活きることはほとんどありません。(将来的にはコマンドというだけで天と地ほどに大きく評価が変わります)
その上、コストが6なことから、異様にカードパワーが高い「アルバトロス」と併用することもできません。

つまるところ、今のデュエプレでコントロールやコンボに特化しない性能をしたクリーチャーは
サポートの優秀な種族である
5コスト以下である
自前でSAを持つ、あるいは「運命の選択」などで容易にSA化できる
のいずれかは最低条件として求められる傾向にあります。
「オーラヴァイン」はこのいずれにも該当しないところから、第一段階では活躍が難しいと判断されます。
しかしながら、打点を持ちつつある程度意図的な複数体除去ができる性能は唯一無二ということもできます。
まったく活躍の目がないとは言えませんし、原始的なボードの取り合いが勝敗に直結しやすいクイック・ピックなどの限定構築戦では活きやすい効果でしょう。
コスト参照がインフレに対して耐性が高いという点も強みと考えられる、決して悪くはないカードです。
火之鳥ペリュトン

事前評価:5
紙からの変更点はありません。
デッキ進化の詳細な説明が公式に見当たりませんでしたが(見落としてるだけかも)、デッキトップをめくって、それがクリーチャーならその上に重ねて進化できるという効果です。
場はもちろん、墓地進化のように墓地にすら準備をする必要がないのが強みとなります。
ただし、失敗した(デッキトップがクリーチャーでなかった)場合、コストの払い損となります。
この「ペリュトン」であれば、5コスト丸々無駄に払って何も出来ないということになり、失敗した際のデメリットが大きいことがわかるでしょう。
見た目以上にギャンブル性が強く、それが使いづらさにも結びついている能力です。
ただし、出せた場合はやはりアドバンテージの損がほとんどなく、コスト以上のスペックと進化故に即攻撃可能な点が大きな魅力です。
デッキ進化というギミックを使うために、構築をフルクリーチャーに寄せることも十分検討できる能力だと言えます。
さて、ではこの「ペリュトン」はどうかと言うと、コンボ寄りの面白い能力を持ちます。
まず考えられるのは、単体に強力なカードが多く、それでいてデッキのクリーチャー比率が高い『バルガライゾウ』のようなドラゴンデッキです。

「ペリュトン」は進化を下敷きにすることもできるため、このコスト帯ですることが不足しがちな重いデッキでは伏兵とすることができるでしょう。
後々山を操作するカードや、カードの下にカードを置ける能力が登場した際には、自壊ギミックと合わせたコンボを狙うこともできます。

運に左右されやすい点は上位の対戦環境で採用されづらい要因となりますが、面白い個性を持ったカードです。
凰翔竜機バルキリー・ルピア

事前評価:8.5
FT:ドラゴンとファイアー・バードの友情が新たな絆を生み出す!
紙からの変更点は以下。
進化元のアーマード・ドラゴンがドラゴンに緩んだ
”「バルキリー・ルピア」以外の”という制約が加わった
超探索とならなかった点は構築自由度が増しすぎることの歯止めでしょうか。
名前の通り、「バルキリー・ドラゴン」を意識したカードです。
コストを見れば「ジャック・ライドウ」も相互互換と考えられるカードですね。

1弾の「バルキリー・ドラゴン」はともかく、「ジャック・ライドウ」と比較すると進化元を必要とする点で「バルキリー・ルピア」の強さはわかりづらいところがあります。
このカードはサポートとシナジーありきのカードです。
代表格は「ボルシャック・NEX」から出すルートでしょう。

3コスト「コッコ・ルピア」→「ボルシャック・NEX」+効果で「バルキリー・ルピア」に進化+「バルキリー・ルピア」の効果で究極進化をサーチ→次ターン「バルキリー・ルピア」の上に究極進化、と繋がります。
このプランを起点として、「バルキリー・ルピア」がいることで多様なゲームプランを考えることが可能となります。
たとえば、現状でも以下のような組み合わせが可能です。
4コスト「バディ」からスタートして「バルキリー」を回収して5コストで出し、「ボルシャック・NEX」または究極進化をサーチして6コストで出す
3コスト「コッコ・ルピア」から4コスト「ボルシャック・NEX」を出し、「バルキリー・ルピア」を「コッコ・ルピア」の上に載せ、効果で「バルケリオス・ドラゴン」をサーチしてそのままG0で出して5打点揃える
ファイアー・バードとドラゴンを同時に持つことから、独自の使い方が可能となります。
選択肢はカードプールの増加に比例していくでしょう。
踏み倒しができる進化カードということで、「マッハ・ルピア」がいなくともSAで即時打点を形成できる点などもポイントですね。
まさか今回実装されるとは思っていなかったので①の「ボルシャック・NEX」のところで紹介してしまったが、登場からはるか未来で活躍を見せたカードでもあります。
デュエプレでも長い活躍が期待できそうです。
超竜サンバースト・NEX

事前評価:7
FT:神をも凌駕する、まさに太陽の一撃!
紙からの変更点は以下。
進化元がアーマード・ドラゴンからドラゴンに緩んだ
出たターンの初め限定のアンタップキラーを得た
基礎パワーが1000上がり、T・ブレイカーを得た
12000以上とバトルする時に+12000される効果が、13000以上とバトルする時に+13000になった
紙では劇場版デュエル・マスターズの第2作目の入場者特典だったようです。
思い出深く『連ドラ』に入れている友人がいましたね。
wikiで見た程度の知識なのですが、この映画の興行収入が4.45億円を記録したと知って結構驚きました。
ジャンルも時代も違うことから比較対象にはならないのでしょうが、邦画は(公開規模と予算にもよるが)1億行けばまあ成功という評価軸を耳にしたことがあるからです。
この頃のデュエマ、そんなに人気があったのか…
もう一つ余談になってしまいますが、この映画の元にもなった背景ストーリーの話を。
①の記事で書いた通り、時空の裂け目から発生したオリジンたちに対抗すべく、各文明勢力や究極進化獣が奮闘します。
が、究極進化獣のもたらす進化パワーが時空の裂け目を拡大させ、敵に塩を送る格好となってしまいました。
そこから「神帝」と称される古代のゴッドが現れ、究極進化獣たちは瞬く間に敗れ去ります。
各文明は必死に抗い続けるも、「4体神」とされる「神帝」は強力で、オリジンたちも追い打ちをかけて現代の5大文明連合軍は追い込まれていきます。
そうした状況で、火文明は最後の希望として「NEX」の究極進化を目指しました。
そして、「ボルシャック・NEX」は「サンバースト・NEX」へと進化し、ついには「神羅ライジング・NEX」へと究極進化を遂げていきます。
さて、そうした背景で究極進化へ向かう途上の「サンバースト」ですが、今回の強化によって敵対するゴッドすべてにバトルで勝つことができるようになりました。(「ヘヴィ・メタル」には相打ち)
さらにゴッドでなくとも1体目であればアンタップキラー効果によってほぼ確実に処理することができ、続けてタップされているクリーチャーを軒並み処理することができます。
「スピア・ルピア」と併用すればパワー・タップ状態に関係なく更地とすることもでき、強烈なカウンターを叩きこむ可能性を秘めたカードです。

今回の上方修正によって「マザー」には正面から負けるようになってしまいましたが、まあかわいいところでしょう。
ドラゴン主体のデッキは守りが薄くなりつつも「スパーク」などのカウンター戦術に長けたカードは採用されてきたので、このカードもそこと相性が悪くないことを考えれば組み込まれていく可能性があると言えます。
難点は、ドラゴンを進化元とする割には効果がコントロール寄りな上に7コストが重く、フィニッシャーとしての素質が弱いところです。
とはいえ、独特な性能は十分魅力的で、相手側の構築にこのカードが含まれるかを想定すると難しい場面は頻発してくるでしょう。
神羅ライジング・NEX


事前評価:9.5
FT:邪悪なるオリジンの神の復活を止めるため、究極進化したNEXが立ち向かう!
紙からの変更点は以下。
ルナティック進化を得た
進化元が進化アーマード・ドラゴンから進化ドラゴンに緩和された
最もパワーが小さいクリーチャー1体を破壊する効果がすべてになった
破壊された時の効果で、自分の最もパワーが小さいクリーチャーを破壊するデメリットがなくなった
背景ストーリーでは、先ほどの「サンバースト」のところで述べたように、「神帝」に対抗すべく進化を遂げた「NEX」の姿です。
激闘の末に無事「NEX」は勝利を収め、他5文明連合軍もオリジンへの反撃を再開するものの、そこに天空から突如新たなゴッドが…というところでお話はこのゴッドが登場する時までのお楽しみに。
さて、性能を順番に見て行きましょう。
「羅月サンライズ」の方はこの時点で優秀な効果です。
4コストであることから、3ターン目に「コッコ・ルピア」を出していると次のターンに「バディ」や「センチネル」から繋がって出すことができます。
手札に都合よくない場合も、「バディ」から「バルキリー」をサーチしてくれば、次ターン「バルキリー」に進化させながら効果で引っ張って出すことが可能です。
場に出ればまずファイアー・バード限定ながらも1:2交換の手札交換ができるのみならず、破壊された時に墓地からリアニメイトする御膳立てができます。
ここまでで最低3:3交換以上がほぼ約束されており、その質も考慮するとぶっちゃけこれだけでもかなり強いです。
それこそ、「ザークピッチ」を落としておければ3:6の破格なアドバンテージ交換さえ狙うことができ、強力な後続が続くとなればゲームの流れを大きく変え得るでしょう。

4ターン目に出したこのカードを、5ターン目の「ヘヴィ」で自壊して、即座に「ザークピッチ」を出すルートなどの搦手も検討可能です。
次に究極進化した「ライジング」についてですが、こちらももちろん強力な性能を有しています。
出た時の効果は最小を破壊するというところで地味に感じますが、アドバンテージをキッチリとってくれる点で十分有用です。
破壊された時も含めて2体以上破壊できることがほぼ約束されており、「最小」という言葉のイメージからは離れた強さがあります。
2つ目のゴッドスレイヤー(ゴッド限定のスレイヤー)の能力はほぼオマケですが、あって困るものでもありません。
タップされた「ヘヴィ・デス・メタル」の除去に役立つ場面もしばしば見られるでしょう。
ちなみにこの効果は背景ストーリーとの関連で持っているものです。
極端なゴッドメタをした不格好なデザインというわけではない点を強調しておきます。
最後に破壊された時のリアニメイト能力ですが、これも「羅月サンライズ」同様打点を維持出来るかなり強力な能力です。
ドラゴンとファイアー・バードの両方が対象となることで探索は濁りやすいですが、それが些細なことに感じられるほどの能力だと言えるでしょう。
進化は出せないものの、トリガーで破壊された時にも「ボルシャック・NEX」を出せばそこから「バルキリー」を出して追撃可能な点は是非とも覚えておきたい点です。
除去を行いながらビートでき、加えて耐性も備えていることから総じて極めて強力なカードだと判断できます。
課題となりそうな点は三つ。
一つは速攻系のより早いデッキに対して、どの程度守りを維持できるかです。
「コッコ・ルピア」初動のデッキは、どうしても4ターン前後にゲームを終わらせに来る『速攻』を苦手とします。
最も想定しやすいミッドレンジ気味の構築がされた場合、メタ読みで『速攻』が台頭して来ることは大いにあるでしょう。
二つ目は破壊以外の除去に弱い点です。
一応、出た時効果でアドバンテージを少なからず確保できていますが、それでも「ヘヴンとバイオレンスの衝撃」をトリガーで踏むだけで有利交換を取られやすいです。
特に同速のデッキ相手に「サーファー」を踏んでしまうと、負けに繋がるテンポロスにもなり得るでしょう。
三つ目は同じ火文明の速度が近い切り札「アポロヌス・ドラゲリオン」の存在です。
登場以来活躍を続けるフィニッシャーに勝る性能を持つかどうか、かつて敗れ去った数々の切り札を眺めると迷いが生じてきます。
しかし、数々の懸念点を挙げながらもこのカードが強力であることに変わりはありません。
永きにわたって環境で活躍する可能性を秘めた、非常に優秀なカードです。
余談ですが、他の「神羅」と違って名前にムーンが付かないのもそのはず、このカードはそちらのサイクルとは異なるカードだからです。
火文明のムーンもいるのですが、こちらは…

超神龍イエス・ヤザリス

事前評価:5
紙からの変更点は、出したターン限定だったパワー固定効果が、自分ターン中に永続して発動するようになった点です。
Twitterでの紹介元も勘違いをしていましたが、この能力はパワー固定で、その他の増減は一切受け付けません。
つまり、これと「ローズ・キャッスル」や「ヤミノ・サザン」を併用してもパワーが500から下がることはなく、破壊も行えません。
この能力を上手く使うなら、バトルによる破壊や火力などと併用する必要があるでしょう。

今回「イモータル・ブレード」などの新規クロスギアが登場するので、ひょっとすれば比較的優秀な火力カードである「インフェルノ・シザース」の実装も期待できるかもしれませんね。

また、「ノーブル・エンフォーサー」の効果範囲にもなるため、ブロッカー軍団を無視する方法として使えるのは少々面白そうです。

もう一つ覚えておきたいのは、進化条件が比較的緩く、ブロッカーであれば何でも進化元とできる点です。
「ミルザム」のデメリットを打ち消せる”ミルキャン”が行えることは是非とも覚えておくべきでしょう。

そうでなくとも、たとえば相手が「ヘヴィ・デス・メタル」でワールドブレイクをした盾から「ジャック」がトリガーすれば、返しのターンでそれに進化させることで一方的に破壊することも可能です。
奇抜な能力ながらも、出しどころを見極めれば比較的アドバンテージを取りやすいカードである点はしっかり理解しておきましょう。
光器クシナダ

事前評価:6
FT:エンペラー・キリコはその力によって、異世界から碧眼の伝説龍を使役したのだった。
紙からの変更点はありません。
少しだけ背景ストーリーに絡むことを紹介すると、種族・オリジンは太古の種族であり、その名前は実際の神話に関連するものが多いです。
先にいた「アマテラス」が日本神話でしたが、この「クシナダ」も同じ日本神話で八岐大蛇の生贄にされかける女神・櫛名田姫が元だと考えられます。
さて、肝心の性能ですが、進化を推している弾なだけあって進化獣をサポートする効果です。
今回登場するカードでなくとも、ロック性能を持つカードとの相性がいいと言えます。

各種強力な進化獣、特に耐性を持たないカードにアンタッチャブル効果を付与できるのは、「ロレンツォ」の例を見ても優秀ですね。
進化を主体としたデッキが準備を必要とする都合上、このカードがコストに見合った高いパワーを持ったブロッカーである点も噛み合いが良いでしょう。
選ばれた際のシールド追加効果はその点をさらに補強しており、『速攻』などはこれに「火炎流星弾」を打つのにも頭を抱えると考えられます。
コスト相当のパワーと述べましたが、シールド追加効果はおよそ3コスト相当です。
かなりのパフォーマンスの高さを持った、インフレを感じられるカードの一枚だと言えます。
難点は4コストがそう軽くはない点と、そもそもこういった補助カードを採用する枠があるのか、という点です。
デザイナーズというよりはグッドスタッフ気味な能力をしている点でも先行きは怪しいですが…単体として高い性能を持っている点は覚えておきましょう。
ボッコ・ルピア

事前評価:6
紙からの変更点は、選べたブロッカー破壊能力が小さい順の破壊になった点です。
ブロッカー破壊効果が調整されるのはもはやお決まりですね。
このカードよりも重いドラゴンを先に並べておく必要がある(順当にマナカーブ通りにプレイしたらほぼ腐る)点で汎用性が高いカードとは言えませんが、「ボルシャック・NEX」から出るというだけで評価の上がるカードです。
このあたりは単体ではパワーの低い墓地メタとしてしか機能しない「コンクリオン」が「ピラミリオン」から出せることで良い選択肢となっている点と同じでしょう。

2体程度破壊出来れば十分なことが多く、効く対面には滅法活躍する可能性を秘めています。
一応、効果が使えずに4コストで出した場合も5マナの「バルキリー」の進化元とできる点は短所をカバーできていると言えますね。
環境を見て十分採用検討できるカードです。
ドラゴンをサポートするのがファイアー・バードの常ですが、このカードの場合は逆にドラゴンがファイアー・バードをサポートする格好になるのが面白い点です。
爆進イントゥ・ザ・ワイルド

事前評価:8
FT:世界の果ての、その大いなる場所で、生命は大地へと還る。
紙からの変更点は以下。
使用可能マナが増えなくなった
マナ送り効果が非進化限定だったが、進化も選べるようになった
爆進ダブルが強制になった
この能力を有したカードの数は限られますが優秀なキーワード能力・爆進ダブルが登場しました。
コスト論的に考えてもわかるのですが、3ブースト効果が6コスト相当、マナ送り効果が5コスト相当なので、コスト相応のこれらの内のどちらかを状況に応じて使えるだけでも腐りづらく、非常に汎用性が高いです。
これが爆進ダブルによって、自分の進化が場にいると両方を使用することができると、かなりのパフォーマンスになることがわかるでしょう。
紙では10マナ以上を到達点とするデッキの器用なカードとして採用されることが多く、「アルファディオス」や「ドルバロム」その他出せばゲームを半壊させる切り札を搭載したデッキや『5cコントロール』で使用されてきました。

デュエプレでも同じような使い方が主となるでしょう。
今弾の進化クリーチャーも多数環境入りすると考えられるので、爆進ダブルで使えることも多くあるかもしれません。
大量ブーストカードとしては「ロマネスク」「セブンス・タワー」と並び立つ性能となるため、これらと併せてブースト手段を豊富にした構築も新たに考えていけそうです。

汎用性は高いですが、効果はシンプルなものなので特別な使い方がそうあるわけではありません。
一応、懸念点は爆進ダブルが強制となったことです。
特に3ブーストは一気にデッキ枚数を逆転させ得る効果のため、進化獣共に採用する際には注意が必要でしょう。
紙で使われた期間も長く、デュエプレでもビッグマナ系のデッキが戦える限りは採用候補となっていくと考えられます。
神羅サンダー・ムーン


事前評価:9.5
FT:月が神羅の輝きに満ちるとき、聖なる稲妻が世界に落ちる。
紙からの変更点は以下。
ルナティック進化を得た
呪文を唱える効果がコスト6以上に限定され、探索になった
進化クリーチャーのコスト軽減能力がついた
究極進化の光文明担当です。
順番に見て行きましょう。
「羅月サンダー」の方は出た時点で手札補充をし、即座にアドバンテージを回復することができます。
それのみでなく、加えたカードは究極進化時に踏み倒せることができるので、自己完結した能力です。
二つ目の能力は究極進化しやすいこともありますが、種族にエンコマを持っていることから優秀な進化先と組み合わせることも可能です。

この「羅月サンダー」時点でのメリットは、他にもエンコマであることから「ヴォイジャー」による軽減を受けられる点や、光文明であることから優秀な進化元を活用できる点があります。
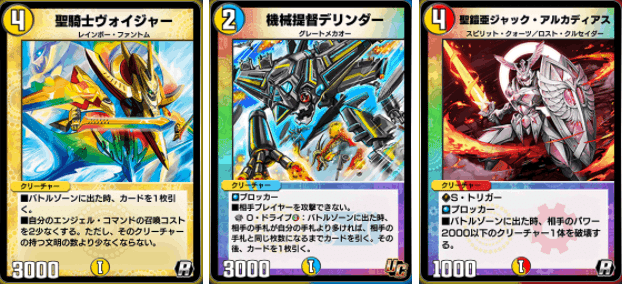
続いて「サンダー・ムーン」の方ですが、コスト6以上で上限なく呪文を唱えられる、ゲームエンド級の効果です。
たとえば「HELL」、「フュージョン」、各種「インビンシブル」呪文と、現状でも十分な選択肢を持ちます。
これがすごいのは「サンダー・ムーン」と対象呪文の計2種のカードでゲームエンド級のコンボが成立するところです。
呪文に関しては色問題も気にする必要がないので、ここにはかなり構築の幅を持たせることが可能となります。
たとえば、『デイガナイト』には現状でも「竜極神」「破壊龍神」のゴッドが採用され、光文明のクリーチャー(なんならG0持ちの「ブラッディ・シャドウ」)もあります。
ここに「サンダー・ムーン」と「フュージョン」(今まで通り「HELL」でも可)を数枚入れて、「サンダー・ムーン」さえ出せればほぼ勝ちというプランを持たせることができてくるでしょう。

色の合うところで考えると『青抜き4cコントロール』も相性の良いデッキです。
マナカーブで言えば「ライフ」→「ウルコス」→「羅月サンダー」→「サンダー・ムーン」と綺麗に繋がります。(ただし、これだと7マナ目に「フュージョン」を埋められない)

「ウルコス」→「羅月サンダー」→「ギフト」+「サンダー・ムーン」で、こちらなら濁りも回避しつつ同じ速度ですね。
これまで今一つ決定打に欠けるところがあったデッキでしたが、「フュージョン」はそれを補って余りある攻撃力となるでしょう。
もちろん「フュージョン」の今までの採用先、『5cフュージョン』に入れることも検討できますが、こちらの場合は白単色が浮きやすい点と、都合よく引けない場合に腐りやすい点には注意が必要です。
もう一つ攻撃的な高コスト呪文である「インビンシブル・フォートレス」で考えてみましょう。

このカードを採用する代表的なデッキ『ボルフェウス』では、
場に2体の進化元
手札に「ボルフェウス」
手札に「インビンシブル・フォートレス」
の計4枚のカードと6ターン要します。
対して「サンダー・ムーン」の方では
場に1体の進化元
手札に「サンダー・ムーン」
のみで成立し、こちらもブーストカードを使えば6ターン前後で成立するものです。(「ライフ」→「ヴォイジャー」→「ピカリエ」+「羅月サンダー」→「神羅サンダー・ムーン」で5ターン)
要求カード数とターンを見ても、『ボルフェウス』に遜色ない使い方をする道が見えます。
もちろん、色が合っているので『ボルフェウス』にそのまま投入することも検討できますね。
進化クリーチャーのコスト軽減についてはパッと思いつく活かし先はありませんが、3コスト軽減はかなり大きな効果です。
それこそ、2体目の「サンダー・ムーン」を出すコストは「羅月」込みでも計6コストに収まってしまうので、2ターン連続で出して「フォートレス」を2回使うこともできるでしょう。
進化プッシュの弾ということで、様々な選択肢を基に考えられる強力な効果です。
弱点は…正直さほど思いつかないのですが、しいて言えば進化元が除去され続けると腐ることと、デッキによっては白単色が有り余る色となる点でしょうか。
このカードと「ライジング・NEX」がかなりカードパワーが高いため、高い確率で環境進出を果たすでしょう。
そうなれば当然メタ対象とされるため、進化元の貧弱なクリーチャーを除去する手段を多くのデッキが搭載すると考えられます。
また、他のデッキも経験してきたように、デュエプレのカードパワーの高いカードは白単色に集中する傾向にあります。
それは2色のデッキなら色事故を減らすメリットとなりやすいですが、3色以上になると色が枯渇するデメリットとしても働きやすくなるでしょう。
とはいえ、結構無理に挙げてる感もあるほどに事前に感じる単体のパワーは非常に高く、環境の中心となる可能性もあります。
コントロールや遅めのデッキが不遇なきらいがあった中で、そのバランスを動かし得るカードです。
余談でちょっとだけ邪推をすると、「サンダー・ムーン」を素で7コストにするのでなく、コスト軽減効果を持たせたのは「母なる星域」が登場するから、と考えることもできます。

7コストを参照してあっさり出されてはとんでもないですからね。
過去時間があった頃には書いたのですが、たまには邪推をまとめた記事も書きたくなります…
まとめ
②に続いて、この記事で紹介したカードも基本的に使い道を考えられる強いカードが多いなと感じています。
インフレを感じるのって、数枚の飛びぬけたカードよりもこういうベースアップにあるので、ゲーム性の変化は楽しみですが同時にゲームスピードの加速に不安になります。
…どこまでも付いていくけどな!
また、これを書く1/19(水)時点で、事前公開カードがもう11弾の時の分くらいに達してしまいます。
1/22(土)に生放送があるようですが、1/27(木)に12弾をリリースするとするならば、1/20・21と23~26のブランク期間をどうするのか。
些細な点ですが気になったので、ひょっとしたら必ずしも木曜日の1/27でなく、火曜日あたりのリリースもあり得るのかもしれません。
まあ、じきにわかることなのであまり邪推せずに待ちましょう。
よろしければ次回の④もどうぞ。
それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
