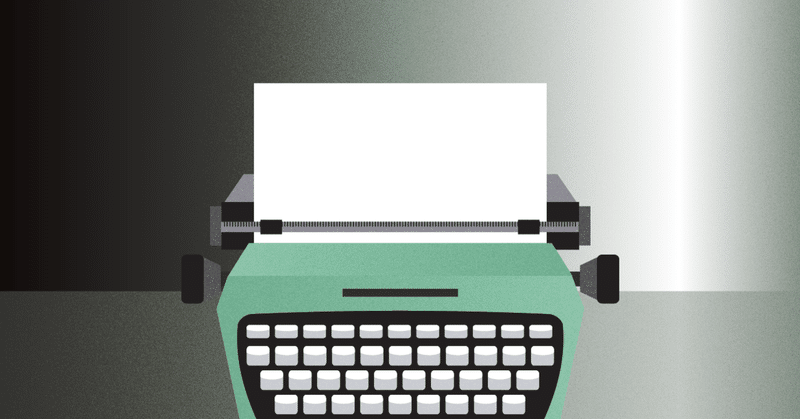
英語で小説を読むヒント(話法)
英語の小説は大きく分けて「1人称の語り」と「3人称の語り」というものがあります。
「むかし、私が大学生だったときに」から始まると「私」が出てくる小説なので「1人称の語り」と言い、「むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました」と始まると「おじいさん」や「おばあさん」が主体となって物語が展開するので、これを「3人称の語り」と言います。
登場人物がどんなことを考え、感じ、行動をしていたのかは「1人称の語り」の方がわかりやすいですよね。「私は、当時は彼女のことが好きだったが、そんなこと恥ずかしくて誰にも言えなかった」と「私の気持ち」や「行動の背景になる心理状態」を簡単に明らかにしてくれます。ですが、「3人称の語り」だと「彼はそのとき何も言葉を発しなかった」と書かれているだけで、「言葉を発しなかった理由」は文脈から情報を集めて考えなければなりません。ですので、3人称の語りの小説を読みながら、登場人物の意識の中に迫るのはとっても困難なのです。
そこで、「ここは、登場人物の心の中の描写で、地の文とは違うよ」ということを表す手段が英語にはあります。それが「話法」なのです。専門的にはThought Presentationというのですが、古くは「描出話法」と言っていました。今ではもう少し細かく考えられています。この話法はLeech and Short (1981)で詳しく論じられるようになったのですが、ここではその議論を簡単にまとめておきます。以下に挙げる6つの文は同一命題である「ある女性がブリスベンにいることが好きである」という事実を伝えているのだが、その伝達方法である文体に差異が見られる。Leech and Short (1981)ではこれらの差異に注目し分類を行ったのである。
(1) She thought that she liked it there in Brisbane. (Indirect Thought)
(2) She thought, ‘I like it here in Brisbane!’ (Direct Thought)
(3) I like it here in Brisbane! (Free Direct Thought)
(4) She liked it there in Brisbane! (Free Indirect Thought)
(5) She thought of her happiness at staying at Brisbane. (Narrator’s Reporting Thought Act)
(6) She liked Brisbane. (Narrator’s Report)
上記の英文は全て同じことを表していますが、小説では読者の受け止め方が違ってきます。例えば、I like it here in Brisbane!という文を見ると、「あ、彼女は心の底からブリスベンの滞在を楽しんでいるんだな」と言う感じで彼女の声が直接聞こえてくる印象を受けます。しかし、She liked Brisbane.という文を見ると、とても客観的に淡々と述べられているという感じで受け止めます。
つまり、同じことでも「登場人物の声が聞こえてくるような語り」と「客観的な語り手による語り」に分けられるのです。それをShortという文体論の研究者は次のようにまとめました。左側に行けば登場人物の声が聞こえてくるような文体で、右側に行けば、語り手の客観性の高い語りになっているというものです。
Character apparently Narrator apparently
in control in control
FDT DT FIT IT ←norm NRTA NR
Fig. 1 Short (1982: 184)
そこで、先ほどの文に「見分けるためのポイント」を示しました。
(1) She thought that she liked it there in Brisbane. (Indirect Thought)
主節の動詞は過去形、that節内で登場人物の心の中の描写を過去形で行う。登場人物を指すときは全て「3人称代名詞」、itという直示表現、thereという場所の表現。
(2) She thought, ‘I like it here in Brisbane!’ (Direct Thought)
主節の動詞は過去形、主節では登場人物は「3人称代名詞」。引用符が用いられ、引用符の中の主語は「1人称」、動詞は「現在形」で登場人物が実際に心の中で思ったことが、登場人物の言葉で表されます。itという直示表現、hereという(話し手の縄張りを表す)場所の表現。
(3) I like it here in Brisbane! (Free Direct Thought)
「〜が言った、思った」という文は存在しない。引用符を用いることなく、「いきなり」登場人物の言葉がそのまま提示されます。主語は「1人称」、動詞は「現在形」itという直示表現、hereという(話し手の縄張りを表す)場所の表現。
(4) She liked it there in Brisbane! (Free Indirect Thought)
「〜が言った、思った」という文は存在しない。登場人物を指すときは「3人称代名詞」、動詞は「過去形」。itという直示表現、thereという場所の表現。
(5) She thought of her happiness at staying at Brisbane. (Narrator’s Reporting Thought Act)
登場人物を指すときは全て「3人称代名詞」、動詞は「過去形」。
(6) She liked Brisbane. (Narrator’s Report)
「〜が言った、思った」という文は存在しない。登場人物を指すときは「3人称代名詞」、動詞は「過去形」。
小説でくせ者は、(4)の「自由間接話法」です。これを誤読する人がたくさん出てきますので気をつけましょう。
そこで、ヘミングウェイの短編小説から引用し、思考表現がどのように出てくるか確認しておきましょう。
“The Battler”
[引用1]
He felt of his knee. The pants were torn and the skin was barked. His hands were scraped and there were sand and cinders driven up under his nails. He went over to the edge of the truck down the little slope to the water and washed his hands. He washed them carefully in the cold water, getting the dirt out from the nails. He squatted down and bathed his knee.
That lousy curt of brakeman. He would get him some day. He would know him again. That was a fine way to act.(53)
[引用2]
Nick rubbed his eye. There was a big bump coming up. He would have a black eye, all right. It ached already. That son of a crutting brakeman.
He touched the bump over his eye with his fingers. Oh, well, it was only a black eye. That was all he had gotten out of it. Cheap at the price. He wished he could see it. Could not see it looking into the water, though. It was dark and he was a long way off from anywhere. He wiped his hands on his trousers and stood up, then climbed the embankment to the rails. (53)
“The Battler”もNick物語と呼ばれているもののうちの1つである。Nickの汽車の無賃乗車がばれて、制動手に殴られ、汽車から落とされてしまう。そして、Nickが線路沿いに歩いてゆくと元プロボクサーのAd Francisに出会う。数多くの闘いを経たことにより、鼻はつぶれ、裂けているかのような細い目。1つしかない耳。そして、隣には黒人のBugsが座っていた。彼らと食事をするNickであるが、最初は機嫌の良かったAdの変貌を目の当たりにする。Adはボクシングの構えでNickに迫り、喧嘩をけしかけてきたのである。しかし、BugsがAdの後頭部を棍棒で殴り気絶させ、Nickは難を間逃れた。Bugsによると、Adは頭がおかしくなっているということだった。そして、Nickはこの黒人からサンドウィッチを手渡され再び線路に沿って歩き出すのである。
この短編は時間のとりかたと、登場人物の意識に重点を置かれて書かれた作品であると考えることができる。出来事が起きた時系列通りに物語が展開するのではなく、物語は出来事の中間部分から語られ始めるのである。
本来の時系列通りに物語が展開するのであれば、Nickが汽車に乗り、そこで無賃乗車が発覚し、制動手に痛めつけられ、汽車から振り落とさる。そして、線路沿いを歩いていると、一人のボクサーに出会う。ボクサーとその連れの黒人とのやり取りが続いた後、Nickは別れて再び一人で歩き始めるという物語である。しかし、この物語の冒頭は物語の出来事の順序としては異なっており、Nickが汽車から投げ出された時点から始まる(”Nick stood up…”)のである。投げ出されたNickは立ち上がり、自分の身に起きた出来事を振り返る。そこで、Nickは”That lousy curt of a breakman. He would get him some day. He would know him again. That was a fine way to act.”と制動手に対してなんともやりきれない思いを表明するのである。ここでは、Nickの心理状況を表すためにモダリティとしてのwouldの使用が見られる。それは、一つ前のパラグラフで動詞feelが用いられていることからはじまる。まず、”He felt of his knee.”とNickは自分自身の足の怪我を案ずる。そこでは、Nickの感覚・触角の描写がなされており、突然、Nickの心理描写を行うのではなく、徐々に内面描写へと迫っていく文体が採用されているのである。
内面描写の部分では、Nickは制動手(breakman)に殴られて悔しく、痛い思いをし、さらには嫌悪感を抱きながら、”That son of cutting breakman.”と心の中で思う。この文はNickのFree Indirect Thought(FIT)の形式になっているといえる。FITは地の文において、語り手が客観的に語ったり、「カメラ・アイ」のアングルで語るというような通常の語りよりも、さらに登場人物の意識や思考内容に迫ることができる文体であるといわれている。 したがって、客観的な語りよりもむしろ主観的な語りになっていると考えられる。Nickの悔しい気持をNick自身に語らせることによって、やり場のない気持を効果的に描写することができるのである。
ここまでの2つのパラグラフは、まずはNickの触覚・感覚をはじめに描写し、その後Nickの心理描写を行う文体であるFITを用いてNickのやりきれない気持をあらわす効果的な表現を生み出しているのである。
さらに、ここで引用してある後半の2つ目のパラグラフも前半の2つのパラグラフとまるっきり、同じような構造を形成していることがみてとれる。”He rubbed his eye.”や”He touched the bump over his…”とあるように腫れあがった目を触る行為を描写している。つまり、ここでも触覚・感覚を表す語が用いられているのである。その後の語りはNickの心理を描写するものへと移行していくのである。”He would have a black eye, all right.”という文も一見すると客観的な語りのようにも見えるが、仮に客観的な語りとするのであるならば一般的に過去時制を用いて”He had a black eye…”となるだろう。過去時制を用いて語るということは語り手はすでにNickの目の回りには黒いあざができているということを知っているのであって、それは客観的な語り手のみにしか知りえぬことなのである。しかし、ここでは”would have a black eye”となっているため、これを語る人物は、その時点では自分の目の回りに黒いあざができているかどうかわからないのである。したがって、ここでの語りは客観的な視点からではなく、登場人物寄りの視点で語られているのである。
つまり、Nick自身にはまだ目の回りがどうなっているのかがわかっていないのである。だからこそ、”He wished he could see it. Could not see it looking into the water, though.”という描写と呼応するのである。もちろんここでの”Could not see it…”はNickの心の描写であり、FITの文体になっているのである。ここでも、前の2つのパラグラフと同様に、突然何の前触れもなくFITという登場人物の心理描写をする文体が使われるのではなく、FITを誘発するような感覚や触角を表す語が用いられるといった、きちんとした言語的根拠のある前触れが置かれているのである。この場面において、Nickが腫れあがった目を触り(“rubbed”, “touched”)、痛みを感じるという触覚・感覚が前提として据えられているのである。
登場人物の心理描写を効果的に行う手段として、ここでとられた方法は、触覚・感覚を表す語が用いられ、その触覚・感覚に誘発されて心理描写が進行する。非常に自然な文体の流れであると思われる。この場面では、Nickは無賃乗車をするという道徳的に反した行為をしており、それが発覚したことによって、制動手に殴り飛ばされた。しかし、Nickは全く自分のした行為に対して反省することなく、反対に自分を殴った制動手に対して復讐してやろうという気持が芽生えてくる。すなわちこの場面がNickは精神的に成熟していないということを示しているのである。客観的な語りと主観的な語りとを交えることが、一定しない、不安定な精神的な「揺れ」を映し出している。
参考文献
Ernest Hemingway, The Short Stories, the first forty-nine stories with a brief preface by the author ,New York: Simon &Schuster, 1995.
Leech, Geoffrey N. and M. H. Short. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. London: Longman. 1981.
Short, Mick. “Stylistics and the Teaching of Literature: with an Example from James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man” In R. Carter (ed.) Language and Literature: An Introductory Reader in Stylistics. London: Geroge Allen&Unwin. 1982: 179-92.
---. Exploring the Language of Poems, Plays and Prose. London: Longman. 1996.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
