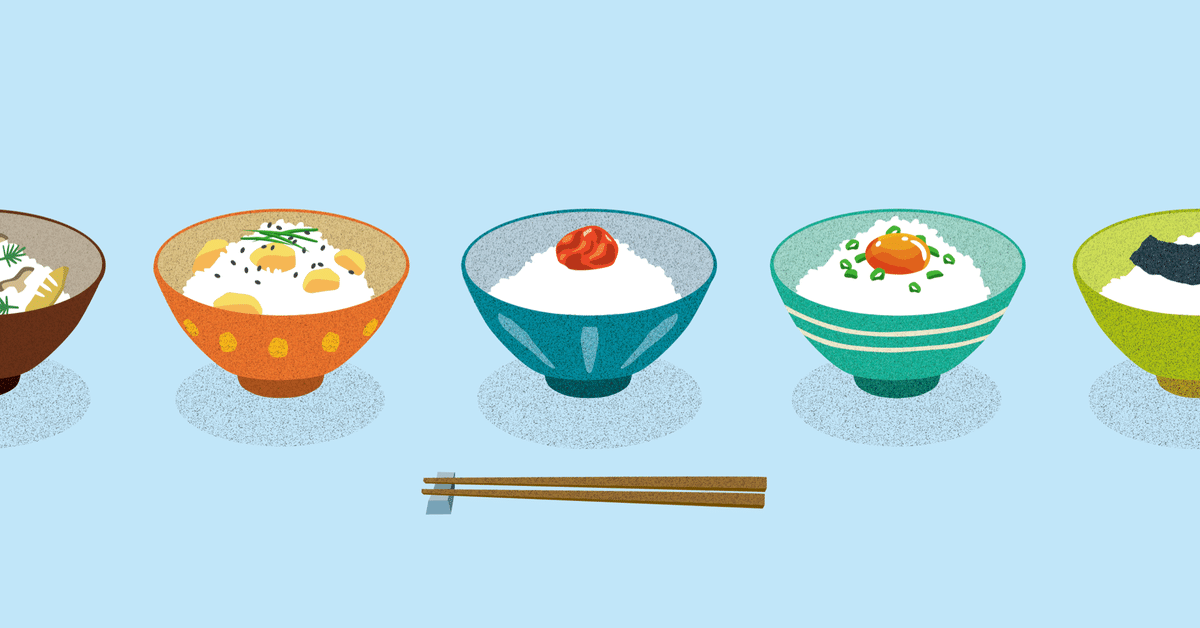
三鷹の小さな小料理屋にて
東京都、三鷹駅。
20代前半の数年間、わたしはこの街で暮らした。
ずっと赤羽で暮らしていたわたしに、「街によって治安はぜんぜん違うのですよ」と教えてくれたのが三鷹だった。緑豊かで街はきれい。タバコの吸い殻が落ちていないし、ずらりと並んだ自転車のほとんどに、駐輪違反の紙がぶら下がっていることもない。ジブリ美術館が近くにあり、「風の通り道」と名前のついたセンスのいい道がある。
赤羽の「食材はとりあえずひとつの鍋でまとめて煮ておけ!」というようなごっちゃり感も好きだ。けれど、三鷹の「小鍋でそれぞれ調理すると、それはそれはおいしいですよ」とそっと教えてくれる雰囲気も好きだ。
***
三鷹駅から、桜並木があるほうに階段を降り、むかしはセブンイレブンとローソンストア100があった道を進んで、ひょいひょいと小道を入ると、その店はある。誰も見つけてほしいとは言っていないけど、でも見つけたならいつでも来れば? と、すり寄りはしないやさしさでひっそりと建っている。
その店でわしわしと食べた魚や、味噌汁や、野菜の炒めたやつや煮たやつが、いまのわたしの一部を作った。
***
とてもお腹が空いていた。けれどお金はなかった。会社員数年目、貯金をするのも上手ではなかった。自分で作る元気もなく、コンビニ飯には飽きていた。
誰かの手料理が食べたい、やさしい味のご飯がいい。できれば人と話しながら、さらに言うなら笑いながら、おいしい時間を過ごしたい。
そんな気持ちでふらりふらり、やがて見つけたのがその店だった。
「あのう、食べるものはありますか」
カラカラとゆっくり扉を開けて、中を覗き込み、おそるおそる尋ねた。店の中では、いまではママと呼んでいる人が、料理を仕込んでいる最中だった。
わたしが小料理屋だと思って扉を開けたところは、飲み屋だった。お酒の瓶がずらりとカウンターに並んでいて、あ、お酒をまったく飲まないわたしはお呼びではなかったかと、扉を開けたことを一瞬で後悔した。
わたしの後悔を察したのか、それとも気づいていなかったのか、別にどうでもよかったのか。ママはこちらを振り向いて、ニンマリ笑って、これだけ言った。
「あるよ」
***
カウンターの席に座ったわたしは、なにか話さなくてはいけないかなと思って、「お腹が減っちゃって」とヘラリと笑った。「準備するから待ってな」とママは言う。なにが出てくるのかわからないまま、料理を待った。
ひとりで飲み屋に入るなんて、初めてだった。わたしはお酒が飲めないので、入ってもやることがない。
小料理屋と飲み屋は、見た目じゃ判断がつかないんだな。そもそも違うものなのだろうか。小料理屋もお酒を提供しているだろうから、つまりは飲み屋でもあるよね。そんなことを考えながら、正体不明の料理をぼんやり待った。
やがてもうひとり、お客さんがやってきた。おそらく常連さんだろうその人は、ママに「珍しく若い人がいるねぇ」と言って、端の席に腰を下ろした。
「お腹が空いてるんだって」
「なにぃ、そうなんか」
「とりあえず、味噌汁」
ことりと目の前に置かれた味噌汁は、汁より具のほうが多いんじゃないかと思うくらい。こんもりと盛られた野菜や揚げが、ほわほわと湯気を立てる。「おいしそう」とつぶやくと、「おいしいよ」と返ってきた。
久しぶりに、人が作った温かいものを食べた。あったかい、具がたくさん、じんわりした気持ちになる。感想はそんなもの。だしがどうとか、具のチョイスがどうとか、そんなことはなにも考えず、ただ「おいしい」と言って食べた。
味噌汁に続いて、またまた茶碗にこれでもかと盛られたお米が出てきて、わたしはひたすら箸でかき込む。「おいしい」とつぶやけば、「おいしいでしょ」と返ってきた。
野菜を炒めたものも、ちくわをしっとり似たやつも、漬物も、「おいしい」と言いながら食べた。そのたびにママは「おいしいでしょ」と笑って、また新しいおかずを出してくれた。
わたしの食べっぷりを見ていた常連のおじさんが、「よく食べるなぁ」とケラケラ笑う。
「腹減ってたんだなぁ」となぜかうれしそうで、「魚、好きか?」と聞いてきた。「だいすき」と返せば、さらにうれしそうに立ち上がって、ママとあの魚がどう、七輪がどう、俺が焼くからどうと話し合い、そして店の外に出ていった。
「どこに行ったの?」と聞くと、「外で魚焼いてんのよ」とママはまた笑う。誰のために、と聞かなくてもわかった。
店にはおじさん以外の客は誰も来なくて、ただご飯を食べるわたしと、ご飯を出してくれるママと、魚を焼いてくれるおじさんが夜を一緒に過ごしていた。
何歳なの、どこに住んでるの、仕事帰りなの。よくある会話はなにもなく、ただただ、料理においしいと言うわたしと、おいしいでしょと返すママと、魚を焼くおじさんがいた。よくわからない夜だった。
しばらくして、こんがり焼けた魚を持っておじさんが店の中に戻ってきた。
やっぱりその魚はわたしの目の間に置かれて、おじさんは少しソワソワしていた。一口食べたら、それはそれは脂がのっていて、けれど七輪で適度に脂が落ちたからかしつこくはなくて、ほんとうにたまらなく「おいしい!」。
わたしがビックリマークをつけて言うと、おじさんはママと同じ顔でニンマリと笑って、「うまいだろう」と言った。
***
それからわたしは、その店の常連になった。
ときには一緒になったほかの客と話したり、カラオケをしたりもしたが、メインはやっぱりご飯だった。
「お金なんていらない」とママに断られた初日も、「もう大丈夫だからもらって」とわたしが言ったあの日も、父を連れて行ったあの日も、最後に行ったあの日も、具沢山の味噌汁と、ほかほかのご飯と、野菜の炒めたやつや煮たやつと、おじさんが七輪で焼いた魚。おいしいと言えば、おいしいでしょと返ってくる会話。
ママはフルーツが好きだ。甘いものは好きじゃないらしい。「じゃあ次来るときは、フルーツ持ってくるね」とわたしは確かに言ったのに、結局一度も渡せていない。お店はまだある。連絡先もわかる。
ひとつのお店が潰れていて、後悔したのは最近のことだ。胃袋を守ってくれた、ついでに気持ちも守ってくれた。そのお礼を言わないままに、ママのお店がなくなったら困る。
七輪で焼いた魚のおいしさを教えてくれたおじさんにも、また会って、できれば魚を焼いてほしい。だってとてもおいしいし、焼いてくれるのがうれしいから。
「おまえは魚が好きだなぁ」と言うおじさんに、言っていないことがひとつある。わたしは魚が好きだとは言ったけど、魚だけが好きだとは言っていない。同じくらい肉も好きだし、野菜も好きだし、お菓子も好きだ。つまりは食べることが好きなのだ。
けれど、「魚を好きなのはいいことだ」とうんうん頷くおじさんを尊重したいから、おじさんの前では、一生魚好きのわたしでいる。
そろそろ、電車を乗り継いで、会いに行ってもいいだろうか。またあのご飯を、食べに行ってもいいだろうか。どうしてこの店に来たのかと聞かれたとき、「おいしそうなものがある気がしたから」と言ったわたしに、「よくわかったね」と笑ってくれたママのご飯が食べたい。
「あのう、食べるものはありますか」
また、「あるよ」って言ってくれたらうれしい。
いただいたサポートは、おいしいものを食べるために使わせていただきます。巡り巡って文章を書くパワーになります。 もりもり食欲パワ〜!
