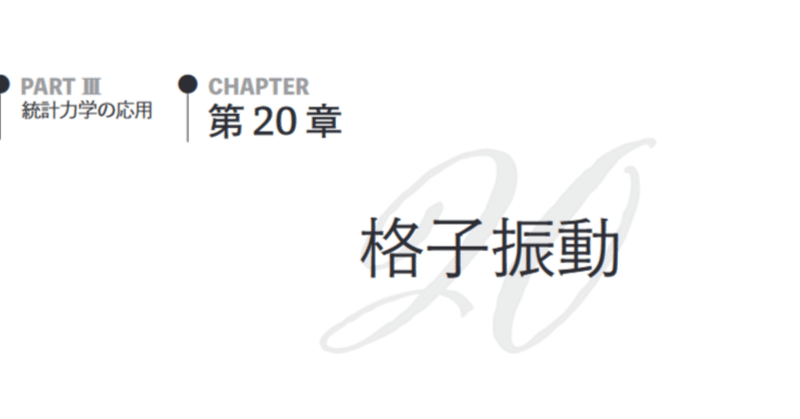
熱力学・統計力学 第20章問題解説
「熱力学・統計力学 熱をめぐる諸相」第20章章末問題の解説。解答例はこちらを参照。
本章では統計力学の典型的な応用例である格子振動を扱っている。統計力学の教科書であればまず間違いなく議論される例である。情報理論など、他の分野を志向しながら統計力学を勉強する方は少なくないと思うが、そういう方にとってはあまり興味のない内容かもしれない。ただ、それほど難しい問題でもないし、非自明な性質も得られるので読んで損はないと思う。大自由度系で起こる集団励起、集団運動は物理系でなくてもありえることである。もちろん、物理主専攻者にとっては必須である。固体物性論の基礎となる。
非自明な性質とは20.3節で議論するものである。(20.21)式は非常に面白い。和を積分にすることによってはじめて得られるふるまいである。そしてまた、問題[20-3]で扱うように、その性質は空間次元に強く依存する。前章でも少し言及したが、空間次元によって熱力学的性質が変わるという問題はこれからもさまざまな系において議論される。
本章ではフォノンという語を用いなかったが、言及しておいてもよかったかもしれない。26.2節で理解に必要な概念を議論した後に言及している。
よくわからないものでも名前をつけてしまうと安心感があるし、その概念の存在を認識しやすくもなる。日常の社会生活でもよくある(**ハラとか)。ただ、それで思考停止状態になってしまう恐れもある。ということなので、もったいぶって、名前をつけるのは26章までお預けにしている。
[20-1] 連成振動
本文で議論した内容を確認する問題。基本的・標準的な計算であり、特殊なことは何もない。
(b). sin関数を仮定するのは、運動方程式が調和振動子型であることによる。
(c). sin関数を仮定するのは、[12-2]で得た固有ベクトルの各成分がsin関数で与えられたことに対応している。やや非自明な置き方であるが、数学的な勘のあるひとは、(A20-1.4)式のような差分方程式から予想できるだろう。
代入して式をいじっていると何をしているか見失いがちであるが、問題は方程式を解くことである。仮定した関数形を代入して式に矛盾が生じなかったら解けたということになる。関数を表す際に用いたパラメータ(この場合はk)の取りうる値は境界条件から制限される。
仮定して問題を解いた場合、他の解が無いかどうかが問題となる。解は複数あることが重要である。線形の問題を解く場合、重ね合わせの原理が成り立ち、得られた複数の解の線形結合で任意の解が表される。具体的にどのような重ね合わせになるかは、初期条件に依存する。なので、特定の問題を解くという動機がなければ、そこまで具体的に計算を進めることはしない。重要なのは固有モードにはどのようなものがあるかである。
(d). 行列で考えるとわかりやすい。[12-2]との対応を考えながら理解するとよいだろう。
解いていると、量子力学の自由粒子の問題を解くのと同じようなことをやっているとわかるだろう。その類似性には意味がある。場の量子論を学ぶとそれがわかる。26.2節で少し議論する。
[20-2] 1次元2種粒子系の連成振動
(c). 「どのような振動」かという問いにどのように答えるか迷うところである。レポートでは振動数を表す固有値しか調べていないことが多かった。振幅を表す固有ベクトルを調べることに気付けるかどうかがポイントとなる。
それぞれの解において、2種類の振幅は符号が逆か同じかになる。つまり、逆位相と同位相の振動である。その結果を得るために$${ka\to 0}$$の極限をとる必要はない。あくまでもわかりやすくするためである。
逆位相の振動を光学フォノン、同位相の振動を音響フォノンとよぶ。くわしくは固体物理の教科書を参照。
分散関係を図にすると以下のようになる。

波数$${k}$$は、前問で扱ったように境界条件を考えると取りうる値が制限され、離散的なものになる。ただ、十分大きな系ではその値はほとんど連続的になる。
音響フォノンの分散関係は通常のフォノンのものとよく似ているが、光学フォノンの場合はかなり異なる。前者の場合、振動数は$${ka\to 0}$$の極限で0になるが、後者の場合正の有限値となる。両者の間にギャップがあることも面白い。これは、その間の振動数のモードが存在しないことを示している。
[20-3] 格子振動の空間次元依存性
20.2節で扱った性質の非自明さは、少しずつ異なった振動数をもつ調和振動子の集合を考えることによって得られるものである。それを扱うには、本問で定義するような数密度$${g(\omega)}$$を用いるとよい。これは第IV部で定義する状態密度とよく似ている。そこでもまた、多数の状態を数密度を定義して扱っている。「状態」の意味はそれぞれにおいて異なるが、和を積分で表すことにより、非自明な性質が現れる余地が生まれる。そのため、状態密度を用いた記述はとても便利である。
状態密度を用いる利点の一つは各種の問題を要素に分割して扱うことができる点にある。そのことは第IV部で理解できるだろう(例えば373ページ(25.5)式の下で議論されている)。本問題は、考え方に慣れ第IV部の議論に自然に入ることができるように用意されている。
(a). 235ページの脚注を参照。離散変数の和を連続変数の積分に置き換えることはしばしば行われる。考え方をぜひ身につけておいてほしい。
この結果から、熱力学関数のふるまいが空間次元に依存することがわかる。
(b). (a)で用いる分散関係は本文で議論する場合の低温領域に対応する。本文では3次元の場合を考えていたが、ここでは任意の次元に一般化する。べき指数が空間次元によって決まる。
(c). 3次元系で密度$${g(\omega)}$$をコンパクトな形でまとめるのは難しいが、1次元の場合は可能となる。19章でも見たように、1次元系ではできることが多い。
(d). 近似の仕方は本質的には本文のものと同じである。$${k}$$の積分を$${\omega}$$のものに直してから行っている。$${k}$$で行うよりはわかりやすいと思われる。
[20-4] 調和振動子模型の圧力
調和振動子系の分配関数は体積に依存しない。粒子は束縛運動をしているから自由粒子みたいに箱を定義する必要はない(1次元1粒子系であるが、有限の箱と調和振動子ポテンシャルを同時に扱った問題を、ここに置いてあるテキスト75ページの章末問題[5-8]で議論している。ただし、箱の大きさは時間の関数として変動している)。自由エネルギーが体積に依存しないことは、系の圧力を定義できないことを意味している。
ただ、本章で扱ったような固体系に外から圧力を加えて圧縮させたりすることは考えられるだろう。それによって格子振動の現象がどのような影響を受けるかを考えることは現実的に面白い問題となる。
ここで扱う模型はそのような現象を扱うもっとも簡単な模型となる。圧力を加えることで格子の形状が変わり、相互作用の性質が変わる。本章で扱っている模型では調和振動子ポテンシャルを用いて相互作用の効果を捉えているが、調和振動子は振動数という唯一のパラメータをもつ。それが体積に依存すると考えると、自由エネルギーが体積に依存するようになり、圧力を定義できる。
定数だと思っていたものが実は関数であったという考え方は、よく用いられる。[7-9]の解説で述べたように、できる操作が増えると変数も増える。
振動数の体積依存性をミクロな理論から得るのはもちろん難しい。そもそも調和振動子を用いた議論が成り立つかどうかもわからない。とはいえ、簡単にできる方策を探ることも有用であろう。
(c)で用いる$${\gamma}$$はGrüneisenパラメータとよばれているものに対応する(参考)。Grüneisenパラメータは、一般に次のように定義される。
$$
\gamma=V\left(\frac{\partial P}{\partial E}\right)_V
$$
今の場合に右辺の量を計算して$${\gamma}$$になることを確認してみよう(このことも問題にすればよかった)。
余談だが、この問題は筆者が作った演習問題の中で最も古いものである。ドイツでポスドクをしてたときに、大学院生と一緒に演習を担当していて、何か作れと言われて作った(ドイツ語わからないので英語で)。どうやって思いついたのかは覚えていない。もちろん、0から全てを生み出すオリジナリティが著者にあるわけではなく、どこかに載っているか、それを改変したものだと思う。今手元にないので確認できないが、Kittelの教科書(固体物理学入門か熱物理学)は見たような気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
