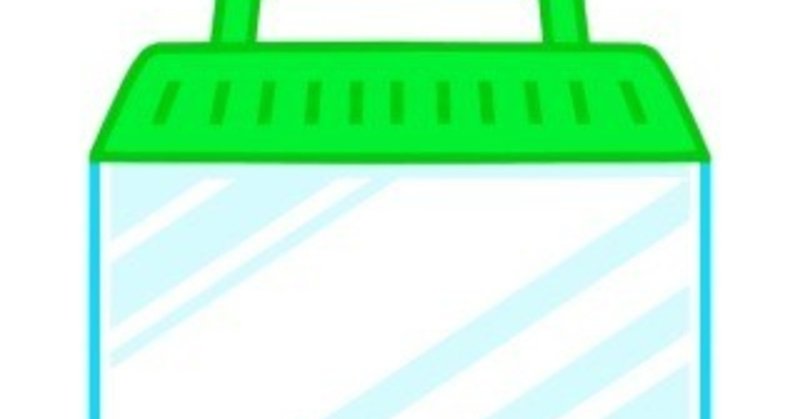
ショートショート「百足」
金曜日の夜、俺は仕事終わりに彼女に連絡をする。いつものルールだった。そうしないとこちらが出るまでずっと電話が鳴り続けることになる。
彼女は美人だ。大学時代に一目惚れをし、俺の熱烈なアプローチで付き合って2年が経とうとしていた。少し俺にべったりしすぎなところもあるが。
週末なので彼女のアパートに向かう。毎週末泊まりに行くのが習慣だ。彼女と過ごすのはとても楽しいのだが、そろそろ我慢できないレベルに達しそうな点がひとつある。
「おかえり!」
ドアを開けると彼女が出迎えてくれた。天使のような笑顔に癒される。そして「やつら」も出迎えてくれた。狭いアパートの部屋に虫かごが所狭しとテーブルを囲むように置かれている。
彼女は理系の大学院生で、ムカデ愛が高じて複数のムカデを飼っており日々愛でているのだ。
付き合っている以上お互いの趣味は尊重し口を出さない方がいいと分かっていてもさすがに辟易している。
デートのときにも小さいかごに入れて一匹は連れていくのだ。街を歩いている人々に顔をしかめられたり好奇の目で見られることも全く珍しくない。
「最近寒くなってきたし今日は鍋だよ!」彼女はにこにことして野菜や肉を鍋に入れていく。グツグツと沸騰しつつある鍋を見つめながら、俺は言いたかった言葉を口にした。
「なあ、ムカデを可愛がってるのは分かるけど正直食欲無くすし、食事時じゃなくても気持ちが悪いからせめて虫かごは目に触れないところに置くかしてくれないか....」
「こんなにかわいい子達のことを気持ち悪いって言うなんてひどい!タツヤも慣れればこの子たちのことがかわいく見えてくるはずだから!外に連れて行くのも、部屋でずっと愛でてるのも他の女の子たちがぬいぐるみをかわいがってるのと根本的には同じだよ!」「はあ......ぬいぐるみと同じ、ねえ....」
鍋の中に箸を入れ具を探り持ち上げた。黒くて細長いとげとげした具だ。はて、こんな具があっただろうかと戸惑う。よくよく見ると彼女のペットであった。10対を超える手足がくっついている黒い胴体。反射的に悲鳴を上げて箸ごと放り投げた。
「何よ。大きな声上げて。」
「ム、ムカデじゃないか! しっかりと虫かごの蓋は閉めておけよ!」
「え?うちの子? どこにもいないじゃない。しっかりしてよ。」
確かに放り投げた箸の近くや周りにやつはいなかった。気のせいか。仕事で疲れていて幻覚を見たのだろうか。どちらにしても生理的に気持ちが悪すぎる。もう、鍋には箸を入れられなかった。
「なんで食べないの?」
「気分が悪くなった。もう食欲ない。周りのムカデの入った虫かご見ながら鍋なんて食えるかよ。」
「どうしたの?大丈夫?」
「ムカデに囲まれた家で暮らしてる女なんかとこれ以上付き合えるかよ、もううんざりだし気持ち悪いんだよ! 別れよう。」
「ねえちょっと待ってよ、好きだよタツヤ、一緒にいて。」
気づくと俺は彼女の家を出て、ひたすら「何か」から逃げていた。
後日、別れ話をするために彼女とカフェで食事した。彼女のマシンガントークで別れを切り出すタイミングを見失っている。退屈で視線を下に落とした。
皿を二度見した。頼んでいたスープカレーから顔を覗かせている何かがいる。目が合った。奴だ。彼女のかごから逃げ出したのか。全身の毛が逆立つ。
「別れよう!頭がおかしくなりそうだ!!!もう帰る!」俺は逃げるように席を立った。「待ってよ! 」彼女の言葉を後に俺は自分のアパートへと直帰した。気持ちが悪すぎる。吐きそうだ。
アパートの階段を登りカギを開ける。いつもの匂いだ。頭のおかしい女から離れ忌まわしい脳裏にこびりついたムカデの像からも逃れられるのだ。俺は安堵して部屋をぼーっと見つめた。
床が蠢いている。電気もつけていなかったのでよく見えなかったが、目が慣れてくると次第に状況が飲み込めてきた。大小無数のムカデが蠢く、真っ黒な床が...............。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
