
『大量絶滅はなぜ起きるのか』うらばなし②目次づくり編 ~かつての章見出し案を大公開!~
弊社のT.W.がブルーバックス『大量絶滅はなぜ起きるのか』の編集を担当しました。その「うらばなし」を披露いたします。
この記事はT.W.の「やってやった感」がほとばしる、いけ好かない文章になる可能性が高いです。ですが、わずかながら、編集者のお仕事紹介文としてギリギリお楽しみいただける可能性もございます。もしお時間が許せば、ご一読ください。
うらばなしよりも、本の中身に関心がある方には、ブルーバックスのWeb記事(第1回、第2回、第3回、第4回)がおススメです。
見出しが大事
書籍において目次はとても重要な存在だと信じています。魅力的な目次だからこそ読みたくなる、読み進められるなんてことが、きっとあるはず(逆に、読んだら面白いのに目次がイマイチで読まれにくい、ということもあるかもしれません)。優れた目次をつくりたい——多くの編集者が共有する思いではないでしょうか。
数の多い「小見出し」はさておくとしても、「章見出し」にはとくに気を使います。以前、「Webに掲載される(Web書店向けに配信する)内容紹介には必ず目次を入れろ」と指導されました。文章で内容を説明するだけでなく、章見出しを併記することで、より本の雰囲気・魅力が伝わりやすくなる、という意味だと思います。指導以来、実践しています。
『大量絶滅はなぜ起きるのか』の章見出しも、いろいろと検討しました。そのときのエピソードをご紹介します。
腕の見せどころ
前回の記事に書いたとおり、尾上先生の構成力は抜群です。構想段階(まだ文章にはなっていない箇条書きの段階)から、ワクワクさせられていました。
何度かのマイナーチェンジを経て、本書のおもな構成は「プロローグ+第1~9章+エピローグ」というかたちに落ち着きました。そして、尾上先生から「なんとか原稿を最後まで書き終えました」とのメールをいただいたのが、2023年4月。その日から、印刷した原稿をつねに持ち歩き、隙あらば読み進めるという生活がはじまりました。
目標は5月下旬までにコメントを用意すること。この時期、尾上先生が学会参加のためしばらく東京にいらっしゃることを知り、それまでにブラッシュアップのアイデアを練ろうと決めたのです。
原稿は……期待どおり、面白い! じつはかなり難しい内容も扱っていますが、ぐいぐい読ませる文章です。仕事を忘れて読みふけってしまうほどでした。正直言って、あまり私からコメントすることもないくらいの完成度だったのです。
この時点で私に何ができるかを考えたときに、やはり目次(章見出し)だろうと注力するポイントを絞り込みました。編集者としての腕の見せどころです。結局、5月の打ち合わせまでに、3パターンの目次案を用意しました。

パターン① パロディ
最初に考えたのは、すべての章見出しを名作ミステリー小説のパロディにするパターンです。こんな感じ。
プロローグ——鳥たちの沈黙(元ネタはトマス・ハリス『羊たちの沈黙』)
第1章 縮みゆく生物(リチャード・マシスン『縮みゆく人間』)
第2章 死因がいっぱい(パトリシア・ハイスミス『太陽がいっぱい』)
第3章 容疑者X(東野圭吾『容疑者Xの献身』)
第4章 不連続絶滅事件(坂口安吾『不連続殺人事件』)
第5章 点と線(松本清張『点と線』)
第6章 ゼロ時間へ(アガサ・クリスティー『ゼロ時間へ』)
第7章 恐怖の谷(コナン・ドイル『恐怖の谷』)
第8章 熱帯に死す(アガサ・クリスティー『ナイルに死す』)
第9章 そして誰もいなくなる?(アガサ・クリスティー『そして誰もいなくなった』)
エピローグ——大量絶滅の迷宮(パトリシア・ハイスミス『殺意の迷宮』)
やや強引に感じるところもありますが、いちおう、各章の内容をふまえた見出しを考えたつもりです(白状しますと、元ネタにした小説すべてを読んだわけではなく、ただタイトルをもじっただけの作品もあります)。
当時つけていたメモを見返すと、このほかにも使えそうなタイトルが挙げられていました。『砂の器』『ねじれた家』『緋色の研究』『長いお別れ』『虚無への供物』『すべてがFになる』『災厄の町』など。
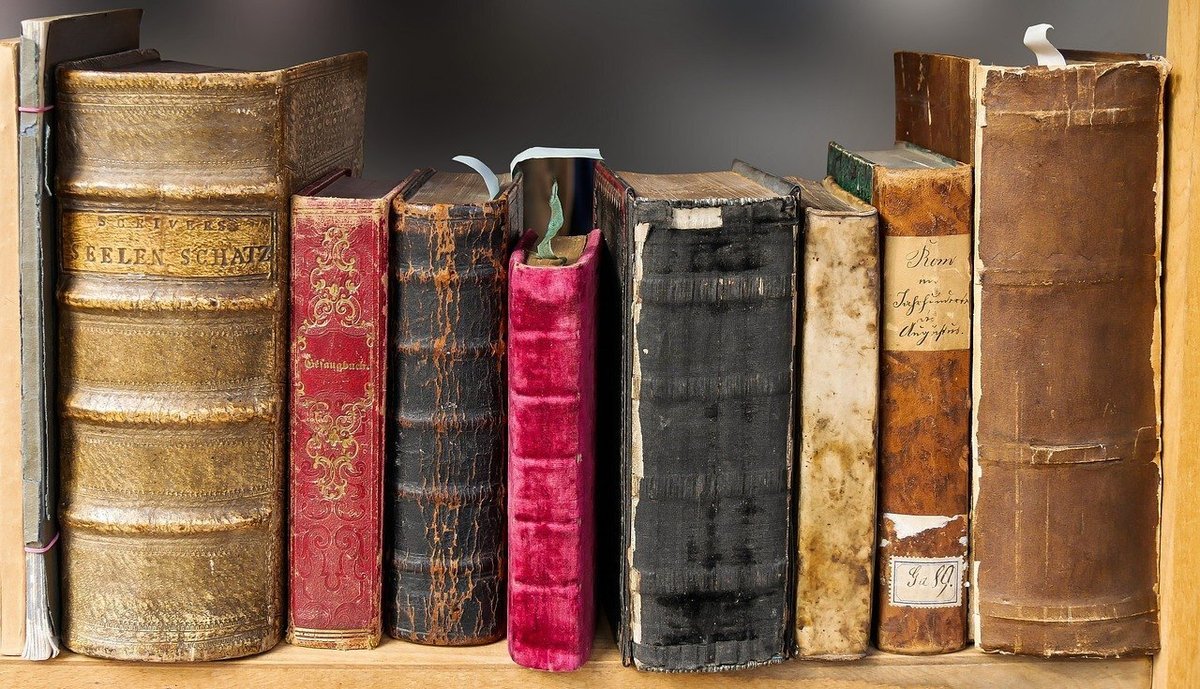
パターン② 二字熟語
次に考えたのは、すべての章見出しを「二字熟語」にするパターンです。尾上先生には以下の案をお見せしました。
プロローグ——異変
第1章 天国
第2章 混沌
第3章 犯人
第4章 指紋
第5章 氷解
第6章 疑惑
第7章 衝撃
第8章 限界
第9章 境界
エピローグ——避難
じつはこのスタイルは、尾上先生の前著『ダイナソー・ブルース』の目次を踏襲したものです。非常にかっこよかったので、いつか真似しようと考えていました。
言葉選びのルールとして、必ず各章の本文中で使われている熟語を使いました。内容を象徴していて、かつ見出しにしたときにダサくならない言葉を探すのは、案外難しかったです。

このパターンは、見出しだけでは内容が伝わりにくいという弱みがあります。なので、教科書では採用しにくいですが、ブルーバックスであれば成立するだろうと考え、提案しました。
パターン③ ストレート
そして最後の案は、前の2つに比べるとストレートなパターンといえます。
プロローグ——見えない糸
第1章 天国に近い場所
第2章 混沌とした世界
第3章 なし崩しの容疑者
第4章 物差しの目盛り
第5章 見せかけの鎖
第6章 蘇る証拠
第7章 荒れ果てた景色
第8章 生命の限界
第9章 よりよい未来
エピローグ——見落とされた舞台
いずれの見出しも、各章の文章中の印象的なフレーズがもとになっています。パターン②で使った言葉を流用した章もあります。すべて「体言止め」で統一して、できるだけスッキリさせつつ、興味を引くことを目指しました。
決定版
以上3つのパターンを尾上先生に見ていただくと、①か②がいいかなあ、というリアクション。その他こまごましたコメントとともに持ち帰って検討していただくことになりました。
そして、尾上先生から原稿の改訂バージョンを受信したのが6月中旬(打ち合わせから3週間弱——早い!)。もう少し時間がかかるはずだったのですが、予定していたフィールド調査が悪天候で中止となり、執筆の時間を確保できたとのことでした。それにしても早い! 集中力が半端ではないのでしょう。
章見出しはパターン②を採用していただきました。一部の章は、私の案とは別の、より適切な言葉に差し替えていただきました。上にお示しした案ではいまひとつしっくりきていなかった章も改善され、ほとんど完成形といえる目次ができあがりました。
最終的には、こうなりました!
プロローグ――大地
第1章 異変
第2章 混沌
第3章 犯人
第4章 指紋
第5章 連鎖
第6章 疑惑
第7章 消失
第8章 限界
第9章 境界
エピローグ――深海
「プロローグ」と「エピローグ」が対(つい)をなす形になり、ぐっと引き締まりました。(同僚がXで「目次だけで、もう面白い!」と言ってくれたポストは、こちら)。
正解
こんなふうに、書籍の目次(章見出し)は執筆・編集過程で変わることがあります。構想段階からまったく変化しないということは、まずないでしょう。目次だけでなく、書名や、カバーの上に巻く帯の惹句も、おもに編集者が知恵を絞る要素です。

いずれも「正解」は存在しないのが難しいところ。正解がないので「解法」もありません。毎回試行錯誤が必要で、いろいろ考えていると、優劣も判断できなくなってしまうことも……。そんなときは、編集部内で多数決をとる手もありますが、票が割れてしまって参考にならなかったりします。
苦労もありますが、考えるのが好きな人には、書籍の編集は楽しい仕事です。
あ、そうだ! この記事の締めくくりは、『大量絶滅はなぜ起きるのか』の「エピローグ」の最後をパクることにします。
答えは何も用意されていないし、誰も知らない。「ファンクーロ!」と大声で叫びたくなった。これだから編集はやめられない。
原文は太字部分が「編集」ではなく「研究」です。
研究にも編集にも、やめられなくなる魅力があるのかも?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
