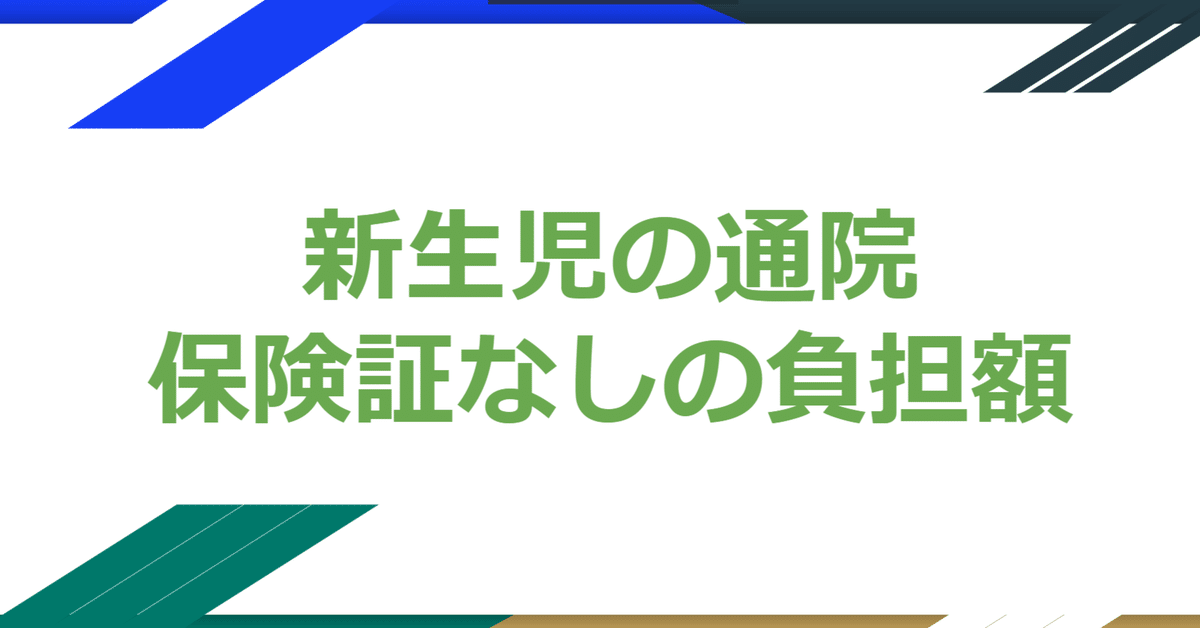
新生児の通院 保険証なしの負担額
保険証がなく、医療費助成がないと
新生児が小児科にかかることで、9,800円 かかりました。
新生児が9,800円 かかるということ、保険証があれば 2,940円 の負担です。
医療費控除があると、ゼロ円 若しくは 数百円の負担です。
改めて、健康保険制度の手厚さを感じます。
9,800円の負担だと病院に行くことを尻込みしてしまうところを、2,940円 であれば まだ一歩が踏み出しやすくなります。
これが、高齢者になり、2割・1割 負担となると 2割で 1,960円、1割負担となると 980円 です。 ますますハードルが下がります。
この根底にあるのは、「リスクは早い内に摘む」ということです。プロジェクトマネジメントでもそうですが、小さいリスクである内に摘むことで被害を最小限に抑えることが出来ます。
病気で言うと症状が悪化すればするほど、対応に手間と技術が必要となり、コストがかかります。
そうなると、最初の一歩のハードルを下げることで、全体のコストを下げることが出来るのは自明の理です。
一方でハードルを下げすぎると、特段の症状がなくても頻繁に通院し、医療機関や医療費を圧迫するので色々と問題もあると言うことです。
個人的には 定期検診などの初手は低いハードルとなるように大きな助成、程度が上がるにつれてある程度の累進性は設けるべきかなと思います。(医療内容や年齢にて)
医療費助成
日本全国、各都道府県、各市区町村 における子どもの医療費助成については以下の記事で少し調べてみました。
日本全国の各自治体において、手厚い医療費助成があるので普段子育てをしているとあまり 医療費がどれだけかかっているかを意識することは少ないと思います。
新生児80万人/年 として、一回1万円程度、月に一回で12ヶ月/年 18歳まで。
1万円 x 12ヶ月 x 80万人 x 18世代 = 1.728 兆円 ほどはかかる計算ですが、国と自治体の全体予算に比べると まぁ 大した金額ではないかなと感じます。


実費となる医療費
唯一 出生届を出し、子どもを扶養に入れ、保険証が発行され、医療費助成の認定を受け の期間(おおよそ数ヶ月)の間で病院にかかる必要があると自費になります。
今回はその経験のまとめです。
小児科の費用

領収書を見ると、「負担割合 100%」となっています。
保険証の提示が出来ず、医療費助成ももちろん無いので、100% の負担です。
保険点数は 「医学管理等」だけで707点 となっています。
点数の表を見ても 707点ちょうどのものはなかったので、何かしらの加算があったのかなと思いますが、小児科の外来関係であてはまりそうなのは以下の2つです。
B001-2 小児科外来診療料(1日につき)

B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)

結果として、どの様な点数付けがされていたのかは分かりません。
調剤薬局の費用

薬局での薬代の負担も100% です。
点数は そうなんだろうな という項目のそれぞれの点数です。
自己負担分医療費の払い戻し
医療機関では 同月中 であれば、保険証と医療費助成証 と 領収書を持参することで 返還をしてもらえるということでした。
また、同月を越えても、保険期間と自治体へ申請することで返還されます。とのことです。
子どもの扶養追加と保険証は即座に申請しておく
手持ちで数万円を気楽に出すことが出来れば特に問題ないですが、とは言え早め早めに申請しておくに越したことはありません。
申請が完了しても、発行までに時間がかかるので、早め早めです。
健康保険証はマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)へ移行し、2024年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。病院・薬局等を利用する際は、マイナ保険証をご利用ください。
2024年12月2日 から現行の健康保険証が発行されなくなりますので、それ以降は新生児についてはマイナ保険証一択になると言うことです。
上の記事でも書きましたが、保険証やら診察券やら全てが一枚に収まるようにしてもらいたいです。
ただ、スマホマイナカードは一台に子供の分も入れることが出来るようになるのか?次第でできる出来ないが変わってくると思います。
健康保険と医療費助成 はいろいろな意味で凄い。ということでしたが
自己負担を理由に病院に行くのを渋ると、手遅れになることもあるので、優先順位は 何かあればまずは病院へ行くことです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
