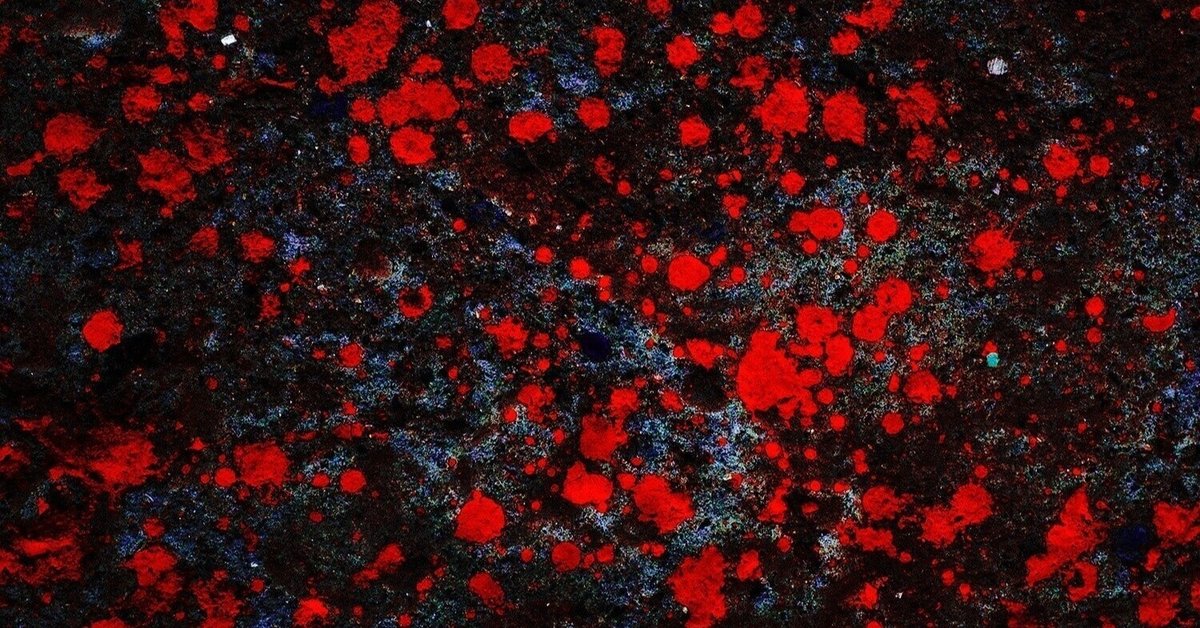
残酷な回想~Ⅱ~(21)
ただ前庭に一家全員が倒れていた。父と母も、もうすでにこと切れていた。いつでも最強だと思っていた二人が倒れている衝撃が一瞬自分の目の前を真っ暗にした。いつでもどんな修羅場でも二人は凛々しくそこに生きているものだと言えた。泣いている暇はないのに目がかすんだ。そして急に澄み、またかすむ。顎を伝う熱いものは何だろう。
紅夜はなぜこんなことになったのか情報収集するために家に入った。すると自室に手紙が置いてあった。母の字だ。
紅夜
私(わたくし)たちは戦っています。武家が十二家集結しているようです。反乱に見えますが裏で糸を引いているのは天皇であることが推測されました。故に今この手紙であなたがすべきことを伝えます。
まず家のもの以外のあなたにとって親しい人の記憶を消しなさい。自分だけの記憶を消す薬はあなたの布団の下にあります。そして名前はそのまま使いなさい。怪しまれることはないでしょう。
次に姿を隠しなさい。できるだけ表に立たず影にいなさい。そのまま三年、暗殺者として生きなさい。暗殺の依頼を受けて金を稼ぎなさい。あなたの技ならできるでしょう。こんなに卑劣な仕事は嫌でしょうが耐えなさい。そして三年後、捕まりなさい。そして死刑を言い渡されるでしょう。でも助けてくれる人がいます。必ず。これだけは信じなさい。
以上
たったそれだけだった。母らしい几帳面な美しい字だった。
紅夜は薬を持って冷雅をカフェに呼び出した。
来た冷雅にほほ笑みかける。
自分があまりにも出来すぎてしまっていることに紅夜は内心焦っていた。何かおかしいことに冷雅が気づいてどうしたのかと聞いてくれるのを待っていたのに皮肉なぐらい、なにもないように見えているらしい。
冷雅が飲むコーヒーに薬を入れた。冷雅は何も気づかなかった。冷雅が飲んでから数分後にカクッと眠りに落ちたのを確認して紅夜は店を出た。
そこからは暗殺者としてもう誰もいない月影家に一人で住んでいた。確かに追手が来る可能性があったがその時はその時に殺されても構わないと消極的な考え方をしていた。しかし誰も来なかった。不自然なまでに。それがうれしいのか悲しいのかわからなかった。
暗殺業に手を染めていくうちに自分があと何年これを続けるのかわからなくなる瞬間があった。
そのたびに紅夜は母の手紙を読み返してたり、冷雅のことを思うのだった。自分から捕まる日を待っていた。ただひたすらに暗殺の依頼を受けながらも捕まるのを待っていた。または誰かに殺されてしまってもいいと思っていた。
その日が来た時に冷雅に捕まったのは非常に嬉しかった。冷雅が自分の事をおぼえてなくて本当にほっとした。冷雅は全く変わっていなかった。仕事を完璧にこなすことに神経を注いでいるような彼を見てうれしかった。牢へ行く道ずっと冷雅と歩けるのがうれしかった。恐れも怒りも感じずただただうれしかったのだ。
そして母の予言通り死刑から免れさせてくれた羅貴に会った。
ただひたすらに同じことを思っていた三年間からの解放感はすさまじかった。冷雅がだんだん自分を信頼していってくれた。それだけで十分だった。自分の事をおぼえていなくても自分が覚えている関係を取り戻すのは出来なくてもただ冷雅の隣にいるのは幸福の代名詞であると思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
