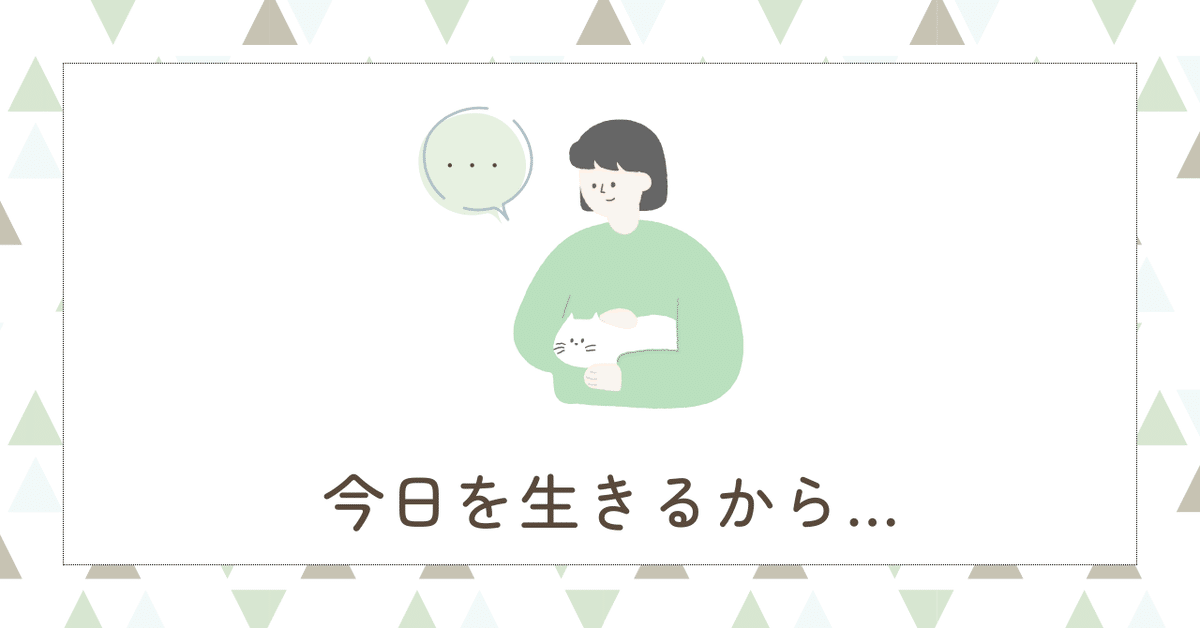
今日を生きるから…
ついに始まった、、、2学期。忙しくなると分かっていてもなかなか動き出せなかった夏休みからのギャップは、やっぱり激しいと感じた。
2学期に向けて取り組んだこと、①教室、職員室の机の整理整頓。②教科書のスキャン。③国語(物語)の1単元分の教材研究。たったこれだけ。でも、これがなかなかにいい。
これらの準備が私にもたらしてくれたことは「明日を生きる、明後日を生きる姿勢」だ。
1学期も週案を書いていたし、毎週の見通しを持てる仕組みの中にいたはずだった。それなのに、毎日考えていたことは「今日を生きること。」今日の1つ1つに緊張し、今日が終わったことにほっとする、そんな毎日だった。気づくと職員室に残っているのは数人。校務文章の負担が少なく、低学年のため時数も少ないはず…。これから何十年もやっていけるのだろうかと思っていた。
2学期が始まり、授業も始まった。「確認しながら始める2学期」の鉄則のもと、一つずつ確認。できない姿を叱るのではなく、確認という形で導いていく。「できることをやっていないと思ったら先生は叱るよ」と少し圧をかける。これまで築いてきた子どもとの関係、子供の理解、学校の仕組みの理解、周りの先生方との連携、すべてがかみ合って回りだしたような感覚があった。子どものコントロールにかけるコストが減った感覚だ。いや、もちろん自分のクラスは明らかに初任用クラス。客観でも主観でも賢くて素直な子が多いクラス。でも、子供をこうやったらうまく動かしてあげられるという無意識の言動は1学期に比べたら確実に身についているのではないかと思うわけである。
「もっと早く帰りたい。」
子どもを動かせると思ったら、人間、欲が出るものだ。放課後の仕事を分析してみると、おおむね「今日を終わらせる仕事」と「明日を始める仕事」だった。1学期は「今日を終わらせる仕事」が長かったなと思う。集めたノートのチェック、図工の後散らかった教室の掃除、どこに置いたか忘れた指導書や教科書探しから始まるなんてこともあった。
「これ全部子どもがいる時にやればよくね?」
ここで役立つ整理整頓や教科書スキャン。使う赤ペンは1本で場所も決めた。指導書はもう持ち歩かない、iPadの中に全部入っているし。体感これだけで1日30分くらい得している気がする。小さなストレスってあるんだと思った。予定通りの場所に予定通りのものがある。予定通りにいかない子供たちを相手にするには、予定通りを増やすことがポイントなんだと感じた。そんなこんなで「今日を終わらせる仕事」の時間も少なくなってきて「明日を始める仕事」にさける時間が多くなった。
「明後日の分もプリント印刷しちゃお」
どうした、早く帰るんじゃなかったのか。また欲が出てきたような、でもよくとはまた違うような充実した暖かい気持ちで印刷した。「これだ!」という感触があった。
「今日を生きるから、明日を生きる、明後日を生きる」と進んでいくことこそ、毎日早く帰るための近道なんだと。
教材研究の仕方も主任に教えてもらい、1単元分やるようになった。10時間分を見通すことは国語だけで言えば1週間ちょっと先を見越しているような感じだ。これをすべての教科でやれば、それこそ前日の教材研究は5分10分で終わることも可能なのかもしれないなと思った。
支離滅裂な思うことを羅列した文章になったが、「早く帰るコツは早めの教材研究」を答えにしておこう。その余裕が「今日を終わらせる仕事」の削減や「明日を始める仕事」の効率化、「明後日、明々後日、、、」と先々の仕事をあらかじめ減らしていくことにつながり、その繰り返しが「早く帰る事」につながっていくと思う。
でも、同時に「今日を生きる」ことを完璧に頭から消してもいけないという意識は持っておこうと思う。「目の前の子どもありき」で子どもたちの前に立ち続けたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
