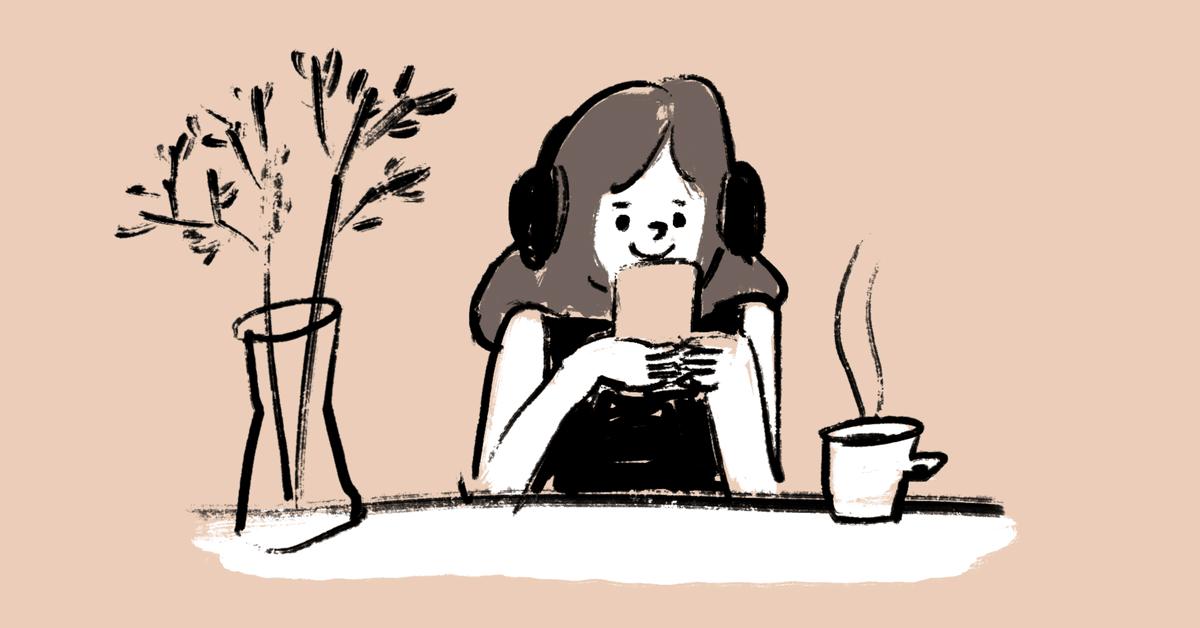
#37 新しいわたしと出会う|思考の練習帖
前回、前々回に引き続き、今日も #思考の練習帖 の振り返りをば。
書いているうちに、予想だにしなかったことを発見したり、思いがけない結論に至ったりすることがある。今回はそんなnoteを集めてみた。
能力の輪
「#05 輪を描くわたし」では、ロルフ・ドベリの『Think clearly』のなかに書かれていた能力の輪について考えた。
自分がこれまでの人生で何に時間と執念を向けてきたかを考えてみると、思い当たったのは「書くこと」だった。noteの界隈ではかなり平凡な回答だと思うのだけれど、まあnoteユーザーだけが人類じゃないのでよしとしよう。
今日までの日々、確かにわたしはひたすら書き続けてきた。
だから、書くこと抜きにしてわたしを語れないし、書くこと抜きにしてわたしの能力も考えられない。わたしはこれまでも、これからも、書き続けるしかないのだ。
もっともっと、たくさんの時間と執念をかけて。
チコちゃん風のかぶりもの
思考の練習帖のヘッダー画像はどれもノウチさんのイラストを拝借しているのだけれど、「#08 被らないわたし」は唯一の例外である。
ヨシタケシンスケさんの『もう ぬげない』っぽくて好き。
大きなかぶりものをしてチコちゃん級の頭のデカさに「重たいよー」「前が見えないよー」と言っているのが今のわたしで、そう気づいたらなんだか滑稽に思えてきて気持ちが軽くなったという話。
そのおかげだろうか、最近はこの閉塞感から解放された感じがする。
主体性の考察
「#09 助手席のわたし」でわたしの仕事に必要なのは子どもたちの主体性を引き出すことだと気がついて、「#11 モチベートするわたし」でニーズが主体性の原動力となるのだと納得し、「#14 行動を探すわたし」で主体性の罠に驚愕し、「#15 Vを掴みたいわたし」で実際に行動公式にあてはめて主体性を引き出す働きかけの計画を立ててみた。
そうして行き着いたのは、ここだった。
3231字も書いたのに、なんだかすっきりしない。Vに辿りつける自信がない。ここに書いたのは机上の空論で、絵に描いた餅だ。これをもとにクライエントとわたしの行動をよく観察して、見逃した随伴性がないかを調べてみよう。そう、成功の秘訣は、成功するまで続けること。めげずにカイゼンし続けるしかない。
思わず、ズコー!と言ってしまいそうになるような拍子抜けっぷり。何かを手に入れるのに楽をしようなんて考えは甘いのだ。地道に観察して、「成功するまで続けること」。OOCEMRでも「選択肢を出し続けよ」とあったじゃないか。
主体性を引き出す旅は続く……。
怒られ分析
「#10 怒るわたし」は、最悪な一日の日記。
とことんうまくいかなかった一日を終えて、むしゃくしゃしながら家に帰ってきたわたしは、noteにそれを書くことにした。書いて頭を整理しなければ、どうにも気持ちが収まらなかったのだ。
その結果は上々だった。ぜんぶ書き終えたころには身も心も軽くなって、その晩はとてもよく眠れた。わたしは自分で言うのもなんだけれど、精神的なリカバリー能力は結構高いほうだと思う。書くという武器が、わたしをいつも希望の光で引き上げてくれる。
これだけ書いたらすっきりした。すっきりするのは大事だ。臭いものに蓋をしても何かの拍子に蓋が開いたら大惨事だし、そういう可能性を残している時点で心が蝕まれていく。
いやほんと、その通りだわ。
年度末ふりかえり
「#18 年度末のわたし」で三つの目標に対する自己評価をした。
怒られ分析と同様、こういうのはわたしの得意分野だ。ふりかえるのが好きなのだ。ふりかえって、課題をみつけて、それを次の「よっしゃ、やるぞ」の燃料にする。気合を入れるのが好きなのだ。
目標に向かって頑張りたいタイプ。頑張っている自分に酔いしれるのが好きなのだ。
それで前に進めるなら、多少見苦しくても結構。わたしは前に進んでいたいのだ。
リフレクション
「#24・25・26 内省するわたし」では、熊平美香の『リフレクション』から「ぶれない軸をもつリフレクション」をやってみた。
問いに答えていくなかで、新しい自分に気づいていく。リフレクション大好き芸人としては大変面白かった。
弱みと強みはコインの裏表。両方を知ることで、ちゃんと「よっしゃ、やるぞ」のエンジンをかけられる。
期待に応えられる自分でありたいと、切実に願ってしまう。それは「誠実でありたい」の価値観につながる。仕事のクライエントである子どもたち、協働者である同僚・上司、そういう人たちに誠実さを認めてもらわずにはいられなくて、だから自分でその期待に傷をつけるのが恐ろしい。
しかし、そもそもその期待というのが幻想なのだけどね。
人の痛みに敏感ならば、それを強みに変えよう。痛みを和らげる方法はわからないけれど、「痛かったね」と寄り添うぐらいはできるだろう。そのためにもコミュニケーションの絶対量を増やすのは優先度が高い。これからますますいろんなことが追いつかなくなっていく予感がしているけれど、ここだけはしっかり押さえておこう。
多様性施策はなぜうまくいかないか
「#30 「違う」わたし」で、目から鱗が落ちた。
ダイバーシティ・インクルージョンという考え方をわたしは大事にしたいと思っているけれど、いつも鼻で笑われたり、そんなのは理想論だと非難されたりして悔しい思いをしてきた。なぜそういうことになってしまうのかを、入山章栄の『世界標準の経営理論』が明快に説明してくれたのだ。
じゃあこれをどうしたらいいのか、という切実な問いへの世界標準の答えはまだないようだ。
わたしなりの答えは、タスク型の多様性に目を向けるということだろうか。
差異のネガティブな側面ばかりが目についてしまうと、ダイバーシティ・インクルージョンからはどんどん遠のいてしまう。だから、ポジティブな側面をどんどん評価しよう(単純だけど)。
わたしの持っていないあなたのその経験からは、どんなことが言える?
あなたのその価値観はわたしにはなかったものだけれど、どんな経験がそれを導いたの?
コミュニケーションを丁寧に重ねて、差異の根源を探るのだ。
それってキメの問題だよね
「#33 メイクセンスなわたし」でセンスメイキング理論というものに初めて触れた。
それまで聞いたこともなかったが、よくよく読んでみるとさもありなんという感じ。新卒で入った会社でよく、「それってキメ(決め打ち)の問題だよね」と言われていたが、要はそれのことだ。
ただ「エイヤ!」と決めたらいいわけじゃない。そこに納得感、腹落ち感がちゃんとあること。決めたらとことんやり抜くこと。そこが弱かったから、わたしは優柔不断だったんだと思う。
選択肢は出し続けるべきだし、マイナス面は徹底的に潰すべきだ。しかし、だからといってずっと同じ場所で二の足を踏んでいたってどうしようもない。行動しなければ始まらないのだ。
今日はここまで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
