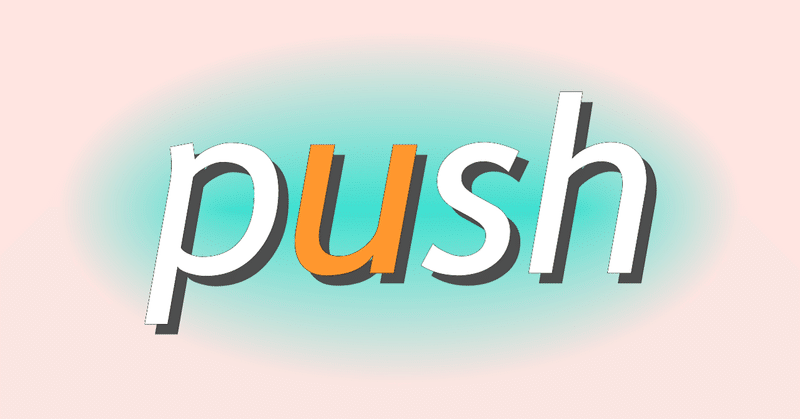
PUSHへと、そしてPUSHからつながる「芋づる」
男達の使う整髪料には、ジェル、ワックス、ムースなどといった種類があります。
「ジェル」は「ゲル」と同じことで(前者は英語、後者はドイツ語)、「シリカゲル」やボールペンの「ゲルインク」、「ゼリー」や豆腐、こんにゃくなどの食品にも見られる、物質の状態です。
「ワックス」は「蝋(ろう)」のことであり、床や自動車などに光沢を与えるため、スキー板を滑らせるためといった用途が有名です。
「ムース」は「泡」を意味するフランス語mousseであり、例えば食品のムースは…
「泡立たせた生クリームや卵白を用い、口当たりがふんわりして滑らかなように作った菓子や料理。」
(小学館デジタル大辞泉)
整髪料のムースも容器から泡状になって出てきます。
商品によっては「フォーム」という名前になっている場合がありますが、これはform(形)ではなくてもちろんfoam(泡)のことです。
「泡」と言えば石鹸・洗剤につきものです。
今は売られていないようですが、以前は「プスムス」という液体石鹸がありました。
『ジョンソン『プスムス』 CM 1989/10』
https://www.youtube.com/watch?v=YnKRxpdmGc4
このテレビ広告の中で「フランスで人気のハンドソープ」と謳(うた)われていますが、その商品名はフランス語で「Pousse Mousse」とつづられます。
「Mousse」が「泡」なのはいいとして、では「Pousse」とは?
「pousse-
〘合成語要素〙(←pousser)「押すもの」の意」
(小学館ロベール仏和大辞典)
ここに書いてあるpousserプセは「押す」という動詞です。
ポンプ・タイプの容器に入っている液体石鹸なので、使うときは上から「押す」動作で出すことになるわけです。
pousserは実は、前回投稿で取り上げたpellereの一族です。詳しく見ていきましょう。
フランス語pousser
ラテン語pellereは英語で言うdriveやpushに当たると前回書きましたが、strike(打つ)に当たる意味も存在します。
それに「反復」の意味を付け加えて「繰り返し打つ」を表す形に変形したのがpulsareという動詞です。
このpulsareが昔のフランス語でpoulserに変化し、更に時間の経過とともにLが消えてpousserとなりました。
現代フランス語ではおおよそpushやdriveの意味で使われているようです。
「Ne poussez pas, il y a de la place pour tout le monde.
押さないでください,みんな座れ[入れ]ますから
C'est la curiosité qui l'a poussé à agir ainsi.
このような行動に彼を駆り立てたのは好奇心である」
(小学館プログレッシブ仏和辞典)
英語push
用法
あまりにも基本的な言葉なので英語に元からある単語のような顔をしているpushですが、実は「ラテン系」の輸入品であり、pousserが昔の英語に入ってきてposson/poshen/pushenのような形をとり、現在のつづりに至ったものです。
各種の「押す」を意味するのはもちろんですが、フランス語pousserと同じように「drive駆る」のニュアンスでも使われます。
「push a car to over eighty miles an hour
車を時速 80 マイル以上にあげて走らせる
I pushed him into writing to his parents.
彼にせっついて両親のところへ手紙を書かせた
They're pushing him to enter politics.
彼らは彼に政界入りを盛んに勧めている」
(研究社新英和中辞典)
「押す」に関しては、人間以外が主語になることもあります。
「The slump pushed up unemployment to 23%.
不況で失業率が 23 パーセントに上がった」(同)
「Economists are cautiously optimistic that any recession will be mild. Others believe a downturn could be entirely avoided. They noted that fears of a recession were pushing down prices of commodities like oil, which could help to reduce cost pressures for businesses and benefit the overall economy.
(経済専門家たちはどんな景気後退が起こっても穏やかなものだろうと、慎重ながら楽観的だ。景気の下降が全く避けられるだろうと考える者たちもいる。彼らが言及したのは、景気後退への恐れが石油などの商品の価格を押し下げつつあって、そうなると企業へのコスト圧力が減って経済全体に利益を与える一助となる可能性がある、ということだった)」
https://www.reuters.com/markets/us/strong-us-consumer-spending-seen-driving-economy-first-quarter-2023-04-27/
『ドリトル先生』
Hugh Loftingヒュー・ロフティングの児童文学『Doctor Dolittle』シリーズは、1作目が西暦1920年/大正9年にアメリカで刊行されました。
「日本で本作を最初に紹介した井伏鱒二が表題を「ドリトル先生アフリカゆき」としたことから、以後の翻訳でもこれに類する邦題が付けられることが多い。」
(ウィキペディア)
作中、Pushmi-pullyuという架空の動物が登場しますが、作者自身が描いたこれの挿絵でその姿をご確認ください。
Pushmi-pullyuの画像(左端の動物)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Doctor_Dolittle_characters#/media/File:Story_of_Dr_Dolittle_p107.jpg
「非常に希少な種で、胴体の前後にそれぞれ頭がついている、後ろ向きに二本角のついた有蹄類。本人によると一角獣の親戚らしい。(中略)危機に敏感で、片方の頭が眠っている間も残る片方の頭が起きている。」
(ウィキペディア)
「Pushmi-pullyu」は要するに「Push me pull you」の音であり、「私を押してくれたら、君を引くよ」といった感じでしょうか。
井伏訳では「オシツオサレツ」すなわち「押しつ、押されつ(=押すのと同時に押される)」なので「引く」という言葉は出てきませんが、良い語感だと思います。
西暦1967年/昭和42年に公開されたアメリカ映画『Doctor Dolittle』ではオシツオサレツは双頭のリャマのように実写化されています。
『Doctor Dolittle: The Pushme Pullyu』
https://www.youtube.com/watch?v=5qUr96HmUTw
poussette
poussetteプセットは動詞pousserに、「小」のニュアンスを加える接尾辞-etteが付いて出来た言葉です。
フランス語では、「押す」のイメージと「小」のイメージが重なり合う領域にある物として「画鋲」を意味します。
また、「乳母車、ベビーカー」や「ショッピングカート」もその領域に入る物品です。
下記のアドレスの画像には「Une poussette moderne à 3 roues(3つの車輪のある現代的乳母車)」という題名が付けられています。
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poussette#/media/Fichier:Moderne_kinderwagen.jpg
英語としてのpoussetteプーセット(「セ」を強く読んでください)はカントリー・ダンスの一種であり、以下はその映像です。
『Poussette』
https://www.youtube.com/watch?v=TEXJh0Sj-K0
「外来種」pushに取って代わられた「在来種」
フランス語から入ってきて、「押す」を表す単語の代表の座に就いたpush。
元々英語に存在したscufanというゲルマン系の言葉の影が薄くなってしまいましたが、ドイツ語では同語源のものが健在です。
ドイツ語schieben
「Er schob die Sachen auf dem Tisch zur Seite.
彼は机の上のものをわきへ押しのけた
Er schob seinen Fehler auf seinen Kollegen.
彼は自分の失敗を同僚のせいにした」
(小学館プログレッシブ独和辞典)
(schobショープはschiebenシーブンの過去形です)
1例目では物理的に押すことを言い、2例目では抽象的なもの「Fehlerフェーラァ:失敗」を「押し付ける⇒転嫁する」ことを述べています。
英語shove
英語ではトップの座から滑り落ちたscufanですがその子孫が生き残ってはいて、現代英語としてはshoveという形です。
shoveは「ショウヴ」ではなく「シャヴ」と発音します。loveやdove(鳩)が「ラヴ」「ダヴ」であるようにです。
「She shoved the dictionary across the desk to him.
彼女は辞書を机の向こうから彼のほうへ押しやった
He shoved it back in the drawer.
彼はそれを無造作に引き出しの中へ戻した」
(研究社新英和中辞典)
和訳の方からニュアンスが伝わると思いますが、少々strongな、forcible(力ずく)な、rough(荒っぽい)な「押し」ということになります。
pushとの、このニュアンスの差が分かっていないと次の慣用表現をうまく消化できません。
「if [when] push comes to shove
いざという時には, いよいよとなれば」(同)
ここでのpushとshoveは名詞ですが、どちらも「押すこと」だとしか認識していないと、「《押し》が《押し》にまで至ったなら/とき」になってしまって、理解に苦しみます。
strong/forcible/roughのニュアンスを加味して「《押し》が《力のこもった強く荒っぽい押し》にまで至ったなら/とき」とすれば、押す程度が変化した⇒状況が変化したことが察せられます。
英英辞典でどのように定義しているか見てみましょう。
「when matters become critical; when a decision needs to be made
(問題がきわどくなった時;決定がなされる必要がある時)」
(Collins English Dictionary)
「the situation becomes so bad that you have to do it
(状況がとても悪くなって、それをしなければならない)」
(Cambridge Dictionary)
「when all the easy answers to a problem have not worked, and something else must be tried
(ある問題に対する簡単な答えすべてがうまくいかなかったとなり、他の何かが試されねばならない時)」
(Cambridge Academic Content Dictionary)
そもそも何かの状況が人を「押して」、つまり圧力をかけていたのだが、その「押し」の程度がいよいよ深刻なものとなった時、といった感覚なのでしょうか。
この表現は曲の題名にも時々使われます。
アメリカのバンドVan Halenヴァン・ヘイレンの曲『Push Comes to Shove』(西暦1981年/昭和56年発表)。
『Push Comes to Shove (2015 Remaster)』
https://www.youtube.com/watch?v=2qRP6hNefYg
同じくアメリカのバンドAerosmithエアロスミスの『Push Comes to Shove』は翌1982年/昭和57年に出ました。
『Push Comes to Shove』
https://www.youtube.com/watch?v=QC5GJ--F_qc
シャベル
shoveに対して、道具であることを意味する接尾辞-elをくっ付けたものがshovelシャヴル(シャベル)です。
「土・雪などをすくう長柄で幅広の刃のついた」(研究社新英和中辞典)ものを言うそうです。
動詞としても用いられます。
「shovel the snow away from the steps.
上がり段から雪をすくってのける
He shoveled the food quickly into his mouth.
彼は食べ物をがつがつと口の中へほうり込んだ」(同)
ところで、言葉の上でこんな問題が。
「日本のJISでは足をかける部分があるものをシャベル、無い物をスコップとしている。
通俗的にはシャベルとスコップの区別は様々で、西日本では大型の物を「シャベル」・小型の物を「スコップ」と呼ぶが、東日本では逆に小型の物を「シャベル」・大型の物を「スコップ」と呼ぶとされる。」
(ウィキペディア)
「スコップ」はオランダ語のschopスホップから来ているそうですが、英語shovelと、そして英語scoopスクープと関連の有る単語です。
scoop
この言葉は
「(物をすくう)大さじ,(小麦粉・砂糖などをすくう)スコップ,(アイスクリームなどをすくう)ディッシャー」
(小学館プログレッシブ英和中辞典)
などを表し、またそれに関連する動詞用法があります。
「a measuring scoop
計量スプーン
scoop (up) water
水をすくう」(同)
そしてもちろん、俗に「特ダネ」などと言う使い方の「スクープ」も。
「The newspaper got a scoop on the airplane crash.
その新聞はその飛行機墜落事故をスクープした
The New York Times scooped its rivals with an early report on the accident.
「ニューヨークタイムズ」はその事故をいち早く報道して競争紙を出し抜いた」
(研究社新英和中辞典)
shuffle
「足を引きずって歩く」が原義であると思われるこの単語。
トランプの札を切り混ぜるという意味で有名な「シャッフル」もshoveに関連する言葉です。
カードだけでなく、一般的に「混ぜる」で使われます。
「Don't shuffle the papers together.
書類をごちゃまぜにしないように」(同)
その他に、責任などを「転嫁する」という用法がある点で先程のドイツ語schiebenの共通性を感じられ、興味深いです。
「shuffle off responsibility onto others
責任を他人に転嫁する」(同)
更に音楽の世界では、タッタ・タッタ・タッタ・タッタという感じの跳ねるリズムのことも指します。
『Matteo Mancuso - Blues Shuffle in G』
https://www.youtube.com/watch?v=j8OsuhTDufw
このリズムでの演奏で有名なドラム奏者が、アメリカ人Bernard Purdieバーナード・パーディで、Steely Danスティーリー・ダンの曲『Home At Last』や『Babylon Sisters』における演奏がその典型例としてよく挙げられます。
『Home At Last』
https://www.youtube.com/watch?v=Hx5ZlTyzU-k
『Babylon Sisters』
https://www.youtube.com/watch?v=tV4UVvVFpXI
お読みいただき、ありがとうございました。ではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
