
基礎講座③/市民ミュージアムの今とこれから&社会的処方とは
5/12(日)に基礎講座3回目が行われました。
第1回、第2回基礎講座はことラーたちが集う、ことルームのある「新百合トウェンティワンホール」で行いましたが、今回は場所を移し、「麻生市民館」で行いました。ことラーは川崎市内全域で活動していくので徐々に行動範囲も広がっていきます。

今回の講座は午前・午後で2本立てとなっています。
盛りだくさんの内容ですが、どちらもことラーにとって重要なお話です。
午前中は川崎市市民ミュージアムから学芸員・谷拓馬さん、川崎市役所から担当部署である川崎市市民ミュージアム企画調整担当課長・前田憲造さん、市民文化室新たなミュージアム準備担当係長・植木雅之さんにお越しいただきました。
まずは学芸員の谷さんから川崎市市民ミュージアムのこれまでと現在についてお話いただきました。

川崎市市民ミュージアムは2019年10月の台風19号により被災し、施設及び収蔵品に多大な被害が生じました。
被災後から現在、被災した収蔵品のレスキュー活動を行い続けています。
谷さんからは被災の経緯、文化財レスキューの概要と現状、そしてなぜ文化財や美術品を後世に残すのか、なぜレスキューが必要なのかということが語られました。

話に耳を傾けることラーの表情も真剣です。

以前の川崎市市民ミュージアムについて谷さんから話があったあと、ことラー同士でミュージアムについての話をどのようにきいたのか、共有の時間を取りました。
川崎出身、在住者が多いことラーにとって川崎市市民ミュージアムは訪れた経験があったり、思い出の場所だったりします。

ことラーにも今後、収蔵品レスキューを実際に体験してもらう予定です。
収蔵品を守ることの意味をレスキュー活動を通して実感する機会にしていきたいと思います。
次に前田さん、植木さんから現在の川崎市市民ミュージアムの活動からこれから整備を予定している新たなミュージアムの展望について語られました。

新たなミュージアムの整備がこと!こと?かわさきのプロジェクトのきっかけの一つであること、そのミュージアムにことラーの活動拠点機能が備わることなども伝えられ、ことラーにとってはぐっと自分との関りの強さを感じることとなったようです。
ただ同時に新たなミュージアム完成までの道のりが簡単なものではないことも見えてきました。
これから新たなミュージアムの計画を進めるうえでことラーとも一緒に考えていきたい、ともに作っていきたいという言葉があり、市民参加で作っていきたいという職員の意気込みを感じたお話でした。
3人からの話が終わり、午前中最後にはことラーから川崎市市民ミュージアムについての質問タイムです。

今後の活動に密接に関りを持つミュージアムの話をことラーも真剣に受け取って、疑問や感想を伝えていました。
午後は一般社団法人プラスケア代表理事/川崎市立井田病院腫瘍内科部長である西智弘さんをお招きして、社会的処方についてのお話を伺いました。

「薬で人を健康にするのではなく人と地域とのつながりで人を元気にする仕組み」である社会的処方の考え方は人と地域、そして文化をつなぐことで川崎の人を元気にしていくことラーにとって重要です。
そこで社会的処方とはなんなのか、西さんの活動も含めてわかりやすい事例を絡めて熱をもって解説してもらいました。
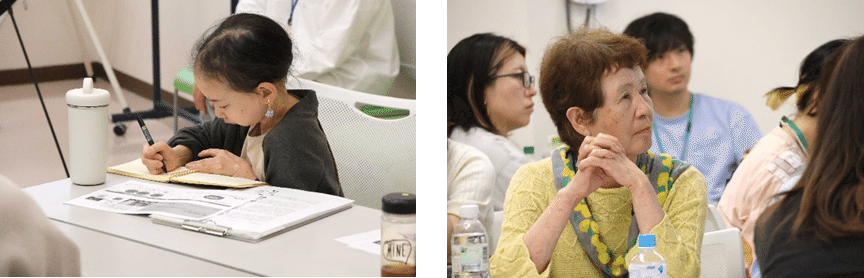
その後、ことラー自身が社会的処方とはどのようなものか考えるワークショップを行いました。
川崎市に住むとある年配の女性を想定して自分ならどんな支援を提案するか、それぞれでアイデアを出し合い、グループで話し合いを進めます。
女性のバックグラウンドやこれまでの経緯を踏まえ、先ほどの西さんからのレクチャーを取り入れつつ、ことラーそれぞれが考えを深めていきます。

最後にどんな案が出たか、班の中でどんな話ができたかを発表してもらいました。


印象的だったのがその発表を聞いた西さんから「ひとや場所の固有名詞が出るといい」ということでした。
支援の内容に「~さんに会えばいい」「~に行けばいい」といった人・場所の固有名詞が出てくることでぐっと具体性が増します。そのためには川崎市をもっと知る必要が出てきます。そういったことも今後ことラーと一緒に取り組んでいきたいと思いました。
活動する場である「川崎市」のこれから、活動する上での考え方の元となる「社会的処方」、二つを改めて考える機会となった今回。
ことラーの活動イメージがより鮮明になったのではと思います。
(こと!こと?かわさき プロジェクトマネージャー 財田翔悟)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
