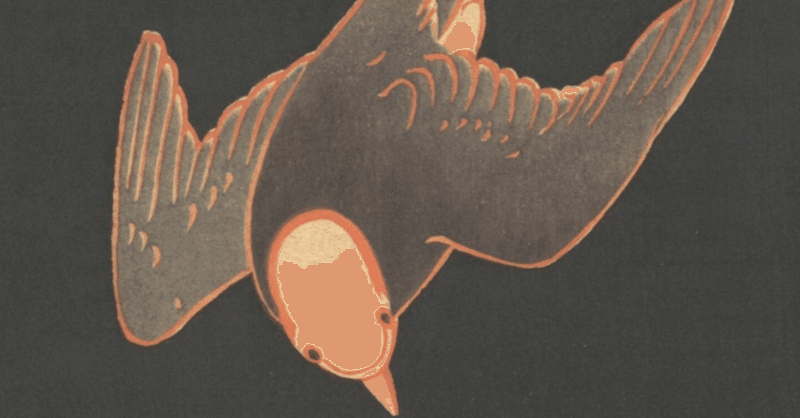
連載小説 「死神捕物帖」(5)
5
入店してから五時間がたつと、もともと多いとはいえなかった客はついにぼくと宮本だけになった。琴美は四人いたホステスを一時間ごとにひとりずつ帰らせ、最後まで残った者には看板を消して掃除を始めるよう伝えた。
琴美が有線を消すと、二人は急によそよそしくなった。目配せをし合い、ときどきぼくを見てにんまりと笑う。何事かぼくには知る由もない計画が二人の間で進行しているようだった。店内BGMが止まると、天井から響くエアコンの排水音がやけにはっきりと聞こえた。腕時計を見ると、もう外にほとんど人がいないだろう時刻を指していた。「お疲れさまです」と掃除を済ませたホステスが店を出て、しばらくすると平塚は話しはじめた。
「平塚……あのな」
宮本は複雑な表情をしていた。口元は笑みに近い形を成していたが、目には諦念の光が宿っている。「えーと……」と小さな声を発して、琴美はカウンターの横にあるバックルームへ消えていった。
ぼくは彼が知らぬ間に経済的に困窮していて、ぼくに金の無心をするつもりかもしれないと身構えた。要求する額面次第では貸すこともできるが、無理な要求なら断るしかない。しかし断ってしまったのち、ぼくと宮本の関係は変わってしまう可能性が高く、疎遠になると「その時」は遠ざかるかもしれないとぼくは懸念した。正直、今ほど宮本哲治と親密な仲が形成されている状態だと、どのタイミングで彼を殺してもぼくに幾ばくかの疑いがかかるだろう。しかし、大事なのは幾ばくの度合いなのだ。警察に対して、知らないわからない、と応じてそこにほんの少しの嘘をまぶせば事足りる程度の結末をぼくは望んでいる。その結末がどんな経緯でぼくの元へやってくるのかは、まったく想像がつかない。ぼくにできることは、極力宮本との関係を自然なままに保ち、すっと彼の命を断てるエアポケットに突入することだけなのだ。これまでに殺した人の数は十八。つまりはエアポケットは四十五年のうち、十八回しか見つからなかったということになる。これが多いのか少ないのかは比較対象がないため、ぼくにはさっぱりわからない。運良くこの数なのか、運悪くこの数なのかを誰に判断できるというのか。
「俺と……琴美の関係はお前も知ってるだろう──」
姿の見えない琴美がエアコンのスイッチを切ると急に店内は蒸し暑くなり、アルコールのすえた臭いが鼻をついた。
「──その……だな。俺たちはもう付き合って六年になるんだなあ、これが。でだな……平塚よ。お前、嫁とあっちの方はどうだ。まだお盛んか。お前は真面目だから、そうかもなあ。うん。家族サービスなんかもちゃんとしてそうだ」
ぼくは「ええ、まあ」と相槌を言い、真剣な表情を崩さずに少しうつむいた。
宮本哲治と琴美は何かを企んでいる。
きっとそれはぼく以外の誰にも言えないことなのだろう。
「そうだろうな。でもな、男と女ってのはどうもその……慣れてしまうとだな……うん。ああ。ちょっと今から変なお願いをするけど、聞いてくれるか」
エアポケット。
琴美はまたもエアコンをオンにし、上方から吹く風がぼくの汗を冷やした。
皆様からのサポートで私は「ああ、好きなことしてお金がもらえて楽しいな」と思えます。
