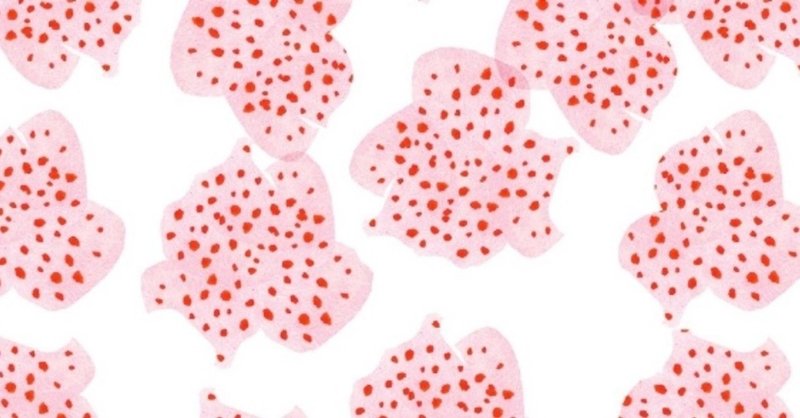
散髪
本日、散髪に行こうと思う。
「散髪かー。緊張するなー。」
いつだってそうであった。いつまでも慣れないのである。
私の意見は言えないのである。たいていはそうならないから。
私の脳と美容師の脳は違うのである。
敗北感を味わさせるには十分なぐらい、美容室は洒落っ気と眩い光を発している。
いつだって、あそこの中には、「あ、なんかいい。」と思わせる、リア充感覚満載の美容師たちがいる。
私が、自分一人で散髪にいったのは、小学生の時であった。
リーゼント風のおっちゃんが、知った顔の小僧が来たと、喜んだものだ。おっちゃんは優しいが色付きの眼鏡をかけていた。眼光鋭くハサミを持つ姿は、鏡越しに恐怖すら感じ、いぶかしげに見ていたことを覚えている。
店で待つ間には、「静かなるドン」を読む。それしか置いていないのである。
なので、純粋な小僧にとっては、おっちゃんはその世界の人にしか思えなかった。
散髪が始まると、なんだか子分になって、これから誰かを一緒に脅しにいくような、勇敢とも言い難い気持ちになった。というのもいつも、同じ髪型になるからである。
まさに静かなるドン状態で、モブ感満載の角刈り気味である。
「あにき、いつもの頼むぜ」とばかりに、その時は意気揚々となっていた。
散髪が終わって、店を出るころには、気分はまさに晴れ晴れとした気持ちのいいものと同時に少し大人になったような気分である。
だが成長するにつれ、そのダサさに気づくのである。いや、語弊とすると、全く自分には似合ってないのである。
みんな「美容室」に通っていた。
わたしはアニキの「床屋」である。
それを知った衝撃ったらありゃしない。
その時から美容室というものが、私の中では、敷居の高いものになっていた。
キラキラして、洒落で、一種の憧れであった。
それからも、床屋に行った。
「本当にこの髪型が嫌だ」と脳は判断していたが、身体は命令を聞く気配は無かった。
あの時に抵抗していたら、指が少なかったかもしれない。
大人になり美容室に行くようになったが、自分の意見など言えるはずもなく、いつも御任せとしていた。自分で何かを指定するようなどころではないのである。
わたしにとっては美容室は敷居が高いのだ。
シャバの世界はまぶしく、空気は歓びを満ちているかのように。
ただしかし、この状況を改善するには、「あ、あの、松坂桃李みたいに。」とかなんとか言って、頼むしかないのだ。
だが、近づくはずもない、むしろあれは松坂様だから似合うわけで、一緒にしたところで顔の構造が異なりすぎるので、むしろ余計にため息をつくことになるのである。
つまり、どうコミュニケーションをとれば、自分が思うようになるのかということである。
1日中、あーだこーだ指定されて、笑顔で髪の毛を切っている側からしたら、顔の疲弊により無表情どころではなく、感情も無くなってきてしまうに違いない。
そんな満身創痍なキラキラお洒落さんに、私の指向なんか、言っているわけにはいかないのだ。
自分で切ることにした。
100均でスキばさみと髪の毛用の普通のハサミの2本を買い、
要は、手首の捻りと髪の毛を落とす間にさささっと、櫛で整えスキスキッとすれば良いはずである。
美容師さんが切る様子は何度も見てきた。
見た回数では、それなりの回数なので、もはや素人と呼・ば・せ・な・い・ぞ。
である。
何だかわけのわからない無意味な自信と練習は想像だけで十分さ、と。
もう成りきっているのである。
ザクザク、チョキチョキ
チョキチョキ
。。
私は、今日「専門家」のところに行こうと思う。
お洒落なキラキラお兄さんに私の稚拙さを味わっていただくとしようか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
