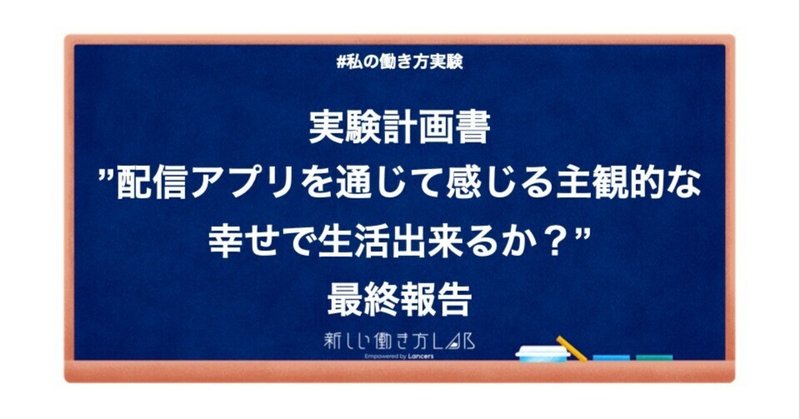
配信アプリ”を通じて感じる主観的な幸せで生活できるか? #研究報告書
◆実験の目的と背景
日々同じ人々と話していると、話題がマンネリ化し固定概念が生まれるもの。そんな状況を変えたいと思っていた時、配信アプリの存在を知り、利用始めたのが切っ掛けです。
開始直後は日々の雑談でしたが、時折会話内での笑いや一体感に小さな幸せを感じる様になり、これまでの生活により一層快適さが生まれました。
配信アプリと聞くと斜に構えるかもしれませんが、経済的な負担を掛けずに人とコミュニケーション可能なツールではないかと考え本実験を実施してみました。
◆検証したいと思っていたこと
生活の一部に配信アプリを取り入れることで、日々の主観的幸福感を得られるか? もし得られるようであれば、どのような行動から感じ取ることが出来たかを検証しました。
◆研究活動の概要
配信アプリを使用して自身の配信、他者の視聴から得られる主観的な幸せが、どこにあるのかを振り返りながらnoteで発信していきました。
ただし、過度な投げ銭は、研究目的から逸脱すると思われるので¥5000/月を上限とします。 また本テーマ幸福学(前野先生)から、実感した主観的な幸せも加味して発信したいと思いました。
自身の気付きを配信して収益化を図るサービスを検討しましたが、こちらは未達になりましたので考察を最後に提示したいと思います。
◆結論と根拠・気づき
1)論点整理のスキルが磨かれる 中間報告でも述べましたが、不特定多数の人とコミュニケーションを図ることは、それぞれの主張を理解することにあると考えます。
会社や町内会、PTAなど、複数のコミュニティーに属した場合、各コミュニテーの雰囲気が異なる状況下で、この論点整理のスキル向上は今後の実生活においても有益であると感じました。
2)共感で幸せを感じられる 論点整理できた上で、同じ共通言語で共感を図るのは非常に幸せを感じました。
これは、お互いに秘密を共有した喜びに近いかもしれません。 また共感で得られた”幸せ”。これは幸福学4因子の1つである”ありがとう因子”に該当し、一番重要ではないかと感じました。
なぜなら他3因子(”なんとかなる”、”やってみる”、”自分らしく”)が、自身で感じる幸せ因子に対して、”ありがとう”因子のみ他者が必要だからです。
このように人との幸せを要素で気付けた点は新たな発見であり、人付き合いが苦手てな私にとって、率先して話しかけるようになったのは最大の成果です。
◆研究に関する考察・これから
自身の未来を考えたとき、SDGsなコミュニティーに属していくだろうと自覚しています。その時、物理的に移動が必要なコミュニテイーに属して、論点整理および意思統一のスキルを磨くことも可能ですが、より簡易的にこのスキルアップを図れるのが配信アプリの利点だとと考えます。
一方で配信アプリが、すべてを克服する万能ツールではないことも主張したいです。論点整理ができても、言語の共通化が図れない場合もあるし、そもそも本音を引出せない場合も想定されるからです。
このような場面では、発言を鵜吞みにしない別のスキルが必要になると考えます(これは本当に大変なスキルで今後も取り組んでいきたいです。。。) 上記のような課題を理解しつつ、私は配信アプリを使用することで主観的な幸せを得ることが可能でした。
また、配信アプリ以外でも幸せを感じる事が発見できたので、今後は各要素を整理して配信する体制を構築したいと考えます。
研究期間中、収益化にココロが傾かなかったのは、自分自身を幸せにする要素を上手く説明出来なかったためです。そのため、感覚を文章で表現するスキルはこれからも学び続けます。
◆全体振り返り
現在の私の職種では男性社員多数の環境に対して、研究員の方には女性が多く、より女性からの視点を考えるいい機会になりました。
加えて結論でも触れた共感するスキルは、女性とのコミュニケーションをより円滑にするのではないかという仮説が生まれました。これは、今後の研究テーマとして検討したいと思います。
最後に幸せを考える上で何が幸せを感じるかは、意識レベルを上げないと過ぎ去ってしまい気が付かない事だと改めて感じました。
つまり、自分自身が感じる小さな違和感や波動を感知する取り組みは、瞑想などのヨガ行為に繋がることも自覚出来ました。
趣味で続けていたヨガと本研究を通じて知り得た幸福学との遭遇を一つのマイルストーンとして研究報告書と致します。
素敵な半年間をありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
