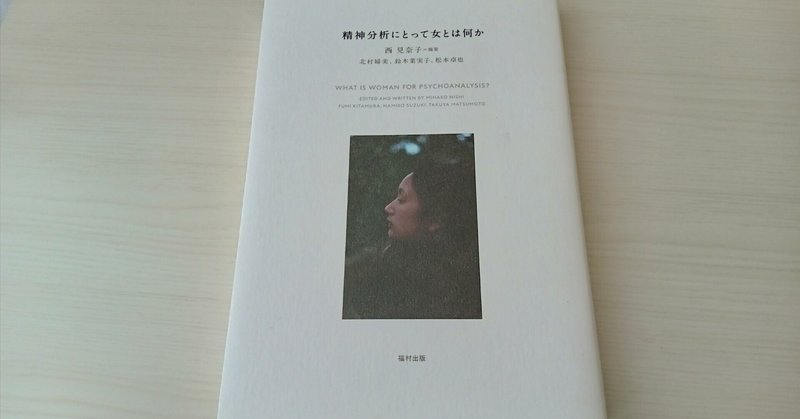
感想『精神分析にとって女とは何か』
西見奈子(編著)・北村婦美・鈴木奈実子・松本卓也 2020 福村出版
タイトルを見た時から、この本は読まねばならぬと思ってすぐに手に入れ、部屋に積み続けていた。
読み終えて2週間ほどが経ったが、私が感想を述べるには歯が立ちそうにない。
四人の著者がそれぞれ別に書いているので、別々に感想を書くほうが、まだたやすい気がする。
1.北村婦美「精神分析とフェミニズム:その対立と融合の歴史」
まず、この第一章だけでも、非常に読みごたえがある。
今よりももっともっと若い時の私は、フロイトが女性について論じている箇所を毛嫌いしていた。
ペニスを持たないことを引け目にも思わないし、ペニスに憧れもしないのに、決めつけられているようで、非常に嫌な気持ちになる。
そういう違和感をすくいあげるところから始まっている論であり、フロイト自身の変化と精神分析自体の変化を概観できるように描く。
そして、まさかここで、私はキャロル・ギリガンが出てくるとは思っておらず、とても興奮した。
ジェンダーの話になると男性と女性に固有のものとしてふりわけられがちなのであるが、「ここで誤解してならないのは、ギリガンが決してこれら二つの倫理原則(正義の倫理と配慮の倫理のこと)を『男性』『女性』というジェンダーの違いに由来するものだとは言っていない」(p.23)ことをきちんと指摘してあることに、嬉しくてたまらなくなった。
地域ごと、時代ごとの変遷を踏まえたうえで、もともと、フロイトの中に男根一元主義だけには収まりきらない両性性を含んでいたことが取り上げられる。
そこから、現代的な多性性、多重性を精神分析が養ってきた手法を通じて関わりうる隘路を見出す刺激的な論だった。
2.鈴木菜実子「精神分析的臨床実践と女性性」
「現実の生活でポジティブな出来事が患者に生じること自体は否定しないが、あまりに短絡的に結婚や出産が治療的達成のしるしとされる雰囲気があることに戸惑いを覚える」(p.62)ところから始まる。
そこからジェンダーと身体との関わりに進み、たとえばヒステリーや摂食障害、性的外傷といった疾患ごとになにが起きているかを概観する。
更に留まらず、生殖補助医療や閉経、LGBTQといった現代的な事情や、セラピストが女性であるとことが男性、女性の患者それぞれにどのような影響を与えるかまで、考察を加えていく。
女性が精神分析的臨床実践を行うに当たり、1度は考えておくべき事柄を網羅している点で、これもまた読んでよかった。
3.西見奈子「日本の精神分析における女性」
1番、苦労を感じた論文である。それは、筆者自身が「はじめに」で書いていることである。
当初、日本精神分析学会の学術雑誌『精神分析研究』における1954年から2018年までに掲載された事例論文を対象として、女性性がどのように語られてきたかという問題を取り上げていた。約60年分のすべての事例論文に目を通すには数ヶ月を要し、なかなか苦労した部分であった。しかし、教育研修セミナーやその後の議論を通して、そうしたものが単なる日本の精神分析を構築してきた世代への批判や日本の精神分析自体への中傷へと落ちってしまう危険があることを知った。そこで、代わりに精神分析における女性の問題を考える際に必要だと思われる視点について論じることとした。
とある。この文を読んで、それでももともとの60年分の事例研究から洗いされたものを知りたいと思わずにいられなかった。筆者の苦労や苦悩が忍ばれた。
しかし、筆者は、そこであきらめるのではなく、日本における女性論の独特な受け入れ方を経て、日本の女性論の独特さを示す「事例」として阿闍世コンプレックスを取り上げる。
阿闍世コンプレックスにも複数パターンがあり、変遷があることは、この本を読んで、私は初めて知った。どれが正しいかを知ろうとすることの無意味さは、レヴィ=ストロースの言う通りであると思うので、その変遷と変遷しない要素に注目すると、面白いことがわかってくる。
それは、あたかも観音菩薩であるかのような「自我を捨てて子や夫のために尽くし、苦しみにたえ、子の支えとなり、限りなく許すことによって最後のよりどころとなる母親」のイメージ(p.163)を思い描き、そのような理想的な母性を男性である治療者たちが体現しようとした。しかし、そうすることで、父親不在のまま、三者関係に至ることがない、母子一体化の幻想が理想化されて、心的成長が疎外されはしなかっただろうか。
また、その理想的な母性は女性性とイコールではない。女性すべてが母親になるわけではなく、母親すべてが自己犠牲的にあらねばならないとすることが、多くの母親となった女性たちがある時、ウロボロスのように荒れ狂わざるを得なくしているように思わずにいられない。
時代背景を考えた時、n=1の話でしかないが、自分の父親や祖母たちのことを考える。
戦争で男性不在の状況ができた時、母親は多忙で、80代の父親はネグレクトのなかで育った。親戚に預けられ、邪魔にならないように過ごしたという。左右を教えてもらえず、時計の読み方も知らなかったので、学校にはだいたいの感覚で登校していたらしい。
父親の母親は、武家の出のお嬢さんで、高学歴であり、辞書の編纂などで働いて収入を得ていた。家事は不得意だったというし、祖父とは妻妾同居であったとも聞く。妾である女中さんが家事をしていたとも。
母方はそこまで極端ではないが、祖母はやはり地主のお嬢さんで、家事は女中がやるものだったらしい。戦争で土地を失い、大家族を養うために着物を売払い、なんとか家事をしていたらしい。
そのような戦後直後の私に連なる二つの過程を思い浮かべると、家事や育児をしない家庭で育って女性達にとって、上記の観音菩薩のような理想の女性像は、求められれば求められるほど、苦しい呪いになったのではないかと想像したりする。
日本に精神分析の文化を打ち立てていった先人たちがどういう家庭に育ったかまでは知らないが、彼らにとって、観音菩薩のような母親が当たり前だったからそれを目指したのか、それとも、観音菩薩のいない家庭に育ったから幻想の母親との一体化を希求する子どもの心を満たすかのように、自分自身が理想の母親としたのだろうか。
様々なことが思い浮かぶ章だった。
日本は2023年になった現在でも、母子一体化した幻想を至上のものとして掲げがちであるように思う。
理想が少しでも裏切られたと感じると、破滅的、破壊的な行動を即座に取りやすいところは、幼稚な万能感の世界に生きていることを示しているように思うのだ。
その理想の構築に、精神分析はいくらかは加担してきてしまったことが、阿闍世コンプレックスの変遷から推察される。
そこから、次はどのように成熟へ、成長へ、踏み出していくか。そのことが、大事なのではないだろうか。
4.松本卓也「補章:ラカン派における女性論」
ラカン派の話なると、私はとてもついていけなくなるのだ。なんでわざわざ記号にしないと気がすまないんだろう、と表面的なところでつまずいてしまい、流し読みに近くなってしまった。十分に理解できたとは、とても言えない。
ただ、これはラカンの言葉からの引用ではなく、バトラーの言葉になるのだけれども、「女というカテゴリーの一貫性や統一性に固執すれば、具体的な種々の『女たち』が構築される際の文化的、社会的、政治的な交錯の多様性を、結果的に無視してしまうことになる」という指摘は、重要な意味を持つ。
「女性」というカテゴリーがけっして全体化されえないという意味を、私はもう少し噛み締めていたいと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
