
第7回ケア塾茶山 『星の王子さま』を読む(2018年3月14日)
※使用しているテキストは以下の通り。なお本文中に引用されたテキスト、イラストも本書に依る。
アントワーヌ・ド・サン=グジュペリ(稲垣直樹訳)『星の王子さま』(平凡社ライブラリー、2006年)
※進行役:西川勝(臨床哲学プレイヤー)
※企画:長見有人(ココペリ121代表)
はじめに
西川:
進行役の西川です。よろしくお願いします。今日は初めての方が結構いるそうで。どんなことからしゃべっていこうかな。
『星の王子さま』は多くの人が読んでる本やと思うんです。僕も子どもの頃読みました。いつ頃から気になりだしたのかなあ。ちょっとはっきり思い出せませんね。
2014年に大阪の「ケア塾たまてばこ」で、はじめてこの本の読書会を僕が進行役になってやりました。その時は13回かけてこの一冊を読みましたね。その後、大阪大学で授業で取り上げたり、非常勤で行ってた大谷大学でも1学期かけて読んだりしました。あと舞鶴の特別養護老人ホームで読みましたね。何回も繰り返して読んでます。
僕は別にフランス文学とか全然詳しくない。フランス語も読めないので、翻訳を読むしかないわけです。でも何て言うかな、毎回読むたびに、いろんなことを考えさせられる本です。
もう解説書の類は山ほど読みましたから、今たぶん家に60冊ぐらいあるんじゃないでしょうか。『星の王子さま』関連やサン=テグジュペリ関連ですね。8割方は目を通してます。
いろんな人がいろんなことを書いてますが、みんなあんまり大したことない。もちろん、ぴかっと光るようなことを書いている人もいるんですけど。
まあ、おそらくどんな学者の方でも、一人で読みきるっていうのはたぶん無理ですね。『星の王子さま』について書いている人のなかには立派な人もたくさんいます。それこそ何十年も研究してる人もいるんです。でもやっぱり、この本は一人では読みきれない内容を持っている。
ぼく自身は「ケア塾たまてばこ」で師匠の鷲田先生の本の読書会はもう10年近くやっていますが、そうでない著者の読書会は、貝原益軒の『養生訓』[*1]とサン=テグジュペリのこの『星の王子さま』だけなんですね。
でも、いろんな人の意見聞いていく中で、全然自分が思いもしなかったようなこととかがちょっと分かりかけたりします。分かってたと思っていたことが「いや、自分の理解だけではないなあ」と思ったり。いろいろ気付くことが多いです。
だからここ、ケア塾茶山でもできるだけみなさんのいろんな話を聞けたらなあと思ってます。まず僕が本文を音読して、その時に思いついたこととか、いろいろ本読んでて知ったことなんかをみなさんにお伝えしたり、っていうかたちで進めています。
非常にゆっくりしたペースでやってますので、この調子でやると1年では絶対終わらないなあって感じです。今回でもう7回目。「ケア塾たまてばこ」だったらもう108ページまで進んでることになりますね。いやあ、まだ全然ですね。なんせ今日は37ページからですから。
[*1] 貝原益軒、『養生訓』:かいばら えきけん。1630-1714、江戸時代の本草学者、儒学者。『養生訓』は益軒83歳の著作で、身体や精神の養生(健康、健康法)についての指南書。現代でも多くの出版社から原文付き現代語訳や口語訳、解説書などが出版されている。
『リトルプリンス・トリック』
最近ちょっと読んだ本に『リトルプリンス・トリック』[*2]っていうのがあります。著者の名前忘れたな。女の人が書いてるんです。フランスのえらいきれいなアナウンサーかなんかやってる人。「トンデモ本かなあ?」みたいな感じですけど、面白くて全部読んでしまいました。
[*2] 『リトルプリンス・トリック』:滝川美緒子、滝川クリステル著、講談社、2015年出版。
いつも僕いっているけど、『星の王子さま』はサン=テグジュペリが絵も描いてるんです。この本はある意味では絵本なんです。絵本ていうのは通常は物語を書く人が先にいて、というか物語が先にあって、それに絵をつける。挿絵というぐらいで、そういう体裁のものが多いんです。
でも『星の王子さま』は若干違うんですよね。もちろん同一の人物がやってるわけですから、まるで別々のこと考えてるわけじゃないです。サン=テグジュペリという人は、癖のように、暇があったらレストランの紙ナプキンであろうと何であろうと、彼はいつも紙切れをポケットの中にいっぱい入れてて、思いついたことなんかすっと書いて、またポケットに入れるっていうようなことをやってたんです。
なんか人と話してる時も手持ち無沙汰になると紙になんかいろいろ落書きしている。その落書きに、この『星の王子さま』の原型になるような、少年の絵がしょっちゅう描いてあったわけです。
それを見た、出版社の人が、サン=テグジュペリに「その子どもを主人公にした子ども向けの本、書きませんか?」みたいなことでいったところから始まったっていうのが『星の王子さま』誕生の定説なんです。
彼はそれまで小説は書いてるんです。小説と、それからノンフィクションみたいなエッセイは書いてました。それで、ものすごく、もう文学的に非常に有名になった人なんですけど、子ども向けの本なんていうのはもうこれ一冊しかないんです。おまけに絵まで描くっていう。しかも、絵についても、ものすごく、もう文章よりもひょっとしたら力を入れたかもしれないっていうぐらいやった。
文章書くより絵を描くほうが絶対時間かかりますからね。まあ文章も、彼はものすごく推敲に推敲を重ねてるっていう話も最初の頃にしました。そして、この絵についてもしっかり見なきゃいけないっていう話もしましたね。
この『リトルプリンス・トリック』っていうやつは、この絵について、ものすごくしつこくしつこく、虫眼鏡で見るようにして、やるんですよ。「どこまでどうかなあ」っていう気はするんけですど。
たとえばこれ、最初のページあるでしょ?この最初のページの、星の王子さまはここで蝶ネクタイみたいのをしていますよね。見開きになった場合はマフラーというか、こういうのやってますね。違うわけです。そして、着けてないときもある。最後倒れる時は、マフラーはないんですよ。マフラーだけがないんですよ。何もない。


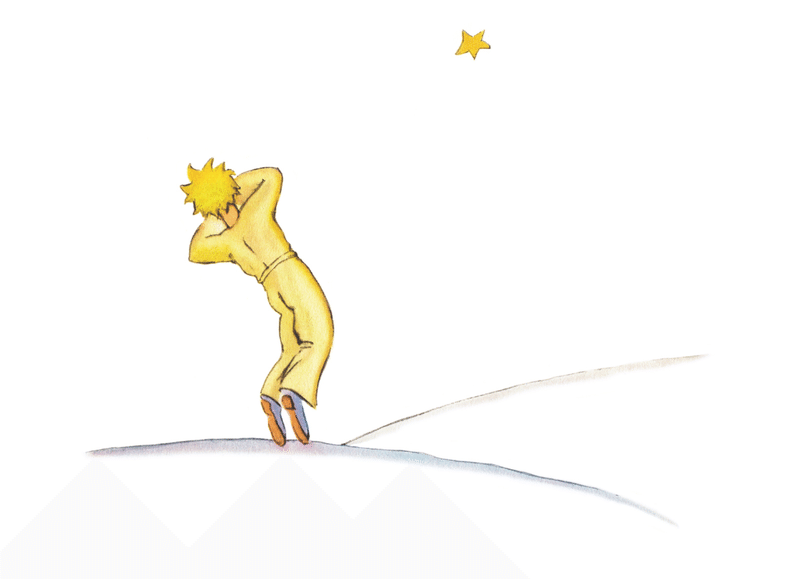
サン=テグジュペリって、ものすごく慎重に、こう計算しつくして文章でも書く人で、やっぱ無駄なことほとんど書いてないんですよ。要ることしか書いてない。だから書かなかったからには書かない理由があるんですよ。
となると、この蝶ネクタイも、蝶ネクタイの理由があるはずなんです。で、その理由が何なのかっていうことを、まあその『リトルプリンス・トリック』っていう本ではいろいろ書いてるんです。
一度読んだら「へぇー」ってな本なんで、ここで中身についてあんまり言いませんが、たとえば、蝶ネクタイをぐーっと大きくすると、何かに似てるっていうわけです。で、もっと大きくしなきゃ分からないんですけど、オリオン座に似てるって言うんですね。

それとか、前回やったこの最初の絵。これボアってなってますけど、なんか蛇って言われたら蛇かなあと思うわけです。これがウミヘビっていうか、ウミヘビ座の絵にそっくりだと。昔は星座絵っていうのがあって絵がいっぱい書かれてあったわけです。そのウミヘビ座の絵にそっくりなんですよ。だからこれはウミヘビ座のことだ、みたいなかたちで、片っ端から絵の中にいろんな星座に関わるようなサインを見つけ出すっていうことをその本では一生懸命やってます。


↑うみへび座の星座絵↑
この王子のこのマフラーのたなびき方も意味があるってなってる。こっちに向いてる、あっちに向いてるっていうのもいろんな理屈をつけてやってるんです。面白いですよ。
この本の中にサン=テグジュペリが星座をすべて組み込んでるっていう話と、だからこの『星の王子さま』は何かを表しているっていう謎解きの本なんです。天文学の知識がないと、正しいのかどうかはよく分かりませんけど。
あと、こう絵の見方については、もうほんとに丁寧にやってて、「なるほどなあー」と思いながら読んでました。ただ、こう拡大して拡大してもよく分からないくらいのところをじーっと見たりするわけです。
たとえばこの有名な絵ありますけど、これの、そのカフスのところ、カフスというかこの折れ曲がってるところの左のほうにこうボタンみたいなんがあるでしょ? このボタンは何を意味するかとかね。なんかそんなことをいろいろ書いてる変わった本がありました。

まあ何て言うのかな、そう一度説明されちゃうと、「ああ、そう」と思って、それ以上次が出てこなくなる。たとえば「それ帽子じゃないよ」「ゾウを飲み込んだボアだよ」って、これ中身見せられたら、次からこれ見ても、これゾウ飲み込んだボアにしか見えなくなっちゃうんですよ。
説明されると、だからこの解釈が他にもうなくなってしまうんですね。だから簡単に人の解説に乗っかるっていうのもどうかなあという気がしますけど、まあまあ、いろんな本読んでるうちに、「いろんな解釈する人がいてんねんなあ」ってきますね。
たとえばこの、これね、飲み込まれてるこれ、この動物。この動物は何なんでしょうか?とかね。これもフランス語のこう諺とか、そういうのを使いながら、「これは実は狼や」みたいな解釈出してきてる人もいます。この尾が長いのが狼の理由らしいですけど。

あとちょっと顔を見てください。変でしょ?何となく。鼻が変だと思いません?当時こうユダヤ人を揶揄するときに「ユダヤ人の鼻はこんなんや」みたいなそんな話がたくさんあるらしい。ということは、これユダヤ人が呑み込まれる図、みたいなものを、こう分かる人には分かるみたいなね。
そんな本もありました。それがどうなんだ、っていうのは、もうちょっとまた考えたいですけど。というか、いろんな絵を見て、注意深く見て、何かメッセージがあるかもしれないというのは、今日の話のところでもありますね。じっくり見ていけば面白いかなあと思います。
まあいろんなこと調べる人がいるんですよ。ちょっと、もうすんだところはあんまり詳しくやりませんけど、ちょっとだけしゃべりますか。これ24ページですけど、『ぼくは王子さまの故郷の星が、小惑星B612だとにらんでいるのですが、それにはちゃんとした理由があります』云々かんぬん、ていうとこあるじゃないですか。
この「612」ていう数字。これについて、三野(みの)さん[*3]ていう奈良女子大の、もう定年退官された人が書いてましたね。この「612」っていうのはね、サン=テグジュペリのデビュー作である『南方郵便機』[*4]っていう小説あるんですけど、その主人公のベルニスの飛行機が612号機なんですよ。
[*3] 三野さん:三野博司(みの ひろし)。1949年京都府生まれ。フランス文学者、奈良女子大学名誉教授、放送大学奈良学習センター所長。アルベール・カミュが専門で、いくつかの『星の王子さま』についての著書がある。
[*4] 『南方郵便機』:“Courrier Sud” サン=テグジュペリ著、1929年出版(日本語訳:、①堀口大學訳、新潮文庫、初版1956年、2012年に再改版 ※『夜間飛行』に収録、②『サン=テグジュペリコレクション1 南方郵便機』、山崎庸一郎訳、みすず書房、2000年出版、など)。
『星の王子さま』はレオン・ヴェルトに捧げられてる本です。サン=テグジュペリは、アメリカで出版されたばかりのまだ仮刷りの『星の王子さま』を一冊(まだ市販される前です)だけ持って、それをずっと持って、結局、偵察飛行に行って帰らぬ人になりました。
出撃する前に友人に「『星の王子さま』は自分の遺書や」みたいなことを言ってたらしいです。だから、彼をよく知ってる人には分かるようなメッセージがもうあちこちに散りばめられてある。そういう読み方もできるんですね。
それで、さっきの「天文学の知識がないとなかなか読めない」という読み方ですけど、あれもあながちはずれてはないかもしれません。でも、こんなファンタスティックな本書いてる人だから「そんなあ」と思うかもしれませんけど、彼、飛行機乗りですから、ものすごく天体についても詳しいんです。
それに、実は数学も大好きで、高等数学の難問をクイズのように解くのが趣味だったみたいです。それに、いろんな機械なんかも発明してて特許とったりしてる。どちらかというと、もう理系バリバリの人なんですね。だから数学やとか天文学の予測とか、そういうことが入れられててもおかしくはないわけです。
そういう関係の本を何冊か読んでて、「へえ、そんなふうに読む見方もあるねんなあ」みたいな感じですね。僕はそういうことはなかなかできませんが、さらっと読んだだけでは分からないことを、やっぱりじっくりと考えていくっていうスタイルは続けていきたいと思います。うん。
全部で48枚の挿絵が、挿絵っていうか絵があるんですけど、これを一つ一つ、一つ一つ、じっくりと見て、そこに何があるのかを理解しようと思ってもねぇ。
『リトルプリンス・トリック』を書いた人はお父さんがフランス人で、ちょっと分からないことがあったらネイティブのお父さんに「原文のところを読んでどんなことを思い出す?」とか、「こういう諺があるけどどう言う意味?」とかって聞きながらやってる。
日本の文化しか知らない自分たちにとってはですね、ちょっと追いつけないとこがいっぱいありますね。でもまあ、絵をじっくり見るという点では、「ああ、これほどこう見るとなんか違うんやな」ということが分かりましたね。
『星の王子さま』の挿絵とは
じゃあ今日は次のところを読もうと思います。いいですかね?初めての人がいるけど、もう今までのとこはすっ飛ばしてしまいますね。はい、バオバブの次のところからいきます。
ああ、王子さま、こんなふうにして、ぼくは少しずつ君の、ささやかで、もの悲しい暮らしぶりが分かってきたのです。君には長いあいだ、日の入りの穏やかなありさまだけが心の慰めでした。そのことを僕は四日目の朝初めて知りました。君がこんなふうに言ってくれたおかげです。
「ぼくは日の入りが好きなんだ。日が沈むのを見に行こうよ……」
「だけど、まだそんな時間じゃない……」
「なにの時間じゃないんだって?」
「日が沈む時間じゃないよ」
初め君はとても驚いた顔をしましたが、すぐに自分で自分のことを笑いながら、こんなふうにぼくに言いました。
「ああ、ぼくはまだ自分の星にいるつもりなんだね」
なるほど、そうです。アメリカでお昼の十二時だと、フランスでは日の入りの時刻です。だれだって、そんなことぐらいは百も承知です。たったの一分でフランスに移動できれば、それだけで、その日の入りは見られるわけです。ただ、残念なことに、フランスははるか遠くにありますから、それが無理なのです。けれども、君の惑星は小さいので、二、三歩自分の椅子を動かしさえすればよいのでした。自分が見たいと思うときにはいつだって、君は夕日を見ていたのです……。
「ある日なんか、ぼくは一日に四十四回も日が沈むのを見たよ」
そして、しばらくして、君は言葉をつぎました。
「ねえ、分かる?……心がほんとうに悲しいとき、人はだれだって夕日が見たくなるものなんだよ……」
「ということは、四十四回も日の入りを見た日は、君はそんなにも悲しくて悲しくてしようがなかったんだね?」
ぼくがきいても、王子さまはなにも答えてくれませんでした。

絵がありますね。もうちょい、絵のことをしつこく言うことにしますね。『星の王子さま』は1942年から書き始めて43年の4月に出版されています。アメリカでまず英語版が出版されて、それからフランス語版が出ています。当時、サン=テグジュペリは、挿絵の場所、サイズについて細かく指示を出してます。場所っていうのは文字との関係です。文章のどこに入れるか、すぐ横に入れるのかとか、後から入れるのかとか。とにかくめちゃくちゃ細かい指示出してるんです。
彼は、指示を守らない編集者に対して、ものすごい怒りの手紙を書いてたりしてます。「絶対許さん!」みたいな感じで。だから、普通の絵本みたいに『星の王子さま』の絵の場合はいつも説明的に配置されているわけじゃないんです。ちょっと離れたところに絵があったりとかする。
たぶんこの平凡社の稲垣さん翻訳版でも――日本語とフランス語でそもそもテキストの量が違いますから――、確実に一緒にすることはできない。
どれが一番サン=テグジュペリの意図に即したものなのかっていうのは、まだはっきり分かっていないみたいです。初版本を見ないと分からない。少なくともサン=テグジュペリは初版本――ゲラというかとりあえず出荷版として、著者だけにまず最初に市販される本――を一冊渡されてますから、それを見て文句言ってるたわけです。「俺の指示と違う」と。
だから、それが言ってみたら一番、サン=テグジュペリの指示に近いんでしょう。今いろんなそのサン=テグジュペリの『星の王子さま』の本が出ています。2005年に日本での翻訳権・独占権が切れてから、いろいろと十何種類ぐらい。でもまあ、絵の場所なんかバラバラ、デタラメです。
みんな絵なんてやっぱどうでもいいと思ってるわけです。サン=テグジュペリ自身は、絶対にその絵と文章との関係っていうのをすごい大事にしている。ものすごく大事なんです。この物語は絵から生まれたと言ってもいいぐらい、絵に力を入れていたわけです。
だから、『星の王子さま』を読むときに、絵をどれぐらい読み解けるかっていうのは、ものすごく大きなテーマになるんじゃないかなと僕は最近すごく思ってます。絵は言葉に比べて文化を超えていく力がありますから、そこらへんはね、じっくり読めると面白いかなと思いますね。
サン=テグジュペリは、どの絵がカラーで、どの絵がモノクロでっていうのも指示してる。だから、モノクロの絵とカラーの絵はどう違うのかっていうことも、やっぱり考えないといけない。でも、ヒントになるようなことを何一つサン=テグジュペリは残してません。星の王子さまと一緒ですね。何を聞いても答えてくれない。一切答えてくれない。王子は質問はするけど、パイロットの質問には絶対答えない人なんです。
ま、質問して、誰かに答えてもらった答えっていうのを知る時、それが本当の自分の知恵になるのかどうかっていうことですね。本当に自分が考えて自分の中で気付いた事柄しかやっぱり自分の知恵にはならないんだっていう。そういう思想がはっきりとこの『星の王子さま』の中にはずっとメッセージとしてあります。
今の僕がやってるように、多くの文学研究者だとか『星の王子さま』の本を書くような人は、一次文献、二次文献、山ほど本読んで書くわけです(中には全然読まないでと書いてるなと思うようなやつもいますけど)。
でも読んでないからオリジナリティのあるものが書けるかっていうとそうでもなくてね。たいてい誰かが考えたことなんです。自分が思いつくようなことは誰かがもっと丁寧に考えてるんです。
そういう意味で、先行研究と言われるような、今までいろんな人が『星の王子さま』についてどんなことを言ってたのかっていうのを読むのも、それはそれで一つ誠実な方法だとは思います。
王子の星の「日の入り」とは?
とはいえ、まあいかんせん、たくさん本読むと、それだけで自分が賢くなったような気になるわけですよ。でも人の意見なんです。自分が考えたことじゃないし、自分が気付いたことじゃないんです。だから蝶ネクタイがオリオン座に似てるとして、そう思った人はそれから『星の王子さま』を読み解いていったわけだから、それなりに努力してる。
でも僕は「これオリオン座に似てる」とか、「星の王子のマフラーの秘密は実はこうなんじゃないか」、「こんなこと言ってる人がいます」って聞いてるだけです。自分が気付いたわけでも何でもない。だからこういう知識は少なくとも僕のものではない。それを書いた人、それを見つけた人のものではあるけれども、僕のものではないんですよね。
そういう権威とかじゃなくって、自分の中で何を見つけるか。だからここの輪読会の中でも、輪読会っていうか読書会でも、僕の言ったことも聞いてもらったらいいですけれど、まずは自分がこれをどう感じるのか、どう思うのかっていうところをですね、丁寧にしてください。
僕が言うのは「分かってるつもりでしょ?こんなん別になんてことはないと思ってるでしょ?いやそんなことないです。ここに秘密があるはずですよ」とか「あるはずですよ」、までのことです。それ以上のことはなかなか言いません。そこらへんね、丁寧に自分で見ていくっていうのが大事かなあと思います。
あともう一個だけ言ってみますけど、今日ちょっとこれ(『星の王子さまとサン=テグジュペリ』河出書房新社、2013年)読んでたんです。昔一度読んだと思うけど、大した本じゃないと思ってほったらかしてたんです。
河出書房新社って、いろんな人に書かせるんですよ。僕も『尾崎放哉 つぶやきが詩になるとき』[*5]に尾崎放哉のことちょっと書きましたけど、まあそういうタイプの、一人の著者がものすごく努力するんじゃなくて、編集者がいろんなやつにいろんなこと書かせて一冊の本にするという、まあお手軽といえばお手軽、まあ雑誌めいた本を作るわけです。この本もそういう本ですけど、結構面白いことが書いてありました。
僕が知ってる有名な人は、別にあんまり大したこと書いてないですね。ていうか、もう知ってるからね。加賀乙彦[*6]っていう小説家がいるんですけど、「ああ、加賀乙彦が言いそうなことやなあ」とか、「森本哲郎[*7]、ああ、あの人が言いそうなことやな」みたいな感じですけど。
面白かったのは僕が全然知らんかった人です。みなさん知ってるかもしれませんね。なんか若い人に人気あるって言ってたから。ちょっと待ってくださいよ。「石井ゆかり[*8]。ライター、星占いやエッセイなどを執筆。独特の文体で老若男女を問わず人気を集める。2010年刊行の『12星座シリーズ』WAVE出版、は120万部を超えるベストセラーとなった」ってありますね。知ってますか?知ってる?あ、すごい。この人がね、面白いこと書いてるんですよ。どんな人ですか? 石井ゆかりさんて。
[*5] 『尾崎放哉 つぶやきが詩になるとき』:河出書房新社編集部、河出書房新社、2016年出版
[*6] 加賀乙彦:かが おとひこ。1929年、東京生まれ。小説家、医学者(犯罪心理学)、精神科医。本名は小木貞孝(こぎ さだたか)。
[*7] 森本哲郎:もりもと てつろう。1925-2014、東京生まれ、評論家。日本の文明批評の第一人者として知られた。東京新聞記者、朝日新聞記者、フリーの批評家、情報番組のキャスター、大学教授、再びフリーと転身している。
[*8] 石井ゆかり:いしい ゆかり。ライター。Webや雑誌などで星占いの記事、日記やコラムなどを執筆している。
A:占い界隈では有名な人です。
西川:
へえー、そうなんだ。この人はサン=テグジュペリと同じ誕生日らしいです。一番最後に「サン=テグジュペリは六月二十九日生まれだが、実は私も同じ誕生日である。ゆえに、私はひそかに、彼と特別な結びつきを感じている」って書いてあります。そらそうですね。
「占星術の言い方で言うならば、私たちは『同じ太陽のもとに生まれた』。サン=テグジュペリもまた、私にとっては『私の星』だ」みたいな文章になってるんです。この人がね、面白いこと書いてあるんですよ。今日のところともちょっと関係のある。
星が小さいため、王子さまは椅子をずらしながら日に何度も「夕陽が沈むの」を見る。でも、それはおそらく、地球で見るような「夕陽」ではあるまい。
実際、私たちも王子さまと同じく、「星」の表面に立っていて、宇宙にずぼと頭をむきだしにして立っている。
しかし、それを五感で「感覚する」ことは難しい。
私たちはしっかりした重力にささえられ、分厚い大気に覆われ、大気中に拡散した光に包まれて生きている。
光が消えても、そこに現れるのは「宇宙の闇」ではなく、あくまで地球の上のものである「夜」だ。
地球上では「昼」と「夜」を感じることはできるが、「宇宙空間にむきだしに突き出ている自分」を感じることは、不可能だ。
これは、王子さまが見ている景色とは、完全に違う。王子さまは宇宙空間にむきだしになって、星と宇宙の、数学的な境界線上で生きているのだ。
そこは、ひんやりして、雲もなく、空の彼方までが見えるのだ。
昼でも星が見えるし、夜も闇ではないのだ。
「宙」で、それが光によって別のものに変わるということはないのだ。
「宙」は「そら」って読みます。こんなこと言う人珍しいなあと思いました。たとえばこれ(『星の王子さまとサン=テグジュペリ』の表紙)。サン=テグジュペリの、王子が星を出て行った時の絵を元にして、デフォルメしてるんです。青空にしてる。
石井ゆかりさんは「こんなわけはない」と言ってるわけです。空は真っ暗で闇だって言ってるわけです。月面の写真を、今日ちょっと調べてたんですけど、アポロ11号とか行ってるじゃないですか。
あれ、太陽の光が当たってる時は月の表面は明るいけど、すぐ真っ暗になります。真っ暗です。だって大気がないから。大気がないから、太陽の光が拡散することないわけです。地面にぶつかるだけなんですよ。地面が反射するだけなんです。
でも私たちは、地球っていう水と空気とが循環している膜に覆われた星に生きてるわけです。雲の上まで頭伸びてないからね。だから昼と夜とは違う。でも昼も夜も地球の上にしかない。
この人は占星術者だから、そういうふうなところが気になったのかもしれませんけど、そうやって考えてみると、この、四十四回日が入るのを見るのが好きだっていうときの光景っていうのは、いったいどんなものなんでしょうか?考えてみても面白いかもしれません。
白く書いてありますけれども、星が見えるということは、僕らで言うところの、夜空とおんなじなわけでしょ? 真っ黒なわけですよ。真っ黒だから星が見えるんですよ。本当は、ね。暗黒の宇宙空間の中にちっちゃな星があって、そこにただ一人立ってる。そして自分を包んでくれる大気も何もない。
星巡りをしていろいろ行きますけども、その人たちもすべてそうです。小惑星に住んでいる人たちはみんなたった一人で宇宙空間にぽつんぽつんとある小惑星に、剥き出しのかたちで宇宙に頭を突っ込んでいるようなかたちでいる。
王子さまはすごい人?
まあ言ってみたら、僕たちっていうか、地球に住んでる僕たちが、この大気に包まれてるっていうこと考えてみたらどうでしょうか。「たとえ遠く離れてても、風の便りにあの人のことを」とかって言うじゃないですか。風が吹いてくると、吹いてきた先にいる自分の懐かしい人とか、愛しい人とかっていうような、気配が自分に届くっていう感性が普通にあるわけです。
同じ空の下っていうのは、空が各地域で違うわけです。だから、「一つのコミュニティ」っていうときに、どういう基準・単位でコミュニティって呼びのかと言ったら、同じ天気の話ができるってことかもしれない。「今日はいい天気ですね」「ああ、ええ天気ですな」って言える間柄が同じコミュニティって言えるんじゃないかと。
たとえ近くであってもですね。たとえば、山の向こう側は雨、こちらは晴れてるってことはしょっちゅうあるわけです。もうこうなると、同じコミュニティとは言えないのかもしれない。地球では、自然とか、気候だとかっていうものが、まあ言うてみたら結びつきを作ってくれるわけです。
ところが、この石井さんが言ってるように、この小惑星っていうか、月面の写真見てもそうですし、はやぶさ[*9]が行ったイトカワ[*10]でもそうですけど、星の、太陽の光を受けてるところは明るいけれども、でも即座にもう真っ暗ですよ。
そういうこう闇の中にある、ぽつんと浮かんでいる小惑星にたった一人でいるっていうのが、僕たちが通常思ってるようなその孤独とは質が違うかもしれない。だからそこらへんの想像力をもって読んでいくと、どんな感じがするでしょうか。実際には体験したことないでしょうけど、どんなものかなあ、てなことを考えてみても面白いかもしれません。
[*9] はやぶさ:小惑星探査機。地球の軌道と似た軌道を持つ、小惑星「イトカワ」を探査している。
[*10] イトカワ:「はやぶさ」が探査している小惑星の名前。日本のロケット開発の父である、故糸川英夫博士にちなんで名付けられた。
「もの悲しい暮らしぶり」っていうやつも、いったい何に理由があるのか。「そんなにも悲しくて悲しくてしようがなかったんだね?」って聞いても返事してくれない人ですから、理由を聞いても教えてくれないんでしょうけど、みなさんはどう思われますか、これ?この王子さまのことば。
「一日に四十四回も日が沈むのを見たよ」
あとから出てくるそのバラとのいさかいの結果と解釈する人もいますけども、恐らくそうではないですね。恐らくそうではない。
話がぽんぽん飛びますけど、小惑星のところに訪ねる旅の中で、王様の話がありますよね。61ページのところかな。65ページの一番最初ね、王子さまが王様にお願いをするんですね。「日の入りが見たいのですが……。お願いです……。お日さまに、沈むように命令してください……」って言って、「まあその時になるまで待て」って言われるんですけど、ね。
ここの話はあとで出てきますけれども、この本ではね。時間の流れとしては、「ああ、まだ僕は自分の星にいるような気がしてたんだね」「今から日の入り見に行こうよ」と言ってるのは、この王様にすぐに「日の入りを見せてくださいよ」って頼んでる王子とほとんど変わらない。分かります?
うん。ここで賢くなってはいないです、たぶんね。王様の言った通り、「やっぱ待たなあかんものや」ということが分かっていないわけです。だから、いつでも日の入りを自分の思うがままにできていたようなあの気持ちっていうのは、まだここでも消えてないですよ、王子っていうのは。
だから、気をつけないといけない。星の王子さまってすごいキャラクター化されていて「星の王子さま、かわいいー」「あの人純粋」とかっていうかたちで、星の王子さまの言うことは何でもかんでもすべて正しくて、まあ人間離れした純粋さを持って、って思いがちですけど、結構そんなことないんです。
王子は子どもとも言えないし、大人とも言えないし、あのね、全部が全部ね、ほほおーって感心するようなことばっかり言ってはいないんです。あの王様と出会った時にきちんと王様から学べば、こんなことは言ってないはずなんですよ。うん。でも、たとえ自分の星にいたとしても、日の入りは待つべきものなのだっていうことを、ちゃんと得心していたら、言ってないはずなんです。そういう意味では、ここは王子がちゃんと分かってないっていうことの証拠になるんよね。
で、この星巡りも、だいたいは、純粋な子どもである王子が大人たちの欺瞞というか嘘を暴いていくって読むのが普通です。大人たちの醜さ。もちろん、まあそうやって読んでもかまわないけれども、僕はそれだけじゃないやろって思います。
何で王子はこの王様の言うことが分からなかったんだろうって思います。常に王子は子どもの側で、正義というか真実の側にいて、大人と呼ばれるものは常に滑稽で惨めでだめでっていうふうに、子ども至上主義のような目で読むと、『星の王子さま』の本当のこう大切なところが見えてこない。
そんな二項対立の単純な物語じゃないですよ。これは「王子が成長していく物語」というふうに読むことができます。星の王子が、自分一人で暮らしていた時、バラといさかいを起こしてバラから離れていく、そしていろんな小惑星を巡って、地球にやって来て、キツネとも出会っていく中で変わっていくわけですよね。
どんどん変わっていく。だからその変わっていく中で、いったい何がどう変わっていったのかっていうことをしっかり読まないと、最初っから「王子はすごいいい人で、大人たちはみんな醜くて笑うべき存在や」って読んじゃうと、もうほとんどね、この本の半分も意味が伝わってこない。
よく考えてみてください。悲しいからって、日の沈むのばっかりを自分の都合に合わせて四十四回も見るような人の暮らし方が正しいと思いますか、みなさん?正しいと思います?どうですか?
これはまだ、王子が成長するためにというか、試練の旅に出かける前の話なんです。だからまあ言ってみたら、これ人間として出来が悪い時の王子の姿なんです。
そういうふうにはっきりと見据えないと「なんか王子って何となくこうセンチメンタルで、なんか影があって」みたいなそういう読み方になってしまう。これは全然だめですね。ここから王子がどう変わっていくのかっていうことです。
どんなことがあったのか知らない。その悲しみの原因は、物憂い原因は、たった一人で生きているということなのか。まあ、これバラはたぶん関係ない。ここにはバラのこと描いてません。バラが載ってないでしょ、この絵には、ね。

バラが存在してませんから、バラとのいさかいが原因ではないんです。きちんとこれを見たら分かるわけです。じゃあバラと出会う前からメランコリックな気分で彼は生きてたわけ。彼は日の入りをただひたすら椅子をずらしながら、メランコリックな気分を、そのごまかすっていうかな。
日の入りを見て、「ああ、沈むんだな」、いや、また「ああ、沈むんだな」って。こんな男どうしたらいいかなあと思いますね。王子さまの、何て言うか、限界みたいなこともしっかりと見据えないと。
このあと王子はどんどん別れていきます。出会った人全てと別れていく。それも“Au revoir”(オーヴォワー)「また会いましょう」っていうような“See you again”(シー・ユー・アゲイン)っていう言い方じゃなくて、永遠の別れで使う“Adieu”(アデュー)っていう。もう「二度と会わない」「おさらば」っていう挨拶でいろんな人と別れていきます。
最初の大人たちというか、小惑星を周ってる時ならまだ分かるけれども、キツネとも、パイロットともそうなんです。バラともそうですね。そうやって別れて振り返ることがないっていうかね。そういう別れ方をどんどんどんどんしていくわけです。
悲しみだとかそういう自分の憂鬱な気分に、ただその自分の気分を盛り立ててくれるような環境というか舞台装置の中で、じわーって自分で一人でいるんじゃないっていう。このあと、明らかに王子の性格とか行動が変わるわけです。だからここの章は、それを見抜いてもらいたいと僕は思います。だから「何となくセンチメンタルでいいやん」みたいな、もう「夕日を見つめる王子っていいわあ」みたいな感じじゃだめですね。
執筆時のサン=テグジュペリとアメリカ
それと「なるほど、そうです。アメリカでお昼の十二時だと」っていうとこありますね。1939年にイギリスとフランスがドイツ・イタリアに宣戦布告して第二次世界大戦に巻き込まれます。ところがナチスにあっという間にフランスはやっつけられてしまう。ヴィシー政権っていうそのナチスに協力するような政権を立てて、まあ一応の休戦状態のかたちみたいになるんです。
サン=テグジュペリは兵隊だったけど、兵役解除になってしまう。もう「ドイツの言うこと聞きます」っていうことになった。そこで、サン=テグジュペリはリスボンからアメリカに向けて亡命します。フランスに妻のコンスエロも置いて、家族も置いて。彼はアメリカでも結構有名な人だったので、アメリカ側にぜひとも自分たちの側についてくれって誘われた。彼はそれに応えるかたちで状況を変えようとしたわけです。
確かに第二次世界大戦は、アメリカが戦争に参加して大きく戦局が変わったっていうことですから、まあ彼の読みは正しかったんでしょう。ド・ゴールがその当時フランスからロンドンにやっぱり亡命して、ロンドンからフランスの住民に対して、「ナチスに対する抵抗運動をしろ」みたいなことを言ったわけです。だから反ナチスという意味では、サン=テグジュペリもド・ゴールも同じくフランスから出て、活動してるんです。
ただ、サン=テグジュペリはド・ゴール派にもならずヴィシー派にもならずっていうことで、政治的には「中途半端なやっちゃ」っていうことになってしまって、ニューヨークでも、フランス人の間でも非常に評判が悪かった。自分の立場がなかった人です。
この本は、その彼がそのアメリカで書いた本です。それも、もう一度、亡命じゃなくてもう一度、フランスの兵隊として、もう一度戦場に復帰する寸前に書き上げた本なんです。
最初に「レオン・ヴェルトに」という献辞がありますね。これはサン=テグジュペリの22歳年上の友人ですけど、彼が亡命する時にフランスに置いてきた、というか、フランスに残っている彼の友人です。
彼はユダヤ人なので、ナチスに追われて身を隠してます。献辞には「このおとなは今フランスに住んでいて、お腹をぺこぺこにすかし、寒さにぶるぶる震えています。そんな人はどうしても慰めてあげなくてはいけないからです」とあります。
彼を慰めるために、この本を書いたわけです。たぶんレオン・ヴェルトはここのところを読めば、サン=テグジュペリの気持ちが痛いほど分かる。サン=テグジュペリはフランスのことをずっと考えてるわけです。レオン・ヴェルトのことをずっと考えている。「アメリカでお昼の十二時」はサン=テグジュペリのことです。
フランスでは日の入りの時刻です。だれだって、そんなことぐらいは百も承知です。「たったの一分でフランスに移動できれば」というのは、サン=テグジュペリが本当に「たったの一分でフランスに移動したいと思ってるよ」っていうメッセージです。
それだけで、その日の入りは見られるわけです。ただ、残念なことに、フランスははるか遠くにありますから、それが無理なのです。
何気なく書いてあるような文章ですけど、これはもう明確に届ける相手がいるわけです。レオン・ヴェルトであり、サン=テグジュペリが愛しながらもフランスに置いてきた仲間たち。『ある人質への手紙』っていう作品を彼は書いてますけど、ヴィシー政権というか、フランスにいるフランス人はナチスにとられた<人質>なんだと書いている。
その<人質>を救うために自分は必ず何かをしなけりゃいけない、っていう思いでずっとアメリカにいたわけです。ところがアメリカにいる間は、腹ぺこだとか寒さに震えるなんてことないわけですよ。アメリカではもうサン=テグジュペリは大変な流行作家でお金にもまったく不自由しない。実際に戦争に巻き込まれる心配もない。そういう自分がもう一度その戦場に復帰するっていう気持ちになる寸前に書かれたのが、このサン=テグジュペリの『星の王子さま』なんです。
で、レオン・ヴェルトに対してこう書いてるっていうことは、どういうことなのか。まあ彼の覚悟をここから読み取ってほしいっていう。これは確実に、フランスにいる人たちに向けて書かれた文章なんです。もともと彼はアメリカがあんまり好きじゃなかったみたいで。
まあそらそうですよね、フランスの元貴族ですから、アメリカのビジネスマン中心のところで生活して面白いわけがない。2年ぐらい行ってるんですけど、英語も全然覚えようともしていない。
たとえばこの、えっと、10ページのところでね、大人たちのことをぼろくそに言うてるところですけど、
けれども、いつだって答えは同じでした。「帽子だね」と。そうなると、ぼくはその人には大蛇ボアのことも、原始林のことも、星たちのことも話さないのでした。その人の頭の程度に合わせてあげるのでした。おとなのトランプ遊びのブリッジだとか、ゴルフだとか、政治向きのこととか、ネクタイなんかのこととか、そんなことばかり話しました。
ここに出てくる「その人の」ってどんな人だと思います?トランプのブリッジやとか、ゴルフやとか、政治の話やとか、ネクタイの話、ファッションの話。たぶん、釜ヶ崎のおっちゃんたちはこんな話しません。ゴルフの話はしません。自動車工場で働いている末端の労働者もこんな話はしない。農園で汗水流している人たちもこんな話はしない。
要するに、ホワイトカラーで、金の計算をやってるようなビジネスマンていうか、サラリーマン、資本主義経済のただ中で働いているまあ白人系の人たちですよね。
そういう人たちをイメージして書いてるわけです。これ実際にはアメリカ人そのものなんですよ。資本主義の最先端を行ってたアメリカ人のことです。当時のアメリカ人のイメージが彷彿とするんです。
だから『星の王子さま』はアメリカでは最初結構ウケが悪かった。どうも自分たちが揶揄されているように思えて仕方がないわけです。「ビジネスマン」って出てきますけど、フランス語でも「ビジネスマン」なんで、確実に「一番人間じゃない」「キノコだ」って言われてるのはアメリカ人のことだと思ってしまう。そんな感じで、アメリカでは『星の王子さま』ってウケが悪かったんです。
せっかく亡命先にこっちで引き受けてやって、あの頼りないフランスやイギリスを応援するために自分たちが命を賭けて、ノルマンディー上陸作戦[*11]とかもう次々と、ナチスをやっつけるために命を賭けてやってるのに、何でこんなボロクソに言われなくちゃいけないんだ、みたいな感じで評判は最初は良くなかったんです。
[*11] ノルマンディー上陸作戦:Invasion of Normandy 第二次世界大戦中の1944年6月6日に連合軍によって行われたドイツ占領下の北西ヨーロッパへの侵攻作戦。
王子の<悲しさ>とは
サン=テグジュペリがフランスを愛する人なのは、他の作品を読んでみても分かるんですけど、この『星の王子さま』の中でも、「愛するフランスのために、まだ自分は何もできていないけれども、命も惜しくないんだ」「フランスのためにっていう思いは常にあるんだ」っていうことを各所に普通の言葉で散りばめている。子どもが読んだら「そらそうやなあ」って思うだけです。いろんな筆者の背景とかを知らないと、分かりにくいところがあるんです。
もともとこの本は、誰にでも、子どもたち全員に、じゃなくて、やっぱりレオン・ヴェルトに捧げられた本なんです。レオン・ヴェルトに捧げられた本。彼は自分のことをこんなふうに言ってます。「私はプロの物書きじゃないから、そんなに勝手に人物を創造したりだとか、あらすじを、ストーリーを考えたりすることはできない。自分が本当に経験したこと、自分が本当に会った人、自分が本当に考えたことしか書けないんだ」と。
『南方郵便機』と、それから『夜間飛行』も、彼のパイロットとしての経験がいっぱい入ってるんですけど、まあとりあえずは小説の形になってるんです。でもね、小説としてはものすごくストーリーが単調で、人物もあんまり出てこない。
まあ言ってみたら、小説家としての力量って言うんですか、ストーリーテーラーとしてはあまり大したことないですね。彼は小説を書くのを長いこと諦めてたんですよ。「もう小説無理や」「もうお話なんか作れない」って感じで。
『人間の土地』っていう作品がありますけど、これもどちらかというともうエッセイ集みたいなもんなんです。自分の体験談ばっかりなんですよ。で、中に、ギヨメとかメルモーズとか、彼が一緒に働いてた人たち全部実名で出てきます。だから、『人間の土地』っていうのは「作りもの」じゃないんです。
そうやって小説家を志しながら、「やっぱ無理や」っていうことで『人間の土地』みたいなものを書いたり、それから新聞社の特派員としての記事を書いたりとかやってた。そんな人間が最後、『星の王子さま』っていう、ほんとのファンタジー、フィクションを書こうとするんですけど、やっぱり彼が経験したことがこれやっぱり根っこにあるんです。全部根っこにある。
だから、非常に荒唐無稽にみえるところも「日の入りを四十四回も見れるようなそんな星に住んでたのか」とそのまま読むだけじゃなくって、ここに書かれてあることの意味をどれだけ掴めるかっていうことです。
この王子の絵どう思いますか、みなさん?これ47ページ。バラの前でキョトンとしてるような王子を見てください。これ別人のように思えるよね。思いません?この絵、他の王子と比べてちょっと違うんです。いろんな王子の絵がありますけど、どこらへんが違うと思います?

これはもういろんなこと言う人がいてね。サン=テグジュペリはそうやって落書き程度ならちゃっちゃっちゃって描くんですけど、やっぱりそれなりのシーンシーンに応じた絵を描くためにはモデルが必要だったんで、いろんな人にモデルになってもらってるんですよね。
それと50ページにトラの絵があるね。「トラなんかちっとも怖くありませんよ」なんて書いてある。でもこれトラに見えないしょ?これ犬しか見えない。これはトラじゃなくて犬をスケッチしたそうです。「連れて行ったらその犬をスケッチされた」とか、そういう資料がいっぱいあるんです。みんながみんな、誰かがモデルになっているわけじゃないでしょうけど。

それとこっちの絵、彼の妻であったコンスエロ・スーシンっていう女性がモデルやったっていう話がサン=テグジュペリの伝記のあちこちに書かれています。そうやって見てみると、この王子さまだけがすごーい女性的な感じがするんだよね。なぜじゃあ、ここでコンスエロをモデルにしたのか、みたいなことも疑問になるかもしれない。

そんなふうになってくると、いろんなこう文献ばっかり読んで、いちいち解釈していくみたいなことになりますね。でも、まあここで僕が大事だと思っているのは、王子がまだ一人で星に住んでいた時の<悲しさ>なんです。
このあとも出てくるし、その前のバオバブの話でもありましたが、彼は非常に几帳面に「面倒だけど、毎日続けることが大切なんだ」ということで、きちんと自分の星の面倒を見ている。おもちゃで遊んだら遊びっぱなし、片付けもしないような、そういう子どもらしい子どもじゃないわけですよ。
きちんと、ほんとに真面目に自分の生活、自分の星をちゃんと手入れするような大人みたいな人やったんです。その時の暮らしぶりの中で、こういうその悲しみに浸ることを、浸るだけでしか慰められないような生き方をしてた。
だからその時の悲しみっていうものを癒すのは、四十四回日の入りを見ても、たぶん癒されてないんです。そういうことを、たとえば自分の人生に置き換えて考えてみると、どういうことなのか。人の悲しみだとかそういうものっていうのは、いったい何によって癒すことができるんやろうか。そのあたりを考えてもらうと面白いかなと思います。
あれこれと「日の入り」の話
次のⅦ章がもう強烈に面白いところなんですけど、いったんここで切って、みんなに話聞いてみましょうかね。夕日をじっと眺めたことがある人とかいます?長見さん、どうですか?
長見:あるよー。
西川:あるんですか?僕はそんなことしたことないんですけど。
長見:本当?へえー。こう沈む直前ね、なんかばーっと燃え上がったようなね。ケア塾たまてばこのところの広大な阿倍野の墓地。あそこ一番西側に行って、日露戦争のなんか戦士たちの墓とか残っててさ、うん。そうすると真西に見事にこう、美しい夕日が沈んでるんですよ。
西川:四天王寺[*12]さん、あるじゃないですか。あれの西の門のところがちょうど日の落ちるところなんだね。
長見:うん、だいたいあの、上町台地[*13]はそういうなんか、みんな日の沈む信仰みたいなん、そのそれを思ったりね。
西川:西方浄土[*14]っていうかね。ちょうど見えるところに、西門(さいもん)やったっけな、西の門が作られてあって。で、四天王寺ができた頃には、すぐそこが海岸だったんだね。今の大阪の地形ってずいぶん変わってますから、すぐそばが海だったわけです。海に落ちていく夕日が見れるところで、まあその落ちる夕日を見ながらなんか瞑想に耽るみたいなことがあったのかな。でもどうなんやろねえ。
[*12] 四天王寺:大阪市天王寺区四天王寺にある寺院。聖徳太子建立七大寺の一つとされている。山号は荒陵山(あらはかさん)、本尊は救世観音(ぐぜかんのん)である。『日本書紀』によれば推古天皇元年(593年)に造立が開始されたという。
[*13] 上町台地:大阪平野を南北に伸びる丘陵地・台地。北部は大阪市中央区の難波宮跡、大阪城付近・天満橋の辺りで、そこから緩やかに小山を形成し、天王寺区上本町の大阪上本町駅付近で台地の頂に達し、そこから下りとなって阿倍野区周辺を経て、何部の住吉区・住吉大社付近に至り、その辺りでほぼ平地になり清水丘を以て終わり、長さ12kmに及ぶ。大阪の歴史の発祥地であり、要所である。
[*14] 西方浄土:仏教における聖域・理想の世界。十億万仏土先の西方にあり、阿弥陀如来がいるとされる浄土のことで、極楽浄土といわれる。
長見:なかなかあの墓場の、あそこから見るのも素晴らしいよ。あのへんに住んでるっての、うらやましいなって思ったもんね。
西川:僕は昇ってくる日の出は好きなんだけどね。寝ぼすけやからあまり見れることないですけど、日の出は大好きでじーっと見たりすることあります。でも、こう日が沈んでいくっていうのはなんか悲しいからね。なんか目を背けてしまうタイプやな。どっちか言うたら。どうですか?
B:夕日が見えるとどっちかいうと、気持ちが落ち着くじゃないんですか。
西川:はい。どうですか?
C:きれいな夕日を見ると、こう誰かに教えてあげたくなる。
西川:
「ねえ、分かる?……心がほんとうに悲しいとき、人はだれだって夕日が見たくなるものなんだよ……」
どう思われますか? そうかなあって感じする?
D:飛行機から、きっと夕日見てはったやろなって思って、
西川:
サン=テグジュペリは見たでしょうねえ。彼は43か44歳で亡くなってるんですけど、その間にものすごい飛行機は進歩してますから。一番最後に乗ったP-38っていうのはアメリカ製の飛行機で、もう今の飛行機とあんま変わらないぐらいピシッと酸素マスクしてバシッと乗り込むような、高度1万メーターまで飛ぶようなやつですけど、最初のやつはプロペラで、パタパタパタパタパタっていうやつでした。『紅の豚』[*15]に出てくるような、操縦室を覆うものもないやつ。風をもろに受けながら運転するみたいなやつですからね。
[*15] 『紅の豚』:スタジオジブリ制作の日本の長編アニメーション作品。1992年公開、宮崎駿監督。
『夜間飛行』って本があるって言いましたね。飛行機が出始めの頃、サン=テグジュペリは郵便物を運ぶ飛行機に乗ってたんですけど、夜間飛行っていうのはできなかったんです。見えないから。山があっても分からずにぶつかっちゃうからっていうことで。
でも、昼間しか飛べなかったら、飛行機の速さが半減するわけです。だから夜にも飛べて初めて、飛行機が文明の利器になるから、命がけで夜でも安全に飛べる航路を開拓していくわけです。今まで人が飛んだことのないその空の道を開拓するために、サン=テグジュペリたちは仕事してたんですね。
そういう意味で、日が暮れてくるっていうのは、最初の頃はサン=テグジュペリにとって、飛べなくなるサインだった。夜間飛行の前は、日が暮れるまでに帰らなだめですから。
だから、よく言われることは、サン=テグジュペリはやはり空に視点を持った作家、空から地球を、人々の暮らしを見た、作家であるということです。やはり初めてのことなんですね。
1903年にライト兄弟が出て以降、飛行機乗りが文章を書くというのは彼が初めてでした。だから飛行機の文学っていう。宇宙の話ですけど、この『星の王子さま』だってそうでしょ?まあ言ってみたら飛行機に乗ることは、ほんとに宇宙とすれ違うようなところを飛んでいるわけです。
今の僕たちにとって、飛行機って、結構安全な乗り物っていうか、しょっちゅう乗る乗り物じゃないですか。でも昭和32年生まれの僕のちっちゃい時は、飛行機なんて、一生に乗るか乗れないかと思ってたんですよ。「飛行機っていうのはお金持ちしか乗らないよなあ」「僕は一生乗れることがあるのかなあ」みたいなことを思ってたぐらい。
『星の王子さま』はそれよりさらに昔です。僕の生まれたのが1957年、サン=テグジュペリが生まれたのが1900年。57年前です。だからその頃に飛行機に乗るっていうことは、ものすごいこう人間にとって未知の世界なんですよね。
その意味で、サン=テグジュペリの文学っていうのは、それまでの文学とはまったく違う視点を持ってるってよく言われます。『星の王子さま』にそれがあるかっていうと、それほどないような気もするけど、さっき言った『夜間飛行』、『人間の土地』なんかの彼がパイロットとしての経験をたっぷり書いてる小説には随所にそういうのが出てきますね。面白いですよ。
E:僕はほとんど読んだことがないので、王子がいる小さな星からこう見た時に太陽っていうのがどれぐらいの大きさなのかが分からなくて。「日の入り」って王子が言ってるっていうことは、視界が太陽から…太陽が自分の星のおかげで視界から消えるんだろうなって想像はできるんですけど、太陽のほうが大きいってことないんやろうか?とか、そのへんのその情景が自分の中で完全に映像化できない感じが、そのへんがもどかしい感じです。
西川:たぶん絵で描いてあるこれが太陽なわけやね。この日が沈んでいくんですよ、これ。

E:じゃあちっさいんですね。
西川:
うん、このぐらいに見えてるわけ。でこれ沈んじゃう。それで、沈んでしまいかけたらまた前に行くんですね。そしたらまた夕日出てくるから。っていうかたちで四十四回。
四十四っていうのもサン=テグジュペリが亡くなる時の歳です。これ四十三回と四十四回って書いてあるやつがあって、第一版と第二版で違う。そんなことをぶつぶつ言ってる人もいますけど。この四十四回っていう数字も、彼が自分の命の終わりを予感してたっていうふうに読み取ることもできるかもしれません。
そんなふうにして全部謎解きしていくと「えーっ」ていう感じがするかもしれませんけれど、サン=テグジュペリはいろんなところにいろんななんかトリックをほんとにめちゃくちゃ入れてる。
普通は「四十四回って意味ないやろ」って思っちゃうじゃないですか。「B612ってなんや、適当につけたんやろ」って思うじゃないですか。
でも違うんです。この本は必ず、必ず意味があるんです。それを全部分かってくれとはサン=テグジュペリは言ってないですよ。「分かる人には分かる」と。そして、質問されても答えない。だって、王子もいくら質問しても答えてくれない。分かる人にしか分からない。
では『星の王子さま』を読むっていうことで何が大切なのか。それは自分で問いを立てるっていうことです。さっと読み過ごすんじゃなくって「これは何なんだろう?」って、「これの意味は何なんだろう?」って。
一挙に分からなくていいんです。そもそも一挙に分かるように書かれてる本じゃない。時の流れの順番が入れ子構造みたいになってます。「ねえ、ヒツジの絵かいて」っていうのはずいぶんあとからなんですよ。王子が、星を出てから、一年以上経ってからの話なんです。地球に来てからほぼ一年になるっていう時に初めて会ってるわけですから。そこから始まって過去に遡って、王子の旅だとか、王子がまだバラと出会う前の暮らしとかが書かれていく。
「昔どこそこ、川に桃が流れてきました。桃を割ったら桃太郎が出て来て、桃太郎が大きくなって、鬼ヶ島に行って」ってこれ、桃太郎の時間通り行くでしょ?生涯の流れ通り行く。そんなふうに行ってないわけ。
いきなり「宝物を持った若者がやって来ました」みたいになる。そして「どうしたの?」って言ってたら、「いや鬼ヶ島に行って」みたいな話からまた急に、「僕が桃の中にいた時はね」みたいな。こんなふうにころころころころ変わるわけです。
だから、最初は何を言うてんのかさっぱり分からない。最後まで読んで、「あ、そうか」て思うようなことがいっぱいあるわけです。
ところが、悲しいシーンなんかは、このあとずーっとバラとの別れが悲しい、みたいなことがずーっと続きますから、バラとのことでこんな悲しんだんだろうと思ってしまう。1、2回くらい読んだ程度なら。
でも、よくよく見てみたら、絵にバラはない。バラは載ってないんです。ということは、バラと出会う前にすでにこういうメランコリックな暮らしをしてたっていうことになるんです。何度も何度もこう読み返してくたんびに少しずつ覆いが剥がれていくっていうような、そういうこう構造になってる本です。それが面白い。
だいたい、最近のよく売れてる本は、読んでる最中はおもしろいんだけど、「もう二度と読まない」「結末が分かったらもうそれで終わり」みたいな本が多い。でも、これは何回読んでも新たに分かるような仕掛けがいっぱいされてます。そこが面白いのかなって思います。
王子の精神状態について
F:なんか四十四回見るってどんな感じかなあって思ってたんですけど。まあなんか時間が戻るっていう感じかなあっていう。なんか言ったらこう、時間の流れを否定するみたいな感じなのかなっていうのは思いました。
西川:悲しいときはそういうもんですかね?悲しいときは時間を止めたいのかな?どうなんでしょうね。
F:うーん。なんか、そうですね。味わい尽くすときはこう沈んだのが見たいのかもしれないけど、それをまだ否定する段階だったらこう、止まったままにすんのかなあって。
西川:
ねえ。「心がほんとうに悲しいとき、人はだれだって夕日が見たくなるもんなんだよ……」っていう。どうなんでしょうね。
『陽はまた昇る』[*16]っていう映画がありましたけどね。ああいうふうに「陽はまた昇る」っていうところに重点を置く生き方と、「いったん昇った陽も必ず沈む」ところに焦点当てて、「いかに太陽といえども沈むんだ」「はー、沈むんだ」みたいな、そこを納得するまで見続ける生き方とはずいぶん違うと思いますね。
諦観というか諦めというか。「陽は沈むものなんだ」っていう。悲しみのときにはそういう諦めるしかないから、そういうのを見るのかなあ。どうなんでしょうね?日の入ってやっぱり何となくもの悲しい気持ちになるんかなあ。あれ何でなんでしょうね?
[*16] 『陽はまた昇る』:1957年に公開された映画。アーネスト・ヘミングウェイの小説『日はまた昇る』を原作としている。監督はヘンリー・キング。脚本はピーター・ヴィアテル。主演はタイロン・パワー、エヴァ・ガードナー、メル・ファーラー、エロール・フリン。
G:さっき、大気がないみたいな話されてたじゃないですか。もしそうだとしたらこの夕日って赤くないんだろうなあって。
西川:赤くないね、見えなくなるだけやね。
G:まぶしいまま消えていく。
西川:だからまあ、言ってみたら夜空の星が位置を変えるようなもんですよね。星もこうやって落ちていきますからね。うん。日が落ちていくって、地球が回ってるだけのことだけど。だから月が沈むのと一緒ですよね。
A:
ここには、日の入りとか夕日っていう言葉はあるけど、さっきの、おんなじこと考えてて、夕焼けっていう言葉はやっぱり出てこないから、夕焼けはその星じゃ見れないのかなあって。
たしか、月に行った宇宙飛行士たちが、青い地球が月のように昇ってくるのを見たっていうので、たぶんそれって石井ゆかりさんが言われたように、真っ黒な中に青い月が昇っていってまた沈んでいく。
西川:
だから、夕焼けの美しさとかっていうよりも、あったものが、見えていたものが見えなくなるっていうことでしょう。この日の入りは。「目の前にあったものが見えなくなるっていう経験」っていうふうに考えたらいいんじゃないですかね。
「悲しみ」っていうのは日本語ですけど、その「叶わない」っていう、要するに「自分の思う通りにならない」っていうことを表す言葉なんです。悲しみっていうのはね。だから要するに自分の能力とか、願いとかが叶えられることがないっていうのが悲しみです。
だから目の前にあるものが必ず消えていく、っていう意味で考えていくと、何も自分は確たるものを、こう持ち続けることはできないみたいな、そういう儚さみたいな、関係の儚さみたいなものが日の入りにはあるわけですよ。見えていたものが見えなくなるんですから。
これが夕焼けだと、夕焼けがその山に照り映えてとか、海原を赤く染めて、とかだったら、「ああ美しいな」っていうふうになるかもしれません。地球上の夕日なら、そういう美しさで、ちょっと悲しい気持ちが美によって感動によってなんか違うところに行くっていうことがあるかもしれませんけど、闇の中で、見えてたものが見えなくなるだけ。そんな日の入りだと、まあ目の前にあるものが消えて行く、そういう経験をやっぱり指してるのかもしれないですね。
G:さっきちょっとDさんおっしゃってたけど、この頃まだ人間が月に行ってないから、大気の関係で、夕日が赤くなるんだみたいなことも、知られてなかったんじゃないかと。サン=テグジュペリは、この星では大気がなくても赤い夕日が落ちていくところを想像して書いたんじゃないかっていうのはちょっと今思いました。
西川:
どうなんでしょうねえ。まあ、ただね、サン=テグジュペリって普通に想像される以上に理科系の人です。自然科学にものすごい詳しいんですよ。いわゆるこう文学者だと思っているととんでもなくって。とはいえ、まあそこらへんは分からないですね。
だって、この宇宙空間を舞台にするっていうこと自体が、普通の人間やったら考えられないわけですよ。このあとも出てきますけど、地球の人間がどれだけいて、それが全部集めたらどれぐらい平方メートルの中に入るか分かるか、みたいな計算したりだとか。結構、そういうことをやる人だから。
G:私はなんかこの四十四回、「数えたんや」っていうのが。なんかすごいなあって。一回見て「あ、もう一回」「あ、もう一回」「あ、もう五回見たけど、もう一回」っていって、四十四回分数えたんやなあっていうのが、なんかすごい。それって四十四回見て「ああ、もうええわ」ってなったのか。どんな感じなんかなあって。
西川:
これ面白いんですけど、Ⅳ章の最初に「君には長いあいだ、日の入りの穏やかなありさまだけが心の慰めでした」って書いてあるからね。日の入りの穏やかなありさまって、飛行士の感想ですけど。
そのことをぼくは四日目の朝初めて知りました。
朝ですよ。朝に「僕は日の入りが好きなんだ。日が沈むのを見に行こうよ」って言ってる。分かります?あの、昼過ぎじゃないですよ。朝っていうことは日が出たばっかりの時です。だからきっと王子は日の出はあんまり好きじゃない。
朝にそんなこと言ってるっていうことはどうなんでしょう。抑うつ的といえば抑うつ的です。うつ的な人っていうのは朝が一番しんどいです。「また一日が始まった」みたいなね。自分にとって堪え難い人生。それがまた始まるっていうことで、うつ病の人は朝が一番辛いんです。そして夜になるとだんだん楽になるんですよ。「もう一日も終わりだ」「もう自分も眠れる」みたいに。
だからもうここらへんも、こうなんかすごくぴったしうまいこと当たってる。もう簡単に書いてあるんですけど、彼は<朝>に言ったんです。そういう意味では王子は、この四日目の時に、実はものすごく悲しい気分だったんですよ。ほんとに悲しい気分だったんですよ。
「ねえ、ヒツジの絵かいて」と言って、いろいろとぼちぼちと飛行士ともいろんなこと話すわけです。これは四日目です。その時に朝っぱらから「ねえ、日の入りを見に行こう」って言う。悲しくて悲しくてしかたがなかった。
続くこの後ろのところ。
「ということは、四十四回も日の入りを見た日は、君はそんなにも悲しくて悲しくてしようがなかったんだね? 」
パイロットは過去のように聞いてます。だからこの飛行士はバカなんです。四日目。王子はその日悲しかったんですよ。でもこのことはあとになったら分かります。王子は、ヒツジを連れて自分の星に帰るっていう、決めてるわけですから。
間もなく飛行士とお別れするっていうことです。その自分の将来が王子にはあるわけです。このあとどういうことが起きるかっていうのは、王子には分かってるわけ。だからこの日悲しかったんですよ。
これは昔話のように書かれているけれども、実は四日目、パイロットと会って四日目の王子は、どんな気持ちでいたのかっていうことが、もうここに書かれてあるわけですよ。
読者はなかなかここに気がつかない。これあとにならないと分からないんです。このあと王子がどんな行動をするのかっていうこと。どんなふうにして自分の人生を生きていくのかっていう。考えてみたら、四十四回日の入りを見た時の悲しみ以上の悲しみをこの日感じていたのかもしれない。だからつい、その四十四回日の入りを見た時のように、自分の悲しみを日の入りで何とかなだめようと思ってしまったのかもしれない。
F:王子の星はちっさいからこう、四十四回じゃなくても永遠に見れるわけですよね。そういう意味ではなんかずっとコントロールできるんだけど、なんか旅していく中で、あの王様に言われたりとかで、時間はコントロールできないんだみたいなことにもなってるのかなって思いますね。
西川:
そうですよね。これ、ほんとに子ども向けの話と言いながら、最後は王子消えてなくなっちゃうんでね。ハッピーエンドとは言い難い内容なんですけど。
最後のほうは、王子は空気銃で打たれた小鳥のように、もうなんか死に怯えるみたいなところも出てきますから。でもそれは全部自分が覚悟しての話なんです。あと数日後にそれがやって来るって。自分がこの星にやってきたということは、あの日がもうじきやって来る、ということ。
でも書いてないですよ。ここの段階では。だから、これ、いっぺん全部物語を読んだ人が、もういっぺん注意深くここまで来て、やっと分かるっていうね。はい。
A:朝は苦手だったらしいとかはなんとなく分かってるんで。あの、私とかだったら、少し前までは朝は昼まで寝てて、夜になるとテンションがなんかぐーんと上がっていって嬉しかったんですけど。なんかひょっとしたら日の出、日の入りを見続けるっていうことは、その間は夜を体験せずに済むわけですから、夜から逃げてたんですかね?
西川:夜のことはあんまり書いてないですね。書いてたかな? 夜の話。夜の話って、砂漠を旅した時に「井戸を見つけに行こうよ」って言った時に眠ってしまうっていうシーンはあります。それでその眠ってる姿を飛行士が見てっていうシーンはありますけどね。基本この星の王子さまって人間離れしたところがあって、砂漠のど真ん中にいてるわりには喉が乾いたとも言わないし、お腹がすいたとも言わないし。
A:あとでそのバラに出会う前からそんな、寂しい気持ちというかメンタル面に問題があったっていうのは、なんか自分に置き換えても。あ、まあ私、摂食障害なんですけど、その発病する前から、その、問題を抱えていて、それがなんか似てるじゃないけど。そのまあ性暴力に遭って摂食障害になったんですけど。その、性暴力に遭う以前から生きづらさみたいなの抱えてて、なんかそれに、何て言うんですかね、いや、うまくまとまらないですけど、そのバラに出会う、バラとのことがいろいろある前から、なんか王子さまも生きづらさ的なものを抱えているのかなあと思って。
西川:
あったんだと思いますよ。十分に満足してたら四十四回も日の入りを見るわけがなくて。でも彼はその日課をちゃんとこなしている。普通の大人らしい生き方をしてるわけですよ。
自分のちっちゃな星を守るためにというか。バオバブの芽はちゃんと毎日毎日抜くし、それで火山の手入れもするしね。で、自分の身繕いが終わったら星の身繕いをするみたいな。きれいにちゃんと日課をこなしていく。
誰もいないから誰に非難されるわけでもないけど、自分で自分を律して自分の住んでる星を大事にしてっていう生き方をしてたんだけれど、「悲しくて悲しくて」「四十四回も日の入りを見ないと」っていうような暮らしをしてたっていうのもありますよね。で、バラとの出会いがまあ、またこの生活をガラッと変えるわけです。
たとえば発病する前からそういうのがあったんじゃないかっていう話でいうと、中井久夫さんっていう精神科医がいます。僕も何度かお話したことがあるんですけど。彼が言うのは「病気が治るっていうことは、病気の前に戻ることじゃないんだ」「発病する前に戻ることじゃないんだ。そしたらまた発病する」「病気を治るっていうことは、病気を超えていくこと」だと。
なる前は、何かやっぱり生きづらさがあったから、生きづらさの中で病気というそういう出来事に出合ってるわけです。だから単純に病気の症状をなくして前と同じようなったら。
「回復」っと言って病気の前に戻ることが、言ってみたら本当の意味での治癒ではないんだと。その病気の経験、それから病気になる前からの自分の流れがいったい何であったのか。違う方向に向きを変えれるかどうかが大事なんだ、って。いつも言われてることですけど。
王子も恐らくそうなんですよね。このメランコリックな感じっていうのがずーっとあるわけです。地球に来てもずっとあります。いろんなこう星巡りしてても、結局は友だちを作らないわけですし。「変なやつだなあ、大人は」とか言ってね。
結構いいこと言うてる人、可愛げのある人たちもいるんですよ。ところが王子は、「大人って変だなあ」って、“Adieu”(アデュー)って、「さよなら」って、「あばよ」みたいな感じで、さっさと見捨てていくわけですよ。
地球にやって来ても、そんな簡単には友だちできてないんです。そのキツネとの出会いから、やっとぼちぼちと変わっていって、そのあとに、今度はパイロットと彼は関係を結ぼうとするわけです。変わっていくわけです、どんどんどんどん。
だから彼はもう一度バラの元に戻るって言うけれども、それはバラと出会って星を出る前の王子じゃないんですよ。やっぱりバラといさかいを起こして出ていって、友だち探すけど全然友だち見つからなくって、っていうそういう紆余曲折があったうえで、またパイロットとも出会って、そのパイロットともつらいお別れをして、っていう王子が帰っていくわけです。
そういう成長物語っていうか遍歴物語っていうのを、この本は素直に書いてないんでね。「昔々あるところに」ってどっかに書いてありましたけど、「こんなちっちゃな星に王子が住んでいました。この王子がこんなこんなこんなことあって、こんなことあって」って、その過去からずーっとこう繋がってくるような時系列で書いてない。
先のことは一切何も明かされてないのに、「ねえ、ヒツジの絵をかいて」って、いきなりその声から登場するんですよ。最初に言いましたけど、王子が出てくるところ、たとえば11ページ。
こんな声が聞こえて来ました……。
「すみません……。ヒツジの絵、かいてよ」
まず声から登場するんです。姿を現すんじゃないんですよ。まず声。
「ヒツジの絵、かいてよ」
「すみません……。ヒツジの絵、かいてよ」
と声で続いてくんです。
バラと出会う前の四十四回日の入りを見ていた頃の彼のこの悲しみを、バラはひょっとしたら、ひょっとしたら癒してくれる存在だったかもしれない。だけど、そのバラとうまくいかなかった。それで出ていってしまう。また戻ろうとする前も、悲しいわけです。
でも、昔の四十四回の日の入りを見た時の悲しみと、最後の四日目、つまりパイロットと会って四日目の朝、「日の入りが見たいんだけど」って言った時の王子の悲しみは、たぶん違うんですよ。で、どこがどう違うのかっていうことを、読み解いていく必要がある。
ともかく『星の王子さま』って、文章さえ読めれば分かるっていう本じゃないんですよ。自分の人生で経験してないと分からない。愛する人と別れたことがない人には分からない。それで自分の願いとか悲しみっていうものがない人にはやっぱり分からないと思います。
「こんな経験一度もないわ」っていう人にはやっぱり分からない。「何の不足があったん?」ってなります。誰かがものすごく彼をいじめるわけでもないし、衣食住に困ってるわけでもなさそう。丁寧に丁寧に自分の世界を作ってます。何がそんなに虚しかったのか、悲しかったのかって。
私たちの中にあるふとした虚しさみたいなものを感じる時っていうのはいったい何なのか。昔の王子の悲しみと、四日目の朝、やっぱり悲しいから「日の入りを見に行こうよ」って言った時の王子の悲しみと、違うと思います。
はっきりと原因の分かる悲しみっていうのは、悲しみっていうより怒りに近い不満であったり不足であったり。そうじゃなくって、何かが悲しい。そんな悲しいことがあったって、何一つ書いてないですよ。でも、悲しかったことがあったんだ、っていうことです。またそれが、四日目にもあったわけです。
人間っていうものの存在において、悲しみだとか苦しみだとかっていうものはなければないほうがいいものなのか。王子は成長しているとしても、やっぱり悲しんではいるわけです。悲しみっていうものが持つ、人生にとっての意味っていうのは、やっぱりあるはずなんです。
でも如何様に悲しむのか、何のために悲しむのか、によって、その意味はやっぱり変わってきます。たった一人で、この四十四回の日の入りを見てた時の悲しみと、王様に「太陽に沈むように言ってよ」って言った時の悲しみと、四日目に、パイロットに、「僕は日の入りが好きなんだ。日が沈むのを見に行こうよ」と言った時の悲しみ。
最後は「見に行こうよ」って言ってるんですよ。ある意味で、これパイロットも友だちになりかけてるんですね。友だちに「一緒に見に行こうよ」って言ってる時なんです。でもこれは恐らく、これから別れるっていうことが分かっている友に対しての言葉ですね。その時の悲しみと、これまでとはやっぱり違うんじゃないですかね。うん。
たとえば何かのことで非常に苦しい経験をするとする。それで立ち直れずに、道を這いつくばって進む気持ちになる。それはその時、急に始まったことじゃなくって、それまでの中にも自分の中にいろんな生きづらさやとかそういうものがあって、っていうことでしょう。
それを、スコーンとなくしてしまうことが本当にいいことなのかどうなのか。たとえばトラウマと言われるようなものは、消したほうがいいのかどうか。過去のつらい思い出というのは、洗脳するかのようにして、きれいさっぱり自分の過去の記憶からなくしたほうがいいのか。病気になった時のつらい思い出っていうのはなくしてしまったほうがいいのか、忘れてしまったほうがいいのか、なかったことにしたほうがいいのか。
さらにいえば、そういう悲しみや苦しみとは無縁の生き方のほうが幸せなのか。幸せっていうか自分にとって意味があるのか、自分が本当に生きたと言えるのかどうなのか。
そう考えていくと、どうやらたぶんこの『星の王子さま』に関しては、苦しみだとか迷いだとか悲しみだとか、人との別れだとかには、必ず意味があるんですよ。必ず意味がある。
でもその時にどう振る舞うべきなのかを、サン=テグジュペリはサン=テグジュペリなりに考えた。この本は王子だけが主人公じゃないんですよ。王子と共にいるパイロット。僕はパイロットの言動にも十分注意を払うべきやと思うんやね。違ったかたちで現れているけれども。
だから僕たちがこの『星の王子さま』の中から、単純に何ていうか人生訓というか、「大切なものは目には見えない」とかっていうのだけに「ほっほおー」とかなるんじゃなくって、細かなところで彼らはいったい何を感じてどう生きていこうとしているのか、っていうところをみないといけない。
悲しみから逃れてないんですよ。でも最後は、笑ったかなと思ったら、「泣いてしまうかもしれない」っていうことなってるでしょ?「ヒツジがもし食べてしまったら」みたいなかたちで。完全にハッピーな話にはなってないけれども。
だから、悩みとか戸惑いというものを抱えながら、それでも生きていく希望はどこにあるのか?僕がこの勉強会を始める前に、「僕にどうしても分からんことがあります」って、「なぜヒツジを連れて帰るかです」って言ってたじゃないですか。なぜヒツジを連れて帰らなあかんのか?
バオバブも食べてくれるかもしれんけど、バラも食べてしまうかも分からんようなヒツジを、なぜ連れて帰りたいと思ったのか。うん。ねえ。非常に合理性、理性とか計画とかだけでコントロールできるようなもので自分の幸せとか他者の幸せっていうのを、世界の幸せっていうものを、かたち作ろうとたぶんしてないんですよ。
ヒツジという無垢なっていうか、無垢というかバカというか、そういう計算ができないもの、善悪の彼方にある存在、そういうものと共に暮らしていくっていう生き方っていうんですか、それこそが「丁寧に生きる」っていうことなんですよ。
「こんなふうに生きればいい」っていうような何か基準があってそれに行くわけではなしにね。だからヒツジって味方になるか敵になるか分からないん存在なんですね。自分にとって本っ当に大切なバラを食べちゃうかもしれない。でも自分の星にとって最大の恐怖であるバオバブを食べてもくれるんですよ。
敵か味方か分からんようなヒツジを連れて帰る。つまり、自分だけで何とかするっていう生活から、ヒツジと共にバラと暮らす生活を選んでいくんですけど。そこにやっぱなんか意味があるんじゃないかなあと僕なんかは思うんです。
A:なんかお話を聞いて、宗教とか信仰に似てるなあって。そのヒツジがハイヤーパワーで、なんか自分ではコントロールできない、どっちに転ぶか分からないけど、それを信じればいいことがあるかもしれないし、でも、なんだ、どっちに転ぶか分からないみたいなところが。あとね、何ですかね、なんかその、私、大学時代、仏教勉強してたんですけど、なんか親鸞とか死ぬまで迷ってるんですよね、死の直前ぐらいまで。でなんか釈尊も、なんか悟ってからも希死念慮[*17]に度々かられて、たぶん過敏性大腸症候群だと思うんですけど、
[*17] 希死念慮:死にたいと願うこと。
西川:下痢で死ぬ、
A:
しょっちゅう下痢して。死ぬ時も、変なもん食って下痢して死ぬんですけど。で、死の直前にもやっぱり希死念慮っていうかなんか、マーラっていう悪魔が度々現れて、「もういい加減死ねよ」みたいな感じの誘惑をするんですよね。まあそれを退けて生きていくんですけど。
悟ったあとも、死の誘惑が消えるわけではなくて、まあそれに対してちゃんと退けていくことはできるけど。やっぱり悩んだりしても、んー、悩みのあまりに死ぬとかいうことはなくなるけど。まあ悟りとか、信仰的な生き方って、苦しみとか悩みがなくなるわけじゃないんだな、みたいなの、その大学時代思った経験があるんですよね。
西川:
うーん。それこそ死の話ですけど、『星の王子さま』って、死についてやっぱり否定的ではないですよね。「死んじゃいけない! 何が何でも生きるんだ!」みたいな思想がない。そういう思想はありません。だからある意味で危ない本だと思います。
読み方によったら「命よりも大切なものがある」っていう思想の持ち主ですから、サン=テグジュペリは。うん。「死ぬことが何だ!」っていうとこがある。まだここまでにはないけど、もうちょっと後ろで「喉が渇いてることが何だ、死ぬことが何だ」「そんなことはどうだっていい」みたいなセリフを吐くとこありますけど。うん。
ともあれ、いわゆるアメリカ的な成功物語「最初はひどい目にあったけど一生懸命努力していったら、報われてちゃんと成功したぜ」みたいな話には本当になってないです。
8時半になりましたので、今日はまあこれぐらいで終わりたいと思います。
(第7回終了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
