
世界最大の英語教育学会IATEFL(転載記事)
みなさん、こんにちは!
Pearson ELT Teacher Awardを受賞した弊社嶋津が4月初旬に行われたIATEFLという国際学会に参加しました!
帰国した嶋津に学会についてELTインターン横井が突撃取材してきました◎
英語教育の世界で名だたる著名人がスピーカーとして登壇された国際学会。
どのような方がいらっしゃったのか。
そこで嶋津は何を聴き、何を伝えたのか、色々と聞いてきました♪
インタビューの様子をご覧ください☆

横井:学会お疲れ様でした!はじめに、今回嶋津さんが参加されたIATEFLとは何ですか?
嶋津:IATEFLとはInternational Association of Teachers of English as a Foreign Languagの略称で、1967年に創設された英国で毎年春に開催される英語を外国語として教える教員や教育関係者のための国際学会です。今回は毎朝5人のPlenary Speakerが一人ずつ3000人のオーディエンスが入る大ホールで行う講演会と20個以上の部屋でそれぞれ行われたプレゼンテーションやワークショップの二段構成でした。Plenary Speakerは大学教授や英語教科書の著者などの著名人です。

横井:50年以上の歴史のある学会なのですね!登壇者は著名人ばかりのようですが、どのような人が学会に出席しているのですか?
嶋津:参加者は主に大学院生から現役の英語教員、大学教員、教育企業の方々や出版社の方々です。
横井:参加者も幅広いのですね。学会期間中にはどのようなお話がありましたか?
嶋津:最先端の英語教育事情は勿論、最近流行りのテクノロジー(ARやAI)を使った教育事例、脳科学や心理学を応用したマインドフルネスのワークショップなど英語教育の一線を超えた議論が盛り上がっていました。
横井:英語教育だけではないのですね!面白そうですね。嶋津さんご自身にはどのような学びがありましたか?
嶋津:英語教育に関しては出尽くされている感があり、斬新な研究結果は少なかった気がします。むしろ英語教育の枠組みを超えた教育全般に関する問題意識が高まっているように感じました。Plenary Speechでも話題になったのが世界で共通して起きている教員研修の問題。大学教員の教育能力を高めるための実践的方法(FD: Faculty Development)と同様の文脈で使われる個人の能力開発(PD: Professional Development)というものがあります。PDの大規模調査で分かった教員研修の問題点としては以下のような現場の声が挙げられていました。
・教室現場と掛け離れている
・短すぎる
・フォローアップがない
・講義が多く、作業が少ない
・時代遅れで廃れている
・レベルが低すぎる
・応用できない
・同僚と話す時間がない
・導入の際のサポートがない
横井:教員の教育能力の向上に関しては日本でも注目を浴びているものですね。この問題はどういう風に変えていくべきなのでしょうか。
嶋津:学校現場での教員研修はどうしても単一的になってしまい、革新的な要素は排除されてしまっています。これが新しいものを受け入れない保守的な組織になってしまう原因になっています。PDにおいては学校や組織だけではなく、教員一人一人の意識にも問題があると言えます。
Teachers are good at routinizing.
「教員はルーチン化するのが得意=教員は同じことを繰り返すのが得意」
これは講演の中で印象的だったフレーズです。
教員のPD参加率は10%に留まり変わろうとしない教員が大多数なのだそうです。学校を変えるためには教員のマインドセットから変えていかなければならないということが言われていました。

横井:ところで、嶋津さんはIATEFLになぜ出席していたのですか?
嶋津:IATEFLには去年も参加しましたが、今回はピアソンに招待して頂き、IATEFLでの受賞スピーチのため出席しました。通常であれば参加費£265に宿泊費や交通費などがかかりますが、今回は東京の自宅から学会会場まで全て手配して頂き、なんと食事代に加えお小遣いまで頂いてしまいました。
横井:お〜とても良い待遇だったのですね!!受賞スピーチではどんなスピーチをされたのですか?
嶋津:受賞スピーチではまず日本の英語教育の現状と未来、今取り組んでいる英語教育プロジェクトについて話しました。日本を含むアジア諸国ではまだ文法訳読式が主流で机上の成績で評価されてしまっている現状、また僕自身の海外大学生活を通して痛感した日本の英語教育に欠けている技能、そしてその問題を打破するためのタクトピアのプロジェクトを紹介しました。
横井:なるほど!受賞スピーチ後どのような反響がありましたか?
嶋津:まず導入で「私は日本の英語教育の被害者です。」と大胆なフレーズから始めたこともあり、たくさんの方から興味を持っていただきました。スピーチ後にはタクトピアのパンフレット100枚全て皆さんにお渡しすることができたり、アジアで教授経験のある先生方やアジアの英語教育を専門とする方々にたくさん名詞をいただいたり、多くの方と関わりを持つことができました。アジアでもキャンプをやってみたいと言う問い合わせもあったので、今後はタクトピアの英語キャンプをアジアでも展開していける可能性が見えてきました。
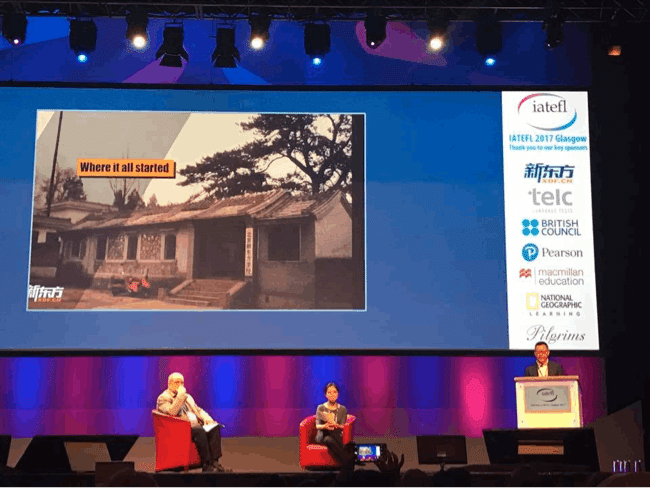
横井:たくさんの方に興味を持っていただいたのですね!日本だけでなく、アジアでもネットワークが広げられたのは素敵ですね!学会全体を通して一番興味深かったことは何ですか?
嶋津:今回のプラチナムスポンサー(学会に一番出資している会社)が中国最大の英語塾「新東方(New Oriental)」だったことです。首からぶら下げる登録証も会場のスタッフも新東方による運営で行われていました。至る所で中国語が飛び交っていて、中国がこの英国の教育市場に入ってきていることを実感しました。

横井:中国企業の成長や参入を身を以て実感したのですね!!他に何か、学会中の面白いエピソードなどはありますか?
嶋津:英語教育界の大物有名人Jim Scrievener(Learning Teachingの著者)と17年以上中国で英語を教えてきたMat Clarkによるトークです。主に1967年に英国人により出版された伝統的な英語教科書が今でもベストセラーになっている中国の英語教育事情についてでした。最新のELT教材が全然売れない理由として中国と西洋での’fun’の定義が違うことを指摘していました。
西洋人は生徒同士がインタラクティブに会話するアクティビティを’fun’と定義するのに対し、中国人の生徒はそれを’fun’と定義していない。西洋の教材をローカライズせずに使うのは賢明ではないということを議論していました。やはりどんなに西洋のものが優れていてもローカルに標準を合わせられなければ需要と供給のバランスをとることは難しいと感じました。

横井:確かに!ローカルな価値観を無視して、そのまま”ヨソで良いもの”を持ってきても失敗に終わるというのはとても納得です。学会には様々な著名人や業界人がいらっしゃったようですが、嶋津さん自身はどのような出会いがありましたか?
嶋津:ピアソンの受賞の件もあり、たくさんの方々に声をかけて頂きました。特に嬉しかったケンブリッジ大学出版の編集者や著者の方々にお誘い頂き、タクトピアのプロジェクトに非常に興味を持って頂けたことです。現在日本のケンブリッジ大学出版とコラボさせて頂いていることもあり、英国のケンブリッジ大学出版の方々にパーティーやランチにお誘い頂き、日本の英語教育の話で計5時間近くいろいろな方々と盛り上がりました。ちなみに、ケンブリッジ大学出版による未発売のPronunciation in Useも頂いてしまいました。*タクトピアオフィスに置いてあります。


横井:英語教育に関する熱い議論が交わされたのですね。個人的に会えて一番嬉しかった人は誰ですか?
嶋津:英語教育界の神様でなんと僕と同じ誕生日のDavid CrystalやELT Teacher Award審査員長のDavid Nuan、そしてベストセラーPractical English Usageの著者Micheal Swanなど写真でしか見たことのなかった方々にお会いできて大変光栄でした。そして、オックスフォードでお世話になった先生やCambridge CELTAのクラスメイトやチューターとも久々に再会したのも嬉しかったです。


横井:最後に一言お願いします。
嶋津:今回招待頂いたPearsonの方々には至れり尽くせりの待遇をして頂きました。このような名誉ある賞を受賞でき大変嬉しいですが、これは一つの通過点に過ぎません。日本の英語教育には課題が山積みです。Plenary Speechにあったように学校組織を変えていくことは非常に難しく、チャレンジの連続です。今後は日本全体、アジア全体の英語教育をより良いものにしていけるよう、タクトピアチーム全体で初心を忘れず精進していきたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
