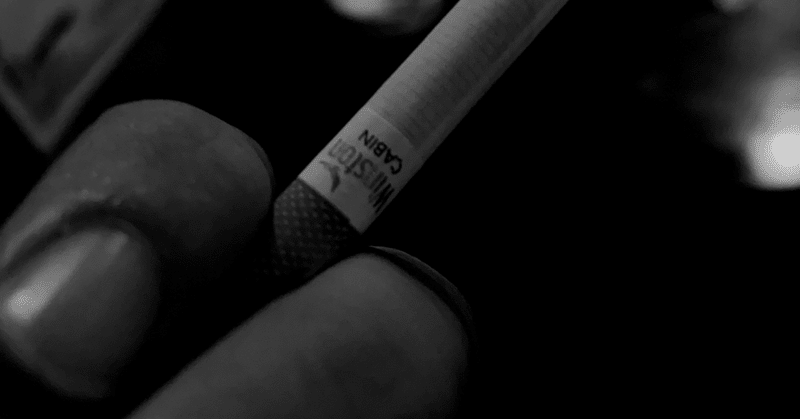
煙草と文化について
僕は珈琲屋ですが煙草を吸います。
現在は水煙草のお店で珈琲を出しています。
煙草を本格的に吸い始めた理由は、珈琲を飲みながら煙草を吸う人を見て「喫煙者が求める珈琲の味」を知りたくなったからです。
“札幌の深煎りは喫煙率の高さから発展した”と仰る方もいます。煙草を吸うと繊細な味は取りにくくなります。現在のスペシャルティコーヒーで扱われるような1ハゼ周辺の珈琲の繊細さは喫煙者には不向きなような気もしています。
やはり煙草には質感がしっかりとした珈琲が合うと思っています。そうなるとやはり深煎り、淹れ方はネルになっていく。
ただ、生豆も発展していますから、質感の強い中煎りで煙草と合うと感じるものをこれまでにありました。
僕が煙草を意識し始めたのは、喫煙可能なお店でスペシャルティを扱うお店が少ないから。
むしろ毛嫌いしている珈琲屋も多いです。
だからこそ、喫煙者のための焙煎を突き詰めればガラパゴス的進化のような味づくりができるのではないかと考えました。
喫茶全盛期、喫茶店を中心に発展した文化があります。やはり利用する人が多ければ多いほど、新たな関係性が生まれ、新たな発展があったということだと思います。
また、喫茶店というシステムと煙草というものがより文化の発展を促したと僕は考えます。
喫茶とは珈琲一杯で居座れる場所であるべきだと思ってます。
社会的身分や性別等を問わず、喫茶というものは珈琲一杯で居座れる場所だったと考えます。
昔は喫茶は男中心だったようですが。
長く居座れば、特殊な関係性が生まれやすくなります。特に性質が違う人同士が接触することでより魅力的な関係、文化の発展に繋がる気がしています。
そういう箱として喫茶はよく機能したのではないでしょうか。
若者の間で水煙草というものが流行っています。その怪しさや、それぞれのお店の内装の尖り方、もちろん香りの良さ、水煙草にはさまざまな魅力があります。
その中で僕が感じる水煙草の最たる魅力とは“長く居座れること”と“会話のテンポが落ちること”ではないかと考えます。
水煙草は基本的に1時間以上、香りが持続します。つまり、水煙草を注文すれば1時間以上の席時間は強制的に確保されるわけです。
また、会話中に水煙草を吸うことによって、会話のテンポが落ちます。
僕はこの会話のテンポというものが、人間関係において最も重要なことではないかと思うのです。
僕は会話のテンポが遅いです。それは頭の回転が遅いことを意味するのだと思います。
会話のテンポが食い違うと、コミュニケーションがうまく行きません。会話の速い人と僕はなかなかうまくコミニュケーションが取れない。ラリーがうまく行きません。
しかし、水煙草を吸っていると、吸う時間で時間が稼げるわけです。相手が水煙草を吸う時間。自分が水煙草を吸う時間。会話のテンポ間というものが強制的に遅くなる。遅くなることをよしとすることになる。
そうすると、ある程度基本的なテンポ感が違う人であっても正常なラリーができるようになるわけです。僕は水煙草の魅力はここにあるのではないかと考えます。
そしてこれは、紙煙草にも言えることです。
長く居座れること。会話のテンポが抑制されること。これは、異なるタイプの人間をつなげるためのとても良いフレームワークではないのかなと思います。
これはかつての喫茶、そして現代の水煙草店に共通して言えること。これによって異種の人間が関わり合い、文化が発展しやすい環境にあるのではないかと思っています。
煙草は百害あって一利なしと言われますが、身体的な健康よりも、心理的な健康を重視する人にとってはあまり関係のないことです。
もちろん体の不調は心理にも影響しますし、副流煙による周囲への迷惑もあります。
その一方でコミュニケーションにおいては、有用に働いていた可能性もある気がしています。
現職場で起こる人間関係は、それはそれは面白いものばかりです。
今後僕が喫茶を開くとき、そこが喫煙可能か禁煙かはわかりませんが、文化が生まれやすい喫茶のシステムというものは踏襲するべきだと考えています。
喫茶とは何だったのか。
それを今日も考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
