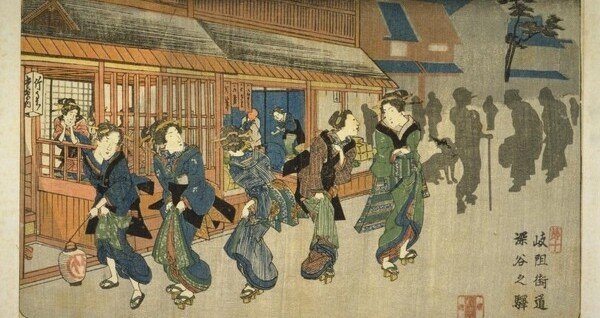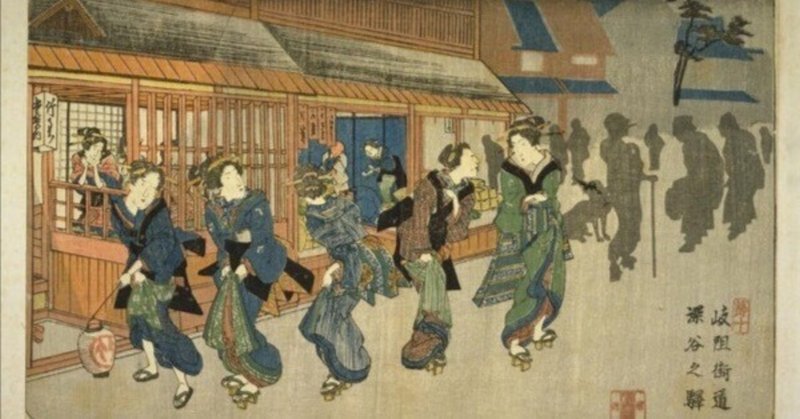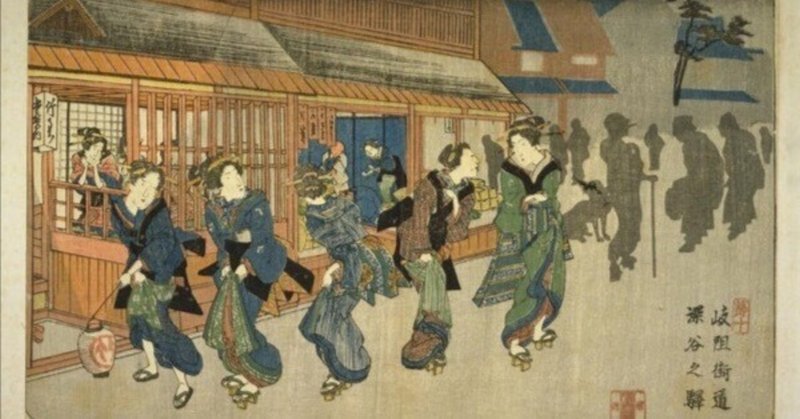2022年6月の記事一覧

みんな、ThresholdやWaystageを知らないor忘れている — そして、みんな話題についての言語技量も知らないor忘れている
CEFRを旗印とする?現在のCouncil of Europeによる外国語教育改革の運動は、1970年代から始まっています。当初はユニット・クレジットシステムの開発がめざされました。その際に、ガイドラインとなったのが、vanEk and AlexanderのThreshold levelとWaystageです。そして、Threshold levelとWaystageは、2020年のCEFR Companion volumeでも、ちゃんと!?言及されています。 そして、この

文化庁の日本語教育の参照枠と標準的なカリキュラム案を再考する② —「実際的な生活活動の領域」と「人とつながる活動の領域」という2領域を
サマリー Ⅰ.「生活」の中に「実際的な生活活動の領域」と「人とつながる活動の領域」という2領域を設定する。 Ⅱ.カリキュラムとしては「人とつながる活動」が基礎となり、それに徐々に「実際的な生活活動」を入れていく。 昨日の発信の続きです。今回は、昨日の提案を新たなカリキュラムの指針としてまとめると!という話です。 1.「実際的な生活活動の領域」と「人とつながる活動の領域」という2領域 従来のカリキュラム案では「生活のために必要な生活上の行為」のみが採り上げられています。

文化庁の日本語教育の参照枠と標準的なカリキュラム案を再考する① — 「生活」の中に「人と交わってお互いのことを話し人生を分かち合うこと」が入っていない!
文化庁は、日本語教育の参照枠と標準的なカリキュラム案の路線で、いよいよ教育モデルの策定を進めようとしています。しかし、これまでの参照枠でもカリキュラム案でも、そこで言われている「生活」は実際的な必要を満たす生活上の行為等のみに限定されており、「生活」の中に「人と交わってお互いのことを話し人生を分かち合うこと」が含まれていません。つまり、生活上で対応しなければならない実用の日本語ばかりが注目されて、人と交わってお互いに自分のことを話して人生を分かち合いながら生きていく交友の日