
日本政府の国連恣意的拘禁作業部会に対する“異議申立て”の不当性を明らかにする弁護士チームによる声明
弁護団の了承を得て、転載します。
日本政府の国連恣意的拘禁作業部会に対する“異議申立て”の不当性を明らかにする弁護士チームによる声明
法務大臣は、2021年3月30日、昨年9月28日付けで送付された国連恣意的拘禁作業部会による難民申請者2名の入管収容に対する意見*1(以下、「同意見」という)に対して、日本政府が“異議申立て”と詳細な事実関係に関する情報提供を行ったと発表した。しかしながら、日本政府のこの対応が正当性を有しないことは次のとおりである。
1 そもそも“異議申立て”という制度は国連恣意的拘禁作業部会の手続に存在しないこと
日本政府が国連恣意的拘禁作業部会の意見に対して“異議申立て”を行ったのは、カルロス・ゴーン氏の刑事勾留に対する同作業部会の意見が出たときが最初と思われる。しかしながら、そもそも同作業部会の意見に対する“異議申立て”という制度は、同作業部会の手続には存在しない。
同作業部会が同意見の中で、日本政府に対して要請した「フォローアップ手続」は、2名の通報者に対して補償を行ったかどうか、権利侵害に関する調査を行ったかどうか、同意見に沿って法改正や実務の変更を行ったかどうかなどを、6か月以内に同作業部会に対して報告することであった(同意見パラグラフ107)。ところが、この6か月の期限が過ぎようとする直前に、日本政府が3月27日付で同作業部会に提出したのは、「フォローアップ手続」として想定されていない“異議申立て”であった。
同作業部会の手続は、日本も理事国を務める国連人権理事会において定められたものであり、日本政府においてはこの手続を尊重し、当然これに従うべきである。とりわけ日本政府は、国連人権理事会の立候補にあたり、「国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)や特別手続の役割を重視。特別報告者との有意義かつ建設的な対話の実現のため、今後もしっかりと協力していく」との立場を表明してきた*2。それにもかかわらず、同手続に従わずに、手続に定めのない“異議申立て”を行ったことの正当性は見出しがたい。
2 事後的な“詳細な事実関係に関する情報提供”も手続に従ったものではないこと
日本政府は今回、“異議申立て”と共に“詳細な事実関係に関する情報提供を行った”と発表したが、これも同作業部会の手続に従ったものではない。
同作業部会は、通報者側と国側のそれぞれから事実関係や法律について情報提供を受けた上で、意見を決定する。ところが、日本政府は、昨年4月に同作業部会から通報者の2人に関する情報提供を求められた際に、個人情報であるため法律上提供できないとして、2人に関する事実関係の回答を一切拒否した(同意見パラグラフ42)。このような日本政府の姿勢については、同作業部会から、手続に協力すべき旨の批判がなされていた(同意見パラグラフ73)。
今回、日本政府は、同意見の決定前に同作業部会から情報提供を求められたのにこれを行わず、同意見が出た後になって事実誤認を主張しつつ“詳細な事実関係に関する情報提供”を事後的に行ったものであり、明らかに不当である。
それどころか、昨年の同作業部会からの情報提供の要請に対しては、個人情報であるため法律上提供できないと拒否しながら、今回の“異議申立て”にかかる今年3月30日の報道発表資料*3においては、通報者の犯罪歴などを含む個人情報を、同作業部会に対してのみならず、広くインターネット上で一般公表している。これが矛盾した態度であることは明白であり、このような恣意的な個人情報の取り扱いにより通報者の社会的評価を貶めることには何ら正当性を見いだせない。
3 同作業部会の意見に事実誤認はないこと
同作業部会の意見の内容から明らかなとおり、同意見に事実誤認はなく、日本政府の主張は失当である。
(1)そもそも、同作業部会の意見の骨子は、日本の入管法には退去強制令書に基づく収容について期間の上限の定めがないこと(同意見パラグラフ91)、収容の必要性・合理性を個別に考慮せずに退去強制令書に基づく収容がなされていること(同意見パラグラフ75、76、90)、司法審査によらず行政判断によって収容がなされていること(同意見パラグラフ75、80、81、89)について、世界人権宣言及び自由権規約に違反すると指摘したのである。この点について、事実誤認がないことは明らかである。
(2)なお、日本政府が報道発表資料で事実誤認と主張している4(1)「両名の収容は、以下の個別の事情を適切に評価し、仮放免の判断を慎重に行うべき事情があるとして、その収容の要否が判断されたものである」については、上記のとおり同作業部会の意見は、収容の必要性・合理性を個別に考慮せずに退去強制令書によって収容を行っていることに加えて、仮放免については行政府に無制限の裁量を与え(同意見パラグラフ75)、収容の理由を本人に告げていない点(同意見パラグラフ76、79)について恣意的だと指摘しているのであって、この点に事実誤認はない。日本政府が報道発表資料で主張する点も、繰り返しなされた収容の必要性・合理性を裏付けるものではなく、むしろ、行政府が無制限の裁量をもって仮放免の許否を決定したことを示すに他ならず、やはり事実誤認の理由とはならない。
(3)次に、報道発表資料の4(2)「作業部会は、両名が行政上又は司法上の審査・救済の機会なく収容されていた旨の意見を表明しているが・・・」については、同引用は不正確である。正確には、同作業部会は「司法による効果的な監視とコントロール」(同意見パラグラフ80)、「収容に異議を唱えるための有効な救済手段」(同意見パラグラフ92)がないと指摘しているのである。同作業部会は、「収容に不服のある者は、・・・各行政処分の取消しの訴えを提起することができる」(同意見パラグラフ49)という日本政府の情報提供や、「時宜を得た有効な司法的救済手段は利用できない」「裁判所が判決を出すまでには1~2年程度かかると思われる」(同意見パラグラフ38)という通報者の情報提供を考慮した上で、効果的な司法救済手段はないと判断したのである*4。また、仮放免不許可処分について行政手続上の救済手段は存在しない。
従ってこの点にも事実誤認はない。
(4)報道発表資料の4(3)「両名の収容は・・・難民認定申請を理由とする制裁でも差別的な対応でもない」については、同作業部会は、これまで複数の国連人権機関が、日本の難民認定率が異常に低いことや、難民申請者の収容が極めて長期化する傾向について指摘を繰り返してきたにもかかわらず、状況が変化していない点を踏まえて、日本においては難民申請をしている個人に対して差別的な対応をとることが常態化していると評価し、これが通報者2名にも当てはまると述べたものである(同意見パラグラフ94~97)。したがって、難民申請者に対して収容が長期化する傾向があるのは差別的だと評価した同作業部会の意見に事実誤認はない。
4 結語
日本政府の今回の対応は、日本が国連人権理事会の理事国でありながら、同理事会の定めた手続に従わず、国連人権保障システムに非協力的であるという姿勢を国際社会に知らしめたものであり、日本の国際的な評価を著しく低下させるものと言わざるを得ない。
さらに国内においては、同作業部会に対して手続として存在しない“異議申立て”をしたと発表し、政府が恣意的な拘禁をしたという事実から目を逸らさせるために通報者の社会的評価を貶めようとしたが、これは人権侵害の被害者に対して効果的な救済措置を与えるべき国際人権法上の国家の義務*5に違反するものというべきである。
このような日本政府の対応に対して強く抗議すると共に、改めて通報者2名が受けた人権侵害被害に対する効果的な救済を求めるため、本声明を発表する。
2021年4月1日国連恣意的拘禁作業部会入管収容通報弁護士チーム
=====脚注===========
*1 国連恣意的拘禁作業部会意見(A/HRC/WGAD/2020/58)
*2 世界の人権保護促進への日本の参画(和文骨子)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000175307.pdf
*3 令和2年9月28日付け送付の国連の恣意的拘禁作業部会による意見書に対する日本政府の対応http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/05_00008.html2
*4 自由権規約2条3(a)は「効果的な救済措置を受けることを確保すること」を各締結国に求めている。
*5 自由権規約2条3項(a)


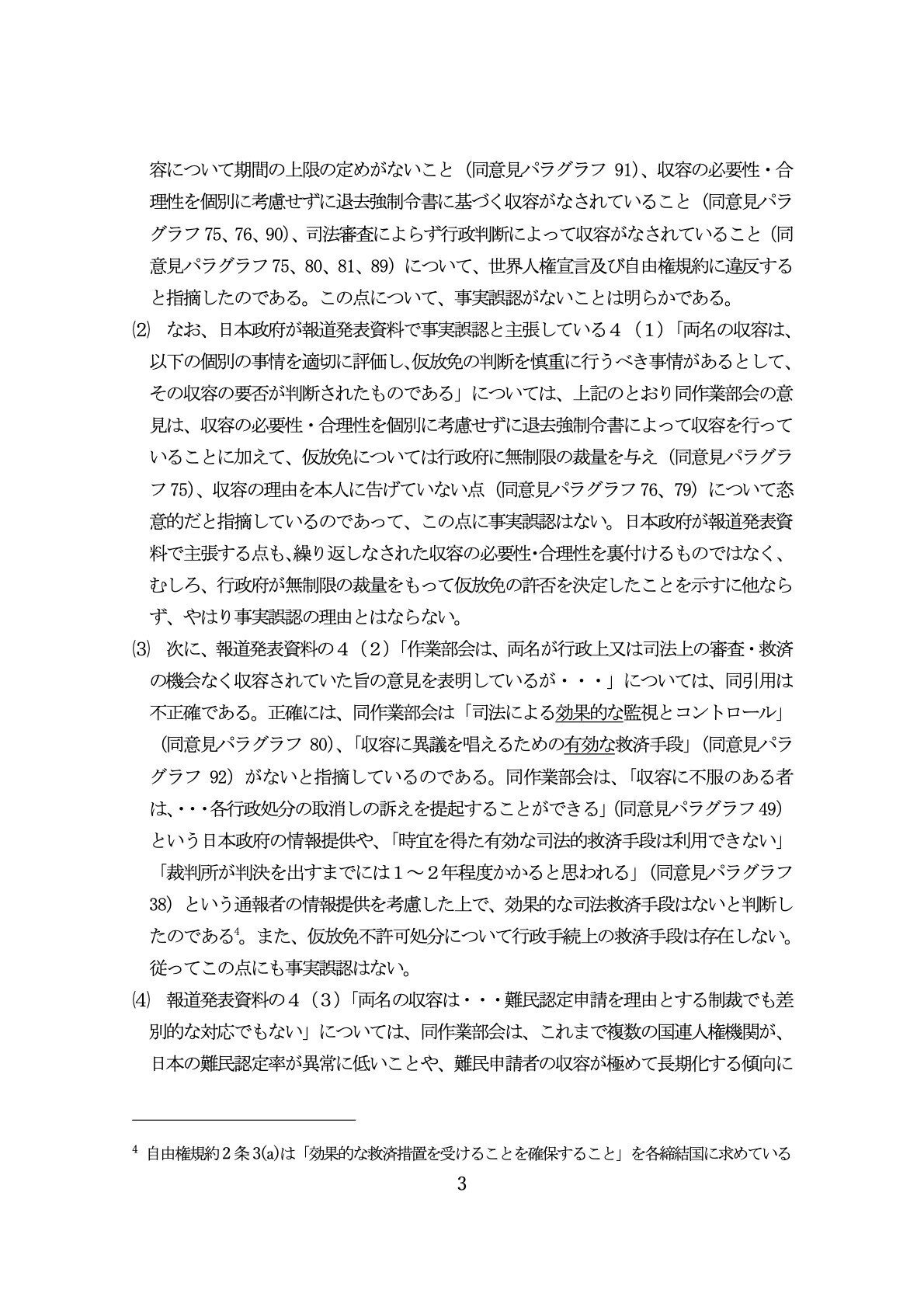

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
