
仮放免中の動静監視に明文根拠なし
安田菜津紀さんの記事でコメントを紹介してもらいましたので、標題の点を少し詳しく。
黒塗りの「仮放免指示」には仮放免中の方の動静監視にかかる記載があるようですが、真っ黒に塗られています。
この件、不開示処分の取消訴訟を起こしましたが、地裁では敗訴。現在控訴中で、7月12日に控訴審第1回期日が予定されています。
遅まきながら、この訴訟中に気づいたのですが、仮放免中の動静監視ができる、明文の規定はありません。入管法ではほかの調査について、ちゃんと条文がありますし、廃案となった入管法で規定がある「収容に代わる監理措置」についても、事実の調査ができるという条文が入れられていました。仮放免だけないのです。
入管は、仮放免取消制度があるのだから当然予定されているなどと主張し、一審判決もこれを是認してしまったのですが、「法律による行政の原理」に反していると思います。
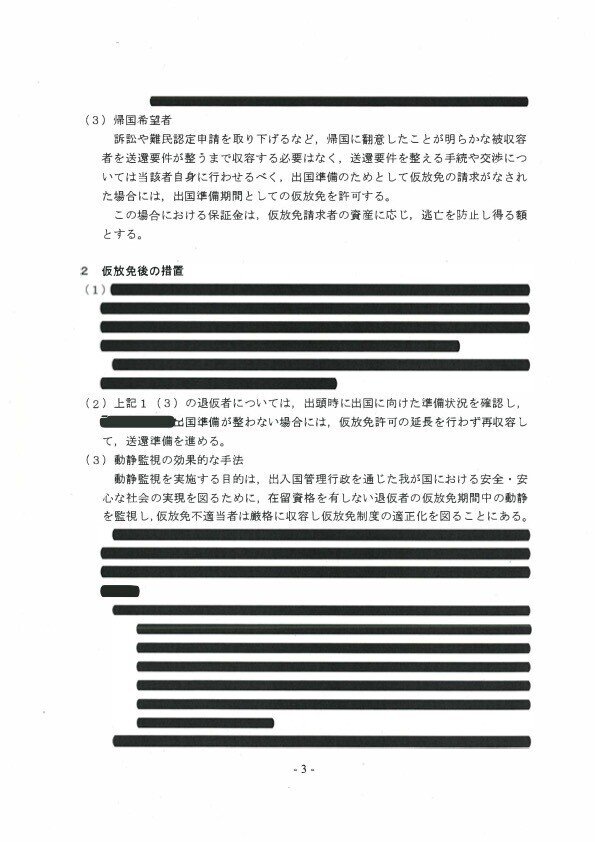


以下は、控訴理由書の一部です。詳しくは以下をご覧下さい。
第2 ①(仮放免動静監視が国の機関が行う事務にあたらないこと)について
原判決は、「入管法54条2項は、仮放免を許可するに当たり必要な条件を付すことができる旨規定し、同法55条1項は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなく呼び出しに応じず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる旨規定していることに照らせば、同法は、仮放免の取消事由等を発見するための調査が行われることを当然に想定しているといえる」として、動静監視が「国の機関(中略)が行う事務」に当たると判断している(原判決13頁「17行目以下」)。
しかし、上記解釈は、「法律による行政の原理」に反し、誤りである(以下、原審原告第4準備書面参照)。
1 「法律による行政の原理」
(1)「法律による行政の原理」は、人々の権利利益の保護のため、行政の主要な部分が国民代表からなる議会の制定した法律によって行われるという原理であり、法治主義の基幹的法理である(甲25・28頁)。
(2)そして、「法律による行政の原理」の内容をなす、「法律の留保の原則」(ある種の行政活動を行う場合に、事前に法律でその根拠が規定されていなければならないとするもの)において、どのような行政作用につき、国会制定法の根拠が必要とされるかは諸説あるが、「今日においても立法実務を支配している」とされる侵害留保説では、国民に義務を課したり、国民の権利を制限する侵害的な行政作用については法律の根拠が必要とされる(ここでいう「国民」には、生活者としての外国人も当然含まれる。)。内閣法11条も「政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることはできない。」としている(甲25・29頁、同32頁)。
2 被仮放免者の動静監視に法律の留保の原則が適用されること
被仮放免者の動静監視は、その「居住実態、生計維持及び被仮放免継続事由の事実関係」に関する動静監視を行うものであるから(原審被控訴人準備書面(2)14頁8行目)、被仮放免者のプライバシーを侵害する行政作用であることは明らかである。したがって、法律の留保が必要な分野である。
3 動静監視に法律上の根拠がないこと
(1)そして、入管法においては、以下のとおり、被仮放免の動静監視以外に対象者のプライバシー侵害に当たる調査については、明確な根拠規定を置いている。
①中長期在留者の情報把握のための調査(入管法19条の37)
②違反調査(入管法27条以下)
③入管法に定める各種処分等のための事実の調査(入管法59条の2。ただし、仮放免許可及び仮放免取消については対象とされていない)。
④難民認定に関する事実の調査(入管法61条の2の14)
⑤入国審査官の調査権限(入管法61条の3第3号。上記①、③、④の調査権限を明記したもの)
⑥入国警備官の調査権限(入管法61条の3の2第2項第1号及び同第4号(前者は上記②の調査権限を、後者は上記①・③の調査権限を明記したもの)
上記のうち、特に入管法59条の2の規定は重要である。
同条は、
・在留資格認定証明書の交付(同法7条の2第1項)
・再上陸のための登録(同法9条8項)
・上陸特別許可(同法12条1項)
・資格外活動許可(同法19条2項)
・在留資格変更許可(同法20条3項本文)
・在留期間更新許可(同法21条3項)
・永住許可(同法22条2項)
・再入国許可(同法26条1項)
・在留特別許可(同法50条1項)
・難民に関する永住許可(同法61条の2の11)
・在留資格取消(同法22条の4第1項)
という、入管法における各種処分について、入国審査官及び入国警備官に事実の調査をする権限を国会の制定する法律で明確に認めたものである。
もし、被控訴人の主張のように、入管法54条2項及び同法55条の規定の存在から被仮放免者の動静監視権限が導けるのであれば、上記各処分についての根拠条文からも事実の調査権限を導けるはずであるから、入管法59条の2の存在は不要のはずである。しかるに、国会が59条の2を制定したのは、対象者のプライバシー侵害にわたる事項に関するものであるから、国会制定法による明確な授権が必要だったからである。つまり、法律の留保が要請される分野だったからである。
(2)2021年第204回国家に提出された入管法案
そして、2021年第204回国会に提出された入管法案(廃案見込み)では、収容に代わる監理措置の新設が提案されているが、監理措置決定及び監理措置取消し決定のために必要があるときには、事実の調査が出来る旨を明文により定めようとしている(法案44条の9及び52条の7。甲28)。これも、法律の留保が要請される分野であるということからの配慮と考えられる。
さらに、同法案では、上記59条の2についても改定提案されているが、そこにも入管法54条2項及び同55条は入っていない。同条に加えられようとしているのは、仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得(法案61条の2の5)、難民等に関する永住許可(法案61条の2の14)である(甲28)。
(3)そうすると、入管法59条の2で、仮放免許可(入管法54条)及び仮放免取消(同法55条)が除外されているのは(しかも今回の法案でも外されている)、立法者の意思としては、これらの各処分においては、事実の調査を認めない趣旨であったと解するほかない。
(4)この点、原判決は、原審における控訴人の上記主張について、「仮に個々の調査がプライバシー侵害を理由に、任意の調査として許容される限度を超えて違法となる余地があるとしても、仮放免に係る動静監視について、およそ明示的な根拠規定がなければ許容されないと解することはできない。」としているが(原判決14頁1行目以下)、なにゆえ「許容されないと解することはできない」と判断するのか、全く理由が述べられていない。法律の留保が不要とされることについて、何ら合理的な説明がされていないのである。
4 小括
以上から、入管法54条2項及び同法55条の規定の存在から、被仮放免者の動静監視を行う権限があるとする原判決の判断は、「法律による行政の原理」に反し、採り得ない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
