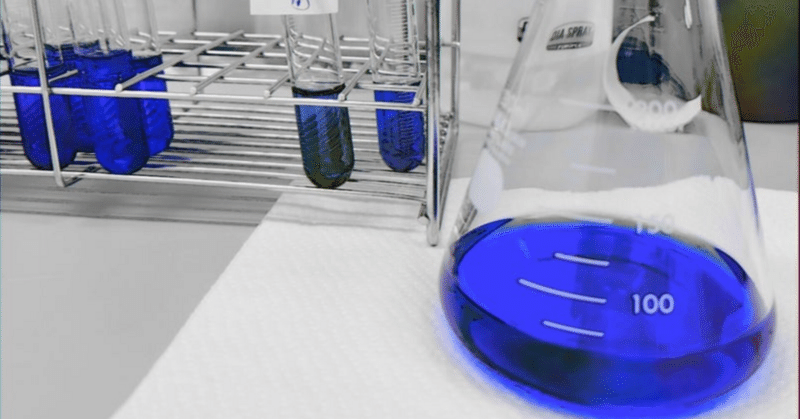
第31話 組織の科学者
いくつもの階段を降り、何枚もの分厚い扉を開けた先。一人の男が厳重に警備された地下の薄暗い一室の扉を開くと、白衣を着た女がこちらにゆっくりと歩いてきた。
「ずいぶん遅かったじゃない」
カツン、カツンと固いヒールの音が響く。
「あぁ、いろいろとあってな」
「女物の香水の香りに、首筋のキスマーク…。ふふっ、あんたもレベッカも飽きないわね」
男は慌てて己のジャケットを嗅いだ。
「犬並みの嗅覚だな」
「あら、"組織の犬"って意味じゃ、あんたもおりこうな犬じゃない?」
「フン…」
女はクスクス笑いながら、何も置かれていない大きなテーブルに近寄った。
「さて。ボスから頼まれてた例の薬が完成したわ」
そして小瓶を3つ並べた。
「効果と証拠の消え具合は保証するわ。これ1本で40万人以上殺せる。でも、解毒剤は1人分だけ。分かった?話は以上よ」
言うだけ言うと、女は奥の部屋に戻っていった。
残されたのはテーブルの上の小瓶。3つ。形も大きさも色も一緒の、全く同じ小瓶が、3つ。
「えっ?あ、ちょちょちょちょっと待って!!」
「何?」
「え、どれが毒のヤツ…?」
「…はぁ?」
「いや、その、どれがどれか分かんないじゃん。ラベルも何もないから…」
「あー、もう!」
女はカツカツとヒールの音を立ててテーブルまで戻ると、横一列に並んだ瓶を一つずつ手にとって、
「だから…。これが毒!」
カンッ
「これが解毒剤!」
カンッ
「こっちが毒で、」
カンッ
「こっちが解毒剤!」
カンッ
「はい!毒はどっち!?」
「え…っと、こっち?」
恐る恐る、女が右手で持った方の瓶を指した。
「…そう。できるじゃない。じゃ、私はこれで…」
女は踵を返して奥へ去ろうとした。男は、今度は女の白衣の袖をつかんでそれを引き留めた。
「だから、何?毒はそっち。今、当てたじゃない」
「今当てただけだったらここから出た瞬間に忘れるのが目に見えてる。…それで俺がしくじったら、お前も道連れになるぞ」
女は男の目をキッと睨み付けてから言った。
「好きでもない男と一緒に地獄に行くなんてこっちから願い下げよ」
女はテーブルに両手をついてため息を一つ。そして右の瓶を指した。
「いい?一回しか言わないから、その陳腐な頭に刻み込んでちょうだい。毒はこれ。持ってみて」
そう言って右の小瓶を差し出す。恐る恐る受けとる男。
「さっきから私が何回も持って振り回してるけど、何も起きてないでしょ?ちゃんと蓋できてるから安心しなさい。いい?毒は軟膏。塗り薬。瓶を振ってもチャプチャプ音が鳴らなければそれが毒の瓶」
「…なるほ……軟膏?え、待って?毒って塗り薬なの?」
「そうよ。そうでもないとこんな小さい入れ物に10万単位の人間殺せる薬入れられるわけないでしょ?」
「いや、まあそうかもしれないけれど…」
「何よ。何か文句あるの?」
「何で塗り薬にしたの?」
「それは…」
女は言葉を濁した。
「まぁ、何となく、よ。ボスの誕生日ケーキ作ったときの生クリームが残ってたから、混ぜてみたら、何か、できた」
「生クリーム!?え、生クリームで塗り薬できるの!?」
「知らないわよ!ただ、ボスに報告したら、「お前らしくていいと思うー」って言われたから。じゃあ、いいかーって思って」
男はため息をついた。
「直接肌に塗らないと意味ないからね。服に付いたら色落ちするから必ず洗剤で洗うこと。もちろん、手袋ちゃんとするのよ?」
「…分かった」
塗料の説明書きみたいだな。男はそう思ったけれど、声には出さなかった。
「じゃあ、解毒剤は?」
「解毒剤はこっちの、チャプチャプ鳴る方」
女は左側の小瓶を差し出した。
「これは点眼薬」
「点眼って、目薬?」
「そうよ。ここに入っている量を余すことなく左目にさしきること。右目にさしたら死ぬからね」
「え、これ全部さすの?溢れないか?」
「そんなの私の知ったことじゃないもん。あ、さっきも言ったかもしれないけど、解毒剤は一人分しかないからね」
「これ、一人分なの!?え、一人分の、しかも片目分の量がこんなにあるの!?何で?」
「何となく。ボスが使ってる化粧水入れてみたら何か、できたから…」
化粧水を入れようと思ったきっかけが気になったが、上司であり組織を統べる人物・ボスが関わっているとあって、男は何も聞かなかったことにした。
「私は、言われた薬を作っただけ。詳しい計画とかそんなの知らないし知ろうとも思ってないわ。だから、あんたがこれをどう使おうと知らないから。…まあ、万が一毒に触れたら私のところに来なさい。24時間以内なら助けたげるから」
女はそう呟くと奥へ去っていった。
残された男と、3つの小瓶。
「待て!」
男が叫んだ。
「もう1つ瓶があるな」
真ん中の瓶を持って振った。カラカラカラ…と音がする。
「これは何の薬だ?俺がボスから聞いたのは4,50万人規模で殺せる毒薬と、その解毒剤だけだ。もう1つの、これは何だ?」
女は足を止めた。フッ…と笑って、
「それは別件であなたに預けるつもりだったの、うっかり忘れてたわ」
「俺に預ける?」
「ええ。レベッカに頼まれてた薬の調合ができたから、あなたに預けておこうと思って」
男は短くため息をついた
「じゃあ、直接彼女に渡せばいいじゃないか」
「イヤよ、面倒くさい。どうせ今日もレベッカのところに帰るんでしょ?その時に渡せばいいじゃない。てか、その時に使ってあげて。効果は実証済みよ」
「だいたい、何の薬だ?」
「ただのニキビ薬よ」
「ニキビ薬?」
男は再び瓶を振る。
カラカラカラ…
「ニキビ薬がカラカラ鳴るって…錠剤か?」
女はニヤリと笑った。赤いルージュが開く。
「いいえ、座薬タイプよ」
<END>
2020年12月27日
R-1グランプリ2021 1回戦 より
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
