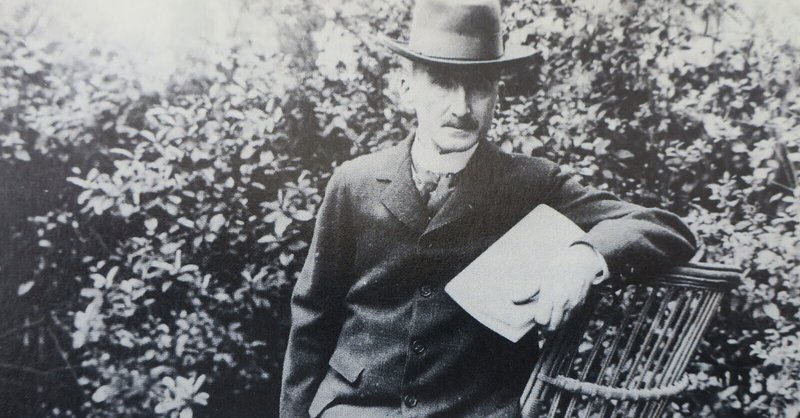
〔直観〕のパラドクス カントに挑戦するベルクソン
『純粋理性批判』を読んだベルクソンは、自らの哲学をカントの超越論的感性論を批判することからはじめた。
カントは〔直観の公理〕を、以下のように定義している。
空間および時間における直観としてのすべての現象を〔量〕の概念のもとに包摂し、そしてこの概念が、直観における多様なものをアプリオリに、規則に従い綜合的に統一するのである。
『プロレゴメナ』
この話は以下の知識を前提とする。
さて、我々に与えられた直観は、この直観に関する判断形式を規定する〔悟性概念〕のもとに包摂されねばならない。
するとこの概念は、与えられた直観の経験的意識を連結し、経験的判断に普遍的妥当性を与える(感官の本分は直観、悟性の本分は思惟にあり、いくつかの表象を一つの意識におい統一したものが判断である)そのような概念が即ち〔純粋悟性概念〕である。
例えば、『直線は二点間の最短の線である』という原則は、直線が〔量〕の概念のもとに包摂せられることを前提としている。
この場合〔量〕という概念の起源は直観ではなく、まったく悟性のうちにあり、「直線の直観」を、この直観に関して下される判断に適するよう、純粋悟性概念としての〔量〕に関し、規定するに役立つのである。
つまり直観の公理は、空間および時間における直観としてのすべての現象を〔量〕の概念のもとに包摂することである。
おそらくベルクソンは、意図的に〔直観〕という言葉をカントのそれに対立させ、逆説的に使用しながら挑戦する。
先ずベルクソンは〔直観〕を〔量〕ではなく〔質〕として捉えているのだ。
ベルクソンの問題(内的生活の領域)入る前に、我々はなぜベルクソンがそのような問題を提出したのか? そこを考えてみなければならない。
図らずも、カントが形而上学の限界と科学の土台をアプリオリに規定したことにより、十九世紀の科学技術は飛躍的に発展した。
とくにベルクソンが生きた十九世紀後半から二十世紀前半は、実証科学の時代であった。
実証科学とは、測定・反復可能な〔量〕を観察し、結果に基づき理論を作る方法である。
ベルクソンは、実証科を否定したわけではない。
それどころか、ベルクソンほど科学を重じる哲学者はないのではないか。
数学や物理や生物学を土台としながら、生命の本質に迫る哲学者がベルクソンである。
それでは、ベルクソンの批判する科学とは何か?
結論から言うと、ベルクソンは実証主義的な性格をもつ人間(人格)を批判しているのである。
「哲学者の役割は生起すべきものを規定することにある」とカントは言い、自らの哲学を実践の領域に発展させたが、十九世紀から二十世紀の世界はもっぱら実証科学により繁栄し、人間までもが科学により存在を規定されるようになっていた(我々はそれをオーギュストコント由来の社会学から実証せずとも、あのマルクス科学をもって知ることができる)
この人間の科学的性格、科学的生活態度は、人間にとって決定的な或る問題から眼をそらせていった。
「単なる事実は、単なる事実人をしかつくらない」とナチス禍のドイツでフッサールが主張するように、人間にとって決定的な問題とは、我々の生命(エラン)にどのような意味があるのかという問いであり、我々が自らの人生に対し、如何なる態度をとるべきかの、自由な決定である。
これはソクラテス以来の、即ち全ての哲学的な問いである。
イオニアの自然学者たちが「ソクラテス以前の哲学者」と呼ばれる所以は、元来科学(フィジック)と哲学(メタフィジック)は対を成すものであり、十七世期のニュートンにあっても、科学を建設することは哲学することであった。
しかし十八世紀にカントが、科学が形而上学の領域へ侵入することを全面的に禁止したため、科学と哲学の道は分れ、哲学は死に、科学は方法、即ち実証科学という技術に成り下がった。
科学者達は方法の意味を問う必要をなくし、たんなる方法の技術者となった。
計測可能な領域において客観的実在性をもつ科学は学問として重んじられ、我々の生活世界は技術のお蔭で驚くほど豊かになった。
ところが、我々の人格は薄くなっているのだ!
「生起すべきもの」を問うことを忘れた近代の行き着く先は、二発の原爆だった。
持続
科学は或る対象を〔量〕という悟性概念に基づき一定の記号に変え、世界の一部を切り取る。
しかし、ベルクソンはあえて科学が進まなかった道、即ち〔質〕という世界を自らの哲学の対象とし、最初の学位論文『意識に直接与えられているものについての試論』(英訳題:時間と自由)を書いた。
ベルクソンは言う、持続のうちで考えられる〔質〕の世界にあるものは、我々の意識に与えられた純粋な記憶の経験であり、生の躍動である。
カントの時間論とは、大体以下のようなものである。
私は私の外にある対象を、物自体ではなく、現象として規定し、そこから空間における対象を、時間において規定された私自身という現実的存在が経験的に認識する意識として証明する。すると意識とは〔外延量〕であり、根底に在するアプリオリな直観によって意識されたすべての現象は〔量〕である。知覚とは、経験的意識のことであり、この意識は、知覚において或る時間に零からその都度達した〔量〕まで増大し得る意識〔内包量〕を有する。すると我々は時間を、空間における常時不変なものに関する外的関係における運動(例えば地上の対象に関する太陽の移動)などにより規定することができる。我々の経験的認識の増大や知覚における進歩は、すべて内感の規定の拡張(時間における進展)にほかならない。時間において継起する何か或るものへの移り行きは、知覚を産出することによって時間を規定し、時間は〔量〕であるから、この移り行きは零から一定の度に達するまで〔量〕としての知覚を産出する。我々はこの〔量〕を〔持続〕と名づけてかまわない。先行する時間における現象は後続する時間における現実的存在を規定し、我々は前後の時間の結合における連続性を現象において経験的に認識し、意識において証明する。
それでは、その意識に直接与えられているものとは何か?
これがベルクソンの問いである。
ベルクソンは〔純粋持続〕や〔イマージュ〕という概念をつくり、カントに挑戦した。
先の文章で、カントの以下の発言に注目したい…『我々はこの〔量〕を〔持続〕と名づけてかまわない』
否! とベルクソンは言う。
〔質〕と〔量〕の混同。
時間とは〔質〕であり、その本質は自由である。
我々はまだ『物質と記憶』や『創造的進化』にまで踏み込むことはできない。
我々はあくまでも初期ベルクソンの問題意識を考えることに徹底したい。
現在の私たちの位置と記憶がそれに先行する位置と呼ぶものとのあいだで私たちの意識がおこなう総合の結果、これらのイメージは相互に浸透し合い、補完し合い、連続することになる。純粋持続とは、互いに溶け合い、浸透し合い、明確な輪郭もなく、相互に外在化していく何の傾向性もなく、数とは何の類縁性もないような質的諸変化の継起以外のものではありえない。
『時間と自由』
カントは人間の意識をも〔量〕と表現したが、ベルクソンはそれを〔質〕と表現する。
即ち、純粋粋続とは〔質的多様性〕であり〔増大する量〕ではない。
すると現在の知覚に加わり想起するイマージュこそ時間ではないか、という『物質と記憶』の命題にはまだ触れられない。
我々の命題とは、即ち〔持続〕と〔直感〕についてである。
先ずは持続から語ろう。
例えば睡眠を例にとる。
①朝まで一度も起きることなく八時間眠れた夜
②悪夢に魘され何度も起き八時間眠った夜
二つの睡眠において八時間という〔量〕は同一であるが、二つの睡眠の〔質〕は同一か?
或は温度について。
10℃という温度は暑いのか寒いのか? 風呂上がりのそれは暑く、朝のそれは寒い。体質により異なり、湿度や日光の因果関係により温度という〔量〕は質的に異なる。
また我々は暫し「昨年の冬は今年よりも寒かった」などという言葉を口にするが、それらは客観的な〔量〕を測定しているのではなく、我々の〔持続〕の内から〔質〕として表象した言語である。
〔純粋持続〕について、より明確な例は音楽を聴く時の意識の流れにある。
メロディーの継起的音楽こそ、ベルクソンが純粋持続の下敷きとした完全なモデルである。
メロディーのなかにある瞬間は数ではない。メロディーの瞬間は生まれた瞬間死ぬためにそこにあるのであり、瞬間は自己を所有せず、立ち止まらない。持続のなかでの瞬間は現在とならず、過去が現在のなかに入り込み、現在とともに未来を形づくる。持続は音楽を演劇に近付ける。メロディーを再現するとは、心のなかでそれを再演することである。
ベルクソンにとって時間とは、『未来を進みつつ膨れるところの過去の連続し進行する持続』である。果たしてそのようなことがあるのだろうか? 習慣という色眼鏡は疑いをもつかもしれない。
しかしこのように考えてくれ給え。
君たちは〈一〉という単位を数学的点として同一に空間へ加え計測する時間、即ち時計の時間というものを信じ疑わないであろう。しかしそのような時間がいくら客観的だと思えようと、よくよく考えてみ給え、時計の針は時を刻んでいるのではなく、次々と別の位置に空間を移動しているだけではないか? すると時間という概念をつくるのは時計の針ではなく我々の意識にあるのではないか? すると時間はあくまでも主観的に、質的に与えられるものなのではないか?
我々は数を時間のなかで数えるものだと錯覚するが、我々は数を数える瞬間を無意識に空間の一点に固定しているのであり、そのような条件でのみ単位を加算し、抽象的な諸単位が一つの総和を形成するのである。
すると空間こそ精神が数を形づくる素材、精神が数を位置づける環境なのではないか?
まだ疑うようなら、君たちはあの「大人になるにつれ時の流れは早まるもの」という習慣の算式が如何なるものか考えてみてくれ給え。
子供の頃は〈体験=体験〉である。これが大人になると〈体験=習慣〉となる。さらに老人になると〈習慣=体験〉である。
我々の内部にある持続とは、数とは何の類似性ももたない質的多様性である。
瞬間毎に異なり流れる時間を連結する記憶が〔質〕として意識に与えるものが〔純粋持続〕であり、即ち本質的な時間とは、純粋持続の内に潜在する無数の瞬間を現在の知覚がイマージュとして表象することである。
我々の〔持続〕が〔質〕であり、それを〔量〕で計測することは不可能であるなら、生命を科学で規定することも又不可能であり、過去を記憶として蓄積する意識は現在において選択し、意志を自由に規定し、未来を切り開くものである。
つまり純粋持続とは個性的な人格のことであり、主観的な自己である。
主観的自己とは、即ち自由な人間である。
直観
持続に関する以上のような考察の結果、ベルクソンに現れた哲学的方法が〔直観〕であった。
しかし〔直観〕とは、使い古された哲学概念である。
主にカント以後のドイツ観念論者は、それを自然の目的論(汎神論)へと使用した。
しかしベルクソンの〔直観〕は、もちろんそれらとは異なる。
ベルクソンは一度カントに戻る。戻ったうえで意図的(逆説的)に〔直観〕という言葉を選択しているのだ。
ベルクソンのパラドクスはここにあり、以下の指摘は重用である。
カントは持続と時間を同一視するという誤謬をおかしたため、因果律から自由を考察する際に、実際には空間と無縁の二つの自我〔フェノメノン〕と〔ノウーメノン〕を与え、我々の認識能力に近づきえない自由の形式を与えざるを得なかった。
しかしカントは超越論的統覚としての内的自我の信頼により、自由を確固不動のものと信じる(信じたい)のである(ここにはルソーの影響を見ることできる)
カントは、なんとしても「自由」と言いたかった。
それだから、なんとかして自由の可能性を実現するため、自由を時間の外に置き〔現象〕の世界と〔物自体〕の世界との間に超えがたい障壁を立てることを選んだ(選ばざるをえなかった)のである。
カントの問題の起源は〔質〕と〔量〕を混同する錯覚のうちにあった、とベルクソンは指摘する。
我々は大抵自分自身に外的に生きており、自我については純粋持続が空間のなかに投影する影にしか気づかない。
したがって我々の生存は時間におけるより、むしろ空間において繰り広げられる。
我々は考えるよりも、むしろ話す。
我々は行動するよりも、むしろ行動させられる。
自由に行動するということは、自己を取り戻すことである。
それは即ち、純粋持続のなかに身を置き直すことである。
カントは、時間と空間を我々の意識とは別のところ(アプリオリ)にあるものだとみなした。
ベルクソンは自らの哲学を始めるにあたり、この常識を崩しにかかった。
時間も空間も、本来我々の意識に関与しているものである。
人間が宇宙の歴史のなかに生命として誕生し、このような意識(反省的判断力)をもったということは、カントの言うようにアプリオリな時空がどこか別のところにあるからではなく、意識を生み出す時空というものがあるのである(ここは創造的進化を掘り下げないと詳しく書けない)
実証科学時代の哲学は、先ず其処から考察するべきではないか?
ベルクソン哲学はカントに挑戦することで、必然的に生の哲学(エランヴィタール)へ跳躍した。
ベルクソン哲学はカントの超越論的感性論をコペルニクス的に転回し、直観をパラドクスさせることによりカントから時空を奪い返すことで始まったのである。
私の直観は反省である、とベルクソンは言っている。
私が真の哲学的方法に眼を開かされたのは、内的生活のなかに初めて経験の領域を見いだした後、言葉による解決を投げ棄てた日であり、その後のあらゆる進歩はこの領域の拡大であった、と。
物を知るのに非常に違った二つの見方を区別する―第一の知り方はその物のまわりを回ることであり、第二の知り方はその物のなかに入ることである。第一の知り方は人の立つ視点と表現〔表象〕の際に使う記号〔象徴〕に依存する。第二の知り方は視点に関わりなく記号にも依らない。第一の認識は相対にとどまり、第二の認識はそれが可能な場合には絶対に到達すると言える。
『思想と動くもの』
生命を分析することは不可能である。
生命とは、エランヴィタールである。
数学により測定される線は不動であるが、時間は動きである。
線はできあがったものであるが、時間はできていくものである。
科学は物質的世界から繰り返し計算することのできるもの、持続しないものを抽出し保持するが、そのとき数えられるのはただ間隙、つまり時間の潜在的停止の数だけであり、我々の意識に直接与えられるものを科学は説明することができない。
私の〔直観〕はなによりも内面的持続に向かう。
それが捉えるのは、精神に対する直接の視覚であり、生物の科学の延長としての生命の哲学である。
我々は生命の躍動を意識によって捉えることにより、有機化の深い原因を突きとめることができるのではないだろうか? 宇宙が精神に結びつく起源の視覚は哲学的であったが、厳密になるにつれ、換言すると静的な述語で表現されるようになるにつれ、科学的となった。
そこで私は哲学に対し、一つの限定された対象(精神に対する特殊な方法として)なによりも〔直観〕を認める。
これによって私は哲学を科学からはっきり区別するが、しかしこれによって私は二つのものに平等な価値を認める。
実証科学は感覚による観察に訴えて得た素材の仕上げを抽象化して悟性にゆだね、純粋数学から力学を通り、物理学および化学を通って生物学へ到達した。
その領域は慣性的な物質の領域である。
我々が科学には物質、哲学には精神と、別々の対象を認めるとすれば、精神と物質は触れ合っているのであるから、両面から得られた結果はたがいに結合するであろう。
私は、ようやくベルクソン哲学のなんたるかがつかめてきた。しかし私は『物質と記憶』を読み返し、ここに加筆する気力をまだもたない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
