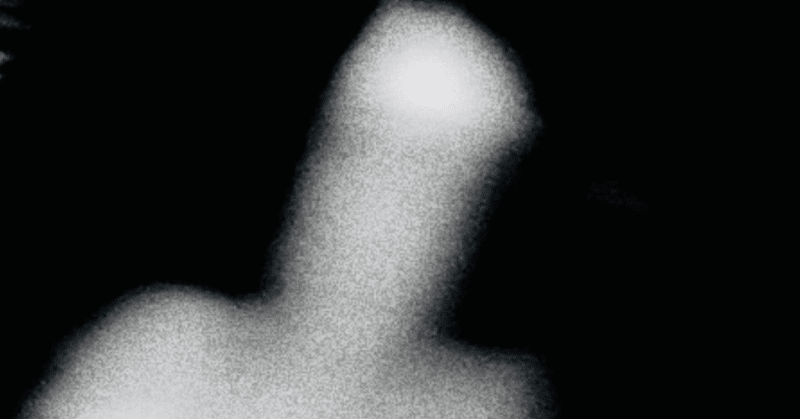
複製技術におけるSNS
ヴァルター・ベンヤミンが、『複製技術時代の芸術』の中で、写真という複製技術が発達したことにより、芸術がもっていたその場限りのアウラが喪失したことを考察し、百年経とうとしているが、SNSにおけるエクストリーム複製技術時代を生きるわれわれにとって、最早ベンヤミンの主張は逆転しているように思う。
Instagramを例にとろう。
13年店を続け、3年前にこのソーシャルネットワークサービスを使い始めた。それから店という「場」のもつ意味(そのリアリティー、つまりアウラ)が変わったことを実感せざるをえない。
ベンヤミンは、写真技術の発明により、芸術の一回性を成立の契機とする〈礼拝価値〉が、写真の指示による〈展示価値〉に置き換えられ、大衆の知覚を引き受けるようになったことを考察しているが、じつは今Instagram内で、この価値は見事に反転しているのだ。
以下、Instagramの〈展示価値〉が現実世界で〈礼拝価値〉を帯びてきていることの考察である。
一枚の写真(それが絵画でも、コーヒーでも、ドーナツでも)いちいち具体例をあげることはしたくないが、SNSにおけるイメージ産業は、情報をまず彼らがそこから利潤を引き出すことの出来る商品に仕立てあげることからはじめ、そしてそれらを大衆の消費能力にあわせて拝むべき記念碑的礼拝物に転化し、送りつける。
そうして今やSNS内で展示された情報が礼拝的な価値を帯びる形態(バエる、バズる)がリアリティーを帯びることになる。
思えば、Instagramもサービス開始当初(僕もその頃は利用していた)はシンプルに個人の現実に対応する現実の模写像として情報が受けとられていたように思う。
あの頃のインスタは〈私と現実〉をつなぐ伝達回路として、まだ機能を果たしていたように思うが、いつの間にかインスタ内の現実の模写像が当の現実より現実的であるという奇妙な現実が生まれてはじめたのだ。
そこでは伝達メディアが伝達内容よりも礼拝的に享受され、現実の模写像であった写真が展示されることによりそれ自体が独立して第二の現実を形成しているのだ。
われわれはイメージに浸透され、SNSで切りとられた現実を当の写真はあくまでも現実のイメージであるにすぎないことを忘れ、現実そのものとあまりにも容易に短絡させることにより現実ではなく現実の似姿を現実そのものと信じ込んでしまっているのだ。
この奇妙な神話は〝バエル〟ために店をやってない者からすると、吐き気を催す光景である。
あまり言いたくない(言いたくはないガ!)SNSを見て店に来る一部の人にとって、店は(或はこの際〝街〟と言ってもよい気がするが)SNSにでかけられた呪縛的イメージを消費する場(展示された礼拝物を拝む場)になっているのだ。そういう人はあらかじめ与えられたイメージしか見ないのだ。店は目的のための手段でしかないのだ。現実はもう隅々までイメージ化されてしまっているのだ。だからもう僕の店はもう〝撮影禁止です〟なんて言えるはずもなく、こんな投稿を本アカにあげられるはずもなく(じつはとてもバカな客がやって来たのだ)インスタに中指なんてたてられるわけないのだ。
ところで、最近の僕は全て写真で考えてしまっているのだ。中平卓馬は半世紀前にお見通しだったのだ。何かできることがあるのではないか。
ベンヤミンは、〈芸術〉という言葉が今世紀の歴史とともに変質し、いわゆる〈芸術〉を支えていた礼拝的価値が他ならぬ写真と映画のもつ複製能力によって崩壊してしまった時、写真が〈芸術〉であるかという問いは、定立としてすでに無意味になったと指摘する。まさしくその通りだと思う。しかしこの問いとならんで、またそれと微妙にからみあいながらもう一つのやっかいな問いがある。写真は表現であるか、否か? おそらくこの問いが発せられる基底には、意識以前に、あるいは意識を超えて物が在り、それをただ記録するのが写真であるとするならば、写真は表現とはいい難いのではないかという疑いがあるように思われる。そしてここには表現とは内的なるものの白であるとする確信がほのみえる。それならば写真は表現でなくてもかまわない、いやむしろ物があってはじめて写真があるというその記録に徹することによって写真は何ものかでありうるというのがぼくの結論である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
