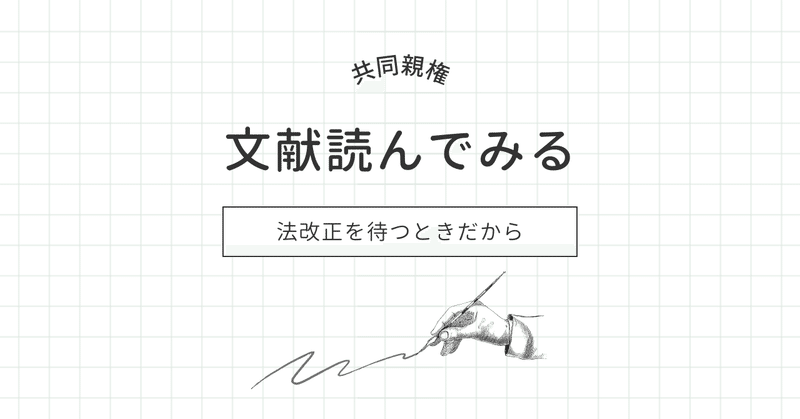
共同親権関連文献紹介1
新年度!
無事、不安そうながらも、わが家の新1年生は、姉と一緒に学童の初日に登所を果たした!!
反響あります
1403日目の発信は本気で
— RK (@koga_r) April 2, 2023
共同親権を求める弁護士はいるよ
きっと、もっと潜在している
親子関係の断絶による人権侵害を防止するための家族法制の実現を求める弁護士有志|弁護士古賀礼子 @koga_r #note #大切にしている教え https://t.co/SsfR8g16zc
改めて知ることもまだある
弁護士会の子どもの権利委員会がまとめたパンフレットがあるのねhttps://t.co/cevuRWF2dn
— RK (@koga_r) April 2, 2023
じれったい時間だからこそ鍛えられることもある
じれったい時間は、学術論文も読んでみて
— RK (@koga_r) April 2, 2023
2021年の家族法学会のシンポジウムのテーマで親権のことを扱っている
この学会の組織のことも調べてみると、お馴染みのお名前を拝見することができたりする
研究者の先生方は社会運動まではしないけど、ヒントはくれるhttps://t.co/ad4TRUjAot
先週の話題も冷めず、議論は発展していくところだし
もう?というか、まだ、たった20日前のことだけど、遠いことのように思うこの女性法律家協会のパブコメを知って、今さらながら動揺した方の意見表明などがあるらしい
— RK (@koga_r) March 28, 2023
国会でも取り上げられたのにね
日本女性法律家協会のパブコメは、民法819条見直し賛成の【甲案】
女性弁護士として誇りに思います https://t.co/uj86muTu9s
とりあえず、国賠のために、以前からいろいろ模索した文献なんかも掘り起こしシェアするのもニーズあるんじゃないかな、と
国賠で提出した文献ももちろんいいけど、その他もたくさんある
たとえばこちら
検索したら全文読めたりする
日本における婚外子の共同親権制度の導入 ――子の権利の視点から――
研究者は、二宮先生に指導を受けた上羅翔太氏である
2015年の立命館法政論集 第13号に収録されているという
歴史から国際比較まで、本当によく検討されている
学説の整理までしている
「おわりに」を引用して紹介するとして、ぜひ全文にアクセスしてもらうといいと思う
共同親権の答えが書いてある!
日本では,親権法における子の権利の重要性が古くから説かれてきたに もかかわらず,婚外子の権利については親権法において疎外されてきたよ うな印象を受ける。近年では離婚後の共同親権の議論とセットとなって婚 外子の共同親権について改正案が出されるようになってきたが,婚外子の 法定相続分差別規定が廃止された今,婚外子の権利について今一度捉えな おすべきと考える。確かに,日本の婚外子出生率は相対的に低く,フラン スでは婚外子出生率が50%を超え,ドイツでも30%を超えている。日本で は2012年の婚外子出生率は2.23%であり,婚外子出生率の推移を見ると, 1970年から1985年までは1%前後を推移していたが,その後微増し,2004 年には2%台に入った。また婚外子の父母の関係性も多様であり,安定的 な関係を持つ事実婚や,一方と別居しているが良好な関係を築いている状 態,母が父を拒む関係など様々である。このように見ると,ドイツ・フラ ンスと比べて,実際の婚外子の共同親権に対する要請は大きくないかもし れない。しかし,だからといって婚外子の父母を求める権利が実現されな くて良いというわけではなく,やはり理念的な側面から共同親権化は実現 されるべきであろう。そのため,これからはすべての子が父母双方により 監護・養育を受ける権利を持つことを出発点として,婚外子の共同親権を 認め,その上でどのような法制をとりうるかを考える必要があるのではな いか。
その上で重要なのは,親権の共同行使をいかに調整するかということで ある。これは離婚後の共同親権の場合についても同様であるが,まず父母 の合意形成を促進するような環境を整えることが求められる。この時に, 父母が種々のサービスを利用しやすくするようなハブ機能を担うワンス トップサービスが重要になってくると考えられる。父母が納得しながら子 の将来について取り決めることができ,合意できない場合には裁判所による介入を受けることができるようになる。このような基盤があることでは じめて,共同親権の制度が円滑に機能するものであると考える。
上羅翔太著
これが「婚外子」の話だ、として、特に離婚問題に直面している当事者が多い中では、わが事と切り離してしまうことも見られるのかもしれない
離婚後の共同親権の場合についても同様、というように、関係のある話なのである
絆とか、親子関係の美化・親子断絶の悲劇化、みたいなステージでは、法改正の突破口にはならない
何が障壁になっているのか、知る人は知っているのである
親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!
